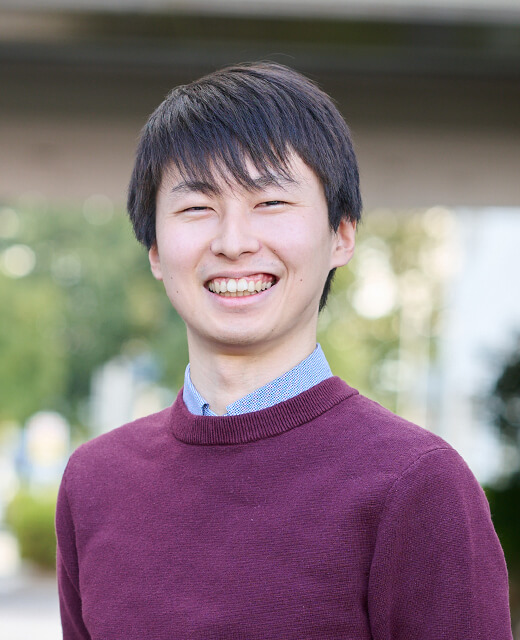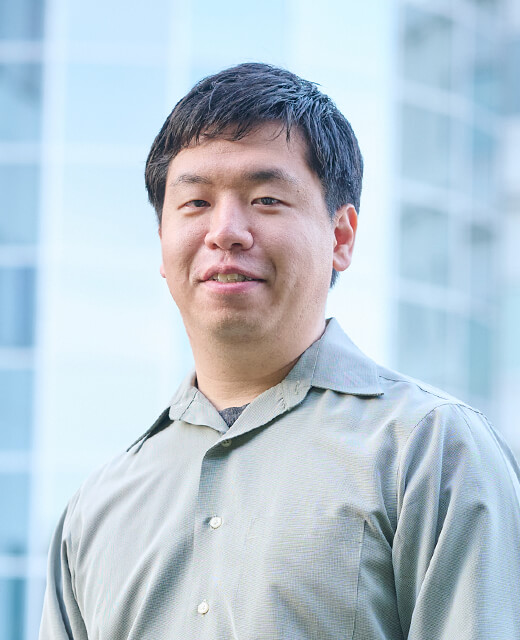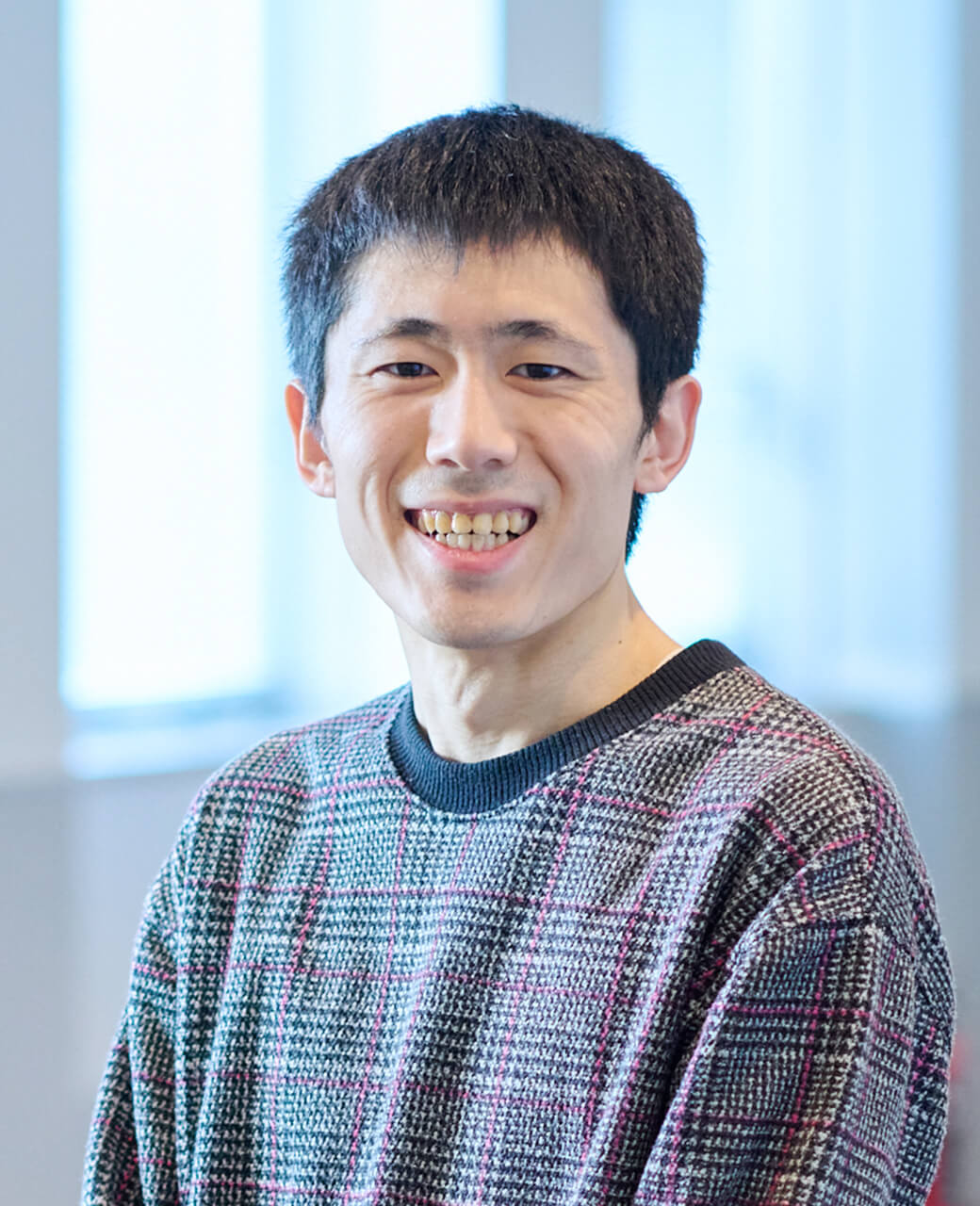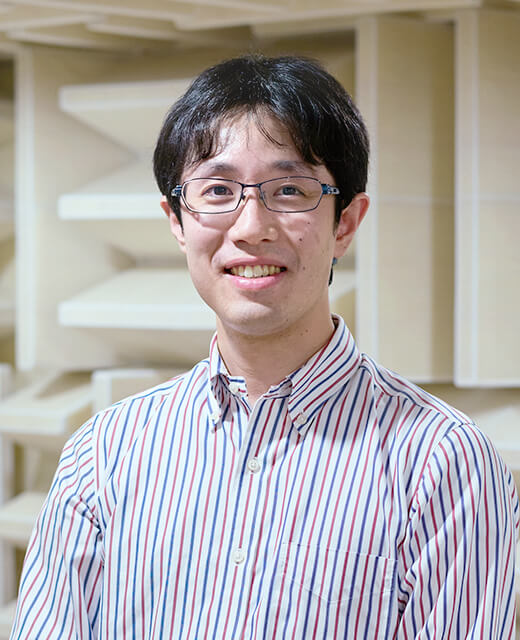エンジニア職|機構開発設計
ヒット商品 “人間工学電卓”の
立役者の1人として。
M.M
2018年入社/第二機構開発部/羽村技術センター
INTERVIEW
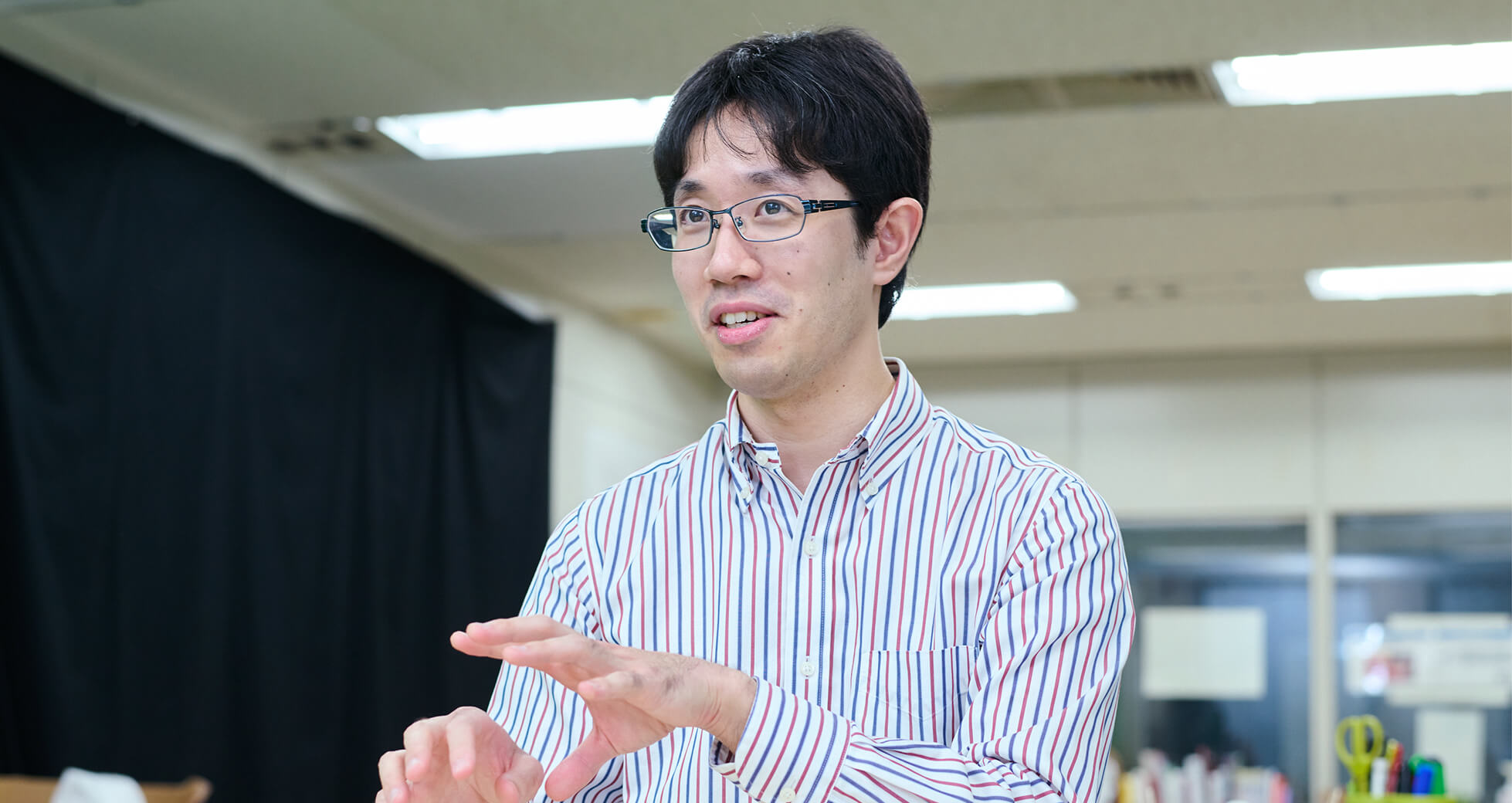
カシオに入社したきっかけ
「音」の世界から、独創的なモノづくりの世界へ。
子どもの頃からチェロを演奏しており、大学院でも弦楽器の弦の振動を計測し、材質の違いで音がどう異なるのかを研究していました。そんな背景もあり就職活動では楽器メーカーや音響メーカーを検討する中で、楽器だけでなく幅広い品目において「この世にない新しい製品を生み出す」というカシオの歴史や姿勢に惹かれたのを覚えています。また、就職活動の軸に据えたのは「自分の仕事によって直接的に商品の付加価値を高めることができ、アウトプットが見えるかどうか」でしたが、モノづくりの規模が大きくなると、業務が細分化されて自分の仕事が見えづらくなる傾向があります。そういう点でカシオはグローバル企業でありつつも、自分の個性や意見が反映できるユニークなメーカーだと感じました。私が入社する数カ月前に新しい技術を使ったカシオの製品がニュースで取り上げられていました。この数年後、自分もヒット商品に携われるとは夢にも思っていませんでした。
これまで、そしてこれからの仕事
大人気を呼ぶ、操作面を3° 傾斜させた“人間工学電卓”。
入社後はコンビニなどで使われるハンディターミナルや電子レジスターの機構設計からスタートしました。時計や辞書のようなB to C製品だけでなく、カシオはこのようなB to B製品もつくっています。その後、入社4年目の直前に一般電卓の機構設計に異動。ここでメイン設計担当として携わったのが、現在、ヒット商品として多くのユーザーに使用されている“人間工学電卓”です。これは操作面を3°の角度で傾斜させることで打ちやすさを向上させた電卓で、かなり斬新なアイデアでした。
家電量販店に行くと目立つ場所に置かれている製品でもあり、愛用しているユーザーには会計や経理といった計算のプロフェッショナルが多いです。そのため時には専門家ならではのなるほどと思わせられる改善要望をいただくこともあり、B to C製品の設計者としては大いに参考にさせてもらっています。開発者・設計者はそのときの最善の力を100%発揮して製品をつくります。しかしそこですべてが終了ではなく、実際のユーザーの声を聞くことで、もっと良いモノへと改善・改良していきます。このサイクルを繰り返すことでカシオの製品は世界中のユーザーから認めてもらってきました。カシオブランドに加わった“人間工学電卓”をもっと良いモノにしていきます。
CHALLENGE

カシオでの挑戦
前例のない「音」にこだわった新たな挑戦。
ユーザーの声を聞いて改善・改良していくのは、電卓の形だけに限りません。カシオ製品全般をより良いものにしていきたいと考えている要素があります。それは私の原点ともいえる「音」。例えば、打鍵音が静かな電卓があれば、繁忙期の税理士事務所や企業の経理部の働く環境もきっと良い方へ変わると思います。あらゆる製品でそれが実現できれば、より多くの人がカシオ製品を使いたくなりますし、ブランド力の向上にもつながるかもしれません。専門知識も必要となる挑戦で、その分、やりがいのある開発ですが難易度も高いです。何の製品のどの音を測定するかによって、最適な測定方法が異なるため、精度高く安定的に測定するノウハウを得ることに苦労しています。電子楽器の音響解析を専門的に行うチームに協力してもらったり、出身大学の先生に相談したりと、社内外あらゆる立場の方々の力をお借りして、これまで誰も取り組んだことのないテーマに挑戦しているところです。
他のメーカーなら、私の挑戦は無謀だと言われたかもしれません。しかしカシオは開発者のアイデアを笑ったりせず、どんどんやってみようと後押しをしてくれる会社。学生時代の専門性を活かすこともでき、入社後に業務を通して得た意外な経験や知識を新しい提案に繋げることもできるのがカシオです。
SPECIAL CONTENTS
PURPOSE&HISTORY
PRODUCT
JOBS×PERSONS
RECRUIT INFORMATION
note
© CASIO COMPUTER CO., LTD.