PROJECT STORY_2
社員対談×ClassPad.net
教育現場のICT活用をサポートする。
端末1つで学びの可能性が広がる
学習アプリを開発せよ。
私たちを取り巻く世の中では
ものすごいスピードでDX化が進んでいる。
それは、教育現場もしかり。
全国の学校で1人1台の端末導入が加速し、
目まぐるしく変化を遂げている。
「時代に合ったより良い教育環境を提供したい」
ClassPad.netはそんな想いから生まれた新たな学習サービス。
ノート機能、辞書機能、数学ツール、
そして先生・生徒間で課題の送受信ができる授業支援機能が
このアプリケーション1つに詰まっている。
そんな新たな学習ツールの開発に挑んだ社員たちに話を聞いた。

U.H.
2005年入社
教育BU 関数戦略部 ICTビジネス開発室 室長
ビジネスモデル、商品・営業戦略・プロモーション施策の立案、推進を担当。また、各関連部門に実行に向けた働きかけを行う。

U.S.
2006年入社
開発本部 第二開発統轄部 第一開発部 13企画室
仕様設計、総合評価を中心に開発スケジュールの管理を担当。また、マニュアル・デザイン部門との調整や営業部門との販促物の内容確認等も実施。

H.T.
1990年入社
営業本部 国内営業統轄部 ES推進部 教育推進室
高校営業の推進役として、全国の学販営業に営業方針・営業戦略の立案を発信。商品販売の推進を担った。

O.I.
1991年入社
教育BU 辞書・英会話戦略部 営業企画室
現場営業への商品企画案の発信及び、開発・企画への市場評価のフィードバックを担当。

教育現場と専門家の声の
ヒアリングから開発がはじまった。
U.H.
新型コロナウイルスの影響で学校教育を取り巻く環境も大きく変わっていきました。学校閉鎖によってオンライン授業が始まり、小中学生1人に1台パソコンを支給する国策も導入スピードが上がっていく。そんなICT化が加速する学校現場に対して、カシオが貢献できることはないかと考え、学習アプリ「ClassPad.net」の開発プロジェクトがスタートしました。当初は長年電子辞書を開発してきたノウハウがあるため、辞書をアプリ化する案がありました。けれども、ただ辞書機能をアプリにするだけでは“学校教育”として実用的ではない。そこで考えたコンセプトが、ノート機能を主体とした学習アプリ。机の上に辞書とノートを広げて勉強する様子をデジタル上で再現するという目標を定め、プロジェクトメンバーをアサインしました。とくに開発の人数はすごかったですよね。
U.S.
数えたことはないんですけど、開発だけで数十人ですね。営業までいれるともっとすごい数ですよね?
H.T.
営業メンバーはそれ以上いますね。
U.H.
この営業みんなが学校とつながっているんですよね。これがカシオのすごい強みで。コンセプト立案後はこのネットワークを利用して、現場の先生から情報を吸い上げました。
H.T.
電子辞書の販売を開始して以来、毎年現場の先生のご意見を元にアップデートしてきました。先生が納得できるものでないと採用してもらえないので、現場の意見はかなり重要。現場で営業していた時代に懇意にしていた先生に連絡をして、ヒアリングしました。
U.H.
そのとき企画側では、教育を研究している専門家へのヒアリングを行いました。そもそもノートの上で辞書を引くことをデジタル上で再現することに意味があるのか、その確認からのスタートだったんです。このコンセプトに対してお墨付きをもらえたのは結構大きかったですね。
U.S.
私たち開発側では、リリース前に策定した仕様が本当に大丈夫かを検証するために第三者機関調査を実施したり、学校利用を想定して社内でClassPad.netを使った模擬授業も行ったりしました。模擬授業では、私が先生役で、役職のある方々が生徒役をしてくださいましたね。リリース後は実際の高校生に使ってもらって、生徒側の意見をもらうこともしています。そこで出た意見を含め、色んな方からいただいた意見のおかげで、今のClassPad.netがあると思います。
リリースまで時間がない。
異例の方法で事態を切り抜けろ。
U.S.
開発するうえで苦労したのはとにかく日程でした。コロナ禍での学校教育に一刻も早く貢献するにはスピードが重要。プロジェクト発足は2020年5月でリリースは2021年4月予定でしたから、圧倒的に開発期間が足りませんでした。
U.H.
そこで「ベータ版」として4月に無料配布をし、使ってもらいながら教育現場の声を聞きながら商品をアップデートしていく方法をとりました。ハードメーカーの私たちにはなじみのない異例のリリース方法でしたが、今思えばベータ版という段階があって良かったのかもしれません。というのも、当時学校現場ではオンライン授業やICT化が全く追いついていない状態でしたので、一旦お試しいただける期間をつくれたと思います。
U.S.
ベータ版としてリリースしてからは、2~3か月に1回アップデートをしています。主だったところですと、作成した付箋を学校内で共有する機能やカメラで撮影した画像を付箋化する機能ですね。
U.H.
カメラもなかったもんね、最初は。
U.S.
実はPC・タブレットにおける学習で、カメラ撮影した画像を活用するシーンは多くないだろうと想定していました・・・ところが、いざ機能を搭載し使ってみるとこれがとても便利なものであることが分かりました。実際、カメラ機能を活用した授業・活動をされている学校の話を聞くことがありますので搭載して良かったと思いますね。カメラ機能はその一例ですが、徐々にアップデートをしながら機能を向上させて、製品版のリリースを目指していきました。
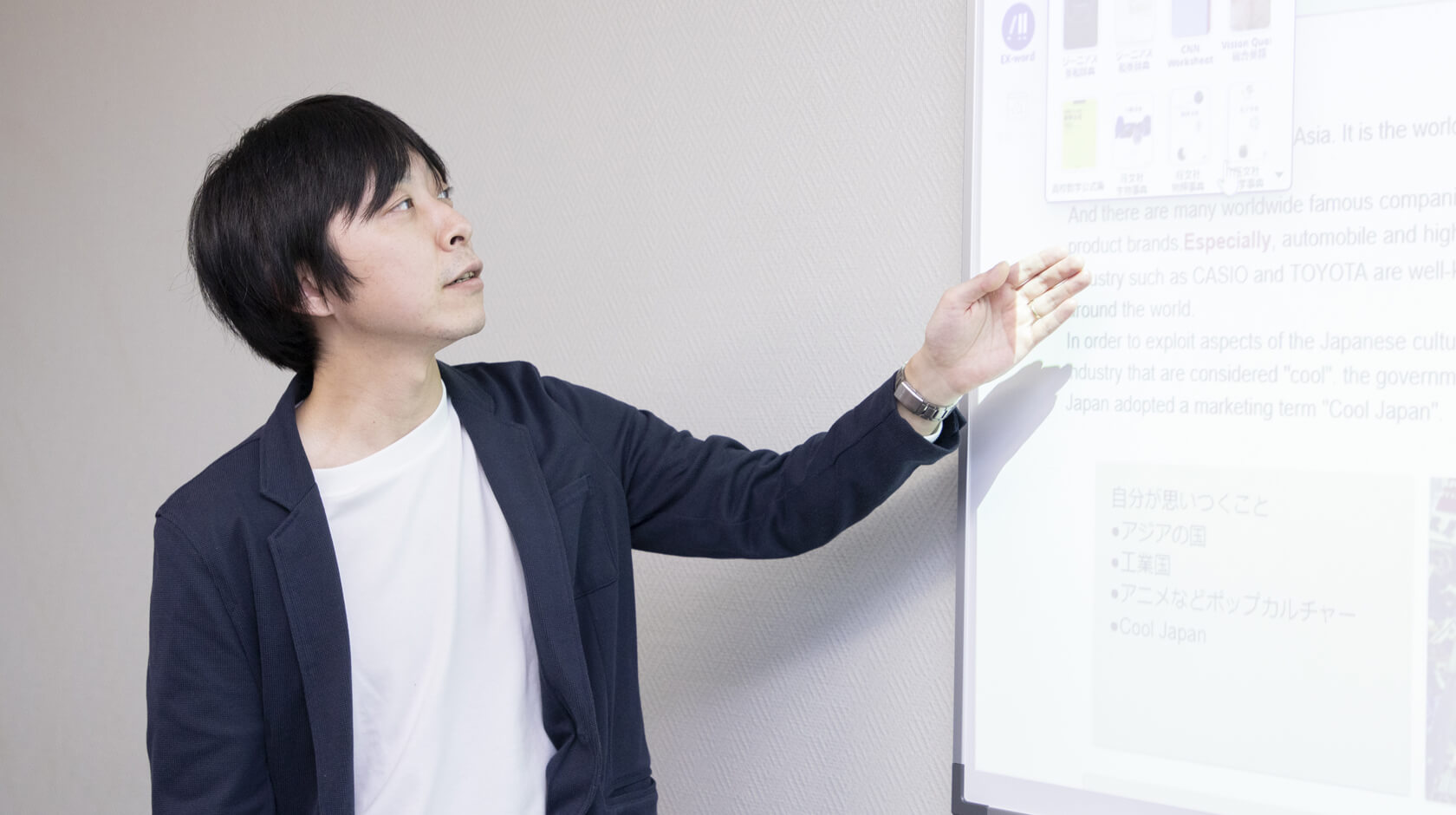
日本全国を行脚し、
現場の営業活動をバックアップ。
H.T.
私のほうでは、全国の営業社員と連携しながら学校への提案活動を行いました。
O.I.
まだアプリは完成していませんでしたが、2020年12月ごろから商品の概要説明ができる状態になっていました。H.T.が行っていた各高校の先生方へのご案内にサポートとして加わり、推進していきました。
H.T.
色んな学校に行きましたよね。しかし、普段電子辞書を提案している現場の営業にとって、手元に物が存在しないアプリの提案にはかなり苦戦していました。人によっては得手不得手がはっきり出てしまうので、現場の営業から同行依頼があれば、できるだけ現場に行くようにしていましたね。
O.I.
直接お伺いできない場合は、各拠点の営業社員が訪問し、私たちはオンラインで参加して機能説明などの後方支援をしました。商品に対してご意見をいただけることもありましたので、企画や開発とも情報共有をしながら進めました。
H.T.
こうした地道な営業活動の甲斐もあり、600校以上にベータ版を導入していただけました。ベータ版としてのリリース時は辞書とデジタルノート機能のみでしたが、その後「数学ツール」と先生・生徒間で課題の送受信ができる「授業支援」機能も加わりました。今後も製品の良さを伝えながら拡販につなげていきたいです。

カシオの製品を通じて、
多くの学生に教育の価値提供をしていきたい。
U.H.
私は、今までは海外をメインターゲットとした関数電卓の商品企画をやってきたので、国内マーケットで現場の声を聞きながら仕事ができたのは新鮮でした。実際に私自身が日本の学校教育を経験しているわけですから、文化まで深く理解している。その点海外については、分かったつもりで開発している部分があったのかもしれないと気づかされました。
O.I.
全く新しいサ―ビスにチャレンジできたっていうのが、すごく良い経験になりました。今までにない学習ツールの提供、そしてほぼ前例のないサブスクリプション型の商品への挑戦。調整業務など大変でしたが、生徒のためになると思うと苦労が実るのかなと思います。
U.S.
実は、今回のプロジェクトで初めてアプリの開発に携わりました。カシオには学ぶ姿勢さえあれば新しい分野にチャレンジできたり、自分でしっかり考えて発信できれば、キャリアに関係なく自分の考えを機能に反映できる環境があると感じましたね。今後も引き続きユーザビリティ評価をしながら、まだまだ精度を高めていきたいです。
H.T.
今まで開発側の人たちと会話する機会がほとんどなかったのですが、今回職種を横断してつながれたことで、1つの商品を立ち上げるのに色んな人が絡んでいることを実感できました。あとはやっぱり、生徒達が3年間この商品を活用して、「大学に合格できた」「学力が上がった」という声が聞けたら嬉しいですよね。
U.H.
あと1つ、今後の展望としてはやっぱり海外展開ですね。日本と同じように海外にも教育のネットワークがありますから、それを使って進出していきたい。とはいえ、私たちが目指しているのはアプリをどれだけ売るかということではなく、カシオのツールを通じていかに良い教育を届けるかです。電子辞書や関数電卓といったハードウェアと、ClassPad.netを合わせてどう良い教育を提供するのか。多くの学生に教育の価値提供をすることが今後の使命ですね。

SPECIAL CONTENTS
PURPOSE&HISTORY
PRODUCT
JOBS×PERSONS
RECRUIT INFORMATION
note
© CASIO COMPUTER CO., LTD.

