
TALK
OJT×後輩
配属部門で共に業務をおこなう先輩社員が新入社員の指導担当として、ともに業務をおこないます。
OJT育成担当者は数年間の業務経験を持っている社員が指名され、上長やチームメンバー、人事チームと連携をおこないながら新入社員の成長をサポートします。
配属されてから約8ヶ月の期間で一人で業務を担当できることを目指したサポート体制を整えています。
2021年に入社した三村さん。その当時のOJT育成の担当が神澤さんでした。
当日はコロナ禍で対面での業務ができないなど、困難な環境を経験しましたが、どのような想いをもっていたのでしょうか。
入社後数年経っていますが、今も同じ部門で業務をおこなう二人に話を聞きました。
MEMBERS

神澤輝斗
2018年入社
経営学部卒。マーケティング部門でデジタル施策(SNS/web広告)を担当。入社時は福岡営業所で九州エリアの営業を担当し、 2021年より神戸本社にてマーケティング部門へ。 現場での営業経験から「シューズを販売する苦しさ」を実感できたことが今の業務に活きていると話す。

三村果穂
2021年入社
政策科学部卒。大学ではマーケティングを専攻。神澤と同じくマーケティング部門でデジタル施策(SNS/web広告)を担当している。入社時から同部門で勤務 。探求心が高く、情報収集や知識習得、スキルアップには徹底的に取り組み、やり切ることのできる人物。
まずは、”育成された”側の三村さん。
Question 01
(1年目を振り返って)苦労したこと、大変だったことは?
三村
入社1年目で最も苦労したのは、自分のスキルや現在の状況( 「ここまではできている」「ここからはまだできない」 )を言語化することでした。新しい経験を重ねる中で、業務の全体像を十分に理解できておらず、曖昧な認識のまま進めていたことが原因だと思います。しかし、自分の状況を言語化することは、育成する側とされる側が互いの認識をすり合わせ、スムーズなサポートを受けるためにも重要だと考えていました。
また、質問やサポートをお願いする適切なタイミングを見極めることにも苦労しました。当時はコロナ禍で在宅勤務が中心だったため、先輩方の業務内容や状況が見えにくく、どのタイミングで依頼すれば良いか判断が難しかったです。
Q.その時にどのようなことをしましたか?
三村
自分のスキルや現在の状況を言語化するため、定期的に振り返りを行いました。具体的には、実際に行った業務内容や達成できたこと、気づいた点などをリストアップし、自分の成長を確認するとともに、改善すべき点を明確にするよう努めました。
サポートをお願いする際には、遠慮せず、相手の状況に配慮した上で行動することを心がけました。例えば、事前に自分なりに調べたり考えたりして、どこが分からないのかを明確にした上で質問するようにしていました。このようにすることで、相手が具体的にサポートしやすい状態をつくることを意識しました。
神澤さんが「分からないことはそのままにせず、いつでも聞いてね!」というスタンスで接してくださったため、分からないことを一人で抱え込まず、積極的にコミュニケーションを取ることができました。

Question 02
OJT育成の制度があって良かったと思うことは何ですか?
三村
新しい視点に気づくことができ、悩んだときに一人で抱え込まず相談できる環境が整っていたことが良かったと思います。新しい業務を始める際には、最初から私一人で遂行するのではなく、OJT担当者が一緒に業務を進めてくださる場面が多くありました。このようなサポートのおかげで、未経験の業務にも安心して取り組むことができました。
さらには、普段の業務では見えにくい「仕事への向き合い方」を学ぶことができました。社会人1年目という経験が少ない真っ白な段階で、仕事との向き合い方のパターンを知ることができたことは、今後のキャリアにおいても貴重な経験になったと実感しています。
OJT担当者との会話を通じて、「こういう悩みをもつのは自分だけではないんだ」と安心することにもつながりました。
OJT育成の制度があったことで、心強い環境で成長できたと思います。

次に”育成した”側の神澤さん。
Question 03
(育成したことを振り返って)苦労したこと、大変だったことは?
神澤
「前提をあわせること」に苦労しました。私が知っていることや理解していることと新入社員が知っていること、理解していることが違うため、スムーズに業務の説明や依頼ができずに苦労しました。
例えば、「ECサイトの会員向けメールマガジンを配備する」業務ではバナーの作成、文面の作成、HTML化、オーディエンス設定など多くのタスクが存在します。それらのタスクを1つずつこなしていくために、私なりにできるだけ細かく説明を行ったつもりだったのですが、必要な情報や業務依頼に対する理解が私と新入社員の間で大きく乖離していたことが多々ありました。その結果説明の時間が想定よりも長くなってしまったり、実際に業務を進める中で認識齟齬が発生してしまったりしました。


Q.その時にどのようなことをしましたか?
神澤
コミュニケーションをより密に高頻度で行い、お互いの認識齟齬をできる限り減らす仕組み作りをおこないました。
まずは環境作りです。リモート会議ツールやチャットを活用したり、会議中に質問時間や業務外の話にも触れる時間をつくることで、新入社員がわからないことを気軽に聞くことができる環境作りを心掛けました。
次に議事録(会議メモ)の作成です。会議で説明する内容は説明しながら議事録を同時に作成し、会議終了後に新入社員に共有することで、後日内容の振り返りや確認ができるように調整しました。
このようにしてお互いの認識齟齬を極力減らし、業務がスムーズに進行するように調整しました。
Question 04
OJT育成をおこなって、得たものはありますか?
神澤
自分自身の業務のより深い理解につながり、幅広い知識を得ることがました。
新入社員とコミュニケーションを繰り返す中で、私自身が咀嚼できている点、できていない点が露呈し、焦りを感じることが何度かありました。咀嚼できている点はより分かりやすく簡潔に説明できるように理解を深め、咀嚼できていない点は徹底的に調べたことで、自身の業務把握や業務の棚卸につながりました。また新しい情報に触れるきっかけにもなりました。
この経験が社外のお取引様やお客様に対して適切に情報を伝えるスキルの向上につながったと感じています。
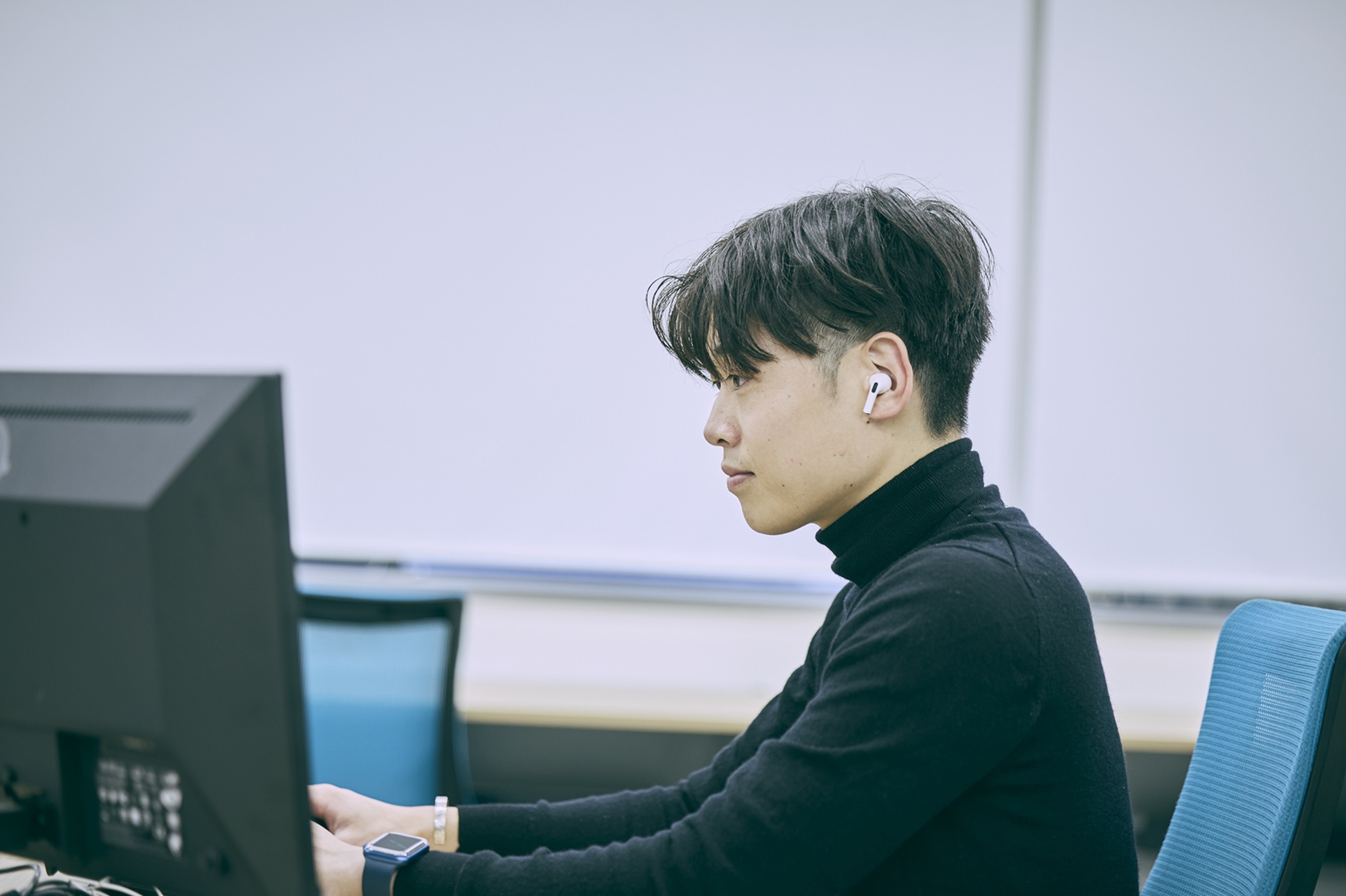
Question 05
OJT育成が終わってから数年が経ちますが、今の活躍をどう見ていますか?
神澤
今の活躍は心強く、頼もしいと感じています。
社内外問わず業務でかかわるメンバーも増え、三村さん主導で業務をおこなうことも増えてきました。今では私が三村さんに助けていただく機会が増えてきたと感じております。今後も切磋琢磨し互いに高めあいながら業務に取り組んでいきたいと思います。質問に対する答えを理解したつもりであったことも、改めて説明しようとすると、うまくできないこともありました。その時は一旦質問を持ち帰って、きちんと説明ができるように自身で学び直したこともありました。
このように新入社員の方に業務の説明や依頼をすることで、自分自身の知識や理解を深めることにもつながり、自分自身も成長できると気づきました。
Copyright © ASICS Trading Co.,Ltd. All Rights Reserved.