モノがまったくない机、こだわりのマウスはじめデジタルツールがたくさんある机、キャラクターグッズ多めの机。動物園みたいなヒューマネージ、机も人それぞれです。
そんななか、「本」が多めの机もあります。きょうは、人事グループメンバーの机に置いてあるオススメをご紹介します。
『新装版 ほぼ日の就職論 はたらきたい。』(ほぼ日刊イトイ新聞、東京糸井重里事務所)
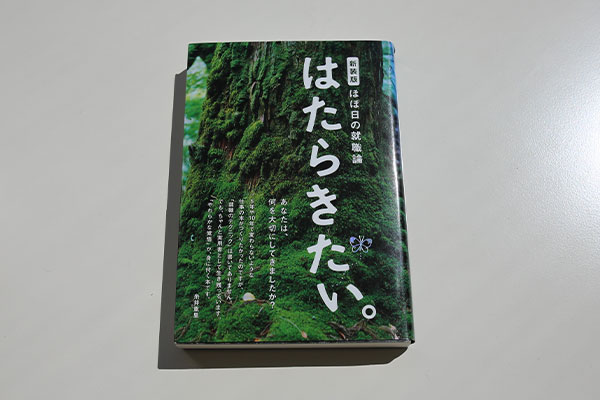
この仕事をはじめてからなのですが、仕事の話やキャリアの話を聴くのが好き。「このお仕事はいつからされているんですか?」「いまのお仕事に就いたのはどうしてですか?」など、営業に来た他社の方や、顔見知りになったレストランで働いている人にも聴いてしまったりします。
この本には、大学教授から矢沢永吉さんまで、いろんな人たちの「仕事」の話が載っています。仕事の内容はバラバラなのですが、失敗したり悩んだり、どうしようもない時期があったり、いろいろなことを経て働き続けている人の話は、それぞれとても面白い。10年くらい前に買った本なのですが、印象に残るフレーズがそのときどきによって違うのも面白いです。
最近いいなと思ったのは「たまにはキャパを超えたものも引き受けないと、力になっていかない」「着地点がわからない仕事を引き受けると、おもしろいんです」というフレーズ。そうかもしれない、がんばろうと思えました。
『クランボルツに学ぶ夢のあきらめ方』(海老原嗣生、星海社)
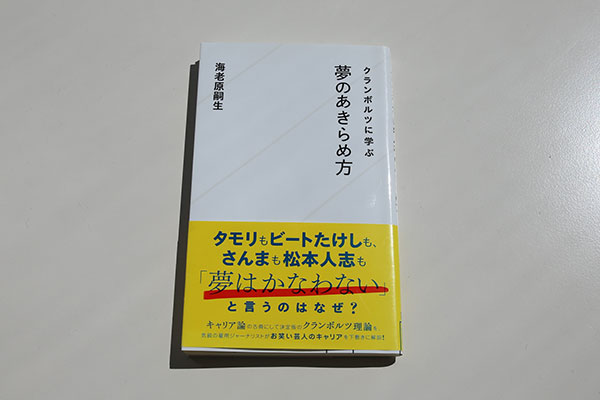
ヒューマネージの社員向け勉強会などでお世話になっている、雇用のカリスマ・海老原嗣生さんの本です。キャリア論には、大きく二つ、「キャリア・アンカー理論」と「プランドハプンスタンス理論」があります。簡単にご紹介すると、
●キャリア・アンカー
自分自身の核となる価値観や欲求に沿って、キャリアプランを描く。自分の適性や価値観にあわせて計画し、意図的に経験・知識・スキル等をつみあげてキャリアを形成するものです(カーナビのイメージ)。
●プランドハプンスタンス
キャリアの8割は偶然のできごとによって形成されるとし、偶然のできごとを利用してキャリア形成に役立てる、また、自ら偶然のできごとを引き寄せるように働きかけ、積極的にキャリア形成の機会を創出するというもの(自由な散歩のイメージ)。
この本は「プランドハプンスタンス理論」について、芸人さんを例に挙げてわかりやすく解説されています。夢をきっちり代謝すれば、必ず「かなう」夢に行きつく。人それぞれだと思いますが、わたしは実感をもって納得できました。
仕事で関わっている領域を好きになって、いろいろ知りたくなって、本を読んでインプットする。そして、インプットしたものをアウトプットする。学生の頃の“勉強”とは違う、社会人ならではの面白いところかな、と感じました。
また機会があれば、こんどは本が並んでいる別の部署のひとのオススメをご紹介したいと思います。


