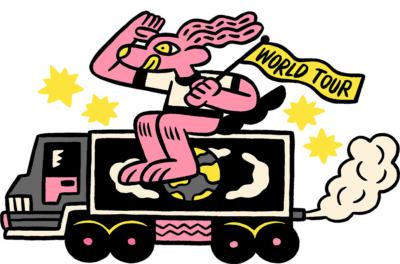会社に依存しないブランド人材になるために
エイベックスで演劇やミュージカルなどの舞台をプロデュースする山浦哲也の経歴は、社内でも異彩を放っています。「会社に依存しないキャリアを積み重ねてきた」と自負する山浦の経歴と、彼が思い描く理想の働き方や組織のあり方をご紹介します。
※内容は全て取材当時のものです
ファーストキャリアは劇団四季の研修生
山浦「私は大学卒業後、劇団四季に研修生として入団しました。研修生とは、丁稚奉公みたいな感じです。入団しているものの、劇団にとってみれば『プロとしてやれるか見きわめる』という立場。ですから月給は、数万円程度でした」
日本の舞台業界を代表する劇団四季の門を叩いた山浦の経験談は、当時の業界の厳しさを物語っています。
当時から劇団四季は日本でも名の知れた劇団で、地方巡業も多く、劇団員には休みもほとんどありませんでした。そんななかで、多くの仲間たちが次々と劇団から去っていったと山浦は振り返ります。そんな厳しい世界に山浦が身を投じる決意を固めたのは学生時代でした。
山浦「脚本家だった父の影響もあり、舞台に興味が湧いて大学在学中に演劇活動を始めました。当時、学生の演劇は決して内向きではなく、外にアウトプットしていることが多く、学生でありながら地方自治体と一緒に公演に取り組むこともありました。
演劇活動を続けながらも自分自身のキャリアを考えるようになり、卒業を控えた大学4年生のときには演出家になりたいと思うようになりました。そんなとき、劇団四季に「演出部」という部門があることを知ったのです。その部署名から『演出が勉強できる!』と思って劇団四季の門を叩きました。
ですが、実態は『演出』ではなく『舞台監督』だったんです。当時、劇団四季では、舞台監督という業務で俯瞰的に演劇を見つめられる素養こそが演出家への道としていました」
演出家という志を持ちながらも、舞台監督の道を歩み始めた山浦は、置かれた場所で芽を出すように、着実に力を伸ばしていきました。
山浦「入団して4年目で『美女と野獣』の舞台監督をやりました。劇団四季は若手に責任のあるポジションを任せるのがすごく早いんですよね。『ライオンキング』の舞台監督をやったのは6年目のときでしたし。
若手ですからすべてを理解しているわけでもないし、監督らしく現場を仕切れるわけでもない。劇団のなかで頑張っていると、多くの方がお膳立てしてくださる環境なんです。ですのでいろんな方の助けを得ながら舞台監督としての仕事をしていました」
そんな山浦の成長の陰には、ある巨匠との出会いがあったと言います。
山浦「劇団四季の創設者で演出を手掛けていた浅利慶太さんには“3月生まれ”という共通点から懇意にしていただき、とても可愛がっていただきました。
時として助手として一緒に時間を過ごしていると、浅利さんは唐突に『お前は何がやりたいんだ』って聞くんです。目の前の仕事に忙しい中でも、そうした投げかけに対して、しっかり答えられる人じゃないとダメ。
毎日同じ公演をやっていても、同世代の仲間で集まって『自分が何をやりたいのか』を議論することを忘れず、浅利さんにアイデアをぶつけるチャンスがあれば、自分の想いをぶつけ続けることを繰り返していました」

やりたいことに素直にーーキャリアの幅を広げた30代
その後約10年間、劇団四季で舞台監督を務め、業界でのキャリアを積み重ねてきた山浦ですが、その後、新たな挑戦の場を求めて、劇団を離れることを決めました。
山浦「劇団四季をやめた後は、フリーで舞台監督をやりながら、リクルートに入社して Webのプロデューサーになりました。ちょうどインターネットが流行りはじめたころでしたし、劇団四季のホームページ立ち上げを担当した経験もあって、Webの世界に興味があったんです。でも 10カ月程度で向いてないなって思って辞めちゃいました」
紆余曲折しながらも山浦は、劇団四季での経験を活かしつつ、新たなチャレンジを続けていきました。
山浦「劇団四季にいたころ、NHKのラジオドラマの脚本賞で賞をいただいたことがあって、その流れでライターの仕事を請け負ったり、お父さん役のモデルとして企業の CMに出演したり……。モーターショーの展示ブースの演出・デザインをしたりしていました」
劇団を離れるも、さまざまな分野で才能を開花させた山浦。しかし、劇団四季時代に厳しい環境の中でも「本当にやりたいこと」を常に自分に問い続けてきた山浦にとって、決して捨てられない想いがありました。
山浦「やっぱり舞台をつくりたいというのは心の中にずっとあったんです。リクルートを離れた理由も、そんな思いがあったからなのかもしれません」
演出への思いを強めるなかで、当時外資系舞台技術会社に所属していた山浦にある仕事が舞い込んできます。
それが後にエイベックスの出会いとなる『BLUEMAN GROUP』の舞台技術の依頼でした。
舞台業界進出前夜のエイベックスに感じた魅力
『BLUEMAN GROUP』といえば、世界を代表するパフォーマンス集団。2007年、エイベックスが六本木にブルーマン専用の劇場を構えたとき、山浦は劇場の運営に関わることとなります。会場を整える“裏方”だけでなく、お客様を相手にする“表方”としても活躍する山浦に、舞台事業の立ち上げを狙っていたエイベックスが声をかけたのは自然な流れでした。
山浦「話が進む中で当時本部長だった黒岩(代表取締役社長CEO)から、『エイベックスでも舞台の事業をやる、それも幅広い舞台事業をやる』と話してくれたんです。
ぜひやらせて欲しいと話し、エイベックス・ライヴ・クリエイティヴに入社しました。まだまだエイベックスの舞台事業のこけら落とし前。担当する社員も自分を入れて2名しかいませんでした」
しかし、事業規模は小さくとも、山浦はエイベックスに大きな期待を寄せていました。
山浦「当時のエイベックスのイメージは音楽レーベルの会社。『BLUEMAN GROUP』の公演も倖田來未さんがアンバサダーとして記者会見に来ていましたし、音楽が事業の中心の会社だと認識していました。
でも、そんな会社で新たに舞台の事業がはじめられるのなら、私にも活躍する余地があると思いましたし、プレッシャーのなかにも自由さを感じたのを覚えています」

独立したプロデューサー集団を目指せ! 理想のキャリアの重ね方とは?
2019年4月、山浦の入社から10年以上が経ちました。現在は、ライヴ事業本部の中にある「シアター制作グループ」を率いています。グループには13人が所属し、ストレートプレイと言われる一般的な演劇からミュージカルまで、当初黒岩が語っていた『幅広い』舞台のプロデュースを行っています。業務の幅は広く、山浦の多様な経験が活きる仕事です。
山浦「シアター制作グループの仕事は多岐にわたります。まず、どんな作品をやるか考えて、演出家に依頼し、演者をキャスティングしたり、制作会社と協力して舞台を整えたり。そして、公演にまつわるイベントやライヴの制作もさせていただいています。最近では、リハーサルスタジオの運営も始めました。
ライヴ事業本部では、音楽のライヴも手掛けていますが、舞台のつくり方はまったく違います。お客様にチケットを買って来ていただくというビジネスモデルは一緒ですけどね」
舞台ならではの苦労を味わいながらも、山浦のグループが手掛ける数々の舞台は、多くのお客様に楽しんでいただいています。いまやエイベックスを支える事業のひとつですが、ここに至るまでは険しい道のりでした。
山浦「いまでこそ、エイベックスが演劇やミュージカルもやっていると少しずつ認識されるようになりましたが、私が入社したころは、『ごあいさつに行かせてください』ってアポを取ろうとすると『スポンサーしてくれるの?』と勘違いされることも多かったです。
黒岩(現社長)の『舞台業界で認められるよう多くの演目をこなし、さまざまなジャンルのものを手掛けていく』という大前提のもとに行っている舞台事業では、エイベックスが長きにわたり積み上げて来たブランド力に頼りきりでは意味がないと考えます。
もちろん、エイベックスの看板を背負ってますし、そのブランド力・存在感は大きなメリットとして事業を行っています。ただ、どういう作品をつくるのか、どういう人脈を活用するのかという“個人の力”も大いに試されるんです。 事業規模が拡大した今になっても、その考えは変わりません。
うちのメンバーにも『エイベックスのブランドに「頼り切らない」キャリアを積みなさい。どこでも食べていけるようになったほうが絶対に強い』と言っています。
何よりも若い人に、いち早くプロデューサーとして自立してほしいんです。最初は誰しもが未経験ですし、年齢や経験なんて関係ないと思います。『こういうことやりたい!』『こういうプロデュースしたい!』という想いを持って入ってきたのなら、ずっと誰かの下で働いていてもおもしろいはずがないんです。
私が劇団四季時代に浅利さんに想いをアウトプットし続けてきたように、若い人も早く自分がやりたいことを経験してもらいたいですね」
だからこそ、山浦のグループでは自分のノウハウや人脈を同じグループの社員に共有することを惜しみません。
山浦「芸能の世界は人とのつながりが一番重要です。その人脈も、僕はすべて渡し、ほかの人もそうしています。それぞれが独立した人材になってくれれば、むしろ、互いに補い合えるようになるはずです」
シアター制作グループを単なる組織にするのではなく、独立したプロデューサーの集団にしたいと山浦は話します。その考えが、山浦が黒岩が語った言葉でエイベックスに感じた「挑戦する自由さ」を保たせているのかもしれません。少なくとも、ブランドに依存しすぎない山浦は、入社から10年以上が経ったいまも、エイベックスを挑戦の舞台としています。
関連記事

©︎avex