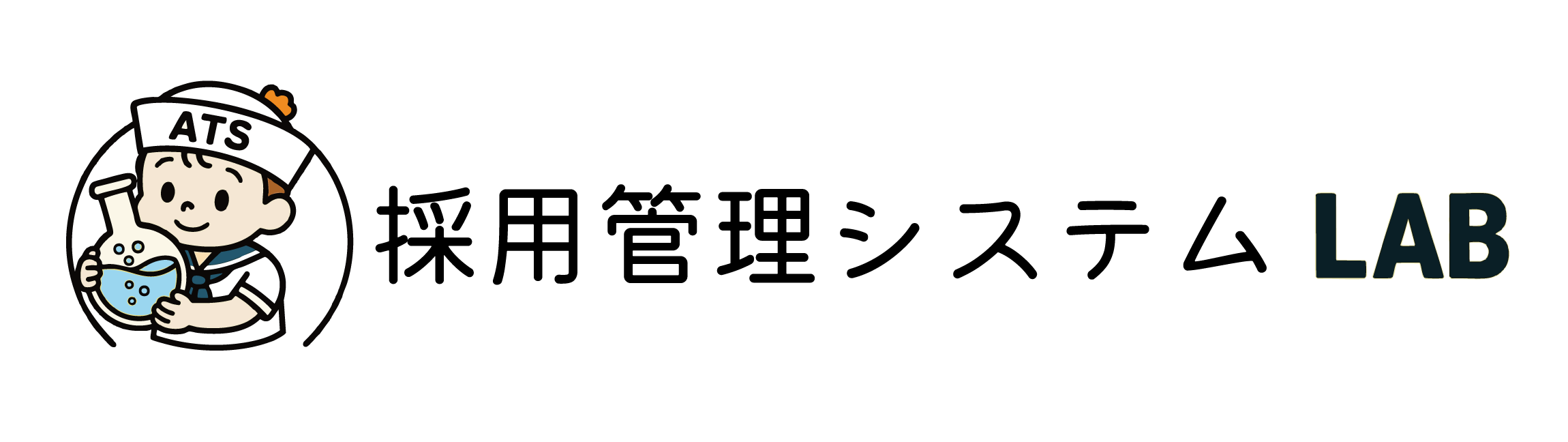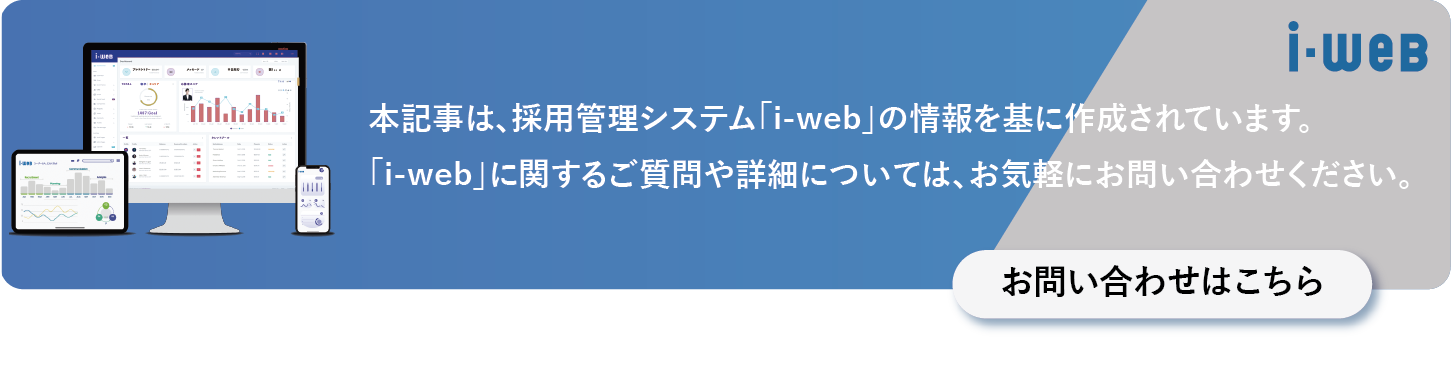一次通過後の“個別フォロー”を回す
――面談申込・電話連絡・専用日程・記録の設計
一次選考通過後は、応募者ごとの不安や関心に応じた個別フォローが鍵になります。
ATS(採用管理システム)では、社員面談の申込〜実施、電話での案内と結果記録、専用日程のその場作成、フォロー履歴の一元管理まで、同じ基盤で回せます。
本記事では、一次通過者フォローの手順を、運用フローとして並べ替えながら解説します。

1.社員面談を“画面内で完結”:申込み→マッチング→オンライン実施
通過者フォローとして、出身校や希望職種等に応じて先輩社員の面談を案内できます。応募者はマイページ上で面談したい社員を選択して申込み、日程が合えば同じ画面でオンライン面談を実施。
ライブセミナーのフォロー施策(若手〜管理職パネル等)はリアルタイムの質疑が強みです。一方、オンデマンド配信はいつでも何度でも視聴できるのが利点。ライブセミナーでは、オンデマンドの弱点(視聴時の疑問に即応できない)を補うために、CMS(Contents Management System)で動画インデックスページやFAQページを用意したり、視聴後アンケート→後日コンテンツ化で埋めることができます。
2. 個別連絡の要:アウトバウンドコール、専用日程作成、メッセージ、評価履歴
分散しがちな電話→専用日程作成→確定通知→履歴といった作業を、採用管理システム上で一連の流れで設計することが重要です。
個別連絡の例
-
アウトバウンドコール:対象の一覧から発信→結果記録まで行え、マッチすればそのまま日程確定に進めます。
-
専用日程作成:事前に枠を作っていなくても、通話中にその場で日程登録→通知まで完結。個別調整が前提の場面に向きます。
-
トークメッセージ:マイページ内の双方向メッセージで、合格者へのフォローや連絡事項を画面内で行えます。
-
評価履歴の記録:面談1回目/2回目…のようにフォローの実施履歴を残せます。誰が誰に何を実施したかをチームで共有しやすくなります。
3. 当てどころを決める:アクセス回数とコンテンツ閲覧の有無
フォローの優先順位は、行動データを手掛かりにします。
面談の誘導、専用日程の打鍵、メッセージの再配信など、限られた時間を“効く”相手に投下するための基準として、アクセス回数と閲覧有無は扱いやすい指標です。
行動データの例
-
アクセス回数が少ない応募者には、まずメッセージ(合否・詳細)の再確認を促し、次の行動を明示
-
アクセスは多いが、特定コンテンツを見ていない応募者には、該当コンテンツの案内を行い、不安の所在に合わせて補足。
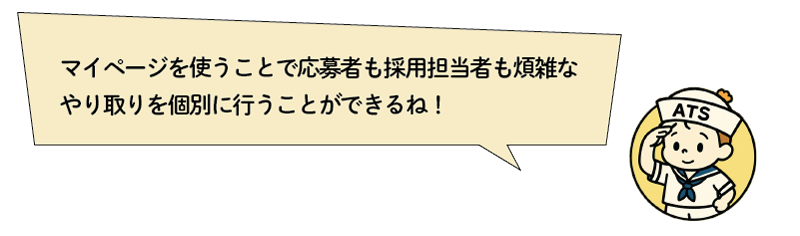
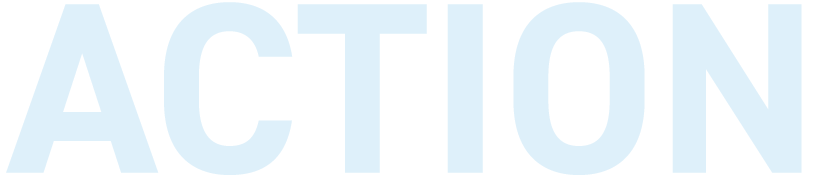
採用管理システムを選ぶなら…
採用管理システムを選定する際には、以下のポイントを確認すると良いでしょう。
CHECK!
・ 社員面談の申込〜実施をマイページ内で完結、ライブとオンデマンドを補完運用ができるか
・アウトバウンドコール→専用日程作成→通知→履歴を同一基盤で連鎖的に設計できるか
・トークメッセージでフォロー連絡を画面内に集約ができるか
・評価履歴でフォローの実施状況を共有し、漏れなどを防止が可能か
・アクセス回数/閲覧有無でフォローの優先順位と当てどころを決定ができるか

© Humanage,Inc.