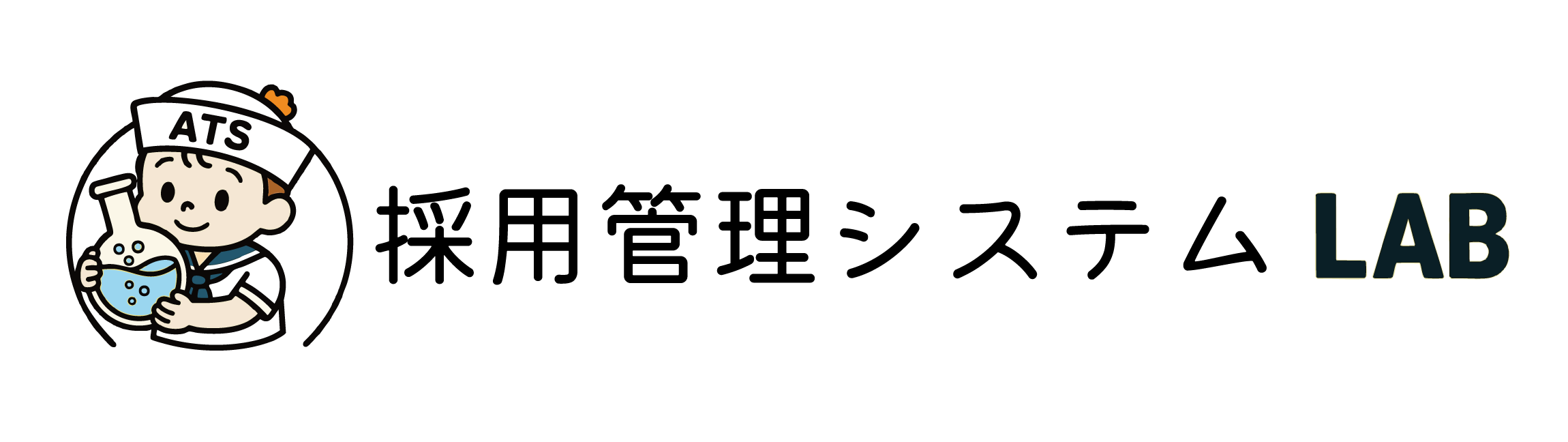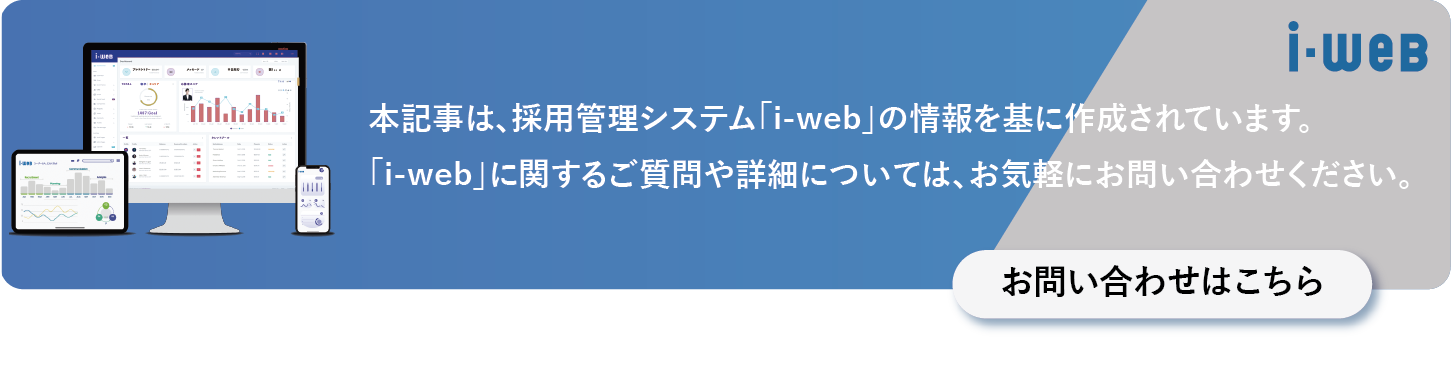書類選考をそろえる
――PDFセット・評価入力・検索設計の基本
提出書類が集まると、情報の置き場所や評価の手順がばらつきがちです。
本記事では、ATS(採用管理システム)のPDFセット/クイックアップロード/評価入力、そして専用ビュー(面接支援モデル)までを使って、書類選考を落ち着いて進めるための基本線をまとめます。「どこを見ればよいか」「どの順で進めるか」をそろえると、担当者が増えても運用が崩れにくくなります。

1. 材料を一箇所にまとめる:PDFセットとデータ取り込み
二次以降の選考では、エントリーシート/適性検査結果/成績証明書/研究概要/履歴書/自己PR/アンケートなど複数の資料を参照します。
PDFセットを使うと、必要書類を一つにまとめて出力できます。応募者がマイページからアップしたPDFに加え、紙で回収した資料をスキャンして格納しておけば、セット対象に含められます(Zip一括やヘッダー用紙を使った取り込みにも対応)。
さらにクイックアップロードで、たとえばインターン評価や連携していない適性検査の数値をCSVで一括登録しておけば、管理画面上で横断参照できます。まず「材料が一箇所にある」状態を作ることが、評価作業の前提になります。
2. 評価入力を“自社の型”に:設問設計と割り当て
応募者一覧の評価ボタンから、5段階評価・合否(合格/不合格/保留)・コメントなどを自社の設問で入力できます。
表示対象はグループ機能で制御でき、選考官A・B・Cに見るべき候補者だけを割り当て可能です。
検索項目の組み合わせで、たとえば部門別/希望順位/文字数/コンテンツ閲覧有無といった条件を作り、確認順の優先度をつけて進められます。
一次は人事で広く確認し、判断が揺れる案件のみ“保留”で抽出→部門へ回すといった運び方にすると、読み直しや差し戻しが減り、全体のスピードが落ちにくくなります。
評価基準や注意事項は画面のメッセージ欄に記載しておくと、期中の基準ブレを抑えられます。
3. 専用ビューでまとめて進める:面接支援モデルの使い方
選考官が専用マイページに直接ログインし、一覧で評価入力/PDF一括出力/コメントができる面接支援モデル(オプション)もあります。
ここでは検索項目のカスタマイズや一括入力が柔軟で、部門が多いケースでも操作が単純化します。
例:「研究職から優先」「保留者だけ先に確認」など、検索で“今見る束”を作って一気に入力。自分が合格/不合格/保留を何名出したかも一覧で確認でき、配分の偏りに気づきやすくなります。
また、PDFセットの一括出力が画面内で完結するため、個別メール配布やフォルダ分けといった周辺作業が減ります。
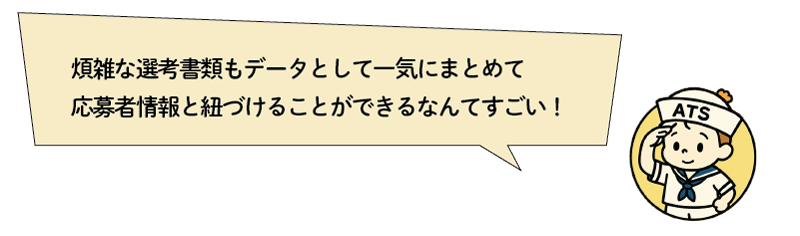
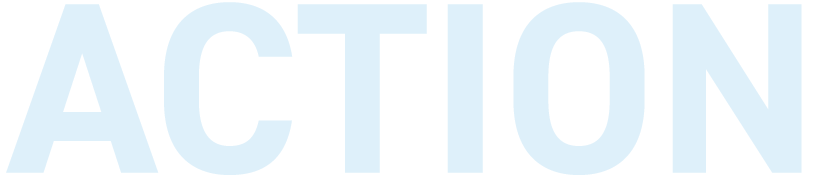
採用管理システムを選ぶなら…
採用管理システムを選定する際には、以下のポイントを確認すると良いでしょう。
CHECK!
・PDFセットで必要書類をひとまとめにでき、スキャン取り込みも一元化できること
・クイックアップロードで外部指標(インターン評価・非連携適性など)をCSV一括登録できること
・管理画面の評価入力が自社設問で設計でき、グループ割り当てで候補者の見せ方を制御できること
・専用ビュー(面接支援モデル)でカスタム検索/一括入力/PDF一括出力まで完結できること
・保留抽出→部門確認など、検索設計で“確認順”を運用に落とし込めること

© Humanage,Inc.