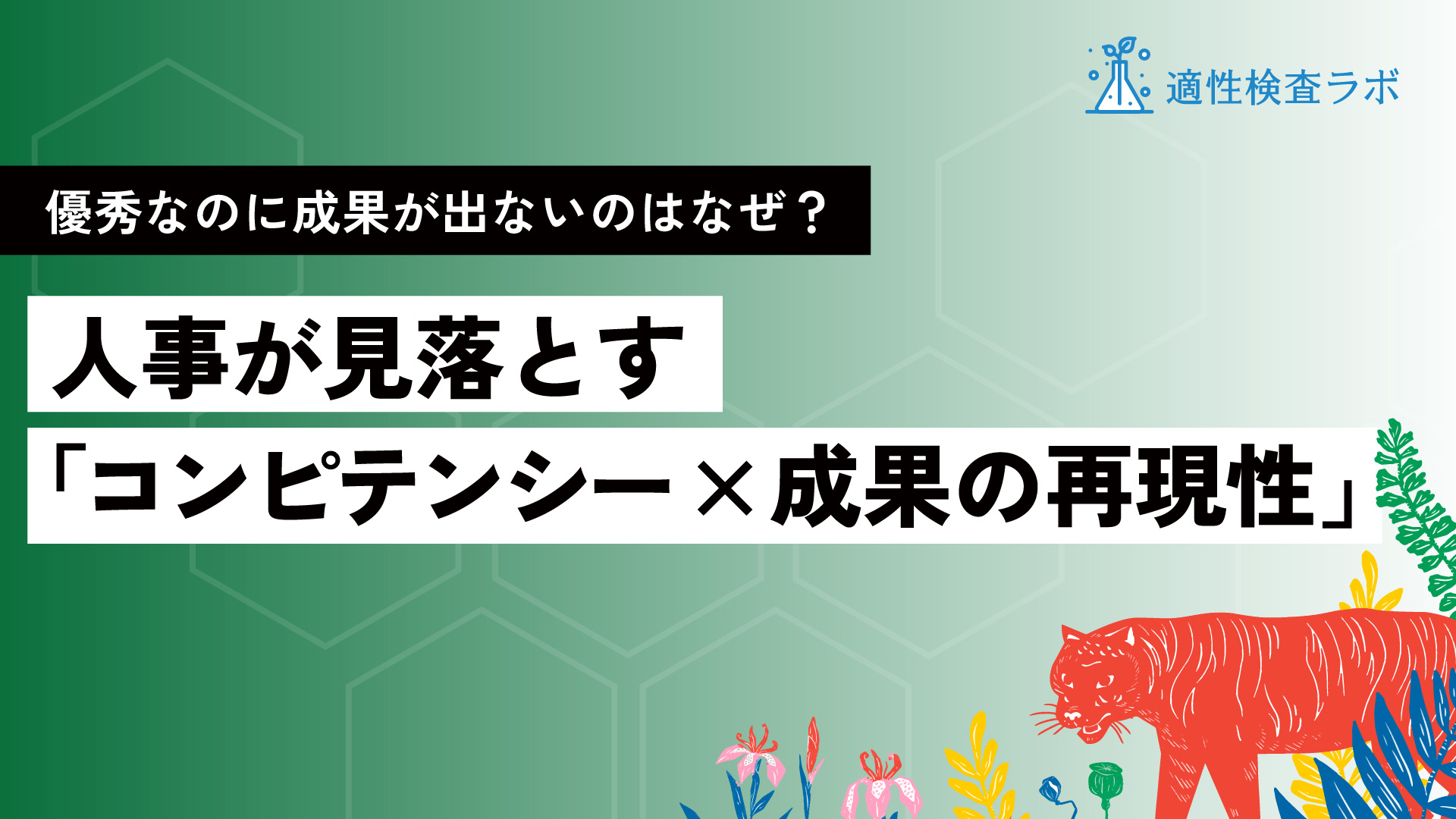
2025.11.14
優秀なのに成果が出ないのはなぜ? 人事が見落とす「コンピテンシー×成果の再現性」
はじめに
「この人、優秀なはずなのに、なぜ成果が出ないのか?」
「ポテンシャルはあるのに、思ったように育たない…」
そんな疑問を、採用や育成の現場で感じたことはありませんか?
成果主義が広がる中で、「どうやって成果を出したのか」という行動の中身が見えづらくなり、人材の本当の価値や将来性を見極めることが難しくなっています。
人的資本経営が求められる今、必要なのは「再現できる成果」を生む力=コンピテンシーという視点です。
本記事では、人事が“未来の成果”を見抜くために押さえるべき考え方と、その評価手法について解説します。
INDEX
1. 成果偏重の人事制度が、人材育成を妨げている
2. コンピテンシーとは何か?──従来の能力評価との決定的な違い
3. 評価の逆転現象──「優秀」なのに成果が出ない?
4. なぜコンピテンシーは人材投資に必要なのか
5. 昇進・登用で失敗する会社の共通点
6. 適性検査で「未来の成果」を見抜く
サービス紹介
1. 成果偏重の人事制度が、人材育成を妨げている
1-1. 成果に応じた報酬制度は本当にモチベーションを高めるか?
多くの企業が成果主義を導入する際に期待する効果は「優秀な人のやる気を高め、生産性を上げる」ことです。
しかし現実では、成果に応じた報酬制度(インセンティブ・昇給・評価ランク差)だけで社員の主体性が高まり、成果創出が加速したケースは多くありません。
なぜなら報酬制度は、人が成果を出した後に還元される仕組みであり、成果を出す前の行動を強化・誘発する仕組みではないからです。
つまり、「頑張ったら報われる」という制度設計は、“モチベーションを押し上げる装置”ではなく、“不満を抑える装置”にすぎないのです。
採用担当・人事が本来着目すべきは、
- どうすれば成果を出す人材が増えるのか
- どうすれば成果を生み出す行動が社内で再現されるのか
という、成果創出のメカニズムそのものです。
1-2. 報酬だけでは人は動かない──衛生要因と動機づけ要因
心理学では、人の仕事意欲を構成する要素は2つに分けられます。
| 種類 | 役割 | 具体例 |
|---|---|---|
| 衛生要因 | ないと不満になるが、あるから頑張るわけではない | 報酬、評価制度、労働環境、福利厚生 |
| 動機づけ要因 | あることで自発性や成果意欲が高まる | 仕事の達成感、自己成長、役割への納得、成果実感 |
多くの企業が注力してきたのは衛生要因(=報酬・評価制度)でした。
しかし報酬は“やる気を失わせない装置”ではあっても、“やる気を生み出すエンジン”にはなりません。
必要なのは、
- 成果に直結する行動を引き出す仕組み
- 行動変容や成長につながる投資(育成・抜擢・配置・フィードバック)
そしてその投資判断の基準として必要になるのが、コンピテンシーです。
1-3. 「人的資本経営」の時代に求められるのは“人材への投資”
2020年以降、日本企業の人材戦略の中心は「成果評価」から「人的資本経営」へと移行しました。
人的資本経営の要点は次の3つです。
- 人材をコストではなく投資対象と捉える
- 投資のリターン(成果)を再現性で測る
- “成果を出せる能力”に投資する
特に3つ目が重要です。
単に優秀な人材に投資するのではなく、“成果につながる能力を持つ人材”に投資する必要があります。
この「成果につながる能力」を見極める基準こそが、コンピテンシーです。

2. コンピテンシーとは何か?──従来の能力評価との決定的な違い
2-1. コンピテンシー=成果につながる行動特性
コンピテンシーとは「成果を生み出す行動の特性」です。
従来の能力評価は、
- 知識があるか?
- スキルがあるか?
- 優秀か?
という“保有前提の評価”でした。
一方でコンピテンシー評価は、
- その能力は成果を生んでいるか?
- その行動は再現できるか?
- 環境が変わっても成果につながるか?
という“成果起点の評価”です。
つまり持っているかどうかではなく、使えているか、結果につながっているかを判断軸とします。
2-2. 優秀でも成果が出せない人がいる理由
採用現場でよくある誤解が「優秀=成果を出せる」です。
実際には、
- TOEICが高得点でも英語で交渉できない
- 論理的でも人を動かせない
- 分析力は高いのに意思決定できない
- 専門知識が豊富なのに顧客価値に変換できない
といったケースは珍しくありません。
これは能力そのものが不足しているのではなく、成果につながる形で能力を“発揮・活用・行動化”できていないことが原因です。
つまり見極めるべきは「能力の大きさ」ではなく「能力の使い方」です。
2-3. 評価すべきは“保有能力”ではなく“活用された能力”
成果を生み出す人材の共通点は、
✅ 持っている能力を
✅ 目的に沿って
✅ 行動レベルで発揮し
✅ 成果につなげている
このプロセスを再現できることです。
反対に成果が出ない人材は、
- 知識があるのに行動に変換されない
- 成功がたまたま環境や運によるもの
- 本人の工夫や意思決定が成果創出に寄与していない
という特徴があります。
企業が採用や登用で測るべきは、成果の大きさではなく「成果を生み出す行動の再現性」です。
そしてそれを定量的に可視化する最も有効な方法が、適性検査を用いたコンピテンシーの測定なのです。

3. 評価の逆転現象──「優秀」なのに成果が出ない?
3-1. 高学歴・高スキルの人が組織で苦戦する理由
現場で成果を出せずに苦しむ人材の中には、いわゆる“優秀”とされる経歴の持ち主が少なくありません。
たとえば、
- 東大やハーバードを卒業した学歴エリート
- 各種資格やMBAなどを保有する専門家
- 高いテストスコアや論理力を持つ人材
こうした人材でも、実際の仕事では「なぜか期待外れ」に終わるケースがあります。
これは、能力自体が劣っているのではなく、その能力が行動に活かされず、成果に還元されていないからです。
つまり、“保有する力”と“成果につながる力”の間には、大きなギャップがあるということです。
3-2. 「知識の剥製化」が起こる会社の特徴
「人材の博物館」とも言えるような会社があります。高学歴・高スキルの人材を数多く採用し、立派な肩書きや資格を揃えている。にもかかわらず、業績が上がらない。こうした会社に共通するのが、知識を飾って満足してしまう風土です。
これは「知識の剥製化」とも呼べる現象です。
- 専門知識はあるが、使わない(=使えない)
- 過去の実績はあるが、再現しようとしない
- 行動せず、存在感だけで評価されてしまう
このような環境では、人材は持っている能力を行動に変換せず、“評価されること”がゴールになってしまいます。結果的に、能力は会社にとっても本人にとっても、死蔵資産となってしまうのです。
3-3. 行動に還元されない能力は“評価ゼロ”
能力には2つの種類があります。
- 頭の中にある能力(知識・理解・スキル)
- 行動に還元された能力(実践・応用・改善)
いくら1を持っていても、2に変換されなければ成果には結びつきません。逆に、知識が少なくても、それを確実に行動に移し、小さくても成果を上げ続ける人の方が、コンピテンシーが高い人材です。
重要なのは、「どんな能力を持っているか」ではなく、「その能力をどう使っているか」。
言い換えると、“行動の再現性”と“成果とのつながり”がない能力には、投資価値はないということです。

4. なぜコンピテンシーは人材投資に必要なのか
4-1. 投資価値は「未来の成果」で決まる
人的資本経営の考え方では、人材を「コスト」ではなく「投資対象」として捉えます。投資という以上、そのリターンは「未来の成果」で判断されなければなりません。
ここで重要なのが、「未来の成果はまだ発生していない」という事実です。
つまり、実績ではなく“将来生み出される成果”を、今の時点で予測し、評価する必要があるのです。
この“未来の成果”を測るための指標として活用されるのが、コンピテンシーです。
4-2. 市場価値のある人材は“将来の再現性”で見極める
市場価値が高い人材とは、環境や組織が変わっても成果を出し続けられる人材です。
つまり、成果の再現性があることが重要です。
一方で、以下のような成果は「たまたま」である可能性があり、再現性が乏しいと言えます。
- 運や環境に助けられた成果
- 前任者の努力の“果実”を偶然受け取っただけの成果
- キーパーソンとの私的なつながりによって得られた成果
このような再現性のない成果をもとにした評価・登用は、組織の競争力を下げる原因になります。
再現性のある成果=自らの行動と判断によって生み出された成果を見抜く視点が、コンピテンシー評価に求められます。
4-3. 成果主義だけでは見抜けない「再現力」という視点
従来の成果主義では、「どれだけ数字を上げたか」という結果のみが評価の軸でした。
しかし、この評価軸では“たまたま”成果が出た人と、“再現可能なスキル”で成果を出した人の違いを見抜けません。
たとえば、以下のような問いが人事には必要です。
- その成果は、次も再現できるか?
- その行動は他の人にも展開できるか?
- 環境が変わっても応用できる力があるか?
成果主義に「再現性」の視点を加えることで、初めて「本当に投資すべき人材」が浮き彫りになります。
その見極めのための評価軸が、まさにコンピテンシーなのです。
5. 昇進・登用で失敗する会社の共通点
5-1. 成果だけを見て昇進させると組織は腐る
「数字を出しているから昇進」は、いまだに多くの企業で行われている評価手法です。確かに、成果が出ているという事実は重要です。しかし、“その成果はどうやって生み出されたのか”という視点がなければ、重大な見落としが起きます。
たとえば、環境や前任者の貢献、他人のサポートなど「本人のコンピテンシーとは無関係な要因」による成果であった場合、それは再現性がありません。そのような人物を昇進させると、組織に「再現できない人が評価される」空気が広がり、部下のモラールは大きく低下します。
昇進・登用は組織における最大のメッセージです。誤った人材を登用すれば、組織文化そのものが腐敗していきます。
5-2. なぜ賢そうな人が早く昇進しがちなのか
よくあるのが、「賢そうに見える人」が早期に昇進するケースです。新入社員研修で積極的に発言し、論理的に話す。確かに優秀に見えますし、実際に知識やスキルも高い人もいるでしょう。
しかし、その後のキャリアで見えてくるのは、「賢く見えただけ」の人材が、実は成果を自らの力で再現できないケースが多いという事実です。
このような人は、初期の評価が高いため、重要な顧客やプロジェクトを任され、環境に恵まれた中で成果を上げます。その結果、さらに評価が高まり、早期昇進につながる──というサイクルが形成されます。
問題は、その人自身がなぜ成果が出たのかを理解していないという点です。「自分は優秀だから成果が出て当然」と思い込んでしまうと、部下指導やチームづくりに失敗し、組織のパフォーマンスを落とす原因になります。
5-3. 組織の“空気”を決めるのは上司のコンピテンシー
上司はチームの文化をつくります。その上司の思考・行動スタイルが、そのまま組織の“空気”として定着していくのです。
- 再現性のない成果で昇進した上司は、過去の武勇伝ばかり語る
- コンピテンシーが高い上司は、行動を言語化し、部下に再現させる
- 自分を正当化するだけの上司のもとでは、部下のモチベーションは続かない
モラール(士気)は、上司のコンピテンシーで決まるといっても過言ではありません。成果主義の副作用として、誤った登用が繰り返されると、組織全体が「成果は運次第」「忖度こそが出世への道」といった歪んだ風土になります。
組織の未来をつくるためには、「過去の成果」ではなく「行動の質と再現性」を評価軸とした昇進基準が必要です。

6. 適性検査で「未来の成果」を見抜く
6-1. 成果の再現性は測れる時代に
「成果の再現性なんて本当に測れるの?」という疑問を持つ方もいるかもしれません。かつてはそうでした。しかし、現在では、行動特性や意思決定パターン、思考スタイルなどを可視化する科学的な手法が整っています。
特に、コンピテンシーに着目した適性検査は、単なる性格診断や知的能力テストとは一線を画します。注目すべきは「どんな場面で、どんな行動をとる傾向があるか」という成果に直結する行動の予測が可能であるという点です。
6-2. 適性検査でわかる“成果につながる行動”とは
成果を出す人には、いくつかの共通する行動特性があります。
- 課題解決に向けた粘り強い取り組み
- 周囲を巻き込みながら進める協働性
- リスクに対する適切な判断力
- 自律的な目標設定と行動習慣
これらは、「性格がいい」「真面目で努力家」といった抽象的な人物評ではなく、具体的な行動スタイルとして測定可能です。
近年では、こうした行動特性を可視化するためのコンピテンシー型の適性検査が多くの企業で導入されています。これらの検査は、個人の思考傾向や行動のクセ、意思決定のパターンなどを数値化し、将来的にどのような成果を再現できる可能性があるのかを予測するための判断材料となります。
6-3. 採用・育成・登用のすべてで投資判断に活かせる
適性検査は、単に「合否を決めるツール」ではありません。適切に活用すれば、人材への投資判断を支える“経営のインフラ”になります。
- 採用:ポテンシャル人材の“伸びしろ”を見極める
- 育成:本人の強みと課題を見える化し、成長支援に活用
- 登用:再現性のある成果行動を持つ人材を選抜
特に、“過去の成果”ではなく“未来の再現可能な成果”に価値があるという視点を持てば、適性検査は最も合理的な人材評価ツールになります。
人的資本経営が求められる時代において、「成果につながる行動を見抜く力」こそが、企業の競争力を左右する鍵となるのです。


サービスの
ご紹介
TG-WEBのコンピテンシー適性検査(A8)は、「成果を生み出す行動特性=コンピテンシー」を測定できる検査です。
単なる性格や知的能力ではなく、「どのような思考や判断が、どのような行動として現れるか」を多面的に可視化します。
採用・育成・登用すべての場面で、“再現性のある成果”につながる行動を見極める判断材料として活用されています。
人的資本経営の観点からも、未来の成果を予測する評価手法として有効です。
ご関心がありましたら、ぜひご検討ください。

コンピテンシー適性検査 Another8

© Humanage,Inc.

