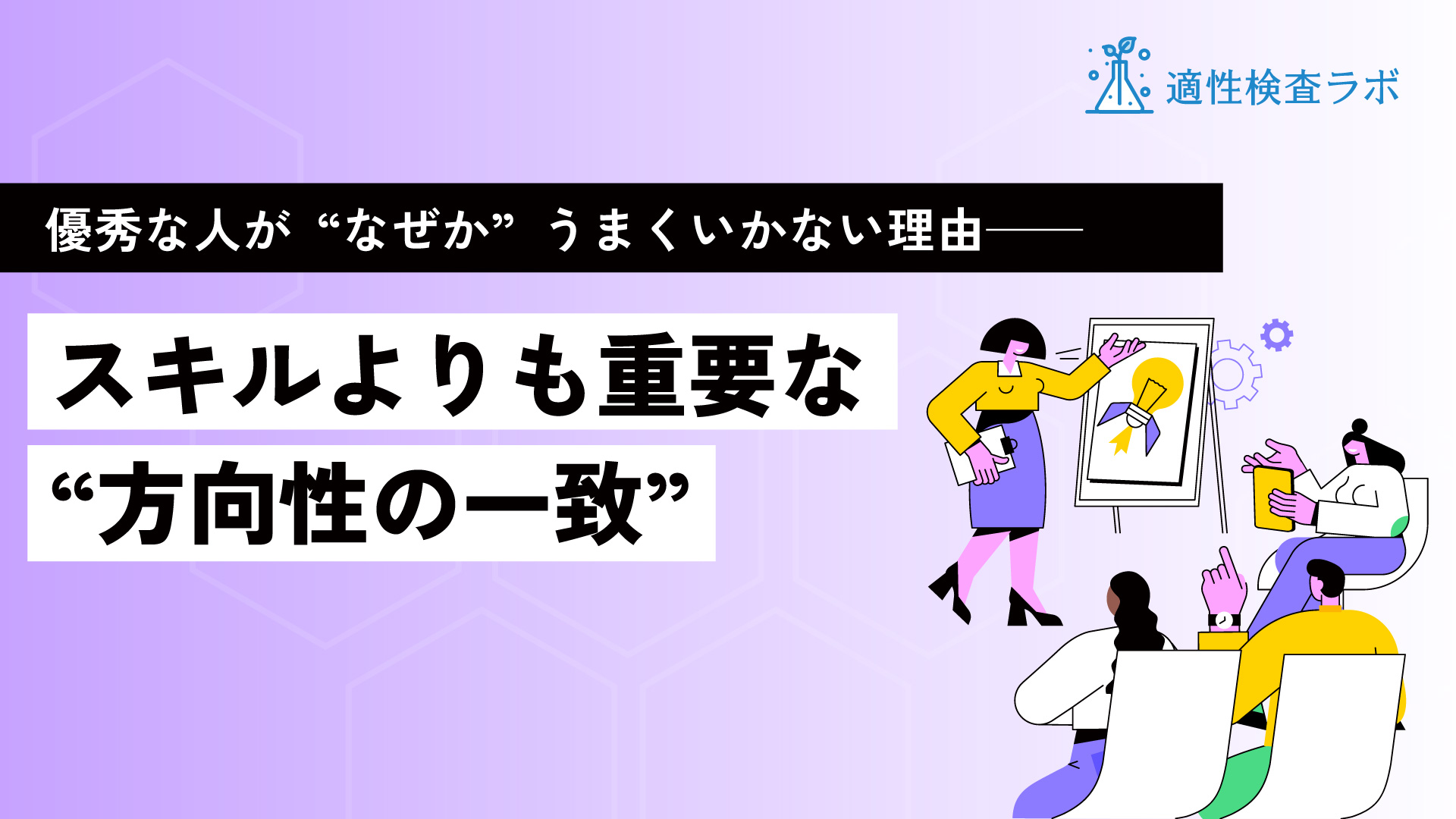
2025.11.07
優秀な人が“なぜか”うまくいかない理由──スキルよりも重要な“方向性の一致”
はじめに
学歴もスキルも申し分なく、面接でも印象は良かった。それなのに、入社後にうまく機能せず、期待した成果を出せない──。採用に携わる方であれば、一度はそんな経験をされたことがあるのではないでしょうか。
いま企業に求められているのは、「優秀な人」ではなく、「自社の価値観と同じ方向を向いて走れる人」。しかし、その“方向性の一致”は、履歴書や面接ではなかなか見抜けません。
本記事では、採用・育成・マネジメントの現場で起こる“ズレ”の正体をひもときながら、その見極め方について考えていきます。
ぜひ、日々の採用活動のヒントとしてお役立てください。
INDEX
1. 採用のミスマッチを生む最大の原因は「方向性の曖昧さ」
2. 目標管理制度が機能しない本当の理由
3. 成果を出せる組織は「目標のゴールイメージ」が明確
4. 「ルール依存型社員」と「自律型社員」の決定的な違い
5. セルフマネジメント時代の採用基準とは?
6. 人材競争力を高めるために、今こそ求められる適性検査
サービス紹介
1. 採用のミスマッチを生む最大の原因は「方向性の曖昧さ」
1-1. 企業のコアバリューは「絞り込み」のためにある
企業には理念や行動指針として「コアバリュー」を掲げているところが少なくありません。しかし、その多くが“理想の羅列”に留まり、採用現場での具体的な判断軸として機能していないのが現状です。
本来コアバリューとは、「私たちはこの方向に進む」という明確なベクトルを示すもの。すべての判断の拠り所であり、候補者がその方向に走れる人材かどうかを見極めるためのフィルターでもあります。
方向性が定まらないままに採用を進めると、「真面目だけど成果が出ない」「能力はあるがチームに馴染めない」といった“ミスマッチ人材”が組織に混在し、やがて生産性の低下や早期離職を招きます。
1-2. 判断がぶれるマネジャーが組織の混乱を生む
企業が掲げる価値観が曖昧なままだと、その価値観を元に部下を導くべきマネジャーの判断もブレていきます。現場のマネジメントにおいて、「これも大事」「あれも必要」と情報や指示が多すぎると、メンバーは何を優先すべきかわからず混乱します。
本来、マネジャーの役割は「絞り込むこと」。しかし日本企業では、あらゆる期待や目標を詰め込みすぎる傾向が強く、結果として何も突出しない、協働も進まない状態に陥ってしまうのです。
採用時点で「この人はこの方向で成果を出せる」という明確な見立てがなければ、その後の配属・育成も軸がブレ続けます。
1-3. 採用前に見るべきは「どの方向に走れる人か」
適性検査や面接を通じて、「この人は優秀かどうか」だけでなく、「この人は、当社の進みたい方向にエネルギーを使える人か」という視点を持つことが重要です。
例えば、自社のコアバリューが「スピード重視」「自己責任」「革新性」だとしたら、慎重に熟考し、周囲の同意を得てから動くタイプの人材はミスマッチになりやすいでしょう。
方向性を明確にし、それに合致した人物かを見極めるには、言語化された価値観 × 適性検査による行動特性の可視化が有効です。

2. 目標管理制度が機能しない本当の理由
2-1. 日本企業に根付く「性悪説マネジメント」
「この制度を悪用する社員がいるかもしれない」といった懸念から、あらかじめ想定される“ズル”を防ぐためにルールを増やす――。日本企業に根付くこの性悪説的な管理思想が、本来の目標管理の意義を損ねています。
制度やルールは、本来「全員が前向きに成果を出すための仕組み」であるべきです。しかし、あらゆる例外や抜け道に対処しようとすると、制度が複雑化し、現場の柔軟性は失われます。
今、必要なのは「最低限のルール+信頼と対話」で組織を運営する姿勢です。性善説に立ち、例外が発生したときはルールでなく指導で対応するマネジメント力が求められています。
2-2. 協力を拒む人材は制度の問題ではなく育成の問題
目標管理制度を導入すると、「それは自分の目標に入っていないのでやりません」と主張する社員が出ることがあります。しかし、それは制度そのもののせいではありません。その人材が、そもそも組織人として成熟していないという問題です。
制度に沿って成果を出そうとする人材と、制度を盾に自分の責任範囲を狭めようとする人材。その違いは育成や採用時点での見極めにかかっています。
適性検査によって、自己判断力・責任意識・協働性の特性を可視化しておけば、制度を活かせる人材かどうかを事前に判断することが可能です。
2-3. 管理よりも「対話」に力を割け
マネジメントの現場では、「ルールを徹底させること」よりも、「どうしたらこの人が自発的に動けるか」を引き出すコミュニケーションの方が、はるかに重要です。
特にZ世代・ミレニアル世代においては、「納得できる目的」や「自分らしさが発揮できる環境」が行動の原動力になります。目標管理も“上からの押し付け”ではなく、本人との対話で目標の意味を共に考えるプロセスに変えるべきです。
その対話を効果的にするためにも、適性検査の結果を基にしたフィードバックは大きな武器になります。表面的なスキルや過去の実績ではなく、内面的なモチベーションや価値観にアプローチすることで、より深い対話が可能になるのです。

3. 成果を出せる組織は「目標のゴールイメージ」が明確
3-1. 数値よりも「目指す状態」を描けるかがカギ
目標は「達成すべき数値」だけを指すものではありません。重要なのは、その先にある「望ましい成果の状態」=ゴールイメージをいかに具体的に描けるかです。
例えば、「売上10%アップ」という目標だけでは、営業現場は「とにかく売れればいい」と短期施策に走りがちです。しかし、「リピート率を高め、顧客の信頼を得る営業スタイルを確立する」というゴールイメージがあれば、行動の方向性はまったく変わってきます。
ゴールの「状態像」を共有することは、個々の判断を統一し、迷わず行動できる組織づくりの基盤になります。
3-2. 適性検査で「行動傾向」や「価値観の合致」を測る意味
組織が定めるゴールイメージと、社員個々の価値観や行動特性が大きくズレていれば、たとえスキルが高くても望む成果は得られません。だからこそ、適性検査によって「この人がどう動くか」「何を重視するか」を把握することが重要なのです。
たとえば、「リスクを取って挑戦する」文化の企業で、慎重で安定志向の人材を採用すれば、早々にミスマッチが起きてしまいます。
面接だけでは見抜けない“無意識の行動傾向”や“価値観の優先順位”を可視化することで、入社前にミスマッチを予防し、定着率とパフォーマンスを高めることができます。
3-3. OKRと1on1を支えるのは人材の“方向感覚”
現代の組織運営において、OKR(Objectives and Key Results)や1on1ミーティングは欠かせないツールとなりました。これらを機能させるために重要なのが、個々の社員が持つ「方向感覚」です。
OKRは「自分が向かうべき方向と成果」を自ら定める手法です。1on1は、その方向性について上司と確認・調整する時間です。もし社員が、自らの価値観や行動スタイルを理解していなければ、このプロセスは表面的なものになってしまいます。
適性検査を通じて「この人は何を大事にして動くのか」を把握することで、OKRの設定も1on1も、“納得と成長”を伴う本質的なマネジメントツールになります。
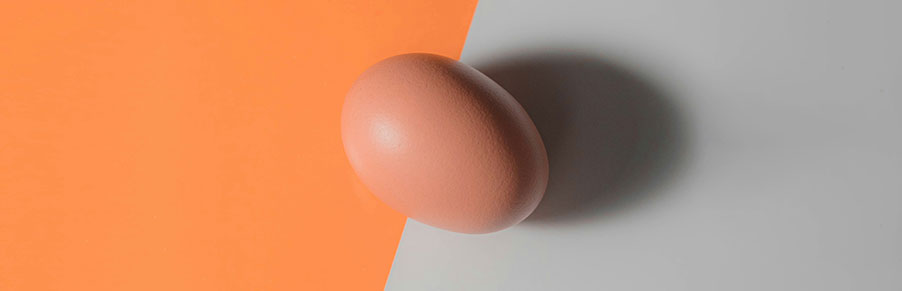
4. 「ルール依存型社員」と「自律型社員」の決定的な違い
4-1. 大人とは「自己判断+成果責任」を担える人
「上から言われないと動けない」「ルールがなければ判断できない」――そんな“ルール依存型”社員が増えているという声を、多くのマネジャーから聞きます。
しかし、ビジネスの世界で成果を出すには、自ら判断し、結果に責任を持つ姿勢=“大人の行動”が不可欠です。
大人と子供の違いは、単に年齢ではなく、「①自分で判断できること」「②その結果に責任を持てること」の2点に尽きます。指示待ちではなく、自分で考え、行動し、成果を振り返って改善できる人材が、今後の組織の競争力を支えていきます。
4-2. 自律型人材を採るなら、“小学生型”企業文化から脱却せよ
「何時に集合」「どこに立つ」「何を持つ」――まるで遠足のしおりのような細かすぎるルールに縛られた企業文化では、自律型人材は力を発揮できません。
むしろ、ルールが細かすぎることで「ここに書いてないのでやりません」という発言を引き出し、自律性を奪ってしまうリスクすらあります。
ルールではなく「目指す姿」「大切にする価値観」を軸にしたマネジメントへの転換が、自律型人材に選ばれ、活躍してもらうためには不可欠です。採用活動でも、自社が「自律を重んじる文化」であることを打ち出しましょう。
4-3. 適性検査で見える「マネジメント耐性」とは
実は、ルール依存型か自律型かは、適性検査である程度把握することができます。
具体的には、
- 「自己判断力」
- 「責任意識」
- 「他者への協力スタンス」
- 「曖昧な状況への対処力」
などの項目から、「この人はどのくらい指示を待つタイプか」「自ら考え動けるか」といったマネジメント耐性が見えてきます。
マネジャーが一人ひとりに細かく目を配るのが難しい今、採用や配置の段階でこの特性を把握しておくことで、人と組織のパフォーマンスを最大化することが可能です。
5. セルフマネジメント時代の採用基準とは?
5-1. 「言われたことはやる」人材では生き残れない
変化の激しい現代において、指示待ち型の人材はもはや通用しません。特にリモートワークやプロジェクト型の働き方が進む中、重要なのは「自ら考え、判断し、行動できる力」=セルフマネジメント力です。
「言われたことはしっかりやる人」は確かに真面目で誠実かもしれません。しかしそれだけでは、ビジネスのスピードや多様な課題に対応しきれないのです。
企業が今求めているのは、「何をすべきか」を自ら定め、「その結果に責任を持つ」自律型の人材。採用基準をこの観点で見直す必要があります。
5-2. コミットメントを軽視する組織は成長しない
「やります」「頑張ります」——その場では前向きな言葉も、あとから理由をつけて取り下げられては意味がありません。大切なのは、その人の“コミットの質”です。
本来、コミットメントとは「必ずやり遂げる」という強い意思表明です。にもかかわらず、日本企業では「とりあえず目標として書いてみた」という“正月目標”のような軽い扱いが多く見られます。
組織としてこの軽視を許してしまうと、「やるべきことが実行されない」「言葉と行動が一致しない」文化が定着してしまい、結果的に企業の成長が止まってしまいます。
5-3. 面接だけでは見抜けない「コミットの質」を適性検査で可視化する
コミットメントは、面接の場では美辞麗句で飾られてしまいがちです。「御社のために頑張ります」「御社の理念に共感しました」という言葉だけで、その人が本当にやり切れる人材かを見抜くのは困難です。
そこで役立つのが、適性検査による「行動傾向」と「責任意識」の可視化です。
以下のような項目が重要です:
- 困難な状況での粘り強さ
- プレッシャー下での意思決定スタイル
- 他者からの期待に対する応答性
これらを数値やプロフィールとして可視化することで、表面的な言葉ではなく、「この人は本当にコミットできるか」を事前に見極めることが可能になります。

6. 人材競争力を高めるために、今こそ求められる適性検査
6-1. 採用基準の曖昧さが中長期的な損失を生む
「いい人がいれば採りたい」「フィーリングが合えばOK」——このような曖昧な採用基準は、短期的には便利ですが、中長期的には組織にとって大きな損失を生みます。
価値観のズレ、行動傾向の不一致は、数ヶ月後にチームの生産性低下や早期離職として現れます。「なんとなく採った人材」のフォローに追われる管理職の疲弊は、今や多くの現場で深刻な課題です。
適性検査によって、採用基準を「見える化」し、「ブレない採用判断」を実現することが、組織の持続的な成長には不可欠です。
6-2. 自社の「コアベクトル」に合う人材かを見極めよ
企業にはそれぞれ、「どの方向を向いて走るべきか」という“コアベクトル(核となる価値観や行動指針)”があります。
これに合致しない人材は、どれだけスキルが高くても、組織内で浮いた存在になり、力を発揮できません。
適性検査は、候補者の「価値観」「モチベーションの源泉」「意思決定の軸」などを把握するのに有効です。スキルマッチだけでなく、カルチャーフィット=コアベクトルとの一致を重視した採用に切り替えることで、エンゲージメントも生産性も大きく向上します。
6-3. 最新の適性検査で、自律・共創・成果責任を可視化する
今、注目されているのは、「何ができるか」よりも、「どのように考え、どう行動するか」を測る行動特性型の適性検査です。
たとえば、以下のような特性を科学的に評価することができます:
- 自律性(自己判断・自己起動)
- 共創性(チームとの協調・巻き込み力)
- 成果責任志向(やり遂げる力、結果への意識)
これらは、面接では見えにくく、入社後の成果と密接に結びつく重要な資質です。
最新の適性検査を活用することで、採用の「未来予測」が可能になります。つまり、「この人は将来、自律的に動き、チームを巻き込み、成果に責任を持てるかどうか」を、定量的に判断できるのです。


サービスの
ご紹介
「言われたことだけやる人」ではなく、自ら考え、動き、成果に責任を持てる人材を採用したい——そんな企業におすすめなのが、TG-WEBシリーズのコンピテンシー適性検査『A8』です。A8は、本人の性格だけでなく、実際の仕事場面でどんな行動をとるか(行動特性)を9つの軸で詳しく測定。たとえば、「自分で考えて動けるか」「チームと協力できるか」「最後までやり切る力があるか」など、面接では見えにくい力を数値で把握できます。
自律的に成果を出せる人材を見極める手段として、『A8』の活用を検討してみてはいかがでしょうか?

コンピテンシー適性検査 Another8

© Humanage,Inc.

