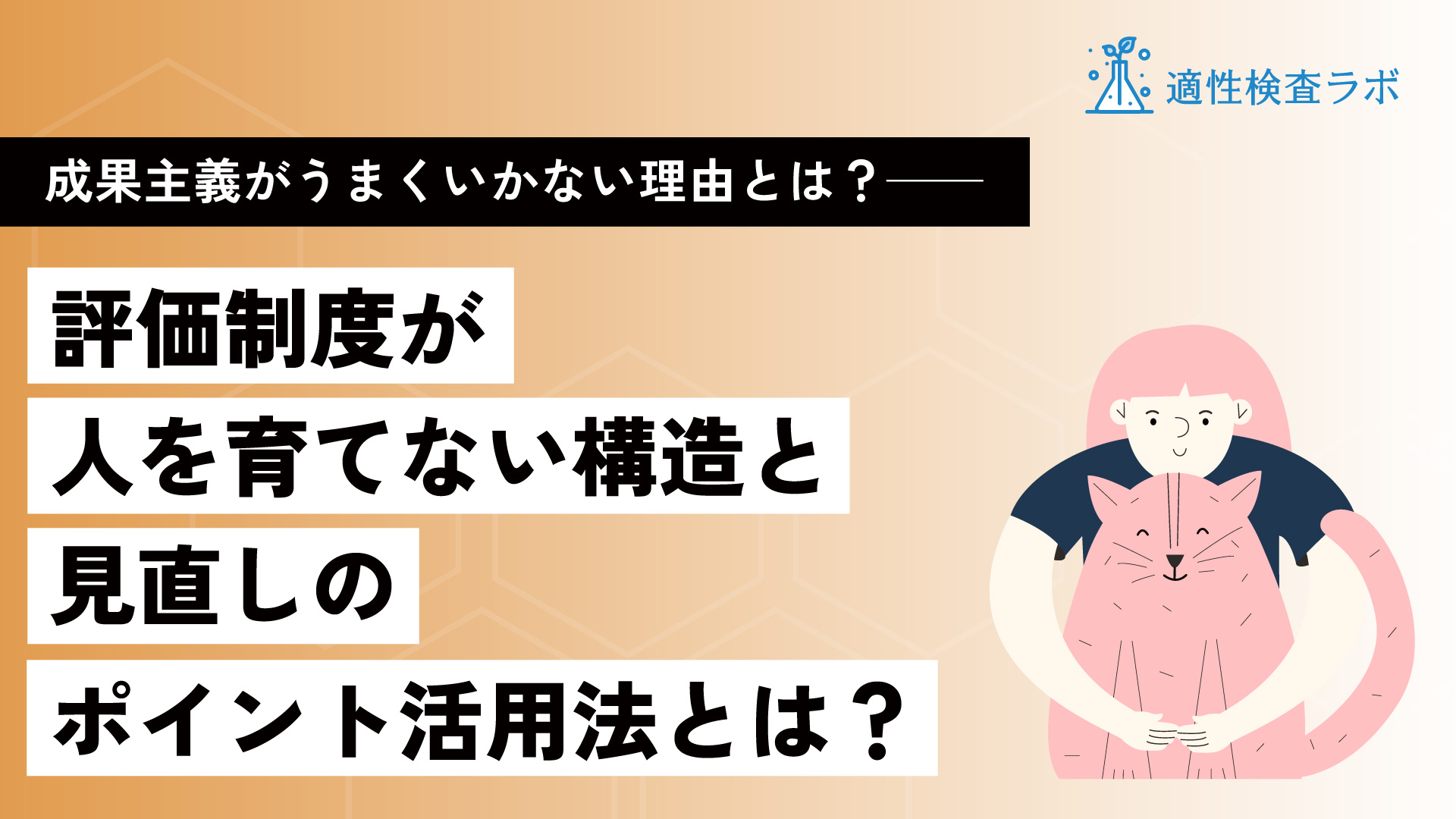
2025.10.31
成果主義がうまくいかない理由とは?──評価制度が人を育てない構造と見直しのポイント
はじめに
「成果を出した人が正しく評価される」
それは当然のようでいて、実際の現場ではなかなかうまくいかない──
そんなもどかしさを感じたことはありませんか?
制度を整えても、評価に納得感がない。
数字で見える成果ばかりが重視されて、チームの協力や挑戦が評価されにくい。
人を活かすはずの仕組みが、いつの間にか“人を疲弊させるもの”になってしまう。
働く人の価値観が多様化し、「どう成長できるか」「どんな経験が得られるか」が重視される時代。
いま必要なのは、“成果を評価する”だけでなく、“可能性を見抜き、育てる”マネジメントへのアップデートです。
本記事では、成果主義が抱える限界と、これからの人事に求められる視点の変化をわかりやすく解説していきます。
「人を見極め、活かす」ためのヒントとして、ぜひ最後までご覧ください。
INDEX
1. 成果主義はなぜうまくいかないのか
2. 報酬では動かない時代の動機づけ設計
3. 評価の軸を「個」から「共」に広げる
4. 育成と評価をつなげる「対話」の力
5. 「実績主義」から「可能性主義」へ
6. 人を見る精度を高めるには?
サービス紹介
1. 成果主義はなぜうまくいかないのか
1-1. 制度が目的化し、現場に混乱をもたらす
成果主義が機能しない大きな理由の一つは、「制度そのものが目的化してしまう」という構造的な問題です。多くの企業が、「公平で透明な評価制度を整えること」=「成果主義の導入成功」と捉えがちです。しかし、制度はあくまで「手段」であり、それを通じて何を実現したいのかが問われるべきです。
制度が形骸化すると、評価のための会議や書類作成に時間が奪われ、現場は疲弊します。肝心のマネジメントは形だけの運用に追われ、本来注力すべき人材育成や関係性の構築が後回しになります。制度を維持することが目的化した結果、「育成されない組織」「人が辞めていく職場」が生まれてしまうのです。
1-2. 数値偏重のマネジメントが組織力を損なう
評価の“見える化”を推進する過程で、多くの企業が陥るのが「数値偏重」のマネジメントです。KPIや業績指標はマネジメントの重要なツールですが、そこだけに焦点を当てると次のような弊害が生まれます。
- チーム内の協力より、個人の得点競争が優先される
- チャレンジよりも、確実な成果を追う保守的行動が増える
- 組織内でのナレッジ共有や後進育成が軽視される
短期成果に偏った評価は、長期的な組織力をむしろ削ぐ結果になりかねません。成果主義が組織全体のパフォーマンスを高めるどころか、「分断」や「萎縮」を生む原因になっているケースも見受けられます。
1-3. 成果主義が人を育てなくなった本当の理由
本来、成果主義は人を育て、組織の競争力を高める仕組みであるべきです。しかし現実には、「成果が出せない人をどう処遇するか」に焦点が移り、「人を活かす」よりも「選別して排除する」制度として運用されている場面が目立ちます。
さらに近年は、働き手の価値観も大きく変化しています。報酬や地位のためにがむしゃらに働く時代は終わり、自己成長や仕事の意味に重きを置く層が増えています。そうした中で、「成果を出せば報われる」だけの仕組みでは、もはや動機づけとして機能しません。
育成されるべきは「成果を出せる人」ではなく、「成果を出せるようになる人」です。成果主義がうまくいかない理由は、この本質的な視点を欠いたまま制度設計と運用がなされていることにあります。

2. 報酬では動かない時代の動機づけ設計
2-1. 金銭的な処遇が限界を迎える背景
かつては、「評価されて昇給する」ことが強いモチベーションとなり得ました。しかし今、金銭的な処遇だけで人を動かす時代は終わりを迎えています。
昇給・賞与といった報酬制度は、仕事の満足度を維持する「衛生要因」にはなり得ますが、仕事への主体的なエネルギー、すなわち内発的動機づけを引き出すには不十分です。
しかも、報酬には「慣れ」があります。一時的には満足感が得られても、それが常態化すれば刺激は失われ、やがて「もっと」を求めるようになります。報酬だけで人を惹きつけ、動かし続けるには、限界があるのです。
2-2. 自律性・つながり・成長感を育てる評価制度へ
人が持続的にやる気を持って働くには、「自己決定感」「周囲とのつながり」「成長実感」という3つの要素が必要だとする理論があります。これは「自己決定理論(Self-Determination Theory)」として、世界中の組織開発に応用されています。
- 自律性:自分の意志で選び、行動できているという感覚
- 有能感(成長感):自分ができるようになっている、役に立っているという実感
- 関係性:誰かとつながり、受け入れられているという安心感
評価制度は、これらの要素を支える仕組みでなければなりません。目標の押しつけや、減点式の評価ではなく、自ら目標を立て、振り返り、対話を通じて成長を感じられるプロセスが求められています。
2-3. モチベーションは「評価」ではなく「経験」から生まれる
「評価」は行為であり、「経験」は記憶に残るプロセスです。制度として評価を設ける以上、その運用が単なる点数づけで終わってしまえば、本人に何も残りません。
一方、上司との対話や、チームからのフィードバック、自分の行動を内省する時間が「経験」として蓄積されると、人は自らの働き方を自覚し、変えていくきっかけを得ることができます。
つまり、モチベーションは評価そのものではなく、「評価を通じて得られる経験」によって生まれます。そしてその経験が、内発的な動機づけとなり、持続的な成果につながるのです。

3. 評価の軸を「個」から「共」に広げる
3-1. 個人評価の限界と、チームワークの可視化
従来の成果主義は、個人の成果に焦点を当てることで、公平性や納得感を追求してきました。
しかし、現代の多くの業務は個人で完結せず、チームで協働することが前提です。特に複雑なプロジェクトやイノベーションが求められる場面では、個人単位の評価だけでは実態を正しく捉えることができません。
- チームメンバーをサポートした
- 他部署との連携を円滑に進めた
- 自分の成果を他人の学びに変換した
こうした貢献は、数字に現れにくいものの、組織全体の成果には欠かせません。個人の業績だけでなく「周囲への影響」や「組織への貢献」を評価軸に含める必要があります。
また、近年では「チームパフォーマンスの可視化」に向けた取り組みも増えており、コラボレーションの質を測るフィードバックやアンケート手法が活用され始めています。
3-2. 心理的安全性のある組織が成果を生む理由
近年の組織行動研究では、成果を上げるチームに共通する最大の要因は「心理的安全性」であることが、さまざまな調査や実証研究によって明らかになってきました。
心理的安全性とは、メンバーが安心して意見を述べたり、ミスや弱みを共有できる状態のことを指します。
このような安心感のある職場では、以下のような行動が自然に生まれやすくなります。
- 意見の違いが前向きな議論につながる
- 課題やミスが早期に共有され、学習機会に変わる
- 新しいアイデアが歓迎され、挑戦が促される
逆に、競争的な評価や成果偏重の風土では、自己保身や沈黙が支配し、イノベーションや協働が阻害されます。
組織が本当の力を発揮するためには、心理的安全性という“見えない土台”をどう築くかが極めて重要なのです。
3-3. 数値では測れない価値をどう評価するか
数値化はマネジメントにおいて強力なツールです。しかし同時に、“数値で測れるものしか評価されない”という錯覚を生む危険性も持ち合わせています。
- 他者に与えたポジティブな影響
- 周囲への支援や共感力
- 組織文化への適応・発信
これらは、明確なKPIには落とし込みづらい要素ですが、組織にとって極めて重要な「無形資産」です。
こうした価値を評価するには、定性的な観察、本人との対話、同僚からのフィードバックといった多面的な手法が求められます。
数値と非数値、定量と定性。どちらかに偏るのではなく、複数の視点をバランスよく取り入れる「ハイブリッド評価」が、これからの標準となるでしょう。

4. 育成と評価をつなげる「対話」の力
4-1. “査定”から“フィードバック”への転換
「評価=査定」という考え方は、評価を一方的なジャッジと捉える構造を生みます。そこには「評価する側(上司)」と「される側(部下)」という力の非対称性があり、対話が生まれにくくなります。
一方、評価を「成長のためのフィードバック」として再定義すると、関係性は一変します。
評価の場は、上下ではなく“対話”の場となり、部下自身が主体的に自分の成長や課題を捉えることが可能になります。
評価を受ける場を、自分の価値を再確認し、未来を考えるきっかけとする——
これが、本来の人材育成に資する評価のあり方です。
4-2. 自己理解と内省が行動変容を促す
行動を変えるには、まず「自分がどんな思考・行動のクセを持っているのか」に気づくことが必要です。
この“気づき”を引き出すために有効なのが、上司との継続的な対話や、振り返りの習慣です。
- 目標をどのように立てたのか
- その行動の背景にどんな考えがあったのか
- 自分の強み・弱みをどう捉えているか
これらを丁寧に掘り下げていくことで、評価は「通知表」ではなく「学びのきっかけ」に変わっていきます。
最近では、自己理解を促進するツールや適性診断を評価プロセスに組み込む企業も増えています。評価を内省の機会とする仕掛けを整えることで、“行動変容のサイクル”を自然と回していける環境が育ちます。
4-3. 上司・部下の関係性が評価制度の成否を決める
どれだけ制度設計を整えても、実際に評価を運用するのは「人」です。
そのため、評価制度の効果を左右するのは、制度そのものではなく、評価を行う上司と、受け止める部下との関係性です。
- 信頼関係があるか。
- 対話の量と質は確保されているか。
- フィードバックが一方通行になっていないか。
このような関係性の質が、評価を「納得できるプロセス」にするか、「単なる査定」にしてしまうかの分かれ目になります。
また、上司側の“人を見る力”や“対話スキル”の育成も重要です。マネージャーが「評価する立場」から「成長を支援するコーチ」へと意識を変えていくことが、これからの評価制度には求められます。
5. 「実績主義」から「可能性主義」へ
5-1. 実績ではなく「将来の伸びしろ」を見る視点
従来の人事評価は、「過去に何を達成したか」「どんな数字を残したか」といった実績ベースの評価が主流でした。これは短期的な処遇決定には有効ですが、将来の活躍を期待できる人材を見極めるには不十分です。
特に、若手や新たなチャレンジを始めた社員にとって、今すぐ目に見える成果を出すのは難しいもの。
しかしその中にこそ、変化への柔軟性や学習意欲、行動の兆しが見えていることがあります。
だからこそ、これからのマネジメントには「何を成し遂げたか」ではなく、「どれだけ伸びそうか」「どんな可能性を秘めているか」という視点が求められます。
評価とは、実績の清算ではなく、未来への投資判断であるべきなのです。
5-2. 処遇より“成長の機会”が人を動かす
処遇や報酬は、確かに働く上での大切な要素です。
しかしそれだけでは、人のエンゲージメントや主体性は持続しません。
特に今の時代、働く人々が最も求めているのは、「自分がどう成長できるか」「どんな経験を積めるか」というキャリアの可能性です。
たとえば──
- 失敗が許容され、挑戦できる環境がある
- 自分の強みが活かされる仕事に出会える
- 学びやフィードバックの機会が日常的にある
こうした“成長の機会”こそが、人の内発的なモチベーションを高め、長期的な貢献につながります。
企業が提供すべきなのは、「結果に応じた報酬」よりも、「可能性に応じた成長の場」なのです。
5-3. 長期視点で人を育てる組織が生き残る
目まぐるしく変化する時代において、即戦力や短期成果だけを求めるマネジメントは、かえってリスクになります。
イノベーションや変革の担い手は、多くの場合、最初から高い実績を持っていたわけではありません。
重要なのは、「育てることを前提とした組織設計」です。
成果が出ていなくても挑戦する人を信じ、支援し、対話を重ねていく。
こうした文化が、結果として「人が定着し、活躍し、組織の未来をつくっていく」ことにつながります。
つまり、“可能性主義”とは、単に優しいマネジメントではありません。
むしろ、長期的に人を活かし続ける「戦略としての育成」なのです。
この視点を持てるかどうかが、これからの組織の競争力を大きく分けていくことになるでしょう。

6. 人を見る精度を高めるには?
6-1. 一律の評価軸では見えない“その人らしさ”
多くの組織では、統一された評価シートや行動基準を用いて、社員を公平に評価しようとします。
このアプローチは「平等性」を担保するうえでは有効ですが、同時に、“その人らしさ”を見落とすリスクも孕んでいます。
たとえば──
- 数値に強い人もいれば、人を支えることに長けた人もいる
- 静かに成果を出す人もいれば、周囲を巻き込むタイプもいる
しかし一律の尺度では、「型にハマる人」ばかりが評価され、「異なる価値を持つ人」が見えにくくなります。
評価制度は、“平均化する道具”ではなく、「一人ひとりの強みを見つけ、活かす視点」で設計・運用されるべきです。
多様性が当たり前になった今、画一的な見方ではなく、多様な可能性に目を向ける柔軟性が、人を見る側にも求められています。
6-2. 直感や主観を超えて、人の特性を可視化する
「なんとなく頼りない」「安心感がある」「自信なさそう」──
こうした印象評価は、経験や直感に基づくものであり、マネジメントの現場でしばしば使われています。
もちろん、マネージャーの“目利き力”は貴重なスキルですが、それが主観のみに依存した評価になると、偏りや属人性を生みます。
結果として、本当の特性や強みが見えず、誤った判断をしてしまうリスクも高まります。
これを防ぐには、人の行動や思考の傾向を“見える化”する仕組みを取り入れることが有効です。
たとえば:
- 行動記録やフィードバックデータの蓄積
- 上司・同僚・本人による多面評価(360度評価)
- 適性検査やパーソナリティ診断による特性の把握
こうした手法により、「感じる評価」ではなく、「理解する評価」へと進化できます。
主観や印象を補完し、共通言語で人を語れる状態をつくることが、人を見る精度を確実に高める第一歩です。
6-3. 「思い込みの人事」から「根拠あるマネジメント」へ
人材マネジメントの現場には、今もなお“思い込み”や“勘”に頼った意思決定が存在します。
- 声が大きく発言が多い →「リーダー向き」
- ミスが目立つ →「ポテンシャルが低い」
- 寡黙で控えめ →「積極性に欠ける」
これらは、評価者側の経験や価値観に影響された無意識のバイアスであり、実際の特性や可能性を正しく反映しているとは限りません。
その結果、活かされるべき人材が埋もれ、期待されるべき場に届かない──そんな機会損失が起きてしまうのです。
だからこそ今求められるのは、「思い込みの人事」から、「根拠あるマネジメント」への転換です。
- 言語化された評価基準をもとに
- 客観的なデータやツールを活用し
- 多様な視点と合意形成を重ねながら
- 一人ひとりの可能性を見出す
このプロセスを重ねることで、組織は人を見る“再現性”と“公正性”を手に入れ、マネジメントの質を飛躍的に高めることができます。


サービスの
ご紹介
未来への投資型マネジメントを実現するには、「人の伸びしろ」を見抜く視点が欠かせません。
TG-WEB「A8」は、仕事で成果を出すための行動特性(コンピテンシー)を、科学的に測定・可視化する適性検査です。
性格や価値観だけでは見えない、「どう行動し、どう学ぶか」といった“伸びる力”に着目。採用や配属だけでなく、評価や育成の対話にも活用できます。
特に育成に対しては受検者本人との対話にも活かせる、本人向けフィードバックシートを標準で用意しています。
個を見極め、可能性を活かす人事の第一歩として、TG-WEB「A8」のご活用をご検討ください。

コンピテンシー適性検査 Another8

© Humanage,Inc.

