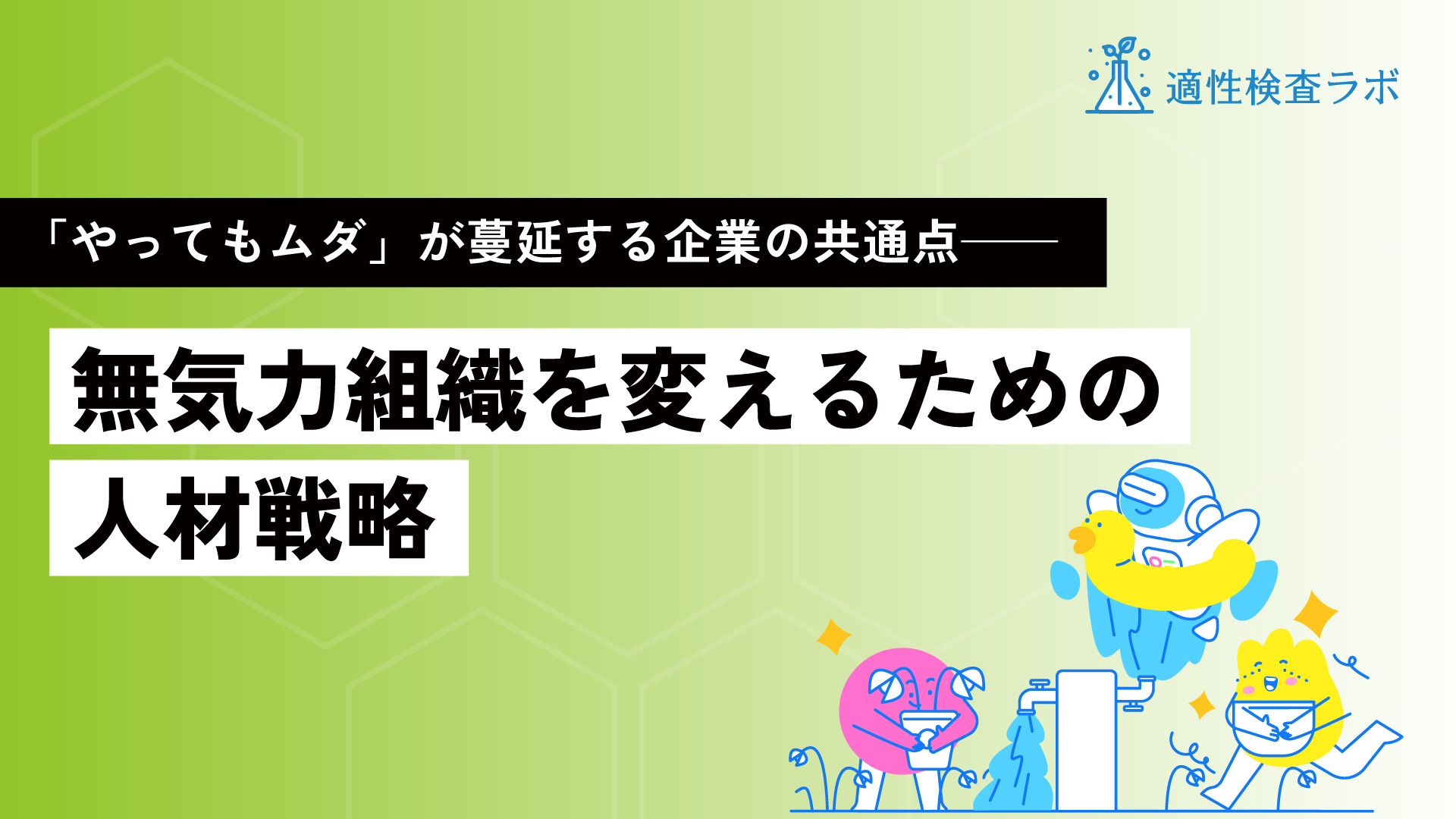
2025.10.24
「やってもムダ」が蔓延する企業の共通点──無気力組織を変えるための人材戦略
はじめに
「学生時代は積極的だったのに、入社して数年で静かになってしまう」
「優秀だけど、挑戦しようとしない」
そんな若手社員を見て、もどかしさを感じたことはありませんか?
採用や育成に力を入れても、現場で主体的に動く人材がなかなか育たない――。
その背景には、組織の構造や評価のあり方が影響している可能性があります。
本記事では、社員の意欲低下を招く要因や、人材の見極め・育成のポイントについて整理し、これからの採用・人材戦略に必要な視点をご紹介します。
人材の可能性をどう引き出すか、改めて一緒に考えてみませんか?
INDEX
1. 企業に広がる「やってもムダ」な空気感
2. 無気力組織に必要なのは、外からの刺激
3. なぜ「変化を起こす人材」が育たないのか
4. 成功する企業の人材戦略は両極型
5. 今求められるのは「価値を創れる人材」
6. 採用・育成の視点を“変化を起こす資質”にシフトする
サービス紹介
1. 企業に広がる「やってもムダ」な空気感
1-1. 社員が動かなくなる心理メカニズムとは
「どうせ言っても変わらない」「何をしても評価されない」――。
近年、職場にこうした空気が蔓延しているケースが少なくありません。意欲的だったはずの若手が、数年でおとなしくなり、提案も挑戦もしなくなる。こうした現象の裏には、“学習性無力感”と呼ばれる心理的な反応があります。
これは、努力しても結果が変わらない経験を繰り返すことで、「自分にはどうにもできない」と思い込んでしまう状態。一度この状態に陥ると、自分の意志で動くことすら避けるようになります。個人の問題というよりは、組織がそういう人を量産してしまう構造にこそ、本質的な課題があります。
1-2. 暗黙ルールが生む“見えない壁”
企業の中には、表向きには「自由に意見を」と言いながら、実際には“空気を読むこと”が強く求められる風土が根付いています。これがいわゆる「暗黙のルール」です。
表面上は歓迎される挑戦も、「今のやり方にケチをつけている」と受け取られたり、「若手が生意気だ」と捉えられたりすれば、その行動は評価されず、むしろマイナスになる場合もあります。
そうした見えない壁に何度もぶつかることで、社員は「動かない方が安全だ」と学習し、沈黙を選ぶようになります。これが、無気力組織の“静かな共通言語”となってしまうのです。
1-3. 年功序列が助長する思考停止
かつては長く働き続ければ昇進・昇給できる仕組みが、社員の安心感や忠誠心を支えていました。しかし、現在はビジネス環境が激変し、年数や在籍歴だけでは組織が回らなくなっています。
それでも年功序列的な評価制度が残っている企業では、若手がどれだけ成果を出しても正当に評価されない、逆にベテランは成果を出さなくてもポジションを保てるといった不公平感が生まれます。
この構造は、社員の「どうせ評価されない」「頑張っても損をする」という心理を強め、組織全体が思考停止に陥る原因となります。

2. 無気力組織に必要なのは、外からの刺激
2-1. 組織に活力をもたらす“別タイプ”の存在
沈滞した組織を変えるには、内部からの変革だけでは限界があります。重要なのは、外部から異なる価値観や行動原理を持つ人材を取り入れることです。
組織の論理に染まっていない人は、「なぜこのやり方なんですか?」「もっとこうできるのでは?」と素直に疑問を持ちます。その問いかけが、組織にとっての“気付き”や“刺激”になり、周囲に小さな波紋を広げていきます。
これが、変化の第一歩です。
2-2. 模範行動が与える組織的インパクト
一人の社員が、自分の意志で動き、変化を起こす姿を見せると、その影響は周囲に確実に波及します。
それは、トップダウンの指示とは異なり、「あの人がやっているなら、自分にもできるかもしれない」という前向きな模倣を生み出します。
このような模範行動の積み重ねは、無意識に広がる“諦めの空気”を少しずつ変えていきます。言葉で伝えるよりも、行動で示すことが何よりも強い説得力を持つのです。
2-3. 管理職やエース社員だけでは変えられない
多くの企業は「管理職が引っ張るべき」「優秀な中堅に期待」と考えますが、変革の担い手は必ずしもその層に限られません。
むしろ、組織の論理から距離のある若手や異分野出身者の方が、柔軟な発想で組織の固定観念を揺さぶる力を持っている場合があります。
組織に新しい風を吹き込むためには、「期待されている人」ではなく、「今は目立っていないが、異質な視点を持つ人材」にも光を当て、意図的に活躍の場をつくることが求められます。

3.なぜ「変化を起こす人材」が育たないのか
3-1. 単発的な競争に最適化された人材像
これまで多くの企業が行ってきた競争は、「他社より少し売れた」「営業手法がうまくいった」など、一時的・表面的な成果を競うものが中心でした。
このような環境では、既存の枠組みの中で成果を最大化する“応用力の高い人”が評価されてきました。逆に、根本から仕組みを変えようとする人や、新たなビジネスモデルを構想する人は、「余計なことをしている」と見なされがちでした。
結果として、組織全体が「与えられたルールの中で勝つ」ことに最適化され、“ルールそのものを変える”力が育ちにくい土壌になっているのです。
3-2. 本質的な競争力を測れない評価制度
多くの評価制度は、「目標達成率」や「売上数字」といった短期的で定量化しやすい指標に偏っています。確かにこれらは重要ですが、それだけでは新たな価値を創り出す力を正しく測ることはできません。
たとえば、将来の成長につながる地道な仕込みや、顧客に寄り添う新たな提案のような行動は、すぐには数字に現れません。にもかかわらず、「今期の数字」が唯一の判断基準となれば、変革を志す行動が評価の対象にならないという矛盾が生まれます。
これでは、挑戦する人材が「頑張るだけムダ」と感じてしまうのも無理はありません。
3-3. 成果主義の落とし穴
成果主義は本来、個人の努力や能力を正当に評価するための制度ですが、目先の成果だけを追い求める運用になってしまうと、むしろ組織の活力を奪う危険性があります。
特に問題となるのは、「自分だけが評価されればいい」という短期的・個人主義的な発想を助長する点です。これにより、チームでの協働や、長期的視点での価値創出が軽視されやすくなります。
さらに、評価されるのは“結果を出した人”であり、その裏で支えた人、仕組みを整えた人は見逃されがち。これでは、変化を支える多様な力が組織に残らなくなるのです。

4. 成功する企業の人材戦略は両極型
4-1. 完全マニュアル型 vs 自走型イノベーター
グローバルに目を向けると、生き残っている企業は大きく2つのタイプに分かれます。
ひとつは、業務を徹底的にマニュアル化・最適化し、誰がやっても高品質を再現できる仕組みを持つ企業。もうひとつは、個々の人材が自律的に判断し、次々と新たな価値を生み出す組織です。
前者は、高効率とスケーラビリティを武器にし、後者は柔軟性と革新性で勝負します。いずれにせよ、組織全体が“どちらかに振り切れている”ことが生存条件となっているのが現実です。
4-2. 世界市場で残れるのは“1社だけ”の現実
技術や製品のコモディティ化が進む中、同じような機能・品質の商品がいくつも市場にあふれています。そんな中で生き残れるのは、「なんとなく良い会社」ではなく、“この分野ではここしかない”という圧倒的な差別化を実現している企業だけです。
その差を生み出すのは、人でも技術でもなく、組織の“思考の深さ”と“実行力”です。中途半端な戦略や器用貧乏な人材では、グローバル市場では埋もれてしまう。これは、国内市場に閉じていた時代とは決定的に違う点です。
4-3. 中途半端な仕組みと人材が企業を沈める
効率化を目指してマニュアルを整備したものの、柔軟性が失われて顧客ニーズに応えられなくなる。
一方で、創造性を重視しすぎてルールが曖昧になり、現場が混乱する――。
こうした「どっちつかず」の状態こそ、最も危険です。中途半端な仕組みと中途半端な人材の組み合わせは、現場の疲弊と顧客離れを招きます。
今の時代に求められるのは、「徹底的に効率化された仕組み」か、「変化に強い自走型の人材基盤」のいずれかに軸足を置いた戦略です。
すべてを中途半端に追いかけるよりも、自社の強みと市場環境に応じて“どちらで戦うのか”を見極め、重点を明確にすることが、これからの組織運営では問われてきます。
5. 今求められるのは「価値を創れる人材」
5-1. 自ら機会をつくり、価値を生む人
変化のスピードが速く、正解が定まらない時代においては、「与えられた仕事をきちんとこなす」だけでは組織は成長しません。
今、企業に本当に必要なのは、自分で機会を見つけ、周囲を巻き込みながら価値を生み出せる人材です。
こうした人材は、業務の指示がなくても「ここに改善の余地がある」「顧客は本当にこれを求めているのか?」と自ら問いを立て、行動に移します。つまり、問題解決ではなく、問題発見からスタートできる人です。
これまでのように、枠組みの中で「正しい答え」を出すことが評価された時代から、「新しい問いを立て、意味のある価値を生む」人が評価される時代に移っています。
5-2. 製品ではなく仕組みを売れる人
今や、どんな商品・サービスも、数年で模倣され、コモディティ化します。差がつきにくくなった市場では、製品単体ではなく“提供の仕組み”や“顧客体験全体”が競争力の源になります。
この時、単なる営業や技術職ではなく、ビジネスの仕組み自体を再設計できる人材が重要になります。たとえば、「売る→終わり」ではなく、「継続利用される仕組み」「データを活用して価値を高めるプロセス」など、顧客との関係性を長期的にデザインできる発想が求められます。
このような視点を持つ人材は、業界や職種を問わず、今後あらゆる分野で求められる存在となるでしょう。
5-3. 平均的な優秀さでは競争に勝てない
これまで多くの企業が「まじめでコツコツ」「協調性が高い」といったアベレージ型の人材を評価してきました。確かに、安定した業務運営には不可欠な存在です。
しかし、市場が縮小し、変化が常態化した今の環境では、“平均的な優秀さ”だけでは打ち勝てないというのが現実です。
企業が生き残るためには、「枠を超えて考えられる人」「異質な視点を持ち込める人」「他人の評価より目的に集中できる人」など、従来とは異なる軸の優秀さを発掘・育成していく必要があります。

6. 採用・育成の視点を“変化を起こす資質”にシフトする
6-1. 潜在力の可視化が必要な理由
これまでの選考は、学歴や経歴、過去の成果に重きを置いてきました。しかし、今求められているのは、「これまで何をしてきたか」ではなく、「これから何ができるか」を見る視点です。
つまり、目には見えにくい「変化を起こす資質」や「価値創出のポテンシャル」を、できるだけ早い段階で見抜く仕組みが必要になります。
特に新卒採用や若手層では、まだ実績が少ないため、行動の背景にある考え方・傾向・思考特性などを適切に把握する評価軸が重要です。
6-2. 適性を見る「ものさし」の再設計
従来の適性検査や評価は、「協調性があるか」「まじめに取り組むか」といった組織順応性を測るものが中心でした。
しかし、今必要なのは、「自ら考え、動く力」「未知の課題に挑む柔軟性」「周囲を動かす影響力」といった、変化に強い資質です。
こうした力は、表面的な受け答えや経験だけでは判断できません。だからこそ、認知特性・思考傾向・行動様式などを多面的に測定できるツールの活用が注目されています。
採用現場だけでなく、配置・育成にもこの新しい“ものさし”を導入することで、埋もれていた逸材を発掘することが可能になります。
6-3. 次世代のリーダーを見逃さない採用戦略
変化を起こす資質を持った人材は、最初から目立つとは限りません。むしろ、既存の評価軸では「扱いづらい」「協調性が低い」と見なされてしまうことすらあります。
だからこそ、採用の段階で「異質さ」や「違和感」に価値を見出す視点が必要です。そしてその人材が活きるような土壌、マネジメント、育成施策を設計しておくことが、リーダー層の多様化・若返りを加速させます。
今後の人材戦略は、「過去の成功パターン」ではなく、「未来に何ができるか」に投資できるかどうか。
その見極め力こそが、競争優位の分かれ道になるのです。


サービスの
ご紹介
変化を起こす人材は、学歴やスキルではなく、行動の特性に表れます。
「A8」は、目標への自律性や課題発見力、価値を生み出す資質を可視化する適性検査です。
従来の評価では見逃されがちなポテンシャル人材の発掘や、将来のリーダー選抜にも活用できます。
貴社の採用・配置の判断軸として、ぜひご検討ください。

コンピテンシー適性検査 Another8

© Humanage,Inc.

