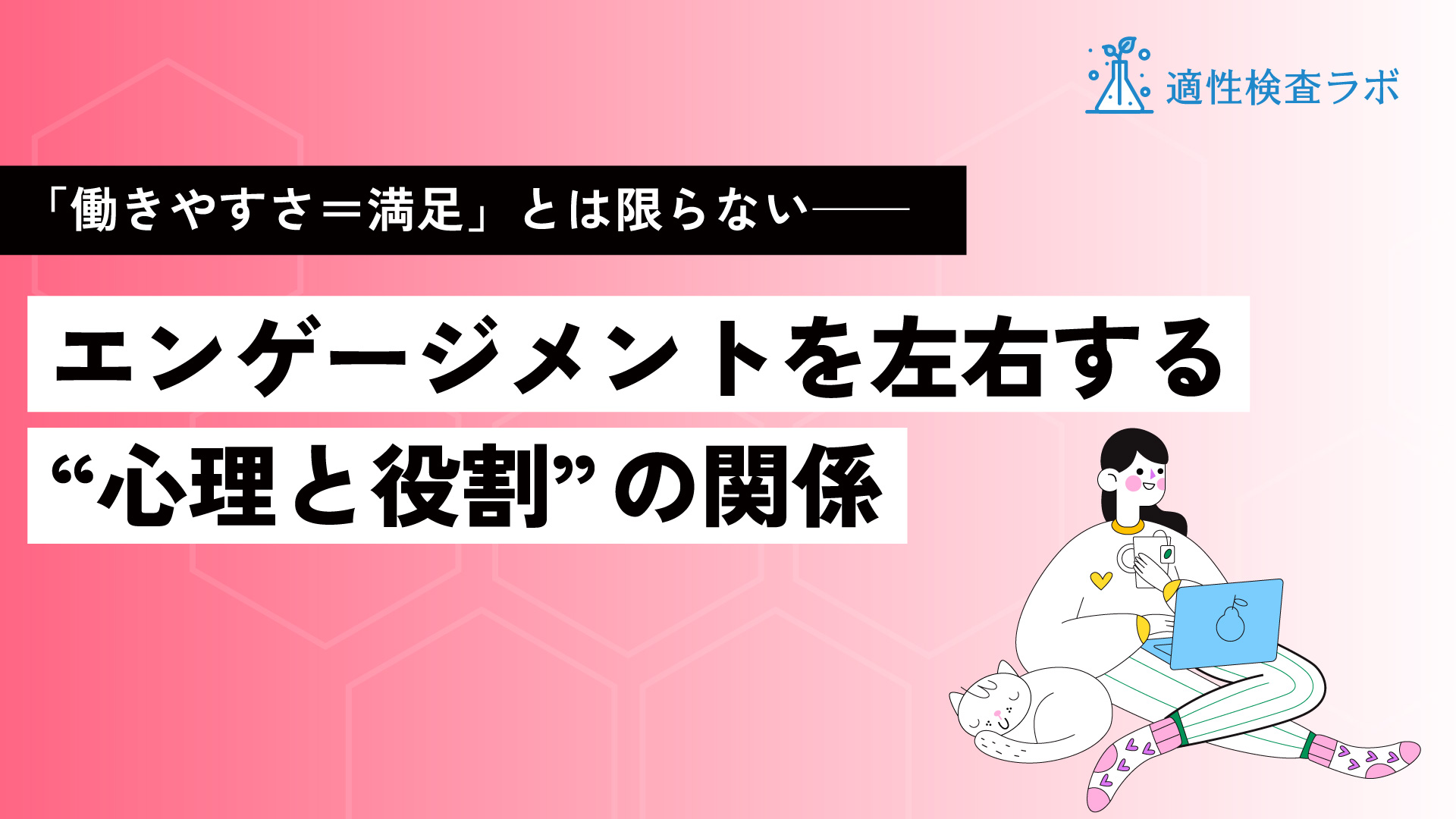
2025.10.17
「働きやすさ=満足」とは限らない──エンゲージメントを左右する“心理と役割”の関係
はじめに
「ワークライフバランス」という言葉はすっかり定着しましたが、現場の実感としては、なお課題が多く残っています。
「制度は整っているのに満足度が上がらない」「働きやすい環境にしたはずが、エンゲージメントが下がっている」――そんな声に、戸惑いを感じている人事担当者も少なくないのではないでしょうか。
その背景には、「時間」や「制度」で働き方のバランスを測ろうとする発想があります。
しかし、働き方が多様化した今、求められているのは「どんな環境であれば、その人が力を発揮できるか」という“心理的な満足”や“役割への納得感”に目を向けることです。
本記事では、仕事と生活の関係を“心理”の視点から捉え直し、エンゲージメントを左右する要因としての“心理と役割のバランス”に着目します。
採用後の定着支援や若手社員のモチベーションマネジメントに課題を感じている方にも、ヒントとしていただければ幸いです。
INDEX
1. 「ワークライフバランス=時短」の誤解を捨てよう
2. 仕事と生活は“心理的に連動している”
3. スケジュール設計は「1ヶ月単位」で考える
4. 成果につながる目標設定の技術
5. ワークスタイルに“バリエーション”を持たせよう
6. 挑戦と学びが、仕事と人生を豊かにする
サービス紹介
1. 「ワークライフバランス=時短」の誤解を捨てよう
1-1. 時間を減らすこと=バランスではない
「ワークライフバランス」と聞くと、いまだに「早く帰る」「残業を減らす」「週休3日制」といった時間のコントロールを思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。
もちろん、労働時間を見直すこと自体は重要です。しかしそれはワークライフバランスの入り口にすぎません。問題は、「仕事と生活、どちらにどれだけ時間を使っているか」ではなく、「自分が複数の役割の中で、どれだけ快適にバランスを取れているか」です。
たとえば、1日12時間働いていても、仕事が楽しく、家庭や趣味にも心理的な余裕を持って過ごせている人もいます。一方で、毎日定時に退社していても、「やりがいがない」「誰にも評価されない」とストレスを感じている人もいます。
つまり、「短い労働時間=良いバランス」とは限らないのです。
1-2. 本当のワークライフバランスとは「役割と重心の調和」
私たちは日々、「職業人」「親」「パートナー」「友人」「趣味人」「地域住民」など、さまざまな役割を持って生きています。
ワークライフバランスとは、それらの役割の“物理的な時間配分”ではなく、心理的な重みのバランスをどれだけ心地よく保てているか、ということです。
たとえば、ある人は「今はキャリアに集中したいから、生活の7割を仕事に費やしたい」と感じるかもしれません。一方で「子育て期だから、今は家族中心で仕事はほどほどがいい」と考える人もいるでしょう。
それぞれの人が自分にとって快適なバランスを定め、その重心を自覚できているか。ここが“バランスが取れているかどうか”を判断する本質です。
1-3. 個人ごとに異なるバランスを“可視化”する時代へ
2025年現在、企業のマネジメントは「多様性と個別性」に向き合うことが当たり前になっています。ワークライフバランスも例外ではありません。
重要なのは、「この人は今、どんな役割にどれだけの心理的エネルギーを割いているのか」「何に価値を置き、何を犠牲にしていると感じているのか」を、感覚だけでなくデータで捉えることです。
たとえば、ストレス傾向や行動特性を可視化できる適性検査を活用することで、「この人は役割間の葛藤が起きやすい」「今の働き方ではエンゲージメントが下がりやすい」といったリスクや傾向を事前に把握することができます。一律の“働き方改革”ではなく、一人ひとりに最適なバランスを可視化し、支援する時代が来ているのです。

2. 仕事と生活は“心理的に連動している”
2-1. 仕事の満足度は、プライベートの回復力に影響する
「仕事は仕事、プライベートはプライベート」と完全に分けて考えるのは理想的に見えて、実際には難しいものです。
人間の心は、日中の出来事を引きずるもの。仕事で満足感を得た日は、プライベートの気持ちも前向きになりやすいのが実際です。
逆に、日々の仕事で達成感や評価が得られないと、どんなに時間があっても「休んだ気がしない」「気分が晴れない」となることも。
働く人の心理状態は、仕事と生活をまたぐ“感情の連動性”を持っているという前提に立つべきでしょう。
2-2. 「そこそこ主義」が内発的動機とエンゲージメントを奪う
「とりあえず定時で帰れればいい」「ほどほどにやっていれば怒られない」という“そこそこ主義”は、一見すると合理的に見えるかもしれません。
しかし、自己決定理論やエンゲージメント研究では、人は自分で意味や価値を感じられない仕事に対して、心が離れていく傾向が明らかになっています。
本人がやりがいを感じていない仕事は、実はプライベートの時間さえも奪っていきます。なぜなら、心理的な充実感が得られないまま「疲弊感」だけが蓄積されるからです。
2-3. プライベートは逃げ場ではなく、再起の場
近年、「プライベートを充実させていれば、仕事のストレスはなんとかなる」と考える人が増えています。確かに、趣味や家族との時間は回復効果があります。
しかし、仕事そのものに満足できていない状態では、いくらプライベートを充実させても、週明けにはまた同じストレスが襲ってくる。これは多くのビジネスパーソンが経験している現実です。
大切なのは、プライベートを逃げ場にするのではなく、「回復→再エンゲージメント」のための場所にすること。仕事で得たポジティブな感情が、生活にも好影響を与え、その逆もまた然りです。

3. スケジュール設計は「1ヶ月単位」で考える
3-1. 「24時間計画」は仕事の本質とズレている
「ワークライフバランスを整えるには、まず毎日の生活リズムを…」
――よくあるアドバイスですが、1日単位のタイムマネジメントでは、現代の働き方には対応しきれません。
予定通りにいかないのが仕事です。急な会議、トラブル、長引く商談。
それなのに「毎日○時に退勤、○時からプライベート」という24時間単位で予定を組むと、理想と現実のギャップに疲弊してしまいます。
学校教育の名残で「日割りでスケジュールを立てよう」としがちですが、社会人に求められるのは変動を前提にしたリズム設計です。
3-2. ハイパフォーマーが実践する“波のある働き方”
実際、成果を出す人の多くは、日々の均等なペース配分ではなく、“波”のある働き方をしています。
たとえば、
- 繁忙週は意図的に負荷を高める
- 次の週は軽めのタスクで整える
- その次の週は思い切って休む
このように「高負荷→回復→中負荷→休息」の波を自ら設計し、1ヶ月〜1年の単位でバランスをとっているのです。
「いつも一定の働き方を保つこと」が理想なのではなく、「波を自分でデザインできること」が、現代における“真の自律型人材”とも言えるでしょう。
3-3. リズムの設計がストレスマネジメントの鍵
人によって、心身の回復に必要な時間もペースも異なります。
だからこそ、自分なりの働き方の“リズム”を把握することは、ストレスマネジメントにも直結します。
ここで活きてくるのが、ストレス傾向や仕事へのエネルギーの波を可視化するアセスメントです。
たとえば、ある人は「負荷が3週間続くとパフォーマンスが下がる」という傾向があるかもしれません。
また別の人は「精神的プレッシャーより、単調作業がストレスになる」など、ストレスの感じ方には個人差があります。
こうした特性を把握しておくことで、「どこで負荷を上げ、どこで緩めるか」という働き方の設計がしやすくなります。

4. 成果につながる目標設定の技術
4-1. 「何をやるか」より「どんな状態をつくりたいか」
「週に1回は顧客訪問する」「会議を3件開く」
――このような“やることベース”の目標は、仕事の多さを増やすだけで成果につながりにくいものです。
大切なのは、「何をするか」ではなく、「どんな状態を生み出したいのか」。
つまり、目標設定の軸を“行動”から“成果イメージ”に変えることです。
たとえば、「説明会を10回実施する」ではなく、
「参加者の50%が“選考を受けてみたい”と前向きに思う状態をつくる」――これが成果イメージです。
目的地が見えていれば、そこに向かう道筋(手段)は柔軟に変えられます。
4-2. 成果イメージから逆算すれば、迷わなくなる
「今週、何をすべきか」「この施策、意味があるのか?」と悩むとき、答えをくれるのはゴールの明確さです。
成果イメージがクリアであれば、今やっていることがそこに向かっているかどうかを判断しやすくなり、迷いや無駄が減ります。
目標が曖昧だと、いつまでも「終わった感」が得られず、働きすぎて燃え尽きてしまうケースもあります。
一方で、成果イメージが明確であれば、「ここまで達成できたから一区切り」と意図的に休息を取る判断もできるのです。
4-3. KPIがあることで、やるべきことが絞られる
成果イメージを設定したら、次に考えるべきは「その達成に最も影響する要素(KPI)」です。
たとえば、
- 顧客との関係性向上がゴール → 「対話数」より「顧客の反応内容」がKPI
- 採用の質向上がゴール → 「応募数」より「一次通過率」がKPI
複数の成果指標(パフォーマンスインディケーター)のなかでも、一番優先すべき軸(KPI)を明確にすることで、行動の優先順位がクリアになります。
KPIがなければ、すべてを頑張る必要が出てしまい、仕事の効率も下がり、当然ワークライフバランスも取りづらくなります。
だからこそ、「目指す成果 → そこにつながるKPI → 今週やるべきこと」へと逆算で組み立てる発想が、これからの働き方には欠かせません。
5. ワークスタイルに“バリエーション”を持たせよう
5-1. 仕事に「変化」を取り入れると集中力が続く
働いていれば、「やることはあるけど、気持ちが乗らない」「集中が続かない」という日は誰にでもあります。
そんなとき、無理に同じ仕事を続けるより、別のタスクに一度スイッチするほうが、結果的に効率は上がります。
たとえば、資料作成に煮詰まったら、軽いメール返信や社内コミュニケーションに切り替える。
あるいは、お客様と話す予定を入れておくことで、頭と気分を切り替える。
人間の集中力には“波”があります。
その波をうまく活用するには、「仕事に変化を持たせること」が有効です。
5-2. 関わる人・場所・服装を変えるだけでも効果的
変化は仕事内容だけに限りません。“誰と働くか”“どこで働くか”“どんな自分で働くか”も、仕事の新鮮さに大きく影響します。
- リモートワークの日にあえてカフェで作業する
- 気分の上がる服で出社する
- 他部署の人とランチに行く
こうした小さな変化の積み重ねが、仕事に対する前向きな感情を保つのに役立ちます。
同じ仕事でも「誰と取り組むか」が変わるだけで視点が広がり、結果としてアウトプットの質も変わってくるのです。
5-3. チーム内の“他者接点”がモチベーションを生む
仕事における“他者との接点”も、エネルギーの源です。
とくに現代は、自律性と同時に“つながり”が求められる時代になっています。
たとえば、
- 他部署の上司にアイデアを相談してみる
- 同世代の若手と雑談して情報交換する
こうした「いつもと違う人と関わる機会」は、視野を広げ、モチベーションを刺激してくれます。
また、ちょっとしたやりとりの中で、「その資料、すごく参考になった」「あの説明、分かりやすかった」といったポジティブなフィードバックを得られると、それだけで「また頑張ろう」と気持ちが上向くものです。

6. 挑戦と学びが、仕事と人生を豊かにする
6-1. 新しいことに挑戦することで“自分の成長”を実感する
いつもと同じ業務の繰り返しでは、飽きやマンネリ感がつきまといます。
そんなときにこそ、「少し新しいチャレンジ」が大きなエネルギーになります。
- いつもと違う言葉遣いで資料をつくってみる
- 新しいツールを試してみる
- 普段接点のない社員に話しかけてみる
こうした“小さな挑戦”でも、成長の実感は得られます。
「昨日より今日の自分が少しでも進歩している」と感じられることは、働くうえでの原動力になります。
6-2. スキルアップがプライベートにも好循環を生む
新しい知識やスキルを習得することは、仕事の充実に直結しますが、実はプライベートにも良い影響をもたらします。
- 「人に話したら面白がってもらえた」
- 「仕事の成果が自信につながった」
- 「資格取得で日々の学習習慣が整った」
こうした経験は、自己効力感を高め、「自分の人生を主体的に動かしている感覚」をもたらします。
また、知識やスキルのアップデートが習慣になると、変化の多い時代にも柔軟に対応できるようになります。
6-3. 「成長できている感覚」がエンゲージメントを支える
最終的に、人が仕事に没頭できるかどうか(エンゲージメント)を左右するのは、「自分が成長している感覚」があるかどうかです。
たとえば、目標に対して自分でKPIを立て、その達成度を振り返る。
あるいは、できるようになったことをメモに残しておく。
こうした自己確認の機会を定期的に持つことで、「やってきたことは無駄ではなかった」という納得感と、「次はもっとやってみよう」という前向きな意欲が生まれます。
エンゲージメントは“気合”や“情熱”ではなく、納得感と手ごたえの積み重ねから育まれるものなのです。


サービスの
ご紹介
エンゲージメントを高め、自律的な働き方を実現する第一歩は、「与えられた仕事」をこなすだけでなく、「自ら仕事を面白くする力」を知ることです。
TG-WEBのジョブ・クラフティング適性検査『Q1』は、個人の「ジョブ・クラフティング力(自ら仕事を工夫し、やりがいを生み出す力)」と「のめり込みやすい仕事のタイプ」を科学的に測定します。
自ら仕事を工夫し、積極的にエンゲージできる人材を見極めることで、採用・配置配属の精度向上、および育成・早期フォローに活用いただけます。

ジョブ・クラフティング
適性検査 Q1

© Humanage,Inc.

