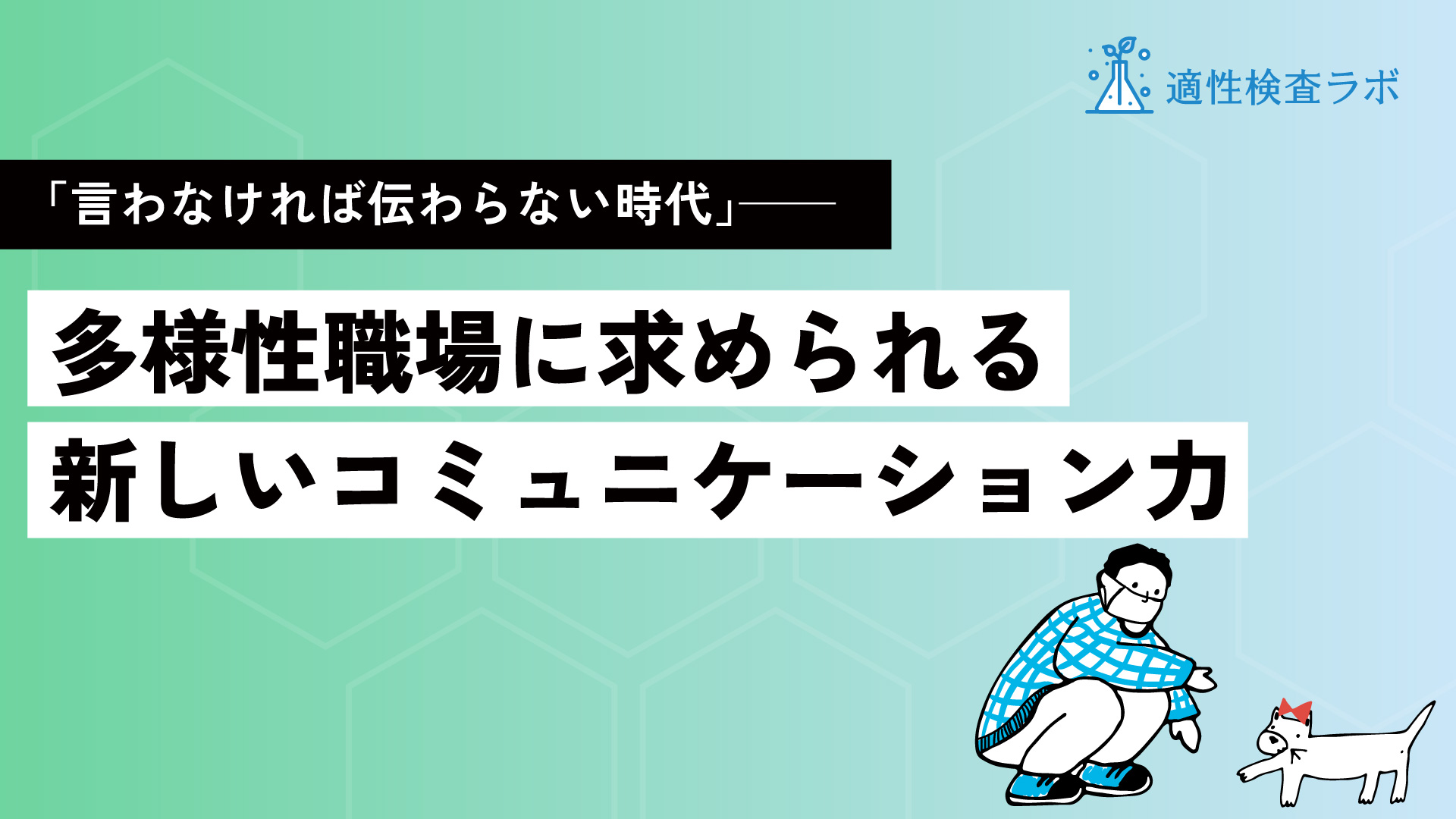
2025.10.03
「言わなければ伝わらない時代」──多様性職場に求められる新しいコミュニケーション力
はじめに
「伝えたつもりだったのに、伝わっていなかった」
そんなすれ違いが、最近増えていませんか?
多様な世代、働き方、価値観が共存する今の職場では、これまで“なんとなく通じていた”はずの会話や指示が、驚くほど伝わらないことがあります。
リモート勤務、フレックス、副業・時短勤務など、働く「時間」や「場所」、関わり方のスタイルがそれぞれ違うことが、意思疎通のタイミングや方法に影響を及ぼしているのです。
つまり今は、「言わなくてもわかる」から「言わなければ伝わらない」時代へと完全に移行しています。
本記事では、多様性を前提とした現代の職場で起きがちなコミュニケーションのすれ違いを整理し、人事や採用の観点から、どのような“伝える力”が求められているのかを掘り下げていきます。
INDEX
1. 多様性が前提の職場で、なぜ意思疎通が難しくなったのか
2. なぜ伝わらない? 言葉の“省略”が引き起こすすれ違い
3. 世代だけじゃない、「使うツール」と「感覚」のギャップ
4. 「好き嫌い」で判断しない:多様性と向き合うための思考
5. 変わる働き方、変わる職場:私たちは今どこにいるのか
6. 採用で見極めるべき「伝える力」とは何か?
サービス紹介
1. 多様性が前提の職場で、なぜ意思疎通が難しくなったのか
1-1. 「共通認識」が消えた職場
かつての職場では、「常識」「マナー」「暗黙の了解」など、言葉にしなくても伝わる“共通認識”が機能していました。社員は似たような価値観・働き方を共有し、「言わなくてもわかる」ことが当たり前だったのです。
しかし、今は違います。社員は多様なバックグラウンドを持ち、働く目的もスタイルもバラバラ。年齢、性別、国籍だけでなく、フルタイム・時短・リモート・副業などの働き方の違いも加わり、「共通認識」を前提としたコミュニケーションは、もはや通用しなくなっています。
「言わなくてもわかる」ではなく、「言わなければ伝わらない」時代が到来しているのです。
1-2. 価値観・背景・働き方の多層化
多様性とは、単に人の属性の違いだけではありません。
- 「働く目的」…出世を目指す人、プライベートとの両立を優先する人
- 「情報の扱い方」…リアルタイムで共有したい人、非同期を好む人
- 「コミュニケーションの温度感」…オープンに議論したい人、慎重に距離をとりたい人
このように、職場には無数の“価値観のレイヤー”が存在しています。どれが正解というわけではなく、立場や背景が違えば、物事の受け取り方・伝え方が違うのは当然なのです。
だからこそ、同じ言葉を使っていても、「伝わり方」が人によって大きく異なります。表面的な言葉のやり取りだけでは、誤解や摩擦が生まれやすくなっているのです。
1-3. 「揃える」から「活かす」マネジメントへ
かつては、社員の考え方や行動を「揃える」ことがマネジメントの役割でした。価値観を共有し、同じ方向を向かせることで、組織としての一体感をつくる——それが「良い組織」とされていたのです。
しかし今、多様性を前提とした職場では、「揃える」ことよりも「違いを活かす」ことが求められています。
全員が同じ考え方をする必要はありません。むしろ、異なる視点があるからこそ、創造的なアイデアや意思決定の質が高まることもあります。そのためには、互いの違いを認識し、尊重しながら、共通の目的に向かって協働する「伝え合う力」が不可欠です。

2. なぜ伝わらない? 言葉の“省略”が引き起こすすれ違い
2-1. 曖昧な指示が誤解を生む理由
「この件、いい感じにまとめといて」
「なんかちょっと、ズレてるかな」
こうした曖昧な言葉は、以前であれば“行間を読む”ことで何とかなったかもしれません。しかし、受け手の前提が多様化している今では、「いい感じ」が何を意味するのかが、人によってまったく異なります。
曖昧な指示は、受け手側の解釈に委ねられるため、やり直しや認識ズレが発生しやすくなります。結果として、双方の信頼関係が損なわれたり、「自分の仕事が評価されない」と感じる要因にもなり得ます。
2-2. 文脈依存コミュニケーションの限界
日本のコミュニケーション文化は、いわゆる「高コンテクスト」型。
つまり、「全部を言葉にしなくても、相手が汲み取ってくれる」ことを前提としています。
しかし、今の職場は以下のような構成が当たり前になっています。
- リモートワーカー
- 中途入社のメンバー
- 外国籍メンバー
- 職種や専門性が異なるチーム構成
このような環境では、「なんとなくの共有」は機能しません。むしろ、「説明されなかったことが問題」とされるケースも増えています。
もはや“察して”は通用しない。伝える側の責任が、これまで以上に問われる時代です。
2-3. “具体的に伝える”が当たり前の時代に
現代の職場では、「具体的に伝えること」が基本ルールになりつつあります。
たとえば、
- 「やっといて」ではなく「〇日までに、誰に、何を、どの形式で」
- 「よくない」ではなく「どこが、どのように、何と比べてよくないのか」
曖昧さを減らし、受け手が再現可能なレベルまで明文化することが、スムーズな仕事の前提となっています。
これは単なる“丁寧さ”の話ではなく、再現性・生産性・チームワークを支えるためのスキルです。
特に、世代や職種を越えて働く今の環境では、「具体的に伝える力」があらゆる仕事の土台になっていると言えるでしょう。

3. 世代だけじゃない、「使うツール」と「感覚」のギャップ
3-1. 指示が曖昧に聞こえるZ世代、細かすぎると感じる上司
「“これくらい察してほしい”と思って伝えたけど、全然通じなかった」
「なんでそんなに細かく言われないと動けないの?」
このような不満は、世代間だけでなく、“感覚の違い”によっても生まれます。
上司世代(特に昭和・平成初期世代)は、「細かく言わずに任せるのが信頼」だと感じやすく、一方でZ世代は「具体的に伝えてもらえないと動けない」と考える傾向があります。
また逆に、Z世代からすれば「ここまで言わなくても分かってほしい」「その確認、何度も必要?」と感じる場面もあります。
このギャップは、能力の差ではなく、“情報量と関係性のバランス”に対する価値観の違いから生じています。
信頼関係を築くためには、「どこまで伝えるのが適切か?」を共有・調整する意識が欠かせません。
3-2. チャット派とZoom/対面派、どちらが「丁寧」?
今の職場では、以下のような感覚の違いが、摩擦を生むことがあります。
- 若手:「チャットで送ったんだから、読んでくれているはず」
- 上司:「大事なことは、対面かZoomで話すのが誠意」
Z世代にとっては、SlackやLINEなどの非同期コミュニケーションが日常です。「既読=伝わっている」と思ってしまうことも少なくありません。一方、上司層にとっては、“時間を割いて対話する”ことが信頼と誠意の証だと感じられます。
この背景には、「どの手段が適切か」という合理性だけでなく、“丁寧さ”の感じ方の違いがあります。
ツールの違いは、それぞれに良さがあります。
大切なのは、「自分が便利な方法」ではなく、「相手がどう受け取るか」を考えて使い分けることです。
3-3. 「気遣い」の形が違うだけで、誤解される時代
たとえば、Z世代の若手が「迷惑をかけないように」と遠慮して声をかけなかった結果、上司から「なぜ報告しなかったんだ」と指摘される。
逆に、上司が「任せるつもりであえて声をかけなかった」ことが、若手には「放置された」と感じられる。
これは、お互いに“気遣い”として行動しているにもかかわらず、形が違うことで誤解が生まれている典型的なケースです。
今の時代、「察する文化」はもはや通用しづらくなっています。
気遣いの“つもり”ではなく、具体的な行動や言葉で示すことが、関係構築には欠かせません。

4. 「好き嫌い」で判断しない:多様性と向き合うための思考
4-1. 感情的リアクションでは、理解が止まる
「なんか苦手なタイプ…」
「この人とは合わない気がする」
こうした感情は、誰にでも自然に起こるものです。しかし、それをそのまま判断基準にしてしまうと、相手を知る機会を自ら閉ざしてしまうことになります。
職場では、好き嫌いではなく、仕事の目的に向かってどう協力するかが大切です。
感情的なリアクションで終わらず、一歩引いた視点で「なぜそう感じたのか?」と自分の反応を内省することが、多様な関係性を築く第一歩になります。
4-2. 好きじゃなくても、共に働ける
「気が合う」「価値観が近い」相手と働けるのは、もちろん快適です。
しかし実際の職場では、そうした相手ばかりではありません。むしろ、価値観が異なる人との協働が増えているのが今のリアルです。
大切なのは、「好きになれるか」ではなく、「どうしたら相互理解を深められるか」という姿勢です。
そのためには、相手を“変えよう”とするのではなく、“理解しよう”とすることが鍵になります。
4-3. 無理に合わせず、適切な距離で関わる方法
「多様性を受け入れなければ」と思いすぎて、無理に合わせたり、自分を押し殺してしまうと、かえってストレスになります。
他者との違いを認めることと、無理に同調することは別物です。
価値観や感覚が異なる相手とは、必要な距離感を保ちながら、建設的に関わるという方法もあるのです。
「全員とわかり合う必要はない。でも、共に働くには“橋”を架ける意志が必要」
——これが、多様性と向き合う職場におけるリアルなスタンスではないでしょうか。
5. 変わる働き方、変わる職場:私たちは今どこにいるのか
5-1. 「海外との協働」が日常化した今
かつて「海外とのやりとり」は、特別なプロジェクトや限られた職種に限られていました。
しかし今は、メールやSlackで世界中のチームとつながり、オンライン会議で国境を超えて仕事を進めるのが日常になっています。
この環境では、語学力以上に、「相手に伝える力」「文化の違いを尊重する姿勢」が重要になります。
伝わる表現、誤解を生まない配慮、立場の違いを前提とした対話力——
こうしたスキルがなければ、同じ英語を話していても「通じない」ことは多々あります。
もはや、「グローバル人材」は一部のエリートではなく、すべてのビジネスパーソンの基本要件となりつつあるのです。
5-2. 社内にもある“異文化”をどう乗りこなすか
「グローバル対応」というと海外をイメージしがちですが、実は社内にも“異文化”は存在します。
- 本社 vs 支社・店舗
- 営業部門 vs 開発部門
- ミレニアル世代 vs Z世代
- フルリモート社員 vs 出社メイン社員
それぞれの立場や業務特性、価値観が異なれば、「常識」や「当たり前」も大きく違います。
このとき、「言わなくても伝わる」と思っていると、無自覚な摩擦が生まれやすくなります。
大切なのは、“社内だからこそ通じる”という思い込みを捨て、相手の背景を理解しようとする姿勢を持つことです。
5-3. 今後求められるのは「変化への適応力」
技術の進化、組織の再編、働き方の変化……現代のビジネス環境は、常に「変わり続けること」が前提です。
だからこそ、これからの人材には「柔軟性」や「対応力」が強く求められます。
- 相手によって話し方を変える
- ツールやルールの変化にストレスなく対応する
- 目的に応じて、最適な伝え方を選べる
こうした“コミュニケーションの変化耐性”は、職種・業界を問わず不可欠な力です。
今後の職場では、「何を知っているか」だけでなく、「どう伝え、どう動けるか」が、活躍の分かれ目になるでしょう。

6. 採用で見極めるべき「伝える力」とは何か?
6-1. 語学より大切な“伝達の実践力”
グローバル化や多様性の進展により、「英語が話せる人材を採用したい」というニーズは依然として存在します。
しかし、実務で本当に求められるのは、語学力そのものではなく、「伝える力」そのものです。
たとえば、次のような場面です:
- 誤解されないように、丁寧かつ簡潔に伝える
- 相手の立場に合わせて話す順番や表現を変える
- 自分の考えを、論理的かつ感情的に補完して伝える
これらは、英語でも日本語でも共通して求められる「実践力」であり、翻訳では代替できない能力です。
6-2. 適応力・具体性・再現性の3要素がカギ
「伝える力」は単なる“話し上手”ではありません。
採用時に見極めたいのは、以下のような3つの力です。
✅ 適応力
相手や状況に応じて、伝え方を柔軟に変えられる力
✅ 具体性
抽象的な言葉を避け、具体的な事実・行動・目的で説明できる力
✅ 再現性
偶然のコミュニケーション成功ではなく、再現可能なスタイルを持っていること
これらが備わっていれば、言語や文化の壁を越えて、信頼と成果を築くことができます。
6-3. 採用時にこそ必要な「伝える力」の可視化
「伝える力」は、履歴書や学歴では判断できません。
面接での受け答え、ワーク課題、プレゼン演習などを通じて、相手の“言語化力”や“配慮の視点”を見ることが不可欠です。
また、近年では適性検査などで「コミュニケーション特性」や「説明の具体性・論理性」などを可視化することも可能になっています。
採用段階でこうした力を見極めることで、入社後のミスマッチを減らし、「育てやすい」「伝わる人材」の採用につながります。


サービスの
ご紹介
TG-WEBシリーズの《I9 判断推理力検査》は、業務に必要な論理的思考力や要旨把握力を測定し、言語間のつながりを論理的に考える力など、実務で問われる伝達力の特徴を明らかにします。
また《W8 チーム・コミュニケーション適性検査》では、他者との関わり方のクセを可視化し、チーム内でのすれ違いや誤解の起点を事前に把握することが可能です。対話のスタイルが異なるメンバー同士の関係構築にも活用できます。
多様性を前提とした現代の職場づくりに、ぜひご検討ください。

チーム・コミュニケーション適性検査 W8

判断推理力検査 i9

© Humanage,Inc.

