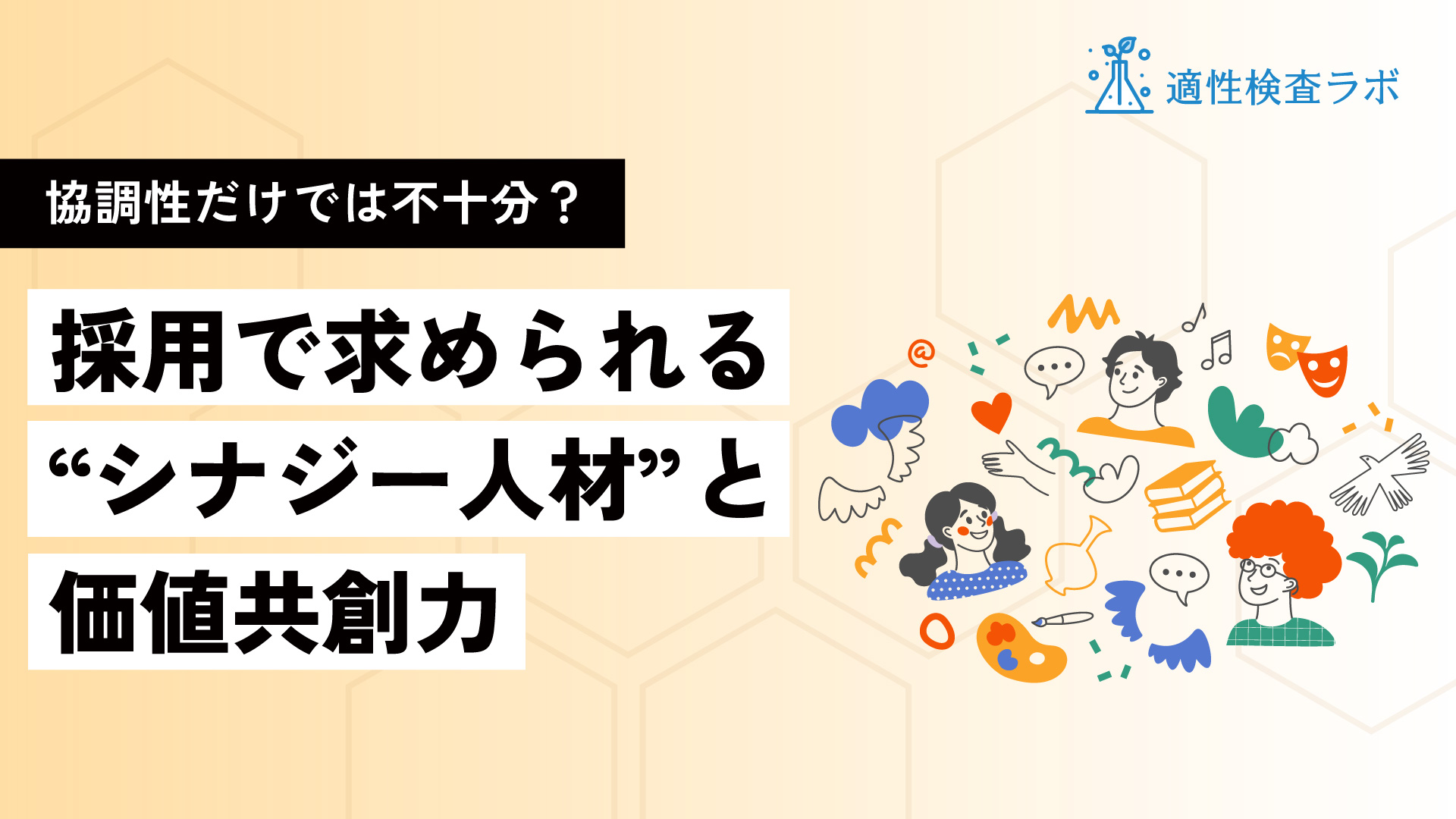
2025.09.26
協調性だけでは不十分?採用で求められる“シナジー人材”と価値共創力
はじめに
採用の現場で「協調性が高い人材」は長らく好まれてきました。しかし今、私たちが本当に求めるべきは、ただ“周囲に合わせる”だけの人ではありません。他者と対話し、違いを活かし合いながら、新たな価値を生み出せる人材――それが、これからの時代に必要な“シナジー型人材”です。本記事では、協調性との違いや、シナジーを生む人材の特性、見極め方、そして実践的な採用の工夫までを、採用担当者の視点からわかりやすく解説します。
INDEX
1. 「協調性」と「シナジー」の違いを理解する
2. シナジーを生む2つのアプローチ
3. シナジーを生む人材に共通する「2つの資質」
4. シナジーを育てる組織と人材の見極め方
5. 明日から実践できる「シナジー型採用」のすすめ
6. 適性検査で“シナジー人材”を見抜くポイント
サービス紹介
1. 「協調性」と「シナジー」の違いを理解する
協調性は“合わせる力”、シナジーは“生み出す力”
採用現場で頻出する「協調性のある人材」という評価。しかし本当に求めるべきは、“協調”ではなく“シナジー(相乗効果)”を生み出せる人材ではないでしょうか。
協調性とは、文字どおり「他人に合わせる力」。チームワークにおいて衝突を避け、場を円滑に回す力ではありますが、それだけでチームの成果が向上するわけではありません。
一方、シナジーとは“他者と関わることで新しい価値や成果を生み出す力”のこと。つまり、自分の強みと相手の強みをかけ合わせて、1+1を3にも5にもしていける人こそ、現代のビジネスパーソンに求められる存在なのです。

2. シナジーを生む2つのアプローチ
2-1. 既存の人間関係を活かしたシナジー創出
シナジーを生み出すアプローチには、大きく2つのパターンがあります。
1つ目は、すでに築かれている関係性を活かして成果につなげるスタイルです。たとえば、同じ部署やプロジェクトチームのメンバー同士が、日々のやりとりや共通理解をベースに協力し合うことで、新たな付加価値を生み出すようなケースです。
このようなアプローチは、社内の信頼関係や暗黙知の共有があるため、比較的スムーズに実行しやすいのが特徴です。すでに存在するチームダイナミクス(役割分担や信頼構造)を活用し、リーダーシップやフォロワーシップを発揮して成果を最大化できることが強みです。
2-2. 新しい関係を自ら築き出す“価値共創力”
2つ目は、これまで関わりのなかった人やチーム、外部との接点を自ら見つけ出し、新たな価値を共創する力です。
これは、単なる協力関係ではなく、“異質な人・組織とのあいだに橋を架ける力”と言ってよいでしょう。
たとえば、
- 他部署と連携して業務改善に取り組む
- 顧客の声をもとにサービスを刷新する
- 異業種とコラボして新事業を立ち上げる
などの行動が該当します。
こうした動きは、固定された組織構造や役割分担を超えていく“越境型の連携”であり、変化の激しい時代にこそ求められるスタイルです。自分と違う視点を持った人と組むことでこそ、予想もしない成果やイノベーションが生まれるのです。
2-3. 外部やグローバルとの“越境連携”が未来を拓く
さらに高いレベルでは、社外のステークホルダーやグローバルな視点を取り入れたシナジー形成が重要になります。たとえば、
- 顧客との対話から新しいニーズを発見する
- パートナー企業とアライアンスを組んで市場開拓を進める
- 海外のチームと協業しながらプロジェクトを遂行する
といったケースがそれにあたります。
これらの連携を成立させるには、異文化理解・多様性受容・対話力・自己認識力といった、より高度な人間力が必要です。
企業としては、単に「チームで協調できる人材」ではなく、“組織の外”でも価値を共創できる資質を持った人材を見極めていくことが、競争優位性の確保につながります。

3. シナジーを生む人材に共通する「2つの資質」
3-1. 「自尊」:傲慢と違う、事実に基づく自信
シナジーを生み出す人に共通する資質のひとつが、「自尊」です。誤解されがちですが、自尊とは自分の価値を、他者との比較ではなく“事実ベース”で認識している感情のことです。
たとえば「自分はこういう経験を積み、こういう成果を出してきたから、こういう価値を発揮できる」と自覚できている状態です。これは「自分はすごいから、他人より上だ」という相対的な“傲慢”とはまったく異なります。
傲慢さは、他人を下げることで自分の立場を確保しようとする心理ですが、自尊が高い人は、他人の成功を素直に喜ぶことができる。このような人材こそ、Win-Winの協働関係を築けるベースを持っているのです。
3-2. 「他尊」:相手を認め、価値を与える能力
もうひとつの鍵は「他尊」。これは、相手の立場や気持ちを想像するだけでなく、相手の存在を認め、相手にとっての“メリット”を提供したいという意識に根ざした力です。
他尊が高い人は、「あの人のここが素晴らしい」「この人の強みを活かせば、より良い成果につながる」という視点で他者を捉えます。そうした相手理解が、自然なシナジー創出と良好な関係構築につながっていきます。
一方で、表面的な「お世辞」や「取り入る姿勢」は、共感性ではありません。本心では相手を認めておらず、利得目的の言動は、むしろ信頼を損なうリスクがあります。
3-3. 自己理解と他者理解が生む“真の協働”
「自尊」=自己理解、「他尊」=他者理解。この2つがバランスよく備わってはじめて、真に価値ある“協働”が実現します。
自分の強みを客観的に把握し、それを土台に、相手の立場・視点・目的にも目を向けること。これができる人材は、「この人とはこう組めば価値が生まれる」と直感的に判断できるため、チーム内外でのシナジー創出に長けているのです。
採用においては、単なる「協調性がある人」ではなく、こうした内面の成熟度を持った人材を見極めていく視点が必要です。

4. シナジーを育てる組織と人材の見極め方
4-1. 適性検査では「自尊」と「他尊」に注目せよ
パーソナリティ適性検査は、「性格タイプ」や「性格傾向」にフォーカスするものが主流でした。しかし、これからの人材選びでは、“どんな性格か”よりも“どう他者と関われるか”がカギとなります。
そのため、現代の採用では、「自尊」と「他尊」の2軸を可視化できる適性検査の活用が非常に有効です。これらの指標は、単なる印象では見抜きにくいため、定量データで把握することが重要です。
4-2. シナジーを生む人はチームを“エンゲージ”させる
シナジーを生む人材は、自分だけで成果を出すのではなく、周囲を“巻き込みながら”成果を高めるという特長を持っています。彼らがチームにいると、周囲のモチベーションが自然と上がり、組織のエンゲージメントが高まるのです。
この現象は心理学的には「情動的共感」と呼ばれ、楽しそうに仕事に取り組む人がいると、周囲にもその感情が伝播するとされています。採用担当者は、「この人がチームに入ったら、場がどう変わるか?」という視点での評価が求められます。
4-3. 採用・育成で意識したい“戦隊ヒーロー型チーム”
理想のチーム像としてわかりやすいのが、“戦隊ヒーロー型”チーム。レッド・ブルー・イエローと、違う特性を持ったメンバーが互いに役割を持ち、補完し合いながら大きな力を生むというイメージです。
このようなチームに必要なのは、多様性を尊重しつつ、自他の強みを認識できる人材。だからこそ、「自尊」と「他尊」は、採用や育成における新しい判断軸として機能します。
適性検査は、こうした“協働力の本質”を見極めるための強力なツールになり得るのです。
5. 明日から実践できる「シナジー型採用」のすすめ
5-1. 応募者の“できることベース”の自己理解を見る
シナジーを生める人材を見極めるうえで、まず注目したいのが「できること」ベースの自己理解です。自尊感情が高い人は、自分を客観的に見つめ、成果や行動という“事実”にもとづいて自己評価ができる傾向があります。
履歴書やエントリーシートでは、「自分は〇〇な性格です」といった抽象的な表現が並ぶことが多いですが、重要なのは「実際に何ができ、どう成果に結びつけたか」です。
採用担当者は、過去の経験の中にある“再現可能な成功パターン”を丁寧に聞き出し、それが今後の職務にどう活かせるかを見極める視点が必要です。
5-2. 面接で問いたい“他者との協働”に関する質問例
協働力やシナジーを見抜くには、具体的な行動とエピソードに着目した面接質問が有効です。以下のような質問が参考になります。
- 「これまでに、自分とは価値観が異なる人と一緒に仕事をした経験はありますか?どのように関係を築きましたか?」
- 「自分の強みを活かして、周囲に貢献できたと感じたエピソードを教えてください」
- 「チームで成果を出すために、あなたが意識していたことは何ですか?」
- 「新しい人と仕事を始めるとき、最初にどんなアクションを取りますか?」
このような問いかけを通じて、相手への他尊や自発的な関係構築力、自分の強みへの理解度を見極めることができます。
5-3. 「協調できるだけ」から脱却する組織づくりへ
これからの時代、組織に必要なのは「自律的で、かつ他者と価値を創出できる人材」です。つまり、自分の武器を持ちつつ、他者の強みにも価値を見出し、掛け算の関係を築ける人です。
そのためにも、採用基準や評価軸の見直し、そして「協働」を前提とした育成設計に転換していくことが、組織全体の進化につながっていくのです。

6. 適性検査で“シナジー人材”を見抜くポイント
6-1. なぜ従来のテストでは不十分なのか
これからの採用において求められるのは、単なる知識やスキルではなく、能動的に関係を築く力、自己理解と他者理解の深さ、多様な立場との協働力といった、複合的かつ内面的な資質の見極めです。
そのためには性格特性の把握にとどまらず、先に述べた「自尊」や「他尊」といった指標を確認し、候補者がどのように自己を尊重し、同時に他者を受け入れられるかを丁寧に見極めることが不可欠です。
6-2. 適性検査で注目すべき指標とは?
では、適性検査において「シナジーを生める人材」を見抜くには、どのような資質に注目すべきなのでしょうか?
代表的な着眼点は以下のとおりです。
自尊に関連する資質
- 主体性:自分から動く意欲があるか
- 自己効力感:「やればできる」という前向きな認識
- 自己認識の現実性:理想と現実を適切に把握しているか
他尊に関連する資質
- 他者受容性:自分と異なる価値観にも耳を傾けられるか
- 感情理解力・傾聴力:相手の立場や感情を汲み取れるか
- 関係志向性:自ら人間関係を築こうとする意欲
こうした資質は、行動特性や性格傾向を可視化するタイプの適性検査を活用することで、多面的に把握することが可能です。
6-3. 設問例と、シナジー資質の読み取りポイント
具体的には、以下のような設問を通じて応募者の特性を読み解くことができます。
例:
- 「チームで意見が分かれたとき、あなたはどう行動しますか?」
- 「自分の意見に自信がある場合でも、他人の意見に耳を傾けられますか?」
このような質問に対する回答を通じて、以下のような特性を見極められます。
- 自分の意見に固執しすぎない柔軟性
- 他人の視点を尊重しながらも、自己主張を適切にできるか
- 感情に左右されず、建設的に意見を交わせる対話力
また、「過去に周囲と協力して成果を出した経験」や、「その際にどのような感情があったか」といった深掘り質問を通じて、共感性や内省力の深さ、関係形成の主体性などをより具体的に把握できます。
適性検査は、面接や履歴書だけでは見抜きづらい“協働力”や“内面の成熟度”を客観的に把握できる強力なツールです。面接と組み合わせることで、従来の「協調性評価」では捉えきれなかった、“関係性を生み出す力”=真のシナジー創出力を見極めることが可能になります。


サービスの
ご紹介
「人に合わせる力」ではなく、「価値を共創する力」を見極めたい——そんな採用ニーズに応えるのが、ヒューマネージの適性検査です。チーム・コミュニケーション適性検査『W8』では、心理学的見地に基づき、「自尊」「他尊」の観点から、周囲と協力して成果を生み出すことができるかどうかを測定。さまざまな意見や価値観の人とも協働して成果をあげる力を採用時点で見極めます。単なる同調ではない“協働力”を捉えるヒントとして、ぜひ導入を検討ください。

チーム・コミュニケーション適性検査 W8

© Humanage,Inc.

