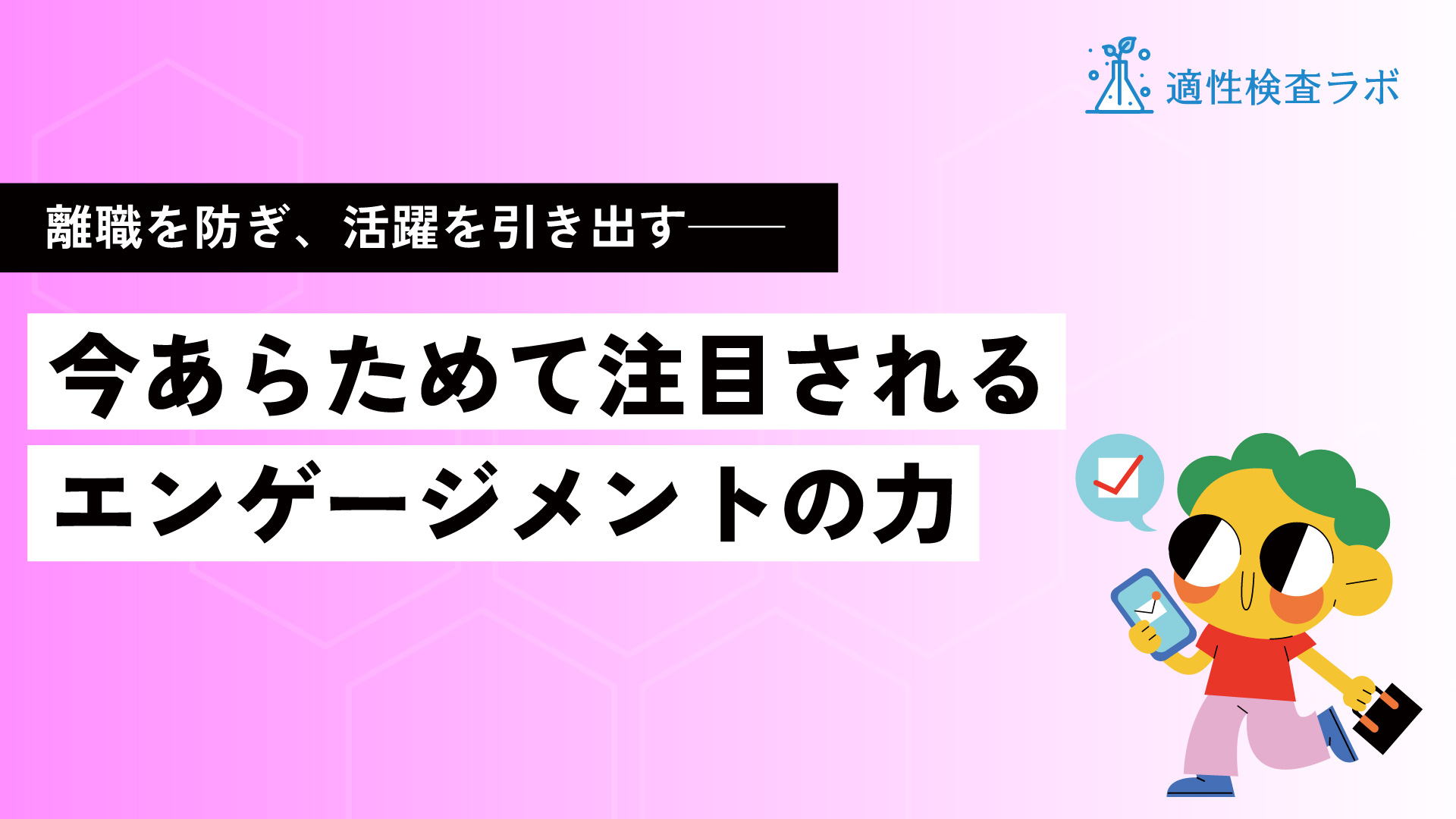
2025.09.19
離職を防ぎ、活躍を引き出す──今あらためて注目されるエンゲージメントの力
はじめに
「なぜあの社員は辞めてしまったのか?」
定着や活躍を支援する立場として、そんな問いに直面したことはありませんか。
スキルも性格も申し分のない人材が、なぜか定着せずに辞めてしまう。
一方で、想定以上のパフォーマンスを発揮する社員もいる──その違いを生むキーワードこそが、「エンゲージメント」です。
近年では、Z世代を中心に、“やりがい”や“楽しさ”を重視する働き方へのシフトが加速しています。
従来の評価軸やマネジメント手法だけでは、社員の活躍や定着を十分に支えきれない時代に入りつつあります。
本記事では、エンゲージメントの本質にふれながら、職場でどのように高めていけるか──その実践的なヒントを、人事・採用の視点からお届けします。
INDEX
1. エンゲージメントが「離職防止」と「活躍」に効く理由
2. 本当の「仕事が楽しい」とは?のめり込みのメカニズム
3. エンゲージメントを高める3つの感情的資源
4. 若手が「成果」を実感できる職場をつくるには
5. 自走する社員を育てる「内発的動機付け」のコツ
6. 会社や上司が“障害”にならないために
サービス紹介
1. エンゲージメントが「離職防止」と「活躍」に効く理由
1-1. 辛さを我慢する時代は終わった
「仕事は辛くて当たり前」「我慢して一人前」──。
かつてはそれが“普通”でした。しかし、現代の働き方では、その価値観はむしろリスクです。
複雑化・高難易度化する仕事では、「辛いけどやる」は通用しません。心を削りながら働けば、早かれ遅かれ燃え尽きます。うつ症状やメンタル不調での離脱も後を絶ちません。
いま、求められているのは「のめり込める仕事」「楽しさを感じられる仕事」に人をマッチングさせることです。
これは“わがまま”でも“甘え”でもなく、持続可能な働き方をつくるための戦略です。
1-2. “楽しい仕事”はワガママではなく、組織の武器
若手世代が「楽しく働きたい」と言うのは、決して自己中心的な発言ではありません。
むしろこれは、企業の生産性・創造性を上げるカギになります。
人は「楽しさ=内的報酬」があるときにこそ、最大のパフォーマンスを発揮するからです。
実際、仕事を心から楽しんでいる人は、離職率が低く、顧客満足度やチーム全体の成果にも良い影響を与えることがわかっています。
社員が「この仕事、楽しい」と感じられる状態=エンゲージメント。
それは、定着と活躍を同時に実現する最強の状態です。
1-3. コミットメントとエンゲージメントの違い
「エンゲージメント」は、「コミットメント」と混同されがちです。
- コミットメント…責任・義務感に基づく“やらされ感”
- エンゲージメント…自発的にのめり込む“やりたさ”
コミットメントは、外的報酬(給料・昇進)とトレードオフのような関係で成り立ちますが、エンゲージメントは報酬がなくても自然に「もっとやりたい」と思える状態です。
現代の多様な働き方においては、エンゲージメント型の働き方でなければ、長期的に成果も満足感も維持できません。

2. 本当の「仕事が楽しい」とは?のめり込みのメカニズム
2-1. 外的報酬 vs 内的報酬
仕事の“楽しさ”には、大きく分けて2つの報酬があります。
| 種類 | 例 | 特徴 |
|---|---|---|
| 外的報酬 | 給与、昇進、表彰など | わかりやすいが、効果が持続しづらい |
| 内的報酬 | やりがい、達成感、成長実感など | 見えにくいが、深く持続する |
「結果が出れば給料が上がる」という仕組みは、確かに人を動かします。
しかし、その効果は一時的です。特に、若手社員やZ世代は、“どんな体験をしたか”“どんな意味を感じたか”に強く価値を置く傾向があります。
つまり、仕事そのものが自分にとって意味があるか、面白いか、前に進んでいる実感があるか。
この“内的報酬”があるからこそ、人は自然に前向きに働けるのです。
2-2. “テーマ”より“プロセス”に楽しさを見出す
「やりたいことが見つからないんです」
若手社員からこうした声を聞いたことがある方も多いでしょう。
でも実は、働く楽しさは“やりたいテーマ”からではなく、“目の前のプロセス”から生まれることが多いのです。
- 地味な事務作業でも、「どうすればもっと早くできるか?」を考えるのが好き
- ルーチンワークの中に、自分なりの工夫を見出すのが楽しい
- 「ありがとう」と言われる瞬間にやりがいを感じる
こうした感覚は、自分が何に価値を感じるかという“内発的な動機”に根ざしています。
やりたいテーマが明確でなくても、「やっているうちに楽しくなる」ことは十分あり得ます。
だからこそ、「仕事が楽しい=夢を叶えている」ではありません。
楽しさは、日常の小さなプロセスの中から育てていくものなのです。
2-3. ワーカホリックとの違い:燃え尽きずに働くには
「仕事にのめり込む」と聞くと、「それってただの仕事中毒では?」と思うかもしれません。
ですが、ここには明確な違いがあります。
| タイプ | 原動力 | 結果 |
|---|---|---|
| ワーカホリック型 | 義務感・不安・恐れ | 疲弊・燃え尽き |
| エンゲージメント型 | 好奇心・やりがい・意味 | 成果・満足感・持続性 |
ワーカホリックは、休むことに罪悪感を抱き、常に「もっとやらなければ」と自分を追い詰めます。
一方、エンゲージメント型の働き方では、自然にエネルギーが湧き、集中して働いても疲れにくいのが特徴です。
この状態には、「活力」「献身」「熱中」という3つの要素があります。
- 活力:朝起きたときに「早く仕事がしたい」と思える状態
- 献身:仕事に誇りと意味を感じている状態
- 熱中:時間を忘れて作業に没頭している状態
これらが揃っていると、多少のストレスや困難があっても、「もう少し頑張ってみよう」と前を向けるようになります。
それこそが、真に“強い”人材の特徴です。

3. エンゲージメントを高める3つの感情的資源
3-1. 活力:朝起きて「早く仕事がしたい」状態
「朝、目が覚めたときに“ああ、また仕事か…”と思う」
そんな状態では、どれだけ能力があってもパフォーマンスは出ません。
逆に、「今日はあれをやってみよう」と仕事にワクワクを感じて起きられる状態──
これが、エンゲージメントの最もわかりやすいサインです。
この“活力”は、業務内容そのものだけでなく、
- 自分が成長できているという実感
- チームや上司からの期待
- 目指すゴールへの納得感
など、環境や人との関係からも湧いてくるものです。
だからこそ、日々のマネジメントでは「今どれくらい活力を持って働けているか?」を定期的に確認することが重要です。
1on1や雑談の中で「最近ワクワクした瞬間あった?」といった問いかけをしてみるだけでも、ヒントが得られます。
3-2. 献身:自分の仕事に意味と誇りを持つ
エンゲージメントの2つ目の要素は、「献身(dedication)」です。
これは、「自分のやっている仕事に価値がある」「誇りが持てる」と感じられること。
決して“会社のために犠牲になる”という意味ではありません。
献身がある人は、
- 多少大変でも粘り強く取り組める
- 組織の一員として自分の役割に自覚を持つ
- 自分の仕事が誰の役に立っているかを把握している
という状態になります。
ポイントは、「与えられた目標」ではなく“納得できる目標”に向かっているかどうか。
納得感があるからこそ、責任を持ってやり遂げようとするのです。
この“意味づけ”は、仕事の内容よりも、上司や周囲がどう伝えているかに大きく左右されます。
「この資料作成、面倒かもしれないけど、これがあると営業メンバーが自信を持って提案できるんだよ」
──そんな一言が、仕事の意味をガラッと変えるのです。
3-3. 熱中:時間を忘れて没頭できる仕掛けを
エンゲージメントの3つ目は「熱中(absorption)」です。
これは、気づけば時間を忘れて集中しているような“没入状態”を指します。
ゲームや趣味で「気づいたら2時間経ってた…」という経験、誰もが一度はありますよね。
あの感覚を、仕事でも味わえるかどうかがポイントです。
熱中を引き出すためには、
- 難しすぎず、でも簡単すぎない“ちょうどいい負荷”
- フィードバックが早く、結果がすぐ見える
- 作業の途中で「今、どこにいるか」がわかる
といった“フロー状態”を生む条件を整えることが有効です。
また、「細かい中断を避ける」「集中タイムを設ける」など、物理的な働き方のデザインも効果があります。

4. 若手が「成果」を実感できる職場をつくるには
4-1. 小さな成果の可視化が“やる気”を生む
「成果を出せ」と言われても、特に若手社員にとっては、
何が成果なのか、どのくらいで評価されるのかが見えにくいことがあります。
ここで大事なのは、「小さな成果」を丁寧にすくい上げて伝えることです。
たとえば:
- 「さっきのMTG、発言の切り口が良かったよ」
- 「提出物、前より格段にわかりやすくなってたね」
- 「あの確認フロー、チーム全体が助かったよ」
こうした声かけひとつで、若手は「自分は役に立てている」と感じます。
達成感が可視化されると、人はもっと頑張れるのです。
「褒めすぎると調子に乗る」という声も聞きますが、
適切なポイントでの“承認”は、むしろ責任感を育てます。
4-2. 顧客からの感謝がエンゲージの起点になる
もうひとつ、若手にとって強力なモチベーション源になるのが、“お客さまからの感謝の声”です。
社内の上司や同僚からのフィードバックも大切ですが、
「この人のためになった」と実感できたとき、仕事の意味がグッと深まります。
可能であれば、
- お礼メールを見せる
- 電話対応後に「今の、すごく感謝されてたよ」と伝える
- 顧客アンケートのコメントを共有する
など、顧客のリアクションを可視化する工夫を取り入れるとよいでしょう。
仕事の結果が「誰かの役に立っている」と実感できること。
それこそが、エンゲージメントの源泉です。
4-3. ネガティブ指摘より、ポジティブフィードバック
もちろん、改善点を伝える“指摘”も必要です。
ただ、エンゲージメントを高めたいなら、伝え方が重要です。
- NG:「ここダメだったね」だけで終わる
- OK:「ここは惜しかった。でも、前回より進歩してるね」
人は、否定だけでは改善意欲が湧きません。
一方で、ポジティブなフィードバックがあると、「もっと成長したい」と自然に思えるのです。
特に若手社員は、自分の“成長ストーリー”を意識する傾向があります。
だからこそ、できるだけ進歩・変化・貢献の視点で、フィードバックを重ねていくことが効果的です。
このように、「エンゲージメントを高める仕組み」は、特別な制度やツールがなくても、日々の関わり方の中に実現できる要素がたくさんあります。
次章では、社員が“自走する”ようになる内発的動機づけの工夫について掘り下げていきます。
5. 自走する社員を育てる「内発的動機付け」のコツ
5-1. 自分で目標設定できる環境を整える
人は、自分で決めた目標に対しては、驚くほど責任感を持ちます。
逆に、誰かに押しつけられた目標に対しては、どこか他人事になりがちです。
「主体性を持って動いてほしい」という期待があるなら、
まずは社員が自分で目標を設定できる土壌を整えることが必要です。
もちろん、放任するわけではありません。
「何のために」「どんなゴールを目指すのか」を、上司とすり合わせながら、共に“合意形成”するスタイルが重要です。
今や、マネジメントは「管理」から「支援」へ。
一方的に“与える”のではなく、“引き出す”コミュニケーションが、内発的動機付けの起点になります。
5-2. 意味づけの力:「誰のための仕事か?」を問い直す
目の前の仕事に対して、どんな“意味”を感じているか。
ここが、エンゲージメントの差を決定づける大きな要因です。
- 「なぜこの仕事をやるのか?」
- 「この先に誰が待っているのか?」
- 「どんな価値を生み出しているのか?」
こうした問いかけを日常的に行える組織は、強いです。
意味を自分で“見出せる”人材は、たとえ困難な状況でもへこたれず、創意工夫しながら前に進みます。
逆に、“意味を感じられない”まま働く人は、いずれ疲弊し、離脱してしまいます。
仕事の意味づけとは、モチベーションではなく「人生における仕事の位置づけ」の話。
ここに納得があると、人は“やらされる”のではなく、“やりたくなる”のです。
5-3. 笑いと創造性が、エネルギーを蓄える仕掛け
張り詰めた空気が続く職場では、心も体もエネルギーが持ちません。
だからこそ、“遊び”や“ゆとり”の要素を意識的に取り入れることが、実はとても大切です。
- 雑談OKのミーティングを設ける
- あえて意味のないことをやってみるワークを行う
- チーム内で「笑いのツボ」を共有する
一見、業務とは関係がなさそうに思えるこうした取り組みが、創造性と回復力(レジリエンス)を支えてくれます。
実際、エンゲージメントが高い人は、笑いのあるチームで働いていることが多いのです。
笑いは、信頼関係や心理的安全性を表すひとつのサインでもあります。
楽しい空気のない職場では、アイデアが生まれにくく、失敗も共有されづらくなります。
一方で、笑いのある職場は、前向きな挑戦が生まれやすい環境といえるでしょう。

6. 会社や上司が“障害”にならないために
6-1. 「不当な目標」は聞き流してOK?
働く中で必ずぶつかるのが、「納得できない目標」や「理不尽な指示」。
すべてに全力で応えようとすると、心がすり減ります。
ここで必要なのは、“働く側のスタンス”を決めておくことです。
- その目標は、自分の成長につながるか?
- その指示には、納得できる背景があるか?
- 職場に「対話の余地」があるか?
こうした問いを通して、自分がどこまで応えるかの“境界線”を引いておくことが、健全な働き方を守る上で不可欠です。
企業側も、あらかじめ「目標や働き方は対話によって調整できる」という文化を築いておくことで、早期離職や燃え尽きを未然に防ぐことができます。
6-2. 評論家社員・評論家上司にならないために
何かうまくいかないことがあると、つい「会社が悪い」「上司が悪い」と言いたくなるもの。
逆に上司も、「最近の若手は…」と口にしてしまいがちです。
でも、それでは何も変わりません。
必要なのは、“自分ができること”に意識を向ける姿勢です。
- 社員側 →「自分にできる小さな工夫はあるか?」
- 上司側 →「どうすればもっと相手の力を引き出せるか?」
評論家になるのは簡単です。行動する人が、職場を動かします。
エンゲージメントの高い組織には、「できる人」ではなく、「動く人」がいます。
“人のせいにしない文化”は、信頼と協力の基盤となります。
6-3. “正当な楽しさ”がある組織文化へシフトしよう
最後に大切なのは、「仕事が楽しい」と口にできることを、当たり前として受け入れられる組織文化です。
- 辛さを美徳としない
- 忙しさでマウントを取らない
- 楽しく働く人を白い目で見ない
こうした“昭和的メンタルモデル”が残っている職場では、エンゲージメントはなかなか育ちません。
一方で、「楽しいって言っていい」「もっと楽しもう」と言える雰囲気があれば、
自然と人はアイデアを出し合い、互いに支え合いながら成果を生み出すようになります。
仕事における“楽しさ”とは、甘えではなく、前向きな力や創造性を引き出す原動力なのです。


サービスの
ご紹介
エンゲージメントを高めるには、本人の努力だけでなく、組織側の理解と設計が不可欠です。TG-WEBでは、ストレス対処力を測定する「G9(コーピング適性検査)」と、活力・献身・熱中といった“のめり込み資源”を測定する「Q1(ジョブ・クラフティング適性検査)」をご提供しています。社員がどんな環境で力を発揮し、どんな支援があると前向きに働けるのか──そのヒントを見える化する手段として、ぜひ一度導入をご検討ください。

コーピング適性検査 G9

ジョブ・クラフティング
適性検査 Q1

© Humanage,Inc.

