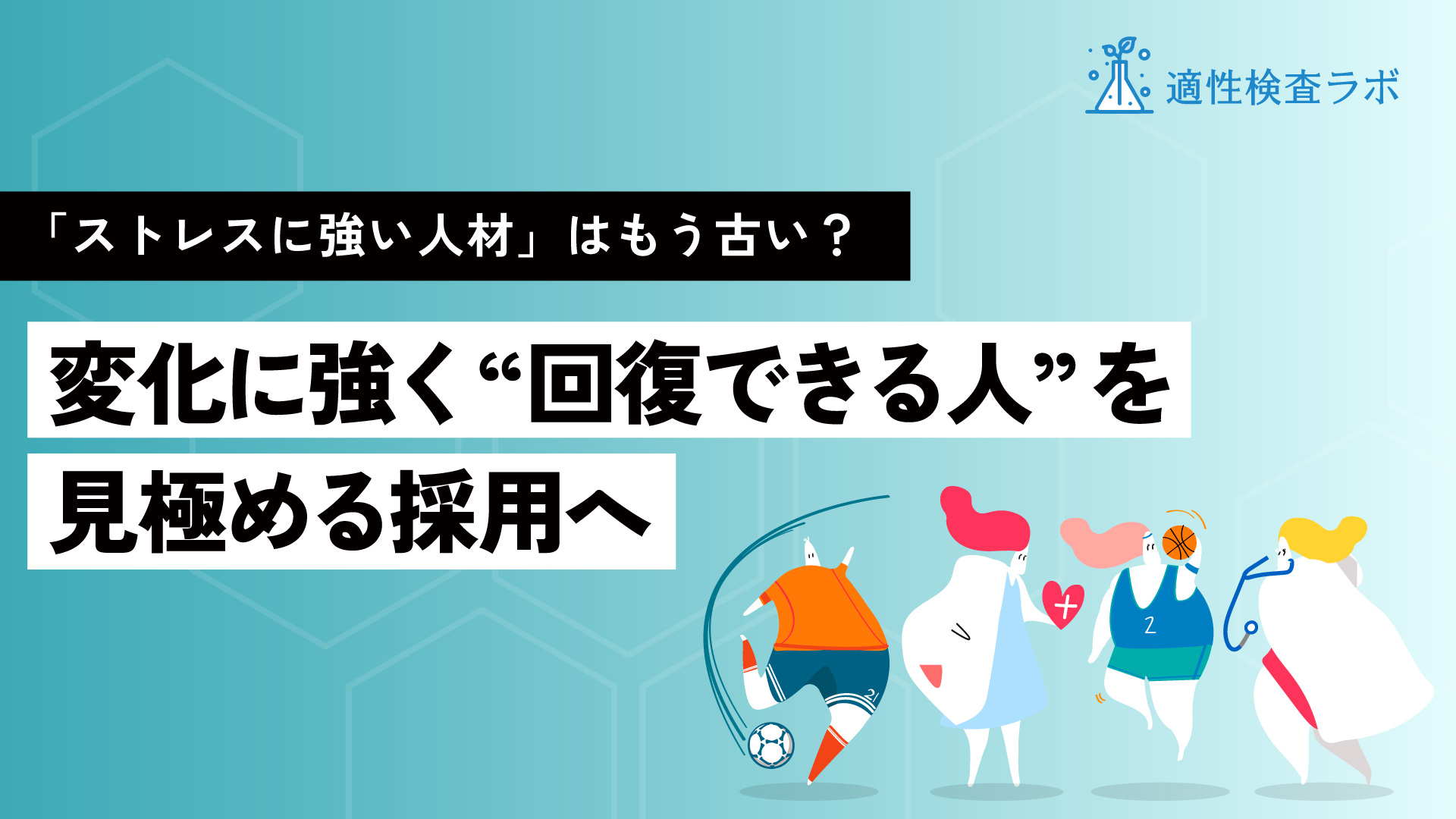
2025.09.12
「ストレスに強い人材」はもう古い?変化に強く“回復できる人”を見極める採用へ
はじめに
ビジネスの現場では「ストレス対策」が注目されていますが、実は“ストレス”という言葉の使い方に誤解が多いのをご存じでしょうか?
原因となるストレッサーと、体や心に出るストレス反応が混同されているため、対策が的外れになりがちです。
最近の職場で増えているのは「うつ病」そのものではなく、環境のプレッシャーによって一時的に落ち込む「うつ状態」。リモートワークの孤立感やSNSによる比較など、新しいストレス要因も登場しています。
だからこそ今求められるのは、耐える強さではなく“しなやかに対処する力”。この記事ではそのポイントと、採用・育成で活かせる適性検査の視点を解説します。
INDEX
1. 「ストレス」の誤解が企業を混乱させる
2. 増えているのは「うつ病」ではなく「うつ状態」
3. リモートワーク時代のストレッサーとは?
4. 折れない人材の共通点|ストレス対処力(コーピング力)
5. 適性検査で見抜く“折れない若手”とは?
6. これからの採用に必要な視点
サービス紹介
1. 「ストレス」の誤解が企業を混乱させる
1-1. ストレス=悪?その認識が逆効果に
「ストレス=悪」と考えていませんか?多くの企業で見られるこの認識は、実はストレス対策を見誤らせる原因になっています。
ストレス自体は、生理的にも心理的にも人間に備わった自然な反応です。緊張感や不安があるからこそ、集中力が高まり、成長につながるケースも少なくありません。問題なのは、過剰なストレッサーや、持続的なストレス状態に陥ることで、心身に悪影響が出てしまうことです。
本来、適度なストレスは「良いプレッシャー」として働きます。ところが現場では、ストレス=排除すべきものと捉え、対処すべき対象があいまいなまま対策が講じられていることが多く見られます。
1-2. 「ストレッサー」と「ストレス反応」の混同
「上司がストレスだ」「ストレスで体調が悪い」——このように語られる“ストレス”には、実は二つの意味が含まれています。
前者はストレスの原因であるストレッサー(刺激・環境)を指し、後者はその結果としてのストレス反応(身体や心の変化)を指しています。
心理学的には、この2つを厳密に区別して扱います。しかし実際の企業や日常会話では、それらが混同され、「ストレス=漠然とした嫌なもの」として認識されがちです。そのため、何を解決すれば良いのかが曖昧なまま、ストレス対策が場当たり的に行われてしまうのです。
1-3. ほとんどの企業が“反応”だけを対処している
現在、企業のストレス対策は、ストレス反応を和らげるリラクゼーション型の取り組みに重きが置かれるケースが多く見られます。
マインドフルネス、アロマ、カウンセリング、福利厚生の充実などは大切な施策ですが、これらは主に「結果への対処」であり、「原因の解消」までにはつながらないこともあります。
たとえば、長時間労働や理不尽な指示といったストレッサーが放置されれば、休養や癒やしの施策だけでは十分な改善が期待しにくいでしょう。
つまり、ストレス反応を和らげる施策に加え、ストレッサーそのものを見極めて対応する視点も重要になってきます。

2. 増えているのは「うつ病」ではなく「うつ状態」
2-1. 適応障害とは何か?
近年、メンタル不調を訴える社員が増え、「うつ病が増えている」と感じる企業は多いかもしれません。
しかし実際に増えているのは、「うつ病」ではなく、環境的な要因によって一時的に心身のバランスを崩す適応障害=うつ状態です。
適応障害は、「ストレッサーが存在すること」が明確な前提です。
たとえば、「業務負荷が大きすぎる」「人間関係が著しく悪い」「業務の意味を感じられない」といった状況下で、気分の落ち込みや睡眠障害、集中力低下などの症状が現れる状態を指します。
2-2. ストレッサーがある限り、状態は続く
適応障害の特徴は、ストレッサーが取り除かれれば比較的短期間で回復するという点です。
つまり、根本原因が業務過多であれば、業務の見直しや配置転換で症状が軽快する可能性が高いのです。
しかしこの状態が放置されると、本人のエネルギーは消耗し続け、慢性化・深刻化していきます。
重要なのは、「本人の性格の弱さ」ではなく、「環境に対して適応困難が生じている」こと。企業として、個人を責めるのではなく、ストレッサーを正しく捉えて調整する視点が求められます。
2-3. 一時的なうつ状態を「うつ病」と誤認する危険
うつ状態は、あくまで環境起因の一時的な反応です。
それにもかかわらず、「この人はもううつ病だから復職は難しい」といった誤解が広がると、回復可能な人材を見捨ててしまうリスクがあります。
また、本人自身が「自分はもうダメだ」と思い込んでしまうこともあります。
しかし、ストレッサーを取り除いたり、周囲の支援を得ることで、驚くほどスムーズに回復する例は多くあります。
うつ病との混同を避けるためにも、ストレス反応の背景にある環境要因に目を向ける視点が必要です。

3. リモートワーク時代のストレッサーとは?
3-1. 「人間関係ストレス」から「孤立ストレス」へ
以前は、上司・同僚との人間関係がストレスの中心にありました。しかし、リモートワークやハイブリッド勤務が当たり前となった現在、多くの社員が新たな形のストレスに直面しています。それが「孤立ストレス」です。
物理的な距離が心理的な距離にもつながり、気軽な雑談や相談の機会が失われ、「誰ともつながっていない」と感じる孤独が心身に影響を与えるケースが増えています。
表面的には業務が回っていても、内面では「自分の頑張りが見えていない」「誰も気にかけてくれていない」と感じる状態が蓄積し、ストレス反応を引き起こしているのです。
3-2. SNSと成果主義が若手を追い詰める
現代の若手社員が抱えるもうひとつのストレッサーは、成果への過剰なプレッシャーです。
SNSを通じて他者の成果がリアルタイムに可視化される時代において、若手は常に“誰かと比べられている”という無言の圧力を感じています。
特に、成長スピードの速い同期や、影響力のある上司の存在は、「自分はダメだ」「置いていかれている」という無力感を生み出します。成果主義自体が悪ではありませんが、評価基準が明確でなかったり、支援が伴わなかったりすると、成果を出せない自分を責め、メンタル不調に陥る若手が増加します。
3-3. 30代管理職手前が“第2の山”に直面する理由
もうひとつ、見落とされがちなのが「30代後半〜管理職手前層」に増えているメンタル不調です。
この世代は、プレイヤーとして成果を出すだけでなく、後輩指導やマネジメントも求められ始める時期。
にもかかわらず、明確なロールモデルや十分な教育が用意されていないことも多く、「期待に応えられない自分」への自己否定感が強くなりがちです。
さらに、ライフステージの変化(育児・介護など)も重なり、「会社でも家庭でも苦しい」という板挟み状態に陥るケースも。ストレッサーは若手だけでなく、“もう折れてはいけない立場”の層にも確実に広がっているのです。

4. 折れない人材の共通点|ストレス対処力(コーピング力)
4-1. 我慢するのではなく「対処」する力
「ストレスに強い」とは、単に我慢強い人を指すわけではありません。むしろ、我慢に頼りすぎる人は、限界を超えた時に一気に崩れる危険性があります。
本当に折れない人材とは、ストレスに対して柔軟に“対処できる人”のこと。つまり、感情を抑え込むのではなく、「どうすれば乗り越えられるか」を自分なりに考え、行動できる力がある人です。
この“ストレスへの対処行動”のことを、心理学では「コーピング」と呼びます。
4-2. 問題解決コーピングと支援獲得コーピング
コーピングにはいくつかの種類がありますが、特にビジネスシーンで重要なのが以下の2つです。
問題解決コーピング
原因を明確にし、自ら行動を起こして状況を改善しようとするスタイル。たとえば、「上司とのすれ違いを話し合いで解消する」「業務の優先順位を見直す」といった対応です。
支援獲得コーピング
自分一人で抱え込まず、上司・同僚・家族など周囲に助けを求めるスタイル。たとえば、「一人では抱えきれない業務量を相談する」「メンタル面の不調を上司に共有する」などが該当します。
この2つのコーピングができる人材は、変化や困難な状況でも粘り強く対応しやすく、結果として「折れにくい」人材といえます。
4-3. 「支援を求める力」は今の時代の武器
支援を求めることに抵抗を感じる人は少なくありません。「迷惑をかけたくない」「弱く見られたくない」という心理が働くからです。
しかし現代の複雑でスピードの速い仕事環境では、“助けを求めるスキル”はむしろ成果に直結する力となっています。
一人で抱え込むことでエラーが起きたり、限界まで我慢した結果として離脱するより、早めに声を上げて周囲と連携できる人の方が、チームにも企業にも貢献しやすいのです。
「支援を求める力」は決して弱さではなく、適応力と主体性の現れ。この視点を採用にも、育成にも組み込んでいくことが、これからの企業に求められています。
5. 適性検査で見抜く“折れない若手”とは?
5-1. ストレス耐性ではなく「対応力」を測る
従来の「ストレスに強い人材」の見極めは、「我慢強いかどうか」「打たれ強いかどうか」といった“耐える力”に焦点が当てられていました。
しかし今の時代、それだけでは不十分です。
環境の変化が激しく、ストレッサーの種類も多様化している現代では、耐える力よりも“どう対応するか”の行動力が求められます。
たとえば、「業務負荷が高い」「人間関係がギクシャクしている」といった状況に対し、問題を言語化したり、支援を求めたり、工夫して乗り越えられる人が、“折れにくい”人材なのです。
つまり、「ストレス耐性」よりも「ストレス対応力(=コーピング力)」の有無こそ、採用で見るべきポイントになっています。
5-2. 現代型の適性検査で“ストレス対応力”を可視化する
では、こうした「対応力」はどうすれば見抜けるのでしょうか?
現代の適性検査では、ストレスを受けた際にどんな行動を取る傾向があるか(=コーピングスタイル)を測定できるものもあります。
例えば、以下のような特性を可視化できます。
- 問題を冷静に分析し、打開策を考える傾向があるか
- 感情的に反応しがちか、抑えがきくか
- 周囲に助けを求めることに抵抗があるかどうか
- ストレス状況でも粘り強く関与し続けるか、すぐに諦めるか
これらは、書類や面接だけでは見抜けない領域です。反応ではなく「行動傾向」や「価値観」に踏み込んだ設計がなされているため、表面的な印象に惑わされず、実際の職場適応力を判断できます。
5-3. 面接では見えない“折れやすさ”の正体
面接では、誰もが「前向きで、頑張れる人間」に見えます。
特に新卒や若手の応募者は、受け答えの模範解答を準備して臨んでおり、「本音」や「反応のクセ」は隠れがちです。
たとえば、「ストレスがかかると自責的になりすぎて自分を追い込むタイプ」や、「支援を求められず、孤立しやすいタイプ」などは、面接では非常に“優等生”に見えることも多いのです。
こうした傾向は、職場に入ってからじわじわと表れ、突然離脱やメンタルダウンにつながるリスクになります。
だからこそ、採用段階で“折れやすさ”を見極めるには、適性検査の活用が効果的です。特に、ストレッサーへの対処行動や思考パターンに焦点を当てた検査は、現代の採用において欠かせない視点となっています。

6. これからの採用に必要な視点
6-1. 「状況変容型」コンピテンシーが未来をつくる
これからの時代に必要とされるのは、「どんな環境でも同じように力を発揮する人材」ではなく、状況に応じて柔軟に行動を変え、適応していける人材です。これを、「状況変容型コンピテンシー」と呼びます。
変化に強い人材は、万能で完璧なのではありません。
むしろ、自分にとって不利な状況や困難な場面に直面したときこそ、行動を切り替えたり、周囲の力を借りたりすることができる。そうした“変化に対応できる柔軟性”が、これからの企業に必要な力なのです。
6-2. 採用は“結果”ではなく“回復力”を見る時代へ
これまでは、「成果を出したことがある人」「高い能力を持っている人」が採用で重視されてきました。
しかしこれからは、「失敗や挫折をしたとき、どう立ち直るか」「回復力があるか」といった“プロセス”や“柔軟性”に注目が集まっています。
特に若手・未経験層の採用においては、過去の実績よりも、困難への向き合い方や乗り越え方の方が、長期的な定着や成長に直結します。
言い換えれば、「成果主義」よりも「回復主義」にシフトしているのが、現代の採用の潮流です。
6-3. 採用後のオンボーディングと支援体制の再設計
採用で“折れにくい”人材を見極めるだけでなく、入社後の支援設計も重要です。
今、多くの企業で問われているのは、「採用後にどう育て、どう守るか」という視点です。
- 新人が最初に孤立しないようなメンター制度の設計
- ストレス状況を早期にキャッチする仕組み(アンケート・1on1)
- コーピング力やレジリエンスを育てる研修や面談の導入
こうしたオンボーディング施策が、「せっかく採った人材を離脱させない」鍵となります。
適性検査と面接でポテンシャルを見抜き、入社後に適切な環境と支援を提供する。この一連の流れが、これからの採用・定着戦略に欠かせない視点です。


サービスの
ご紹介
面接では見抜けない「折れやすさ」や「対応力」を見極めるには、TG-WEBのG9とB5の併用が効果的です。
G9では、ストレス状況でのコーピング行動(対処スタイル)を可視化し、B5では性格傾向や対人スタイルを多面的に把握可能。
“どんなときに崩れやすいか”“どの環境で力を発揮するか”を見抜くことで、採用だけでなく配属・育成・定着支援まで活用できます。
特に変化の大きい今の時代には、耐える力よりも対応する力を見極める視点が企業に不可欠です。ぜひ導入を検討してみてはいかがでしょうか。

コーピング適性検査 G9

ベーシックパーソナリティ
適性検査 B5

© Humanage,Inc.

