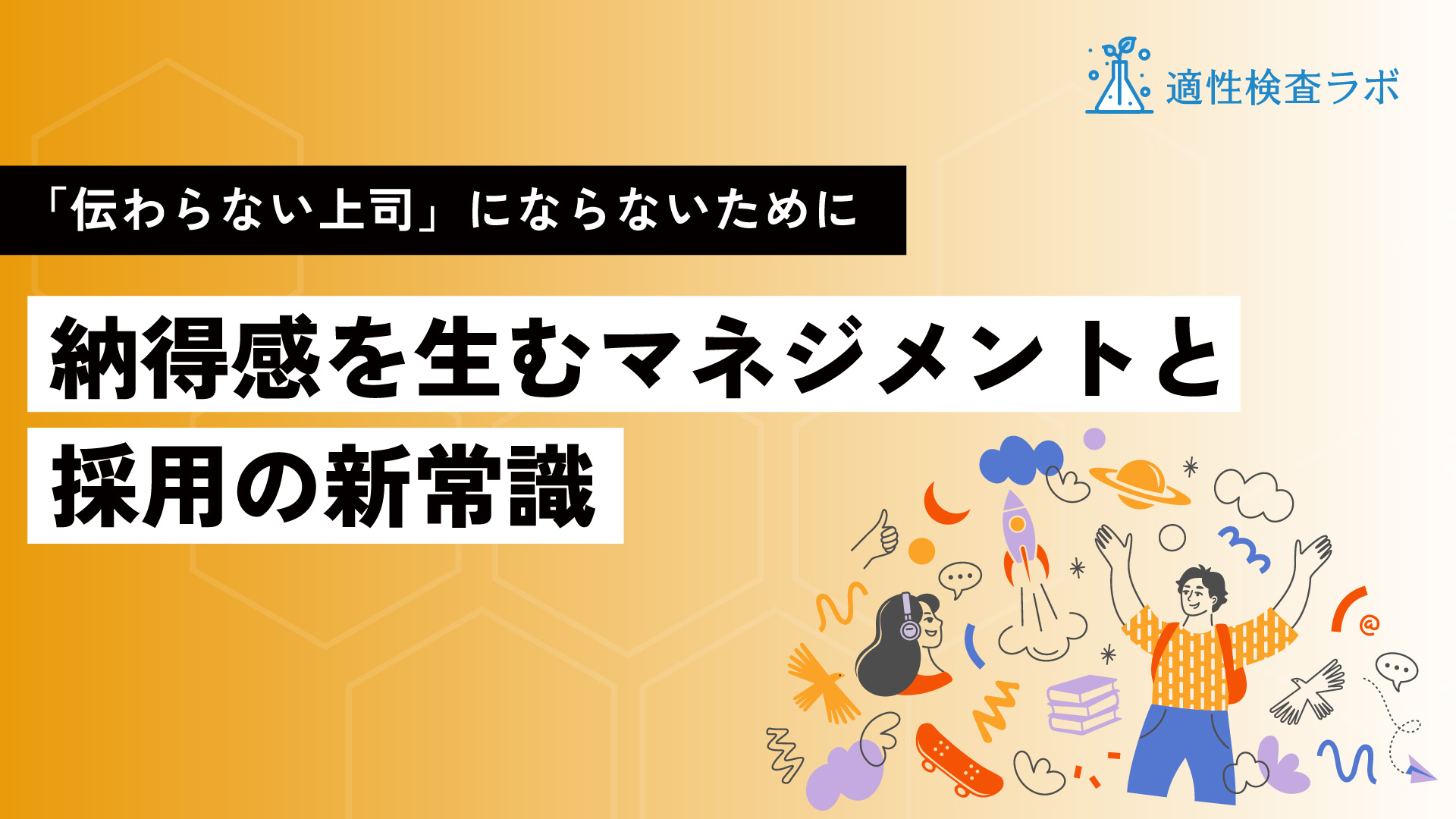
2025.09.05
「伝わらない上司」にならないために──納得感を生むマネジメントと採用の新常識
はじめに
「なんとなく伝わらない」「きちんと説明したつもりなのに、納得してもらえない」
そんなふうに感じたことはありませんか?
上司の立場や制度のルールだけでは、人はもう動いてくれない――
価値観が多様化し、“従うのが当たり前”ではなくなった今、相手にきちんと伝え、理解してもらう力が、これまで以上に問われています。
採用の場でも、「スペックは十分なのに、なぜかフィットしない」「どこがうまくいかなかったのか分からない」
といった“見えづらい違和感”に直面することがあるはずです。
この記事では、現代の組織で本当に求められている“人を動かす力”と、その力をどう見抜き、どう育てていくか――
そんな問いに、行動特性の視点から迫っていきます。
INDEX
1. 「正当パワー」が求められる時代へ
2. 信頼される上司・尊重される組織の条件
3. 高コンピテンシー人材の6つの行動特性
4. 「指示通りの優秀さ」を超える人材とは
5. 「できる力」を見える化する適性検査の役割
6. 「正当な自分」を支える人材マネジメントとは?
サービス紹介
1. 「正当パワー」が求められる時代へ
1-1. ソーシャルパワーとは何か?
組織において、人が人を動かすとき、そこには「力(パワー)」が介在します。心理学や組織論では、これを「ソーシャルパワー」と呼び、主に5つに分類されます。
- 報酬パワー(報酬や昇進などを与える力)
- 準拠パワー(人間的魅力による影響力)
- 専門パワー(知識やスキルに基づく信頼)
- 強制パワー(叱責や罰を与える力)
- 正当パワー(役割や規範に裏付けられた納得感のある影響力)
このうち、もっとも深く・持続的に人を動かすのが「正当パワー」です。
それは、「なぜこの指示を出すのか」「なぜこの判断をしたのか」を、きちんと言語化し、相手に納得してもらう力のことです。
1-2. なぜ「正当パワー」が注目されているのか
かつての日本型組織では、「上司の命令には従うのが当たり前」という空気が支配していました。しかし今は、働く人の価値観が多様化し、従来のような上下関係や常識が通用しない場面も増えています。
報酬パワーや強制パワーは短期的には効力があるかもしれませんが、信頼や主体性を生み出すことはできません。
今、企業が本当に必要としているのは、納得と共感によって人を動かせる「正当パワー」を持った人材です。
特にZ世代以降は、「なぜそれをやるのか」「その仕事に意味があるのか」に非常に敏感です。
言い換えれば、“説明責任”を果たせないリーダーや組織は、簡単に見透かされてしまうのです。
1-3. 支配から共創へ:リーダーシップの進化
現代に求められるのは、指示命令型の「支配的リーダーシップ」ではなく、メンバーとの共創を前提としたリーダーシップです。
上司だから従うのではなく、「この人の言うことなら納得できる」「一緒にやりたい」と思わせる力。それが、正当パワーです。
そしてこの力は、肩書きや経験年数ではなく、日々の言葉と行動の積み重ねでしか育ちません。
だからこそ、誰もが「正当な力」を持てる可能性を持ち、それをどう育てるかが問われる時代なのです。

2. 信頼される上司・尊重される組織の条件
2-1. 「不当さ」はどこから生まれるのか
不当な上司、不当な組織。そう聞くと、どこか極端で特殊な存在のように思えるかもしれません。
しかし実際は、「なんとなく納得できない」「なぜその指示が出たのか分からない」という日常の小さな不透明さが、組織の“不当さ”として蓄積されていくのです。
不当さは、明確な悪意や暴力だけでなく、説明不足・感情的な判断・場当たり的な対応といった、曖昧なふるまいの中にも潜んでいます。
この小さな不信の積み重ねが、やがて大きな離職や不祥事、組織崩壊につながることもあります。
2-2. 上司の説明責任と、部下の納得感
信頼される上司とは、常に“正しい判断”ができる人ではありません。
重要なのは、「なぜその判断をしたのか」を言語化し、相手に伝える責任を果たせるかどうかです。
部下にとっての納得感は、上司が完璧であることではなく、誠実に説明しようとする姿勢にこそ宿ります。
また、納得感は一方的に「与えるもの」ではなく、対話を通じて共につくっていくものです。
指示と理解のあいだに“対話の余地”があることが、正当パワーを生む土壌になります。
2-3. 心理的安全性が、正当パワーを支える
現在、多くの企業やチームビルディングの研究において注目されているのが、「心理的安全性(Psychological Safety)」という概念です。
これは、「自分の意見を率直に言っても大丈夫」「ミスしても否定されない」という信頼感のある職場環境を指します。
この心理的安全性が確保されていないと、たとえ上司が正論を伝えていたとしても、部下は心を閉ざし、指示は響きません。
逆に、安心して発言できる環境があるからこそ、人は本音を語り、主体的に動き出せるのです。
つまり、正当パワーはただ「説明すればいい」「筋が通っていればいい」ものではありません。
相手の声に耳を傾け、対話できる空気を醸成できるかどうか――それこそが、現代のマネジメントに求められる力なのです。

3. 高コンピテンシー人材の6つの行動特性
3-1. 課題として捉え直す視点
問題に直面したとき、そこから逃げるか、立ち向かうか。それだけでなく、「どう捉えるか」も、行動の質を大きく左右します。
高いコンピテンシーを持つ人は、問題を「障害」ではなく、「解決すれば前に進める課題」として再定義します。
これは思考の柔軟性であり、自己効力感の現れでもあります。
「できない理由」ではなく、「どうすればできるか」に視点を向ける。
この前向きな構えが、変化を自ら生み出す力につながっていきます。
3-2. 自分なりのペースで一歩を踏み出す
「まずやってみる」という言葉は正しい反面、プレッシャーにもなりがちです。
しかし、高コンピテンシー人材は、自分の中にある“納得”を起点にして、行動を起こすことができます。
他者に合わせて無理をするのではなく、内発的な動機に基づいた一歩を、自分のペースで踏み出すことが重要です。
それは小さな行動かもしれませんが、当人にとっては大きな前進です。
“行動できる人”とは、「大きく動ける人」ではなく、「動こうとする意志を持つ人」です。
3-3. 情報発信と、沈黙の価値を両立する
かつては「情報を持っている人が強い」とされましたが、今は「情報をどう発信するか」が問われています。
高いコンピテンシーを持つ人は、必要な情報をタイミングよく共有し、周囲との認識を合わせることができます。
一方で、発信ばかりが評価されるわけではありません。
あえて発信しない「沈黙」の選択が必要な場面もあります。
伝えるべきときに伝え、黙るべきときは黙る――その判断ができるのも、成熟した発信力の一部です。
3-4. 状況変化に気づく感受性
物事の“空気”や“変化の兆し”を敏感に察知できる人は、環境への適応が早く、チャンスも逃しません。
ここで言う感受性とは、感情的に揺れやすいということではなく、状況の微細な変化をキャッチできる認知の感度です。
高コンピテンシー人材は、固定観念に縛られず、フラットな視点で物事を観察しています。
そのため、表面的には何も起きていないような場面でも、小さな違和感に気づき、行動につなげることができます。
3-5. 思いつきで動かず、考えて整える
「変化を起こす人」は、突飛なアイデアを出すだけの人ではありません。
高いパフォーマンスは、綿密な分析と、丁寧な判断の積み重ねによって生まれます。
一見、直感的に動いているように見える人でも、その背後には日頃の観察・学習・思考の積み重ねがあるのです。
思いつきをただの思いつきで終わらせず、構造化して、行動の選択肢に落とし込む。
それが、コンピテンシーの高い人の思考スタイルです。
3-6. 自分の言葉で、伝わる表現を選ぶ
高コンピテンシー人材は、難しいことを難しく語るのではなく、本質を自分の言葉でわかりやすく伝える力を持っています。
専門用語を並べて賢く見せようとするのではなく、相手の立場に立ち、「どうすれば伝わるか」を考え抜くのです。
また、「自分の言葉で語る」ということは、自分の考えに責任を持つということでもあります。
曖昧な他人の言葉ではなく、確かな理解に基づいた発信が、信頼と共感を生むのです。

4. 「指示通りの優秀さ」を超える人材とは
4-1. 変化に適応するだけでなく、創り出す
これまでの企業では、環境の変化に“素早く対応できる人”が優秀とされてきました。
しかし、今は変化のスピードが速すぎて、受け身の適応だけでは追いつかない時代です。
だからこそ必要なのは、自ら変化を創り出す人材です。
与えられた枠組みの中で優秀であるだけでなく、新しい課題を発見し、チームや組織を前に進められる人が求められています。
4-2. 組織に依存せず、目的を共有する
優秀な人材とは、「言われたことを正確にこなす人」ではありません。
むしろ、「この目的のために、何ができるか」を自ら考え、組織と対等な関係で動ける人が評価されるようになっています。
いま、組織に求められるのは相互依存型の関係性です。
つまり、社員は会社に依存せず、会社も社員に頼りきらない。お互いが目的を共有し、協力し合える関係が理想です。
4-3. 多様な価値観とマッチする採用へ
「真面目で、指示通りに動く人」は、かつての採用基準では理想的でした。
しかし今は、個人の強みや価値観を尊重し、いかに組織との“相互マッチ”が取れるかが重視されています。
それぞれの人が持つコンピテンシーの特性を把握し、活躍しやすい環境を見つける。
その視点に立つことで、「良い人材を採る」から「合う人材と出会う」採用へと、考え方がシフトしてきています。
5. 「できる力」を見える化する適性検査の役割
5-1. 自分の認識と他者評価のギャップに気づく
採用や配属の場面で、「期待した人物像と実際の行動が違った」という経験はありませんか?
人は、自分自身の強みや弱みを客観的に捉えるのが難しく、面接や履歴書の情報だけでは本質を見抜けないことがあります。
適性検査は、本人の自己認識と客観的な行動傾向のズレを可視化するための有効な手段です。
これにより、企業側は「本人の言葉では見えづらい部分」にもアプローチでき、より精度の高い人物見極めが可能になります。
5-2. 成果だけでなく、働き方の相性も測る
いくら能力が高くても、その人に合わない環境に配属すれば、力は発揮されません。
逆に、少し不安のある人材でも、適したチームや上司のもとでは、高い成果を上げることがあります。
今、求められているのは「能力」だけでなく、働き方のスタイルや価値観のマッチングです。
適性検査を通じて、「この人がどう働くのか」「どのような場面で活躍しやすいか」を把握することが、ミスマッチのない採用・配属・育成を支えます。
5-3. 配属・育成・離職防止に活かせる可能性
適性検査は採用選考だけでなく、配属判断・OJT設計・リーダー育成・離職リスクの予測など、幅広い領域で活用されています。
たとえば、コンピテンシー傾向を分析すれば、「この人は指示型の上司と相性が良い」「抽象的なミッションには弱い」といった“働き方のクセ”が見えてきます。
こうした情報は、面談・フィードバック・人材配置戦略の根拠として活用可能です。
感覚や経験則だけに頼らない、科学的な人材マネジメントを実現する手段として、適性検査の導入は非常に有効です。

6. 「正当な自分」を支える人材マネジメントとは?
6-1. 日々の選択が「その人の仕事力」をつくる
個人のパフォーマンスは、「スキルの高さ」だけで決まりません。
目の前の課題にどう向き合うか、どう判断し、どう選択するか――
その日々の行動こそが、その人の「仕事力=コンピテンシー」を形づくっていきます。
採用時点では見えにくいこの“思考と行動のクセ”を、可視化・言語化しておくことが、長期的な人材活用のカギとなります。
6-2. 周囲との関係性を育てる力を評価する
コンピテンシーは「個の能力」だけではありません。
今の時代、重要なのはチームや上司と信頼関係を築き、組織に影響を与える力です。
つまり、どれだけ優秀でも、「孤立する人」や「信頼されない人」は活躍しづらくなってきています。
適性検査は、個人がどのような関係性の中で力を発揮するかを見極めるツールとしても機能します。
人の「ポテンシャル」を、関係性の文脈で評価できることは、今後ますます重要になります。
6-3. 自社の未来をつくる人材をどう見抜くか?
これからの採用・配属・育成で求められるのは、単なる「即戦力」ではありません。
環境に適応し、周囲を巻き込み、正当な理由と言葉で人を動かせる力――それが、これからの企業を支える人材像です。
その人が“どんな力を持っているか”だけでなく、
“どんなときにその力を発揮できるか”を見抜くには、感覚ではなく、構造化されたツールが必要です。
適性検査はその第一歩です。
単なる選抜ツールではなく、人と組織の未来をつくる「対話の起点」として、導入を検討していただきたいと考えています。


サービスの
ご紹介
人の力は、肩書きや過去の経験だけでは測れません。
「どんなふうに課題に向き合うか」「周囲とどう関係を築くか」といった、日々の思考や行動の積み重ねこそが、その人の“仕事力”を形づくります。
そうした“見えづらい力”を可視化する手段として、適性検査の活用が注目されています。
TG-WEBの「A8」では、変化対応力や課題への取り組み方など、業務遂行に必要な9つの行動特性から“できる力”を測定。
「W8」では、上司や同僚との信頼構築、情報共有のスタイルといった“チームの中で活きる力”を見える化します。
これからの人材マネジメントでは、「誰を選ぶか」だけでなく、「どう活かすか」がより重要に。
TG-WEBの導入を、ぜひご検討ください。

コンピテンシー適性検査 Another8

チーム・コミュニケーション適性検査 W8

© Humanage,Inc.

