
2025.08.29
適性検査で若手マネジメントが変わる!納得感と自律を育む新手法
はじめに
「最近の若手は何を考えているのかわからない」「頑張って育てようとしても、すぐに辞めてしまう」──
そう感じたことのあるマネジャーや人事担当の方は、決して少なくないはずです。
上司世代と若手世代の間には、「働く意味」や「動機づけの構造」に関する根本的な価値観の違いがあります。
本記事では、そのギャップの正体を明らかにし、若手のエンゲージメントを高めるために必要な視点や対話のヒントをご紹介します。
また後半では、適性検査を活用したマネジメント手法にも触れていきます。
若手育成に悩む現場の方にこそ、お読みいただきたい内容です。
INDEX
1. 上司と部下のギャップ:何が「わかり合えない」のか?
2. 旧時代のパラダイム:なぜもう通用しないのか?
3. 「働く動機」の進化:外的報酬から内的報酬へ
4. なぜ若手が辞めるのか?エンゲージメントを生む“正当さ”の重要性
5. 多様性が価値を生む:パフォーマンスを引き出す適性理解
6. いま適性検査が再注目されている理由
サービス紹介
1. 上司と部下のギャップ:何が「わかり合えない」のか?
1-1. 世代間で異なる「働く意味」
2025年現在、企業内では昭和・平成生まれの管理職と、Z世代〜ミレニアル世代の若手社員との間に大きな「働く意味」のズレが生じています。上司世代は「出世・収入」をモチベーションに、理不尽にも耐えて働くことが美徳とされてきました。
一方、Z世代を中心とした若手は、「自分らしさ」「納得感」「共感」を働くうえで重視しており、外的報酬(給与・肩書き)よりも内的報酬(成長実感・やりがい)に価値を置きます。この価値観の変化こそが、「わかり合えない」根本原因です。
1-2. 「上司の言うことに納得できない」若手の心理
現代の若手社員は、「なぜそれをやるのか」「自分にどんな意味があるのか」に納得できなければ動きません。「上司が言うから」「ルールだから」といった動機づけは通用せず、むしろ反発や無関心を生むことさえあります。
これはサボりや甘えではなく、情報が溢れ、選択肢も多様化した時代を生きてきた彼らなりの“リスク回避”とも言えます。納得できないまま無理に働くことで心身をすり減らすくらいなら、無理をしない──それが彼らの防衛本能なのです。
1-3. 働き方の前提が変わった令和時代
かつて「仕事は我慢と忍耐」「プライベートは犠牲にするもの」とされていた時代は終わりました。今や「ワークライフバランス」「自律的な働き方」「心理的安全性」といったキーワードが主流です。
副業・リモートワーク・柔軟な働き方が浸透する一方で、会社への帰属意識や忠誠心は薄れつつあります。企業にとっては、「社員を縛る」より「社員に選ばれる」存在であることが求められているのです。

2. 旧時代のパラダイム:なぜもう通用しないのか?
2-1. 昭和型の“3つの掟”とは
かつて多くの企業で暗黙の了解とされてきた「三つの掟」がありました:
- プライベートを犠牲にして働くこと
- 個人の価値観を持ち込まず、会社の方針に従うこと
- 仕事は辛くて当たり前、歯を食いしばってでもやり通すこと
これらは、長期雇用と年功序列の安定が保障されていたからこそ成り立っていました。しかし現代では、その保証は崩れ、働く個人も変化を求めています。
2-2. ハングリー精神と成果主義の限界
1990年代以降、多くの企業が成果主義を導入し、「頑張れば報われる」社会をつくろうとしました。しかし現実には、「上司の主観で評価が決まる」「成果が出ても昇進しない」など、制度の限界が浮き彫りになっています。
若手社員は、先輩たちの疲弊した背中を見て育ってきました。出世しても家庭を顧みず、健康を害してまで働く姿に、未来を感じられなくなっているのです。かつての「出世こそ成功」のモデルは、もはや憧れではなくなっています。
2-3. 精神論マネジメントの終焉
「気合いが足りない」「ハングリーさがない」「逃げずにやり切れ」といった言葉は、今や逆効果です。こうした精神論に対し、若手は「何を言っているかわからない」と感じています。
精神論は人を一時的に動かすかもしれませんが、長期的な成果や信頼関係は生まれません。今必要なのは、「個人の価値観に寄り添いながら、どうすれば自律的に仕事を楽しめるか」を一緒に考え、支援するマネジメントです。
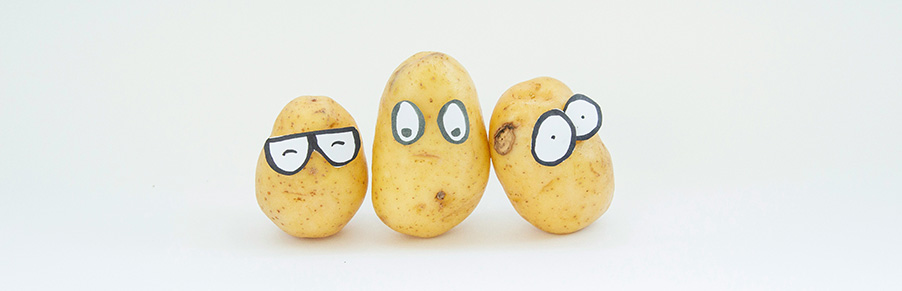
3. 「働く動機」の進化:外的報酬から内的報酬へ
3-1. 欠乏動機から成長動機へ
これまでの働く動機は、「お金が欲しい」「安定が欲しい」「評価されたい」といった“欠乏動機”が中心でした。何かが足りないから、それを埋めるために働く――そうしたモチベーションは、長らく当たり前とされてきました。
しかし近年の若手社員は、より“成長動機”にシフトしています。つまり、「自分が何者になれるのか」「どんな力をつけていけるのか」に価値を感じ、動機づけされる傾向があります。
これは、自己実現欲求や自己成長の欲求が、従来よりもずっと早い段階から顕在化していることを意味します。だからこそ、働く環境や上司が「成長につながっている」と実感できなければ、モチベーションは持続しません。
3-2. 若手が求めるのは「面白い仕事」と「成長実感」
給与や昇進よりも、日々の業務に「意味」や「納得感」があるか――。若手にとっての仕事選びや職場選びの基準は、こうした“質的価値”にシフトしています。
特に重視されるのが、「面白さ」と「成長実感」です。ただし、ここで言う“面白い”とは娯楽的な意味ではなく、「学びがある」「挑戦できる」「変化がある」といった内発的な刺激を指します。
上司が「これ、いい経験になるよ」と伝えるだけで、若手が驚くほど前向きに取り組むケースは少なくありません。逆に、「言われたことをただやるだけ」の状態が続くと、あっという間に離職リスクが高まります。
3-3. 「やりがい搾取」ではない“本物の内的報酬”
一方で、気をつけなければならないのが「やりがい搾取」です。これは、内的報酬(やりがい)をうたっていながら、実際には過剰な業務負担や曖昧な評価基準のもとで働かせることを指します。
若手は“やりがい”という言葉に敏感です。空虚なスローガンや押し付けではなく、「自分で納得し、成長を実感できる環境」を整えることが重要です。
つまり、内的報酬はあくまで“与えるもの”ではなく、“共に育むもの”。適性や性格に合った役割や関わり方を見つけることで、本物のエンゲージメントが生まれます。

4. なぜ若手が辞めるのか?エンゲージメントを生む“正当さ”の重要性
4-1. 「正当な理由がなければ、納得しない」若手社員のリアル
最近の若手社員は、「それが正しいと思える理由」がなければ納得しません。例えば、配属や異動に対して「なぜ自分がその部署なのか」を説明されなければ、不信感が募ります。
これは自己中心的なのではなく、情報にアクセスできる環境で育ち、「自分のことは自分で判断する」という感覚が強いためです。「会社の都合だから仕方ない」「前例があるから」では通用しないのです。
正当な理由と納得感のない人事や評価は、エンゲージメントを著しく下げ、早期離職の引き金となります。
4-2. マネジメントは「指示」から「共感」へ
かつてのマネジメントは、情報を握る上司が「指示する」スタイルが主流でした。しかし今の若手社員に対しては、それだけでは機能しません。
必要なのは「共感」をベースとしたコミュニケーションです。「あなたの考えもわかるけど、こういう理由でこれをやってほしい」と伝えるだけで、若手の受け止め方は大きく変わります。
彼らは「上司の人間性」や「誠実さ」もよく見ています。共感力と説明責任がマネジメントにおける新しい武器となるのです。
4-3. 若手をつぶす前に知っておくべき“報酬構造の変化”
いま若手が求めているのは、「給与」や「安定」ではなく、「正当な評価」と「働く意味」です。これは報酬構造が、外的報酬から内的報酬へシフトしたことを示しています。
報酬構造を理解せず、旧来型のマネジメントを続けると、結果的に「期待の若手」をつぶしてしまうことになります。逆に、内的報酬の提供ができれば、離職は防げ、エンゲージメントも向上します。
ここで重要な役割を果たすのが、「適性検査」などの客観的なデータです。人材の“納得感”を支える材料として、いま再び注目されています。
5. 多様性が価値を生む:パフォーマンスを引き出す適性理解
5-1. 優秀な人材だけでは組織は機能しない
組織は、「優秀な人」が何人いるかではなく、「いかに互いを活かし合えるか」で成果が決まります。
個人の力が強くても、方向性がバラバラであればチームは機能しません。
だからこそ、異なる強みや価値観を持つメンバーが互いを補完し合い、シナジーを生むチーム作りが求められます。その前提となるのが、「違いを理解する」ことです。
5-2. 適性検査で“違い”を見える化する意義
性格・思考パターン・行動傾向といった“見えにくい個性”は、経験や直感だけでは正しく把握できません。
そこで役立つのが、適性検査です。例えば、性格特性やコミュニケーションスタイル、ストレス対処の傾向などを可視化することで、「なぜこの人はこう考えるのか?」を理解しやすくなります。
これは、上司部下の関係だけでなく、チーム全体の相互理解や役割分担にも大きな意味を持ちます。
5-3. チームにシナジーを生む“違いの活かし方”
適性検査で得られるデータは、“個性の差”を「問題」ではなく「強み」として捉え直すヒントになります。
たとえば…
- 慎重な人にはチェック業務やリスク管理を任せる
- 感受性が高い人には、人の気持ちに配慮する役割を託す
- 決断力のある人には、推進力のある仕事をアサインする
このように「その人らしさ」に合わせた関わり方ができれば、メンバー全員が持ち味を発揮しやすくなり、結果としてチーム全体のパフォーマンスが高まります。

6. いま適性検査が再注目されている理由
6-1. 適性検査は「内的報酬」と「正当さ」を支えるツール
近年の若手が重視しているのは、「自分が納得できる理由」と「自分らしさを活かせている実感」です。これは、“内的報酬”であり、“評価や役割の正当さ”とも言えます。
適性検査は、その納得感を支える材料になります。
- なぜ自分がこの仕事を任されたのか
- なぜこの役割が自分に合っているのか
こうした問いにデータで応えることができれば、本人の自己理解や上司との信頼関係が深まり、モチベーションの源になります。
6-2. 採用ミスマッチを防ぐだけではない“組織開発”への応用
適性検査はもともと「採用」の場面で用いられてきましたが、今ではその活用範囲が広がり続けています。
- 配属・配置転換の判断材料
- 育成計画の立案
- マネジメントの個別対応方針
- 内定者や若手のフォローアップ
つまり、「入社前」だけでなく、「入社後」にこそ適性データを活かすべきタイミングが数多くあるのです。
6-3. 若手マネジメントにこそ必要な「新しい物差し」
若手との関係づくりにおいて、「経験」や「感覚」に頼ったマネジメントでは通用しにくくなっています。むしろ必要なのは、一人ひとりの価値観や適性を踏まえた“新しい物差し”です。
適性検査は、その物差しの基盤となるものです。共通言語として使えば、「納得感のある対話」や「個別最適な育成」が実現しやすくなります。
企業にとって適性検査は、「選ぶためのツール」から、「活かすためのツール」へと進化しつつあるのです。


サービスの
ご紹介
TG-WEBの「コンピテンシー適性検査(A8)」は、性格や価値観ではなく、実際の行動特性に着目した適性検査です。
論理性・主体性・対人性など、仕事で求められる8つの行動特性を可視化し、「この人はどんな場面で力を発揮しやすいのか」「どのような働き方がフィットするのか」といった傾向を客観的に把握できます。
また、「ジョブ・クラフティング適性検査(Q1)」では、「個人⇔集団」「定型⇔非定型」の視点から、その人が没頭しやすい仕事を導き出します。
配属・育成・マネジメントの納得感を高めたい場面において、有効な判断材料となります。
若手とのズレに悩むマネジメント層の方に、ぜひご活用いただきたい検査です。

コンピテンシー適性検査 Another8

ジョブ・クラフティング
適性検査 Q1

© Humanage,Inc.

