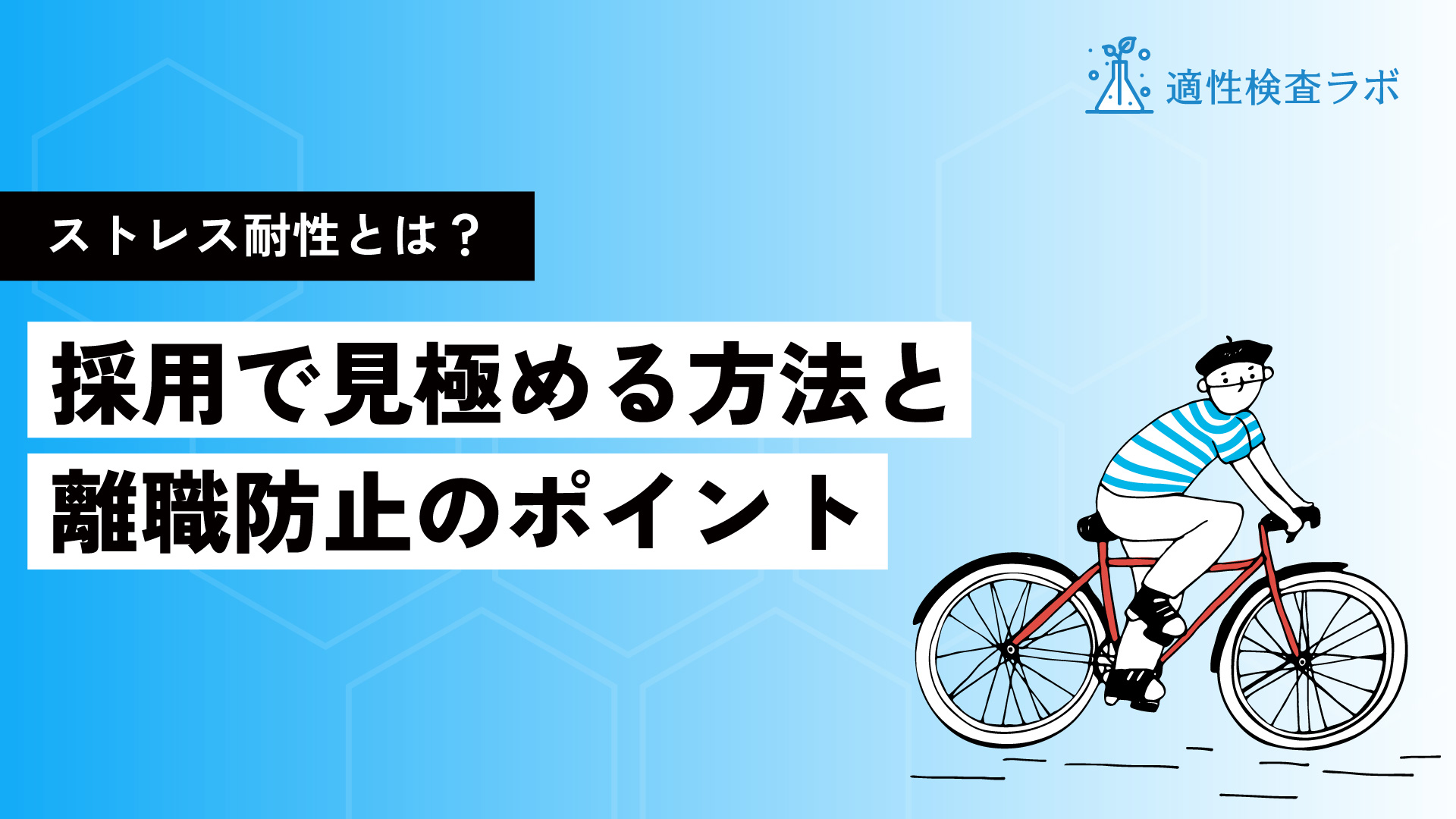
2025.08.22
ストレス耐性とは?採用で見極める方法と離職防止のポイント
はじめに
「せっかく採用したのに、思うように力を発揮できなかった」「環境の変化に対応できず、短期間で離職してしまった」――そんな経験はありませんか?
現代の職場では、急な組織変更や業務の増加など、日常的にストレスの種が生まれています。だからこそ大切なのは、候補者がどんなふうに困難に向き合えるか、つまり“ストレス対処力”を見極めること。本記事では、ストレスマネジメントの基本から活用法まで、採用と育成に役立つヒントをご紹介します。
INDEX
1. 採用担当者が直面する「ストレス耐性」課題
2. ストレスマネジメントの基本
3. 個人編(1)ストレッサーを明確にする方法
4. 個人編(2)コーピングのリストアップと実行のコツ
5. ケーススタディから学ぶストレス対処
6. 採用・人材育成に活かすために
サービス紹介
1. 採用担当者が直面する「ストレス耐性」課題
1-1. 採用後のパフォーマンスを左右する“ストレス対処力”とは
現代の職場では、業務量の増加、リモートワークによるコミュニケーション不足、急な方針転換など、精神的負荷を高める要因(ストレッサー)が日常的に発生しています。こうした状況で成果を出し続けるためには、単に我慢強いだけでは不十分です。
鍵となるのが「ストレス対処力(コーピング能力)」です。これは、ストレッサーを正しく把握し、行動や考え方で負荷を軽減する力を指します。ストレス対処力が低い人は、些細な変化やトラブルに過剰反応し、集中力や意欲を大きく損ないます。一方、高い人は冷静さを保ち、必要なサポートを得ながら課題を解決し、安定的に成果を上げます。採用後の活躍を長期的に維持するためには、この力の有無を見極めることが重要です。
1-2. なぜ今、ストレスマネジメントを採用戦略に組み込むべきか
働き方改革やDX推進などによる業務環境の変化は加速しており、ストレスマネジメントは“個人任せ”にできない状況です。変化に適応できず、メンタル不調から休職や離職に至るケースは珍しくありません。
スキルや経験だけで採用を決めると、突発的な負荷や組織の変化に弱い人材を採ってしまうリスクが高まります。特に若手は社会経験が浅く、自分なりのストレス対処法が確立していない場合が多く、環境変化に直面すると急速に疲弊する傾向があります。
一方、ストレス対処力の高い人材は変化に強く、長期にわたって安定した成果を出し続けます。採用段階で「ストレスへの向き合い方」や「対処傾向」を把握し、適切な人材配置や育成計画に結びつけることは、企業の採用戦略において大きな優位性となります。

2. ストレスマネジメントの基本
2-1. ストレッサーとコーピングの関係
ストレスマネジメントの出発点は、「ストレッサー」と「コーピング」という2つの概念を理解することです。
| ストレッサー | ストレスの原因となる出来事や状況。例として、業務量の多さ、人間関係の摩擦、裁量権の不足などがあります。 |
|---|---|
| コーピング | ストレッサーに対処し、心身への負担を軽減するための行動や思考の方法。積極的に状況を変える行動もあれば、あえて距離を取る方法もあります。 |
重要なのは、同じストレッサーでも人によって受け止め方や対処の仕方が異なるということです。例えば、厳しい納期を「やりがい」と感じる人もいれば、「圧迫感」と感じる人もいます。この違いがパフォーマンスの差を生み出します。
2-2. 高いストレス対処力がもたらす企業へのメリット
ストレス対処力の高い社員は、困難な状況でも冷静に優先順位をつけ、必要なサポートを引き出しながら業務を進めます。その結果、次のようなメリットが企業にもたらされます。
1. 離職率の低下
ストレスが長期的な不調や離職に直結するリスクを抑えられます。
2. 生産性の維持
変化やトラブル発生時にも業務の停滞を最小限にできます。
3. 組織の柔軟性向上
チーム全体で負荷を分散しやすくなり、急な異動やプロジェクト変更にも適応しやすくなります。
採用段階でストレス対処力を把握することは、組織全体の安定性と持続的な成果に直結します。

3. 個人編(1)ストレッサーを明確にする方法
3-1. 個人編(1)ストレッサーを明確にする方法
ストレスマネジメントを実際に機能させるためには、まず「自分が何にストレスを感じているのか」を把握することが欠かせません。
多くの場合、ストレスの原因は「忙しい」「疲れた」といった漠然とした感覚としてしか捉えられていません。しかし、そのままでは適切な解決策を見つけることはできず、対処行動も後回しになりがちです。
そこで第一歩として取り組みたいのが、ストレッサーを言葉にして“見える化”する作業です。職場で困っていること、負担に感じていること、嫌だと思っていることを具体的に書き出してみましょう。例えば、
- 会議や打ち合わせが立て続けに入っている
- 担当業務の範囲が広すぎる
- 通勤時間が長く、自由時間が少ない
こうしてリストアップすると、負担の正体がひとつの大きな問題ではなく、複数の小さなストレッサーの積み重ねであることに気づくことがあります。
3-2. 深刻度と問題解決の困難度による優先順位付け
リストアップしたストレッサーを前にすると、「どれから取り組めばよいのか?」と迷うことがあります。すべてを同時に解決する必要はなく、むしろ同時に取り組もうとすると挫折や意欲低下につながります。
そこで有効なのが、「深刻度」と「問題解決の困難度」という2つの基準でランク付けする方法です。
- 深刻度:負担を感じている度合い(大・中・小)
- 困難度:解決に必要な労力や他者からのサポートの得やすさ
最初は「深刻度が低く、困難度も低い」ストレッサーから取り組むのが効果的です。小さな成功体験を積むことで自信がつき、より大きな課題に取り組む準備が整っていきます。

4. 個人編(2)コーピングのリストアップと実行のコツ
4-1. 積極的・消極的コーピングの使い分け
ストレッサーに優先順位をつけたら、次は「具体的にどう対処するか」を考えます。この行動や思考の工夫が「コーピング」と呼ばれるものです。
コーピングには大きく分けて2種類あります。
| 積極的コーピング | 状況を改善・変化させるための行動(例:スキルを習得する、業務プロセスを見直す、他者に協力を依頼する) |
|---|---|
| 消極的コーピング | あえて行動を控え、距離を取る方法(例:成り行きに任せる、一時的に関与を減らす、状況が変わるまで様子を見る) |
基本的には積極的コーピングを優先するべきですが、心身が疲弊しているときには消極的コーピングを組み合わせることでエネルギーを温存できます。重要なのは「状況に応じて両方をバランスよく使い分けること」です。
4-2. 実行可能性と優先度で選ぶ3つの原則
コーピングを実際に行動に移す際には、「実行可能性」と「優先度」を意識して選ぶ必要があります。以下の3原則を参考にすると、無理なく進められます。
1. 取り掛かりやすい課題から実施する
最も負担の小さいストレッサーに対して、自信のある方法を試すことで、成功体験を積むことができます。
2. 深刻度の高い課題にはいきなり挑戦しない
最初から大きな問題に取り組むと失敗のリスクが高まり、意欲低下を招きます。小さな成功を積み重ねた後に挑むのが効果的です。
3. 結果にこだわりすぎない
努力しても解決できない場合は、切り替えて次の課題に移ることが大切です。いつまでも1つの問題に固執するとエネルギーを消耗してしまいます。
このプロセスを繰り返すことで、難易度の高いストレッサーにも段階的に対応できるようになります。
5. ケーススタディから学ぶストレス対処
5-1. プロジェクトの重複に追われたAさんの改善事例
Aさん(29歳・IT企業のプロジェクトマネージャー)は、同時進行の案件が4本あり、クライアントとの打ち合わせや社内調整で毎日スケジュールが埋まっていました。休日出勤や深夜作業も常態化し、気づけば食事や睡眠のリズムが乱れ、作業ミスも目立つようになっていました。
自身の業務を振り返る中で、「全て自分で確認しないと気が済まない」という傾向が負担を増やしていると気づきます。そこで、メンバーへの権限移譲をテーマにコーピングを実施しました。具体的には、タスクごとに責任者を決め、週1回の進捗ミーティングで状況を共有する体制を導入。最初は細部が気になって手を出しそうになることもありましたが、「任せるための準備時間」を確保することで徐々に不安が減少しました。
結果として、1か月後には夜間作業が半減し、クライアントとのやり取りもスムーズ化。Aさんは「負担を減らすことは責任放棄ではなく、チーム全体のパフォーマンス向上につながる」と実感するようになりました。
5-2. 組織改編による役割混乱から立ち直ったMさんの回復プロセス
Mさん(35歳・メーカー経理部門)は、組織改編で新たに海外拠点の財務管理を任されることになりました。しかし、上司からの指示は抽象的で、部門間の役割分担も曖昧なまま業務が進行。急なレポート依頼や方針変更が相次ぎ、精神的な疲弊が進んでいました。
ストレッサーを洗い出すと、上司の指示の不明確さや部門間の連携不足など、自分の力だけでは解決が難しい問題が多く含まれていました。そこでMさんは、比較的取り組みやすい「新しく配属された部下との関係づくり」に着手しました。まず、日々の雑談やランチを通じて信頼関係を築き、次に海外拠点とのメール対応や資料作成を一部任せるようにしました。
並行して、信頼できる同僚に業務の進め方や情報整理のコツを相談し、サポートを受けられる体制を整備。その結果、精神的な負担が軽減され、役割の曖昧さによる混乱も徐々に減少。Mさんは「自分で変えられない部分に固執せず、動かせる部分から改善する」姿勢を取り戻すことができました。

6. 採用・人材育成に活かすために
6-1. 面接や配属前に把握しておきたい「ストレス対処傾向」
ストレス耐性や対処傾向は、入社後のパフォーマンスや離職リスクに直結します。特に、新しい環境や予期せぬトラブルへの対応力は、職務適応のスピードや成果の安定性に影響します。
面接だけでは、候補者の「困難に直面したときの行動パターン」や「サポートの求め方」「感情のコントロール方法」を十分に見極めることは困難です。また、同じような経歴やスキルを持つ人材でも、ストレス対処傾向が異なれば、配属後の活躍度合いや定着率は大きく変わります。
採用段階でこれらの傾向を把握できれば、適材適所の配属や、早期からのフォロー体制づくりが可能になります。
6-2. 科学的アセスメントを活用した人材見極めのすすめ
ストレス対処傾向を正確に把握するには、本人の自己申告や面接時の印象だけでは不十分です。そこで有効なのが、心理学や行動科学に基づいた適性検査やアセスメントの活用です。
科学的アセスメントでは、
- どのようなストレッサーに強いか/弱いか
- 積極的・消極的コーピングのバランス
- 周囲からのサポートをどの程度活用できるか
- ストレス反応が高まったときの行動傾向
といった点を定量的に測定できます。これにより、配属先との相性や、必要な育成方針を事前に把握できるため、採用のミスマッチや早期離職の防止に直結します。
また、既存社員に対してもアセスメントを行うことで、ストレスマネジメント研修や個別サポートの優先順位をつけやすくなり、組織全体のパフォーマンス向上につながります。


サービスの
ご紹介
面接や自己申告だけでは、候補者が実際にどのようにストレスへ対処するのかを正確に見極めるのは困難です。そこで役立つのが コーピング適性検査「G9」 です。G9は、積極的・消極的コーピングの傾向、周囲のサポート活用力などを数値化し、客観的に可視化します。採用時に導入することで、候補者の適応力や持続的な活躍可能性を把握でき、適材適所の配属やフォロー計画に直結します。変化の激しい時代に備え、ストレス耐性を“見える化”する取り組みをぜひご検討ください。

コーピング適性検査 G9

© Humanage,Inc.

