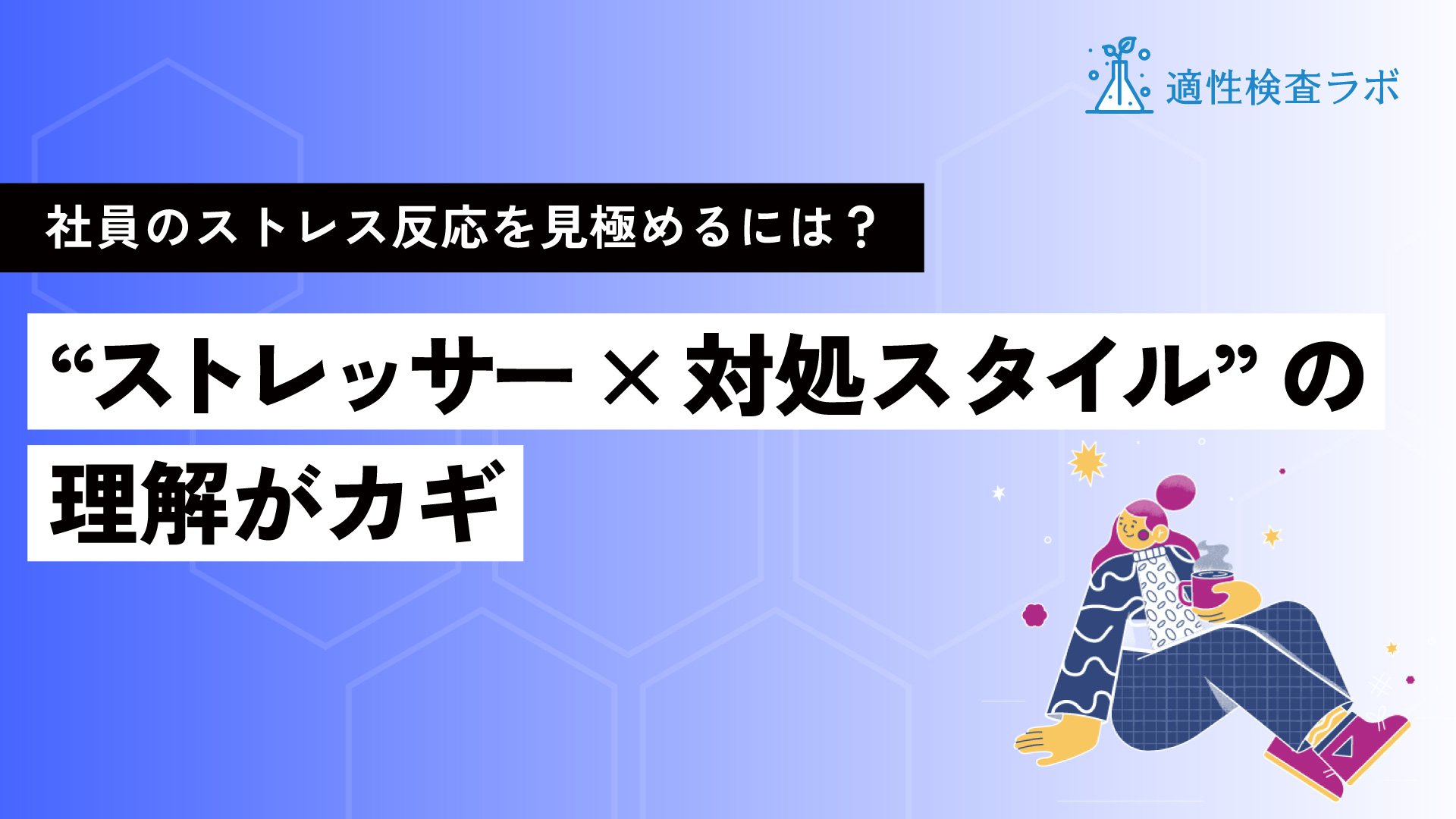
2025.08.08
社員のストレス反応を見極めるには?“ストレッサー×対処スタイル”の理解がカギ
はじめに
「ストレス耐性のある人材がほしい」「若手がすぐに辞めてしまう」
――そんな悩みを抱える企業が増えています。
しかし、ただ“ストレスに強い人”を求めるだけでは、根本的な課題解決にはつながりません。
重要なのは、「どんなストレッサーに対してストレスを感じやすいのか」そして「どのようなコーピング(対処スタイル)をとる傾向があるのか」を理解することです。
本記事では、職場におけるストレッサーの種類や、それに対する反応・行動傾向の違いについて、専門的な視点からわかりやすく解説します。
若手の離職防止や人材のミスマッチ防止、職場ストレス対策を検討中の方は、ぜひご一読ください。
INDEX
1. ストレスの原因「ストレッサー」とは?
2. 職場で見られる量的ストレッサー
3. 職場で見られる質的ストレッサー
4. イベント型と慢性型ストレッサーの違いと影響
5.コーピングとは?ストレスへの対処スタイルを知る
6. ストレスを和らげる「ソーシャルサポート」と「ソーシャルスキル」
サービス紹介
1. ストレスの原因「ストレッサー」とは?
1-1. ストレッサーの基本概念
私たちが感じるストレスには、必ず「原因」となるものが存在します。
このストレスの引き金となる要因は、心理学の分野では「ストレッサー」と呼ばれます。たとえば、「業務量が多い」「評価に対するプレッシャー」「人間関係のもつれ」などが職場でよく見られるストレッサーです。
ストレッサーは、同じ出来事であっても、個人によってその受け止め方が異なります。ある人にとっては「やりがいのある挑戦」でも、別の人にとっては「負担の大きなストレス源」になることもあります。
つまり、ストレッサーとは“状況そのもの”というより、それをどう認知し、どう対応するか”に左右される非常に主観的なものです。
この「認知のしかた」や「対処スタイル」を把握することで、ストレスを受けやすい場面や対応傾向を事前に知ることができます。
1-2. 職場ストレッサーに着目する理由
現代の職場環境では、複雑化・多様化したストレッサーが日常的に存在しています。
人間関係の摩擦、目まぐるしい変化、役割や責任の曖昧さ、そして情報の過多。これらは、従業員の働き方や心理状態に影響を与え、時にはパフォーマンス低下や離職リスクにつながります。
このような背景から、企業が人材を見極める上で、「業務上どのようなストレッサーに弱い傾向があるか」「その際、どのように対処するか」に注目することは、極めて重要です。
特に、経験が浅い若手層では、過去のストレス体験が乏しいこともあり、実際にストレスがかかったときの行動傾向を事前に把握することが難しい場合もあります。
そのため、近年では、ストレッサーに対する捉え方や行動パターンを可視化するようなアセスメントを活用する企業も増えています。これは、採用後の定着支援や、個々の特性に応じたマネジメント設計にも役立ちます。

2. 職場で見られる量的ストレッサー
2-1. 業務量過多が生む慢性的負担
職場でよく見られるストレッサーの一つが、「業務量の多さ」による負担です。
人員不足や業務の偏りが慢性化している組織では、社員一人あたりのタスク量が膨大になりやすく、長期的なストレスにつながります。
このような状態では、次のような変化が見られることがあります
- 集中力の低下や判断ミスの増加
- 睡眠の質の低下や体調不良
- モチベーションの低下や無力感
ただし、すべての人が「忙しさ」をストレスと感じるわけではありません。
なかには、忙しいほどやる気が出る、タスクを処理することに達成感を覚える、という人もいます。
この違いを生むのが、その人自身のストレッサーに対する認知のしかたと、実際の対処行動(=コーピング)です。
このような観点から、最近では、個人が「忙しさ」という状況に対してどのように反応するのかを測定・分析するアセスメントも注目されています。
2-2. 時間的切迫のプレッシャー
業務量と並んで多くの人が抱えるのが、「時間の足りなさ」によるプレッシャーです。
納期、会議、メール対応など、限られた時間のなかで複数のタスクをこなす必要がある現代の職場では、タイムプレッシャーが日常的なストレッサーになっています。
次のようなケースが、ストレスを引き起こす要因となりやすいです
- 優先順位がつけられずに焦る
- 想定外の依頼でスケジュールが崩れる
- 周囲に助けを求められず、1人で抱え込む
こうした状況下で、冷静に対応策を考え直す人もいれば、過度に焦ってパフォーマンスが下がってしまう人もいます。
このように、同じ時間的制約下でも、取る行動や心の持ちように大きな個人差があるのです。
そのため、「どのような状況でタイムプレッシャーを感じやすいか」「その際にどんな反応をしやすいか」といった傾向を理解しておくことは、人材配置やマネジメントにおいて非常に有用です。

3. 職場で見られる質的ストレッサー
3-1. 役割不明瞭と指示の曖昧さ
「自分のやるべきことがわからない」「何を求められているのかが不明確」
このような状況は、“質的ストレッサー”と呼ばれるストレスの一種です。
職場では、役職やチーム体制、プロジェクトの方針などが変化する中で、以下のようなケースがよく見られます
- 指示内容が抽象的で、解釈に悩む
- ゴールが明確でなく、達成基準が不明瞭
- 自分の役割と他者の役割の境界が曖昧
こうした不明瞭な状況は、特に真面目で責任感の強い人ほど大きなストレスとなりやすく、「これで合っているのだろうか」と過剰に自己評価を下げる原因にもなり得ます。
重要なのは、役割や指示の不明瞭さに直面した際の反応や行動のパターンです。
「確認する」「情報を集める」「まずやってみる」など、能動的に対処できる人もいれば、思考が停止しがちになる、萎縮してしまうといった傾向を持つ人もいます。
こうした特性は、事前に傾向を把握しておくことで、入社後の適応支援やOJT設計に大いに役立てることができます。
3-2. 裁量権不足が招く無力感
質的ストレッサーのもう一つの典型が、「裁量がない」「自分でコントロールできない」という感覚です。
仕事の進め方や優先順位において裁量が持てないと、人は次第に無力感や被受動感を抱くようになります。
たとえば、以下のような場面が挙げられます
- 常に上司の指示待ちになってしまう
- 自分の意見が反映される余地がない
- 「どうせ決まっていることだから」と感じてしまう
裁量がない状態が続くと、自律的な思考が止まり、指示に従うだけの姿勢になってしまいます。結果として、パフォーマンスだけでなく、成長機会までもが失われる可能性があります。
ただし、全員が「裁量が必要」と感じているわけではありません。
「ある程度決まったフレームで仕事をするほうが安心できる」というタイプもいます。
このように、裁量の多寡に対する適応力や好みには個人差があるため、その人がどの程度の裁量を心地よく感じるか、負担と感じやすいかを見極める視点が、マネジメント上非常に重要になります。

4. イベント型と慢性型ストレッサーの違いと影響
4-1. 職場での突発的な出来事が与える衝撃
「イベント型ストレッサー」とは、ある日突然起こるような、非日常的なストレス要因を指します。
たとえば、以下のような出来事が該当します
- 異動や部署再編などの人事的変化
- クレーム対応やトラブル対応といった突発業務
- 職場での対人トラブルや急な担当変更
こうした出来事は、短期的に強い心理的負荷を与えるため、急激なストレス反応(動揺・不安・怒りなど)を引き起こすことがあります。
重要なのは、このような突発的ストレッサーに遭遇したとき、どのように感情を処理し、対応するかという点です。
「冷静に優先順位を整理して動ける人」もいれば、「頭が真っ白になりやすい人」「自責に陥りやすい人」など、反応には個人差があります。
一時的な反応の強さだけでなく、その後の立ち直りやリカバリーの速さ(レジリエンス)も含めて見ていくことが、実務への適応を判断する上で有効です。
4-2. 慢性化するストレスの怖さ
一方、「慢性型ストレッサー」は、日常的に繰り返し経験するような長期的に蓄積されるストレス要因です。
こちらは静かに、しかし着実に心身へ影響を与えていく特徴があります。
たとえば
- いつも同じことで叱責される
- 評価されていないと感じ続けている
- 忙しさが何ヶ月も続いている
こうした慢性的なストレスは、気づかないうちに疲労感や無力感を蓄積させ、最終的には燃え尽き症候群やモチベーションの喪失につながるリスクがあります。
さらに怖いのは、慢性ストレスに対して「何も感じなくなる」ことで、危機感を持たなくなる状態です。本人も周囲も変化に気づきにくく、対処が遅れがちになります。
だからこそ、「慢性ストレスに対して、どのような習慣的対処行動をとるか」「小さな不調サインを拾えるか」といった傾向を、あらかじめ把握しておくことが、早期のリスク管理につながります。
5. コーピングとは?ストレスへの対処スタイルを知る
5-1. 感情優先型と問題解決型の違い
ストレスを感じたとき、人は無意識のうちに何らかの「対処行動」を取ります。
このような行動を心理学では「コーピング(coping)」と呼びます。
コーピングとは、ストレスの原因や感情に対して、心理的・行動的に対処するためのプロセスのことです。
コーピングには大きく分けて以下の2種類があります
- 感情優先型コーピング
→ ストレスによって生じた不快な感情を和らげることを目的とする。
例:愚痴を言う、一時的にその場から離れる、自分を慰める。 - 問題解決型コーピング
→ ストレスの原因そのものを解消・改善することを目的とする。
例:情報収集をする、上司に相談する、優先順位を見直す。
どちらのタイプが「良い・悪い」というものではなく、状況に応じて使い分けることが大切です。
ただし、問題解決が可能な場面で感情優先型に偏りすぎると、状況が長引いたり悪化することがあります。
一方で、すぐには解決できない状況では、感情を一時的に落ち着かせるアプローチも必要です。
採用や配属の判断においては、その人がどちらのスタイルをとりやすいかを把握しておくことで、フィードバックや支援の方向性を適切に設計することが可能になります。
5-2. 積極 vs 消極コーピングがストレス耐性に与える影響
コーピングスタイルは、積極的か消極的かという視点でも分類されます。
- 積極コーピング
→ ストレス要因に正面から向き合い、具体的な対処行動をとるスタイル。
例:人に相談する、タスクを分解する、視点を変えてポジティブに捉える。 - 消極コーピング
→ 問題を回避したり、感情を抑え込んでやり過ごそうとするスタイル。
例:我慢する、無理に気を紛らわせる、諦める。
積極的なコーピングをとる人は、ストレスに対する回復力(レジリエンス)が高い傾向にあります。
反対に、消極的な対処を取りがちな人は、短期的にはやり過ごせても、ストレスの根本的な解消にはつながりにくく、メンタル面での疲弊が蓄積するリスクがあります。
もちろん、消極的な対処が“悪い”というわけではありません。大切なのは、状況に応じて複数のスタイルを使い分けられる柔軟性です。
適性検査などでは、こうしたコーピングの傾向を可視化することが可能です。
これにより、「この人はどういった状況でどんなストレスに弱いのか」「どんな支援や環境があれば本来の力を発揮できるか」を見極める手がかりになります。

6. ストレスを和らげる「ソーシャルサポート」と「ソーシャルスキル」
6-1. 上司や同僚の支援が持つ絶大な力
職場でのストレス対処力は、個人の努力だけで決まるものではありません。
むしろ、周囲との関係性やサポートの有無が、大きな影響を与えることが多くあります。
これを支えるのが「ソーシャルサポート」と呼ばれる要素です。
ソーシャルサポートとは、同僚・上司・友人・家族といった他者から受ける心理的・実務的な支援のことを指します。
たとえば
- 上司からの具体的なアドバイス
- 同僚からの励ましの言葉
- 困ったときに助けてもらえる環境
こうしたサポートがあるだけで、ストレスの受け止め方や対処行動は大きく変わります。
反対に、周囲からの支援が期待できないと感じている人は、ストレス状況で孤立しやすく、対応力も低下する傾向があります。
人材の特性を把握する際には、「その人が周囲に支援を求めるタイプかどうか」や「支援を受け取れる感度があるかどうか」といった観点も重要になります。
6-2. 高められるスキルとしての「人付き合い力」
ソーシャルサポートの「受け手」であると同時に、その支援を引き出すための能力=“人付き合いのスキル”もまた、ストレス対処力に直結する要素です。
これを「ソーシャルスキル」と呼びます。
具体的には
- 適切なタイミングで助けを求められる
- 相手の立場を理解しながらコミュニケーションが取れる
- 感情をコントロールしつつ、建設的なやり取りができる
このようなスキルを持つ人は、自然と良好な人間関係を築きやすく、周囲からの支援も受けやすくなるため、ストレス状況でも柔軟に対応できる傾向があります。
逆に、コミュニケーションが苦手だったり、孤立しやすい傾向のある人は、ストレスの「出口」が見つからず、長期的に蓄積させてしまうリスクがあります。
ソーシャルスキルは、後天的に高めることが可能なスキルです。
そのため、採用や人材開発においても、「現時点での傾向」を把握し、成長支援の対象として捉えることが大切です。


サービスの
ご紹介
コーピング適性検査『G9』は、職場におけるストレッサーに対する反応や、ストレスへの対処スタイル(コーピング)を可視化するアセスメントです。
量的・質的ストレッサー、イベント型・慢性型といった多様な状況に対し、「どのような環境で負荷を感じやすいか」「どのように乗り越えようとするか」を把握できます。
採用や配属の見極め、入社後の定着支援の一助として、ご検討いただけますと幸いです。

コーピング適性検査 G9

© Humanage,Inc.

