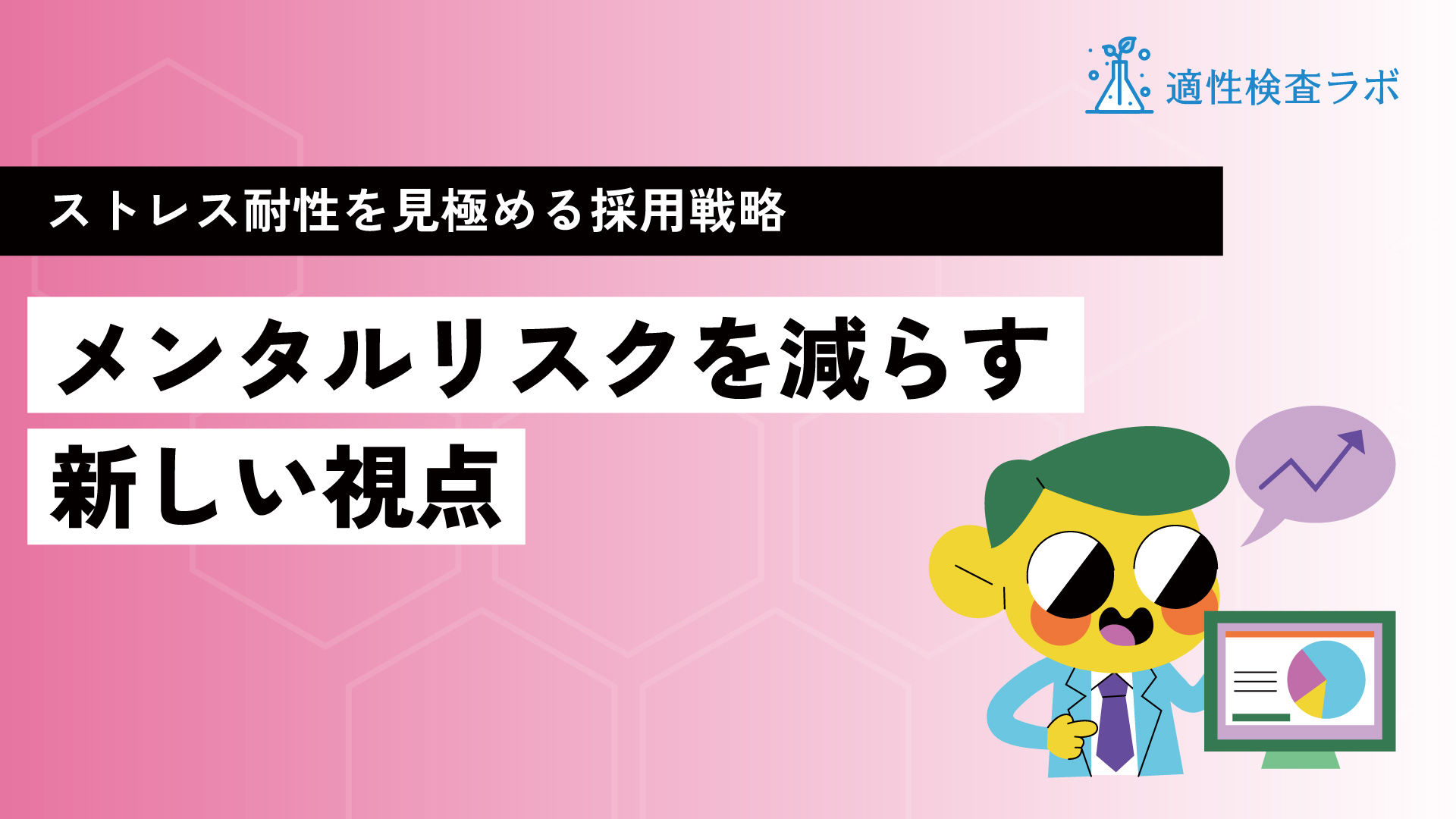
2025.08.01
ストレス耐性を見極める採用戦略|メンタルリスクを減らす新しい視点
はじめに
従業員のメンタルヘルスは、いまや企業経営の根幹に関わる重要テーマです。働き方の多様化や成果主義の浸透、人間関係の複雑化などを背景に、心理的ストレスが高まりやすい職場環境が増えていると言われています。こうした状況の中、メンタル不調による休職や離職、ハラスメント問題の表面化といったリスクは、個人にとどまらず組織全体の生産性や信用にも影響を及ぼしかねません。本記事では、企業が果たすべきメンタルヘルス管理の責任から、多層的な対策の実践、さらには適性検査を活用したストレスマネジメントの可能性までを解説し、持続的な健康経営を支えるヒントをお届けします。
INDEX
1. 増加する職場ストレスの実態
2. 企業に求められるメンタルヘルス管理の責任
3. パワーハラスメントの実態と対応の必要性
4. メンタルヘルス対策の多層的アプローチ
5.ストレスマネジメントと適性検査の可能性
6. 健康経営と生産性を両立させるために
サービス紹介
1. 増加する職場ストレスの実態
1-1. 働き方の変化と心理的負担の増加
テレワークの普及、DXの推進、多様な雇用形態など、企業を取り巻く働き方はこの数年で大きく変化しました。加えて、成果主義やスピード重視の経営スタイルが定着する中で、従業員に求められるパフォーマンスは年々高まっています。その結果、目に見えにくい「心理的な負荷」が増加し、従来とは異なるストレス構造が形成されつつあります。
以前は長時間労働や業務過多といった「量的負担」が主なストレス要因でしたが、近年では人間関係の摩擦や評価制度への不満、キャリアへの不安といった「質的な負担」も大きくなっています。特に若手層やZ世代の間では、心理的安全性を重視する傾向が強く、それが担保されない職場環境ではメンタル不調に至るリスクも高まっています。
1-2. ストレスが企業に与える経営リスク
従業員が慢性的なストレス状態にあると、企業活動に深刻な影響が生じます。代表的なのは「生産性の低下」や「人材の流出」です。集中力の低下、創造性の欠如、対人トラブルの増加など、ストレスの影響は業務パフォーマンス全般に波及します。
また、心の健康問題は一部の社員に限定されるものではなく、どの職種・職位でも起こり得るものです。メンタルヘルス不調による長期離脱者が出た場合、業務の遅延や他メンバーの負担増加といった二次的リスクも懸念されます。結果として、職場全体の士気やチームの機能低下を引き起こす可能性もあるのです。
1-3. 精神的健康の悪化がもたらす社会的・人的損失
ストレスが蓄積し、うつ病などの精神疾患に進行すると、長期的な療養が必要となることもあります。企業側にとっては、復職までのフォローや人員補填にかかるコストが発生し、戦力の損失として大きな打撃となります。
さらに問題なのは、精神的な健康の悪化が「社会的な信用」や「法的な責任問題」にも発展しうることです。従業員の自殺やハラスメント関連の訴訟が報道されれば、企業のブランドイメージや採用活動にも直接的な影響が及びます。メンタルヘルスは個人の問題ではなく、組織全体のリスク管理と捉えるべき時代に突入しているのです。

2. 企業に求められるメンタルヘルス管理の責任
2-1. 安全配慮義務と法的リスクの認識
企業は、従業員が心身ともに健康に働ける環境を提供する「安全配慮義務」を負っています。
従業員が過度のストレスにより精神疾患を発症した場合、企業側の対応が不適切であれば、損害賠償請求や訴訟に発展するリスクもあります。これにより経済的損失はもちろん、企業の社会的評価にも大きな傷がつくことになります。特に、管理職が長時間労働を把握していなかった、ハラスメントを放置していたなどのケースでは、企業と上司双方に責任が問われる傾向があります。
2-2. 管理職が果たすべきラインケアの役割
メンタルヘルス管理は、人事部門や産業医だけで完結するものではありません。日々のマネジメントを担う管理職の「ラインケア」が、職場における早期発見・早期対応の鍵を握ります。
たとえば、業務量の変化、遅刻や欠勤の頻度、表情や態度の変化など、些細な兆候に気づくのは、現場の上司が最も近い存在です。適切な声かけや相談対応、業務調整といった対応ができるよう、管理職自身がストレスやメンタル不調に関する基礎知識を習得しておくことが重要です。
2-3. 自殺や長期休職につながる労務管理の盲点
メンタル不調は突然深刻化するわけではなく、日常の中に小さな予兆が現れることがほとんどです。にもかかわらず、忙しさや属人的な管理体制が原因で、早期対応の機会を逃してしまうケースが後を絶ちません。
「残業時間の把握がされていなかった」「人間関係に起因する問題が共有されていなかった」など、管理体制の甘さが結果として重大な結果を引き起こすこともあります。企業としては、定期的な労働環境の点検や、ストレスチェック制度の活用など、予防的な体制整備が不可欠です。

3. パワーハラスメントの実態と対応の必要性
3-1. パワハラが精神健康に与える深刻な影響
パワーハラスメント(パワハラ)は、職場における深刻な心理的ストレスの要因です。上司などの職務上の優位性を背景とした人格否定的な言動や過度な叱責、無視・隔離などが継続的に行われた場合、被害者は強い精神的苦痛を受け、うつ病などのメンタル不調に発展するリスクが高まります。
問題なのは、パワハラの加害者自身が「教育的指導」と認識していたり、「部下の成長のため」と正当化してしまうことが多い点です。しかし、被害者がストレスにさらされる期間が長引けば、最終的には休職や離職、自殺といった深刻な結果を招く恐れもあるのです。
3-2. 人間関係によるストレスの見逃せないリスク
職場におけるストレスの大きな要因として、業務量以上に人間関係が挙げられるケースが増えています。例えば、上司との相性の悪さ、同僚との軋轢、評価の不公平感など、目に見えないストレスが蓄積しやすい構造にあります。
これらは表面化しにくく、定量的に把握しづらいため、対応が後手に回ることが多くなりがちです。しかし、心理的安全性が保たれない職場では、従業員が本来の力を発揮できず、チームの協働や創造性にも悪影響を及ぼします。早期の兆候を見逃さず、組織として未然に防ぐ仕組みを整えることが重要です。
3-3. ハラスメント防止が職場の生産性を守る
ハラスメントの防止は、単なるコンプライアンス対応ではなく、生産性向上にも直結する取り組みです。社員が安心して働ける職場環境は、エンゲージメントを高め、離職率を抑え、成果を出しやすい土壌を育てます。
そのためには、管理職への定期的な教育や、社内ルールの明文化、相談窓口の設置など、組織としての明確な姿勢を示すことが求められます。また、ハラスメントの未然防止には、従業員同士の信頼関係づくりや、心理的安全性を意識したマネジメントも欠かせません。

4. メンタルヘルス対策の多層的アプローチ
4-1. セルフケア・ラインケアの役割と実践
メンタルヘルス対策は、誰か一人の役割ではなく、全社的な取り組みとして進める必要があります。まず基本となるのは、従業員自身が自身のストレスや体調の変化に気づき、適切に対処する「セルフケア」です。これは、日常の自己観察や生活習慣の見直し、リラクゼーション法の実践などを含みます。
同時に、管理職による「ラインケア」も重要です。部下の状態に気づき、必要に応じて業務調整や相談支援を行う役割は、職場内の一次的な防波堤となります。企業は、こうしたケアを実践できるよう、管理職に対する研修やマニュアル整備を通じた支援を行う必要があります。
4-2. 社内外リソースを活かした支援体制の整備
メンタルヘルス対策を効果的に機能させるには、セルフケアやラインケアに加え、社内の専門スタッフ(産業医、保健師、カウンセラーなど)や外部の支援機関との連携も欠かせません。
たとえば、社内に専門職が不在の場合には、EAP(従業員支援プログラム)などの外部サービスを活用することで、専門的な相談対応や医療機関との橋渡しを行うことが可能です。また、地域の産業保健センターやメンタルヘルスに特化した外部機関とも連携し、多面的な支援体制を整えることで、より安定した対応が可能になります。
4-3. 企業に必要な「攻めのメンタルヘルス管理」
従来、メンタルヘルス対策は「問題が起きてからの対応」が中心でしたが、現在は「予防的・戦略的対応」が主流となりつつあります。つまり、単なるリスク回避ではなく、生産性向上・人材定着を目的とした“攻めの健康経営”として捉えることが重要です。
ストレスチェックの結果や適性検査の分析を通じて、職場や個人の課題を可視化し、配置・育成・マネジメント改善に活用する企業も増えています。働きやすさと成果の両立を目指すために、メンタルヘルスは「守り」から「活かす」フェーズに移行しているのです。
5. ストレスマネジメントと適性検査の可能性
5-1. ストレス耐性や対処力を可視化する重要性
ストレスマネジメントを効果的に実施するには、個人のストレスに対する反応傾向や対処スタイルを把握することが欠かせません。なぜなら、ストレスの感じ方や対応の仕方は人によって大きく異なるため、画一的な対応では十分な効果が得られないからです。
そこで注目されるのが、ストレス耐性やストレス対処力を測定できる適性検査の活用です。こうした検査により、個人の傾向を客観的に把握できます。可視化されたデータは、配置や育成方針の検討だけでなく、本人のセルフケア意識の向上にもつながります。
5-2. リスクの高い人材を事前に見極める視点
採用や異動の場面では、業務能力や意欲だけでなく、「組織にフィットするかどうか」「過度なストレスを抱え込むリスクがあるか」といった観点も重要です。特に、メンタル不調のリスクが高い傾向がある場合、早期にその兆候を把握しておくことで、適切な配慮やサポートを行うことが可能になります。
適性検査によって、例えば「他責傾向が強い」「支援を求めるのが苦手」「不安や緊張が高まりやすい」といった特性が明らかになれば、採用の際だけでなく、配属や上司との相性も含めたマネジメント上の工夫に活かすことができます。これにより、後のトラブルや早期離職の予防にもつながります。
5-3. 採用段階からのメンタルヘルス対策のすすめ
メンタルヘルス対策は入社後に始めるもの、という考えはすでに過去のものとなりつつあります。現代では、採用段階からその視点を持つことが求められています。特に、新卒やキャリア採用においては、職場環境への適応力や自己理解の深さが、定着や活躍の可否に大きく影響するためです。
採用フローの中に適性検査を取り入れることで、候補者自身の強み・弱みをフィードバックしつつ、企業側もその人材の特性に応じた支援を考えることができます。これは候補者への信頼感にもつながり、エンゲージメントを高める施策にもなり得るのです。

6. 健康経営と生産性を両立させるために
6-1. ハイパフォーマーのパフォーマンス維持
メンタルヘルス対策は、課題を抱える人への支援だけに留まりません。むしろ、日頃から高いパフォーマンスを発揮している人こそ、無理を重ねやすく、疲労やストレスに気づかないまま不調に陥るリスクをはらんでいます。
こうしたハイパフォーマーにこそ、ストレスマネジメントスキルの習得を促すことが大切です。自己の状態に気づき、必要に応じて休息や相談ができるリテラシーを持つことで、持続的に成果を出し続けるための土台を整えることができます。
6-2. メンタル不調の予防から活躍支援へ
従来のメンタルヘルス支援は、「不調者への対応」が中心でしたが、今後は「活躍支援」へと発想を転換していくことが求められます。心の健康は、単なるリスクマネジメントではなく、人材の活性化・最適化を図る戦略的アプローチとして活用できるからです。
具体的には、定期的なストレスチェックや適性検査に加え、上司との対話、キャリア面談の活用、社内カウンセリング体制の整備など、日常的にケアが行き届く仕組みづくりが効果的です。
6-3. 全従業員を対象とした健全な職場づくり
真の健康経営は、一部の従業員への対処ではなく、全体を視野に入れた職場環境づくりにあります。誰もが安心して働ける職場、悩みを相談しやすい文化、異変に気づけるマネジメント体制。これらがあってこそ、企業全体の生産性は安定し、離職防止にもつながります。
メンタルヘルスを「個人の問題」として捉えるのではなく、組織の仕組みとしてどう支えるか。その視点を持つことが、これからの企業に求められる健全な経営のあり方です。


サービスの
ご紹介
採用段階からメンタルリスクを見極める――それが可能になるのが、ストレス耐性・対処行動に特化した適性検査「G9」です。ストレス要因への反応傾向や回避・相談行動の特徴を可視化し、リスクの高い人材の早期発見や適切なフォロー設計に活用可能。定着率の向上や配置・育成の最適化にも役立ちます。採用時のメンタル対策として、ご検討してみてはいかがでしょうか。

コーピング適性検査 G9

© Humanage,Inc.

