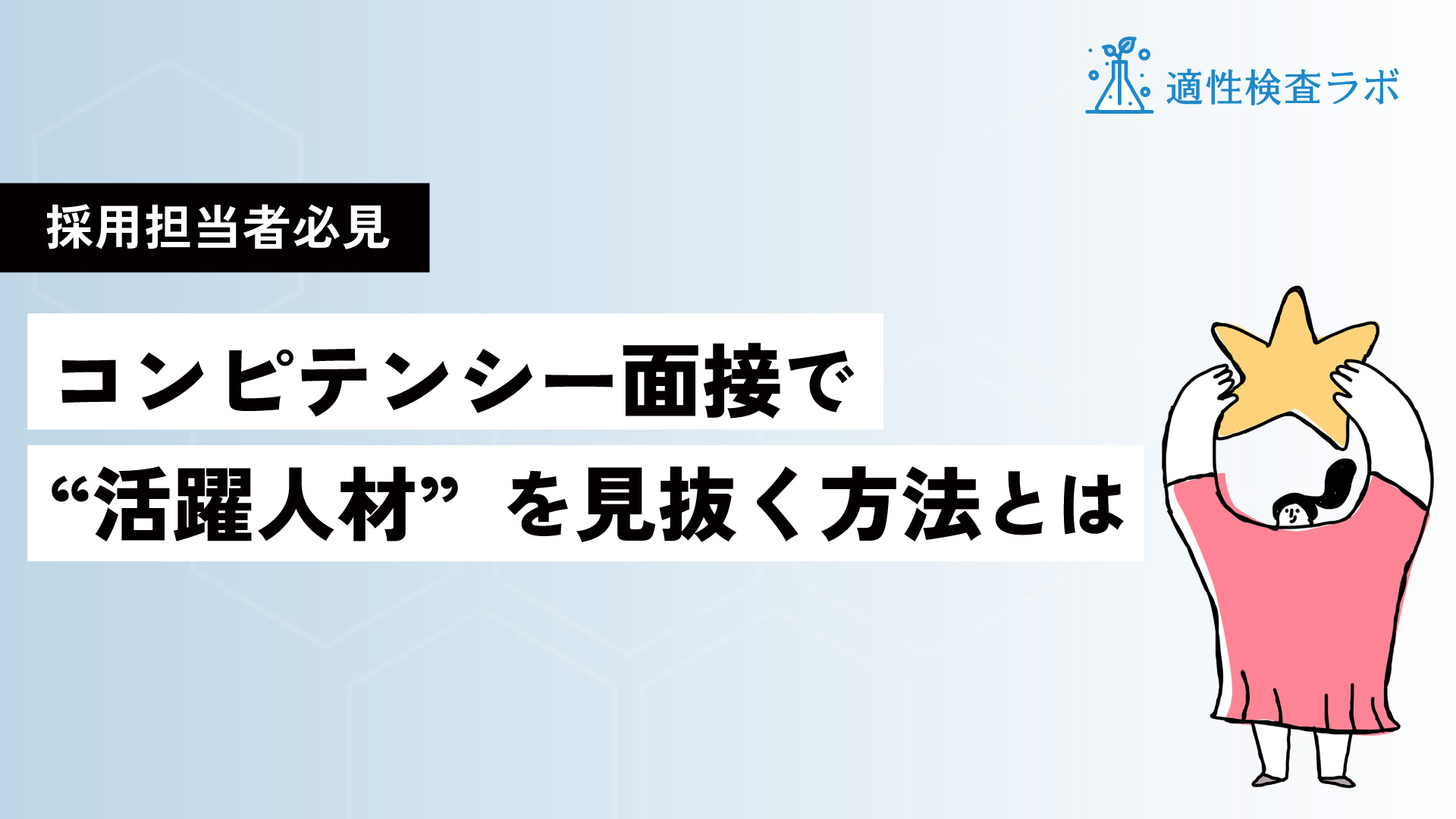
2025.07.18
【採用担当者必見】コンピテンシー面接で“活躍人材”を見抜く方法とは
はじめに
ビジネス環境が加速度的に変化するいま、企業にとって本当に必要なのは「成果を出せる人材」であり、それを見極める基準となる考え方の一つがコンピテンシーです。コンピテンシーとは、知識やスキルといった、持っている能力ではなく、それを実際の行動として発揮し、成果につなげる力を指します。単に優秀に見える人ではなく、実際に組織の中で成果を生み出せる人材をどう見極めるか。その鍵となるのが「コンピテンシー面接」です。本記事では、コンピテンシーの基本的な考え方から、面接手法としての活用法、さらには評価の基準や適性検査との併用について、具体的に解説していきます。
コンピテンシーを正しく理解し、実務に取り入れることで、採用の精度を高め、定着・活躍人材の確保につなげる第一歩となるはずです。
INDEX
1.コンピテンシーとは何か
2.コンピテンシー面接の基本理解
3.コンピテンシー面接の具体的フロー
4.コンピテンシーのレベルと評価軸
5.コンピテンシーの可視化と適性検査の活用
6.成果につながる人材を見極めるために
サービス紹介
1. コンピテンシーとは何か
1-1. 表面的な優秀さと成果の違い
過去、「優秀な人材=高学歴・高スキル」といった評価を行う企業が多くおりましたが、現代では通用しない場面が増えています。なぜなら、どれほど知識や専門性を持っていたとしても、それを活かして「成果」を出すことができなければ、組織への貢献にはつながらないからです。
ここで重要となるのが「コンピテンシー」という視点です。コンピテンシーとは、単なる能力や学歴の有無ではなく、「成果につながる行動ができる力」を指します。言い換えれば、“持っている能力”ではなく“発揮能力”を評価するものです。
たとえば、非常に高い論理的思考力を持つ人材がいたとしても、それをチームの中で有効に使わず、実務に落とし込む行動を取らなければ、結果としてのパフォーマンスには結びつきません。一方で、知識量では見劣りするかもしれない人材が、現場の状況に応じて工夫しながら実行し、着実に成果を上げているケースもあります。
このように、表面的な「優秀さ」ではなく、実際に「成果を出せる力」を持っているかどうか――それが今、採用の現場で求められている人材評価基準なのです。
1-2. コンピテンシーの本質と誤解されがちなモデル
「コンピテンシー=行動パターン」だと誤解されることがありますが、これは大きな誤認です。よくある誤解として、「職種ごとに成功する行動をパターン化し、それに当てはまるかどうかを評価するのがコンピテンシーである」というものがあります。
しかし実際には、真に高い成果を上げる人材は、状況によって最適な行動を変えています。つまり、「常に異なる状況に応じて、柔軟に行動を選び取っている」のが特徴であり、固定化された行動様式に従っているわけではありません。
ここがコンピテンシーの核心です。成果を出すためには、状況を的確に読み取り、必要に応じて思考や手法を変え、即座に行動へとつなげる力が求められます。だからこそ、コンピテンシーを測るには、その人が過去の経験の中で、どのような判断を下し、どのような工夫を行い、どのように行動してきたのかを丁寧に把握することが必要なのです。
「いつも同じ行動をとる人」ではなく、「状況に応じて最適な行動をとる人」こそが、コンピテンシーの高い人材であるという理解が重要です。

2. コンピテンシー面接の基本理解
2-1. 従来の面接との違い
これまで多くの企業では応募者の印象や発言内容、考え方に重点が置かれ評価が行われてきました。いわば「考えて答える面接」であり、応募者が面接の場でどれだけ知識や思考力をうまく表現できるかが評価の中心になるような面接です。
しかしこの方法には、大きな落とし穴があります。印象の良さや話の上手さと、実際に仕事で成果を出せるかどうかは必ずしも一致しません。場の空気を読んで、うまく話せる人が評価される一方で、地道に成果を出すタイプの人材が見落とされるリスクがあるのです。
そこで登場したのが「コンピテンシー面接」です。これは、応募者の知識や考えではなく、「過去に実際にとった行動」を掘り下げて確認する「思い出して答える面接」です。つまり、成果に直結する行動の再現性を見極めるために、行動事実に焦点をあてた評価方法なのです。
2-2. 行動事実に基づいた評価の意義
コンピテンシー面接の最大の特徴は、「事実」に基づいた判断が可能になる点です。印象や主観に左右されやすい従来の面接と異なり、コンピテンシー面接では、候補者が実際に経験したエピソードの中から「どのような課題に直面し、どのような判断を下し、どのように行動したか」を細かく確認します。
このような行動事実の収集を通じて、応募者が成果を生み出せる資質を持っているかどうかを、客観的に評価することができます。また、評価は面接中には行わず、収集したデータをもとに面接後に分析・判断することで、評価のブレを防ぎます。
事実に基づいたこの手法により、印象や先入観に左右されず、組織にとって本当に必要な人材を見極めることが可能になります。特に、新卒採用のように実務経験の少ない候補者を評価する場面では、この「行動の再現性」が重要な判断基準となります。

3. コンピテンシー面接の具体的フロー
コンピテンシー面接では、「応募者の成果につながる行動」を明らかにするために、過去の経験に基づいたエピソードを丁寧に掘り下げることが不可欠です。面接の進行は、あらかじめ設計された4つのステップを通じて行われます。それぞれのステップでは、行動事実を特定し、具体的に引き出すための質問が用意されています。
3-1. 面接のテーマ・課題の特定
まず面接官が確認すべきは、応募者が過去に取り組んだテーマや課題です。ここでの目的は、成果につながるような具体的な状況を設定し、その行動の背景を理解することです。
たとえば、「サークル活動」や「アルバイト」という大きなくくりでは、行動の詳細を把握するのが困難です。そこで「サークル活動の中で、練習に遅れてくるメンバーをゼロにする取り組みをした」といったように、明確なゴールが見えるエピソードに絞り込んでいくことが重要です。
面接官は「その中でもっとも力を入れて取り組んだのは?」「具体的なテーマは何でしたか?」といった質問を活用し、焦点を絞りましょう。
3-2. 工夫・苦労した点の深掘り
次に、その取り組みの中で応募者が直面した困難や、乗り越えるために工夫した点を確認します。このステップでは、高いコンピテンシーを発揮するかどうかの分岐点となる「判断力」「対応力」「実行力」が問われます。
質問例としては、「取り組みの中で、困難だと感じた出来事は?」「それをどうやって解決しましたか?」などが有効です。
ここで重要なのは、「自分で考え、行動したか」という点です。いつも同じ行動しかとらない人物よりも、状況に応じて判断し、適切に対応できる柔軟さのある人材のほうが、高い成果を出す可能性が高いといえます。
3-3. 具体的な行動場面の確認
次のステップでは、実際に行動が発揮された「場面」を特定します。複数のエピソードをまとめて聞くと抽象的な印象しか残らないため、ひとつの具体的な出来事に絞り込むことが求められます。
「その出来事は〈いつ〉〈どこで〉〈どのようなことをした〉場面ですか?」と問いかけることで、応募者が当時の状況を具体的に思い出しやすくなり、面接官もイメージしやすい行動データを得ることができます。
このように、一日の中で一つの場所で起きた場面を明確にすることが、行動事実を定量化するうえで非常に有効です。
3-4. 判断理由と行動への工夫の確認
最後に、応募者がその行動を選んだ「判断理由」と、行動の中で加えた「工夫」を確認します。
「その行動が適切であると判断した理由は?」「他の選択肢と比較して、なぜそれを選びましたか?」「その工夫によって、どんな成果がありましたか?」といった質問で深掘りしていきます。
このステップでは、応募者が単に行動しただけでなく、「意図」や「目的」をもって行動していたかが見極めポイントになります。ここでの回答は、後述するコンピテンシーレベルの判定に直結します。

4. コンピテンシーのレベルと評価軸
コンピテンシー面接では、集めた行動事実をもとに、応募者がどのレベルの行動を発揮していたかを評価します。ただ単に「行動したかどうか」ではなく、「その行動がどれほど高い成果創出力につながるものだったか」を分析する必要があります。
4-1. 5段階のコンピテンシーレベル
評価の基準となるのが、以下の5段階のレベルです
-
レベル5:状況創造行動
まったく新たな、周囲にとっても意味ある状況を作り出す行動。 -
レベル4:状況変容行動
状況を変化させるため、独自の工夫を加えた行動、独創的行動。 -
レベル3:能動行動
いまある状況の中で、工夫を加えた行動、明確な意図や判断に基づく行動、明確な理由のもと選択した行動。 -
レベル2:通常行動
やるべきことをやるべきときやる。 -
レベル1:受動行動
言われたことを言われたときにやる。
この5段階は、応募者が成果を出すためにどれだけ能動的に考え、状況に働きかけたかを定量的に判断するフレームワークとなります。
4-2. レベル評価の判断基準と注意点
評価を行う際には、以下の2点に注意する必要があります。
①行動量ではなく「行動の質」に注目すること
どれだけ多くの行動をしていたとしても、それが低レベルの受動的行動であれば、コンピテンシーが高いとは言えません。高評価とするべきは、状況に働きかけ、成果を創出する力があるかどうかです。
②課題の難易度とレベルを混同しないこと
新卒採用の場合、取り組み自体の難易度が低いことは珍しくありません。しかし、重要なのはその中でどれだけ自分で考え、行動したか。たとえ単純な課題でも、主体的に動き、周囲に働きかけているなら、高いレベルと評価すべきです。
このように、評価は「量より質」「背景より行動」を見極めることが肝心です。レベルごとの基準を理解した上で、過去の行動事実を正確に読み取り、応募者が持つ本質的な力を見抜いていくことが、コンピテンシー面接の成功に直結します。
5.コンピテンシーの可視化と適性検査の活用
コンピテンシー面接は、応募者の行動事実を通じて成果創出力を見極める有効な方法ですが、面接だけではすべてを把握するのが難しい場面もあります。こうしたときに活用したいのが、コンピテンシーの発揮傾向を数値化して可視化する適性検査です。
5-1. 面接だけでは見抜けない要素
面接では、応募者の経験を深掘りすることができますが、以下のような限界も存在します。
- 面接官ごとに質問力や解釈にばらつきが生じる
- 応募者の緊張や表現力により、真の力が見えづらくなる
さらに、行動の再現性や傾向といった観点は、面接だけでは明確に捉えにくい場合があります。そのため、客観的な視点から行動特性を把握する手段が必要とされます。
5-2. 適性検査との併用による精度向上
適性検査では、応募者が成果を生み出す際にどのような行動スタイルを取りやすいかを、複数の視点から測定することが可能です。たとえば、リーダーシップの発揮傾向や、どういったコンピテンシーの発揮パターンがあるかなど、面接では確認しにくい内面的な要素も評価対象になります。
主な活用メリットは以下のとおりです
- 面接前に確認すべきポイントを整理できる
- 面接結果の補強材料として、判断の客観性を高められる
- 応募者の行動特性を、数値や傾向として可視化できる
特に、全国平均との比較指標や発揮傾向の強弱が視覚的に示されることで、面接官間での評価のすり合わせがしやすくなり、採用判断のブレを抑えることができます。
このように、面接と適性検査の併用は、人物の全体像を多面的にとらえ、より精度の高い選考を可能にします。

6.成果につながる人材を見極めるために
不確実性の高い現代において、企業が持続的に成果を上げていくには、「知識やスキルを持っている人」ではなく、「変化に対応し、行動を通じて成果を出せる人」を見極める採用が求められています。
6-1. 採用成功につながる視点の転換
従来の採用では、履歴書や会話の印象など、表面的な要素に引っ張られやすい評価が行われてきました。しかし、それでは入社後の活躍を予測することが困難です。
今求められているのは、応募者の「発揮能力」に注目する視点です。これは、過去の経験の中でどのような行動をとり、どのように周囲や状況に働きかけてきたかを評価することで、成果につながる力を見極めようとする考え方です。
この視点に切り替えることで、以下のような効果が期待できます
- 入社後のミスマッチを抑制
- 部署配属後のパフォーマンスを高精度に予測
- 長期的に成果を出し続ける人材の確保
新卒採用においても、経験の乏しさではなく、行動を通じてどのように課題に向き合ったかを評価することで、ポテンシャル人材を見極めやすくなります。
6-2. コンピテンシー面接実践のすすめ
コンピテンシー面接は、応募者の過去の行動を詳細に聞き出し、その背景にある判断や意図を明らかにすることで、成果に結びつく資質を評価する面接手法です。印象やスキルの保有だけでは見抜けない「再現性のある成果行動」を把握するために有効です。
導入の際には、質問設計や評価基準の明確化、面接官へのトレーニングが不可欠です。また、適性検査との併用によって、面接では見えにくい内面的な行動傾向を補完することができ、総合的な人材判断が可能となります。
成果を生み出せる人材を見極めるためには、「行動の事実」に基づいた評価と、「数値データ」による客観性を組み合わせた多面的な選考アプローチが欠かせません。コンピテンシーを軸にした選考は、その基盤となる有力な手法と言えるでしょう。


サービスの
ご紹介
成果を生み出す人材を見極めるには、行動の質を測る仕組みが重要です。コンピテンシー適性検査「Another8」は、応募者の行動特性や成果創出力を可視化し、面接の精度向上に貢献します。より確かな人材評価を実現したい企業様は、ぜひご検討ください。

コンピテンシー適性検査 Another8

© Humanage,Inc.

