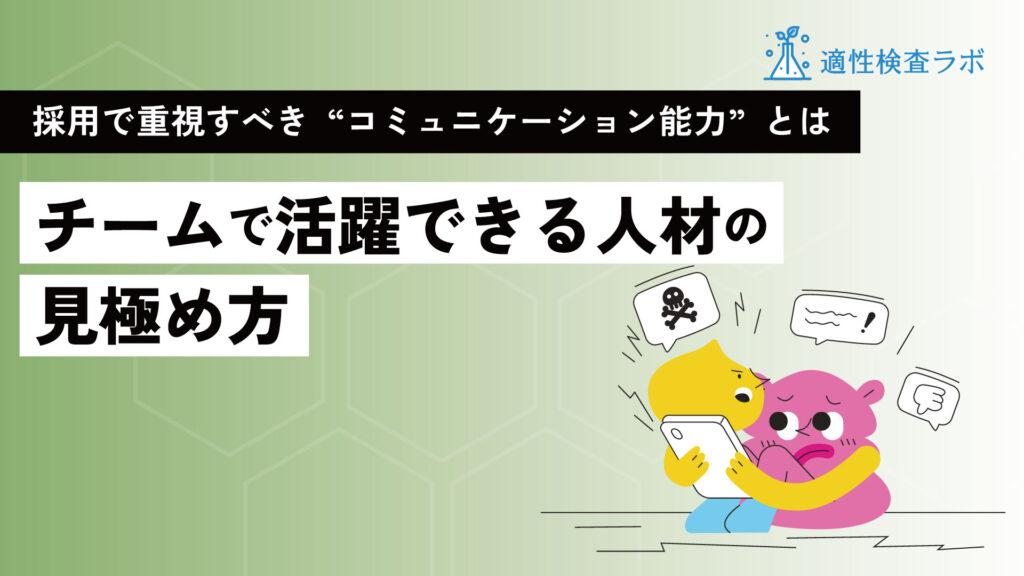
2025.06.27
チームで活躍できる人材の見極め方|採用で重視すべき“コミュニケーション能力”とは
現代のビジネス社会では、多様なバックグラウンドを持つ人々が共に働くことが当たり前になりつつあります。こうした環境の中で、単に「会話がうまい」「空気が読める」といった表層的なものではなく、“本当に”成果につながる「コミュニケーション能力」が必要とされています。
特に近年注目されているのが、「チーム・コミュニケーション」という観点です。本記事では、今後の採用活動において重要性が増すチーム・コミュニケーション能力について、その意義や背景、見極め方法について詳しく解説します。
INDEX
1.コミュニケーション能力とは何か
2. チーム・コミュニケーション能力の重要性
3. チーム・コミュニケーションの見極め方
4. 自尊と他尊の関係がもたらすもの
5. 組織におけるチーム・コミュニケーションの活用
6. まとめとこれからの人材見極めへの提言
サービス紹介
1. コミュニケーション能力とは何か
1-1. 従来の「コミュニケーション能力」観
これまで「コミュニケーション能力」と言えば、「相手の話をしっかり聞き、適切に返す」「協調性がある」など、どちらかというと対人スキルの基礎的な側面を指していました。特に日本では「空気を読む」「和を乱さない」といった文化的背景から、協調性=コミュニケーション能力とされることが多かったのです。
実際に、日本経済団体連合会が企業を対象に実施したアンケート(2018年度まで)では、「選考で重視する点」として16年連続で「コミュニケーション能力」が第1位でした。
1-2. なぜ今、「チーム・コミュニケーション」なのか
しかし、社会の多様化、ダイバーシティの進展により、単なる協調性だけでは成果を生み出せない時代が到来しています。異なる価値観や働き方を持つ人々と協働する場面では、「意見の違い」を恐れずに建設的な対話を行い、相互理解を深めながらチーム全体としてシナジー(相乗効果)を生む力が求められます。
これが「チーム・コミュニケーション」と呼ばれる新たな能力であり、現代の組織において、真に価値のあるコミュニケーション能力とされています。

2. チーム・コミュニケーション能力の重要性
2-1. チームで成果を出すための新しい力
チーム・コミュニケーションが高い人材は、業務を円滑に進めるだけでなく、変化にも柔軟に対応し、チームで成果を創出できる力を備えています。彼らは、自らの意見を適切に主張しながら、他者の考えを尊重し、建設的なやりとりを通じてチームの目標達成に貢献します。
これは従来の「自己主張を控え、調和を保つ」スタイルとは異なり、「意見の違いを前提とし、対話によって新たな価値を創出する」スタイルといえます。
2-2. 採用で求められる「バランス」とは
チーム・コミュニケーションにおいてカギとなるのが、「自尊感情」と「他尊感情」のバランスです。
- 自尊感情が高い人は、自分の価値を理解し、失敗を恐れず行動できます。
- 他尊感情が高い人は、他者を理解し、サポートしようとする姿勢を持ちます。
どちらか一方に偏ると、チーム内での関係性が歪みます。自己中心的になったり、過度に受け身になったりするからです。両者のバランスが取れてこそ、真に協働できる人材といえるのです。

3. チーム・コミュニケーションの見極め方
3-1. 適性検査による評価の有用性
現代の採用活動では、応募者のスキルや経験だけでなく、チームで協働する力を見極める必要があります。特に、チーム・コミュニケーションのように「表に見えにくい資質」を評価するには、客観的かつ構造化されたアプローチが不可欠です。
その手段の一つが、適性検査による評価です。この手法では、応募者の「チームにおける相互作用の特性」を数値化し、可視化することが可能です。
具体的には、以下のような観点から個人の傾向を分析します
- 自分をどう捉えているか(自尊)
- 他者をどれだけ理解しようとしているか(他尊)
これらの特性は、チームでの振る舞いや、役割に対する適応度を測るうえで非常に有用です。採用時にこうした指標を活用することで、単なる社交性や人当たりの良さではなく、「多様なメンバーと協働し、成果を生み出せる力」を見極めることができます。
3-2. 面接と検査のハイブリッドな活用
適性検査は応募者の特徴を定量的に捉える点で非常に有用ですが、それだけで十分とは限りません。より実践的な見極めを行うには、面接と組み合わせたハイブリッドな評価が有効です。
たとえば、検査結果で「自尊が高く、他尊が低い」と示された応募者に対しては、
以下のような質問を通じて、実際の行動特性を深掘りできます
- 「チームで意見が割れたとき、どう行動しましたか?」
- 「相手の意見に納得できない場面で、どのように対話しましたか?」
こうした質問を通じて、単なる自己主張の強さが、実際にはどのようなコミュニケーションとして発揮されているのかを確認できます。
このように、適性検査+面接による多面的なアプローチは、応募者の内面にある「チームとの向き合い方」をより的確に浮き彫りにする手段となります。

4. 自尊と他尊の関係がもたらすもの
4-1. 自他理解のバランスが生む協働力
チームで成果を出すためには、単なる能力や経験だけでなく、「自分を信じる力(自尊)」と「相手を尊重する力(他尊)」のバランスが重要です。
- 自尊が高い人は、自分の価値を理解し、自信を持って行動できます。
- 他尊が高い人は、他者の立場や意見を理解し、相手に敬意を持って接することができます。
この両者のバランスが取れていることで、自らの意見を適切に発信しながらも、他者との対話を通じて新しい価値を共創できるようになります。一方で、どちらかに偏ると、自己中心的な言動や受け身な姿勢になりやすく、協働が難しくなる傾向があります。
4-2. 周囲からの見られ方を意識する力
さらに、自分の言動が周囲にどのように受け取られているかを理解する力(公的自己認識)も、チームでの良好な関係性には欠かせません。
- この力が高い人は、状況や相手に応じて適切なコミュニケーションが取れるため、摩擦を抑えながら信頼関係を築きやすくなります。
- 逆にこの力が低いと、自分本位な振る舞いが誤解や対立を生むリスクが高まります。
自尊・他尊・公的自己認識の3つが高い水準でバランスしている状態こそが、チーム内で信頼を獲得し、成果を共に生み出すための基盤となります。
5.組織におけるチーム・コミュニケーションの活用
5-1. チームビルディングと育成の視点
組織において、チーム・コミュニケーションは採用時の見極めにとどまらず、その後の育成やチームビルディングの基盤としても重要な意味を持ちます。
特に以下のような場面で活用が可能です
- 配属直後のチーム形成:各メンバーの自尊・他尊の傾向を把握し、コミュニケーション上の課題や注意点を可視化することで、初期段階から健全な関係性を築くことができる。
- チームの再編時:新たなメンバーを迎える際、既存チームとの相性やバランスを確認し、摩擦を未然に防ぐ。
- 育成・フィードバック:個々人の自己認識や対人配慮の特徴に応じた育成方針を設計することで、効果的な成長支援が可能になる。
このように、チーム・コミュニケーションの観点を取り入れることで、「人をどう配置するか」「どう育てるか」「どう組織を活性化させるか」といった人材マネジメント全体に深く関与させることができます。
5-2. 異文化環境での実践的意義
近年のビジネス環境では、国籍・性別・価値観・働き方といったさまざまな要素の多様化が進んでいます。このような異文化環境において、従来の「調和を保つ」だけの協調性では、対話も協働も成立しづらくなっています。
異なる価値観に基づく行動を正しく理解し、相互に歩み寄る姿勢がなければ、チームはすぐに分断されてしまいます。
そこで必要とされるのが、以下のような力です
- 相手の視点に立つ想像力(他尊)
- 自己の立ち位置を客観的に見つめ直す力(公的自己認識)
- 感情を安定的にコントロールする基盤としての自尊感情
こうした力が備わっていることで、異なる意見や習慣がぶつかっても、葛藤を前向きな対話に変える力を発揮することができます。グローバル化が進む中で、こうした実践的なコミュニケーション能力は、ますます重要になっていくといえるでしょう。

6. まとめとこれからの人材見極めへの提言
6-1. 多様性時代の採用基準の刷新
これまでの「コミュニケーション能力」は、あいまいで属人的な評価がされることも多く、面接官の主観に左右されやすい領域でした。しかし、チーム・コミュニケーションという概念を導入することで、より構造的・行動的な視点から人材を評価できるようになります。
多様性の時代において、求められるのは以下のような人物です
- 自分の意見を持ち、適切に伝えられる
- 異なる立場の人とも協働できる
- チームで成果を生むことにコミットできる
こうした人物を見極めるには、旧来の評価軸ではなく、行動特性や心理的な安定性に基づく新たな基準が必要です。
そのためには、「バランスの取れたコミュニケーション能力」を見極める新たな視点を、採用活動に積極的に取り入れていく必要があります。
6-2. 今後の組織力強化に向けて
組織の力は、個々の優秀さの足し算ではなく、「チームとしていかに成果を出せるか」によって決まります。つまり、一人ひとりの能力を最大限に活かすための土台としてのチーム・コミュニケーション力が不可欠なのです。
この力は、入社後の育成や環境によって伸ばすことも可能ですが、採用時点である程度の傾向を見極めておくことは、リスク低減と育成効率の面で非常に有効です。
今後、組織力を強化していくうえで必要なのは、次の2点です
- 「チームで成果を出せる人材」を定義し、その視点で採用・配置を行うこと
- 単なるスキルや経験ではなく、人材の持つコミュニケーションの質を評価し、活かすマネジメントを構築すること
これらを実現することで、個の強みを活かしつつ、組織全体のパフォーマンスを最大化することができるはずです。


サービスの
ご紹介
コミュニケーション力は、単に「話せる」「協調できる」といった能力にとどまりません。多様な価値観を持つメンバーと協働し、成果を生み出すためには、自他の理解とバランスの取れた対話力が不可欠です。W8は、自尊感情や他者配慮、公的自己認識といった観点から、チーム・コミュニケーション力を科学的に測定する適性検査です。組織に必要な「協働できる力」を見える化するツールとして、W8の活用を検討してみてはいかがでしょうか。

チーム・コミュニケーション適性検査 W8

© Humanage,Inc.

