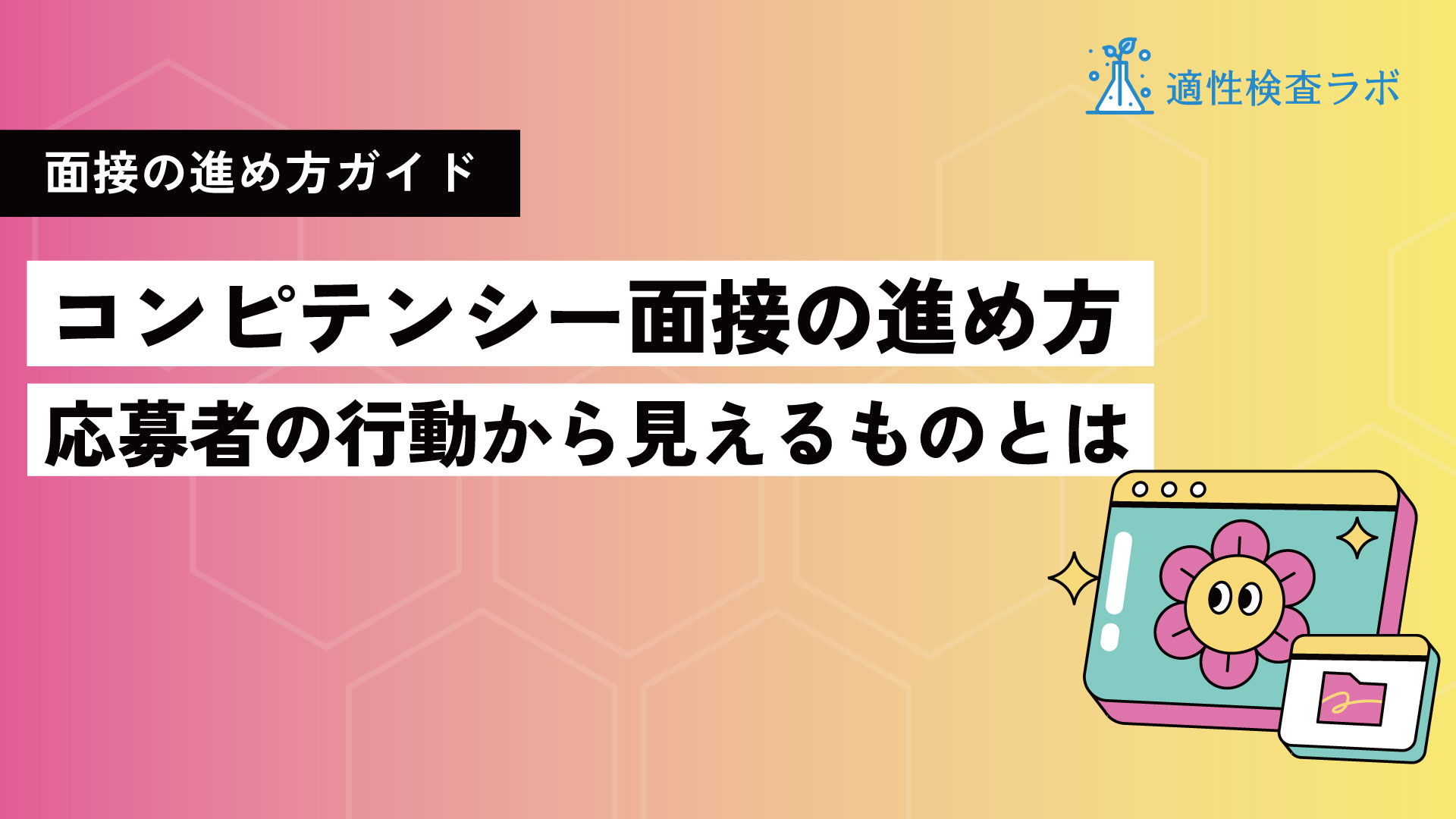
2025.05.16
適性検査の種類と活用完全ガイド|新卒・中途の使い分けから見極め方、導入事例まで
人材戦略において、適性検査の重要性は年々高まりを見せています。特に、ピープルアナリティクスやHRテクノロジーの進展に伴い、適性検査の種類や活用シーンは多様化し、採用の精度向上だけでなく、配属・育成・定着支援など、あらゆる人材マネジメントの局面で欠かせないツールとなりつつあります。本記事では、適性検査の基本から具体的な種類、さらには新卒・中途採用における使い分けの事例までを詳しく解説し、データに基づいた人材戦略の可能性について考察します。
INDEX
1.はじめに
2.なぜ今、行動ベースの面接が注目されているのか
3.コンピテンシー面接の基本を知る
4.実践!行動を引き出す面接の進め方
5.面接の精度を高めるための工夫
6.未来につながる“行動ベース”の選考へ
サービス紹介
1. はじめに
1-1. 面接で「見極めたつもり」がすれ違いを生むことも
採用面接の場で、私たちは「この人なら活躍してくれそうだ」「なんとなくフィーリングが合う」といった印象で判断してしまうことがあります。けれど、選考を終えて配属してみると、「面接で感じた印象と違った」「期待していた行動が見られない」というギャップに直面することも少なくありません。
それは、採用担当者の見る目が甘かったからでしょうか?——決してそんなことはありません。むしろ、人を見ることの難しさに、日々真摯に向き合っているからこそ生じる“すれ違い”だと言えるかもしれません。
1-2. 感覚に頼らない採用が求められている
かつての採用では、候補者の「学歴」や「目立った実績」、あるいは「面接での第一印象」といった、比較的わかりやすい情報をもとに評価する場面が多く見られました。
もちろん、こうした情報がすべて悪いというわけではありません。面接という限られた時間の中で、できるだけ多くの情報をつかもうとするのは、採用担当者として当然の姿勢でもあります。
ただ一方で、「なぜあの人を採ったのか?」「本当にうちの組織に合う人だったのか?」と、入社後のギャップに悩んだ経験を持つ方も少なくないのではないでしょうか。
いま採用の現場では、こうした“感覚頼み”から脱却し、もっと納得感のある選考プロセスを構築しようとする動きが広がっています。限られた材料から“なんとなく”で判断するのではなく、行動や経験など、より客観的な事実に基づいた面接のあり方が求められはじめているのです。
1-3. “行動を見る”という新しい選考の視点
採用において「この人は活躍してくれそうか?」を見極めることは、決して簡単ではありません。面接では誰しも、自分をよく見せようとするもの。だからこそ、“印象”や“話し方”に左右されすぎず、その人の本質に近づく手がかりが必要になります。
そこで今、見直されているのが「行動に着目する」という視点です。
たとえば、学生時代の経験をただ“聞く”のではなく、「そのとき、どんな行動を取ったのか?」「どんな工夫をしたのか?」といった“行動事実”を具体的に引き出していくことで、言葉の裏にあるその人らしさや、再現性のある力が浮かび上がってきます。
このように、「考え方」よりも「実際の行動」に注目するアプローチは、採用の納得感を高め、より適した人材との出会いにつながる可能性があります。
この“行動を見る”という視点を実現する面接手法が、今回ご紹介する「コンピテンシー面接」です。従来型の面接とはどんな違いがあるのか、その特徴を見ていきましょう。

2. なぜ今、行動ベースの面接が注目されているのか
2-1. 「印象評価」は、思った以上にブレやすい
採用面接は、限られた時間で候補者の素質やポテンシャルを見極めなければなりません。そのため、面接官が持つ第一印象や話し方の“雰囲気”などに引っ張られて評価してしまう、というケースも少なくありません。
もちろん、印象も大切な情報のひとつです。しかし、印象はあくまで主観的な感覚であり、人によって大きくブレやすいという弱点があります。ある面接官には「頼もしそう」と映った人が、別の面接官には「少し押しが強すぎる」と感じられてしまうようなこともあるでしょう。
評価のブレが大きいままだと、採用基準があいまいになり、組織としての人材の見極めにも影響が出てしまいます。
2-2. 面接官の“好き嫌い”が評価に影響する理由
人は誰しも、「なんとなくこの人はいい感じがする」といった感覚を持つものです。それ自体は自然なことですが、問題はその“なんとなく”が、知らず知らずのうちに評価に影響を与えてしまうこと。
こうした無意識のバイアスは、心理学の世界では「スキーマ(先入観)」と呼ばれています。一度“好印象”を持った相手には、その後の言動すべてを好意的に解釈してしまう。反対に、“ちょっと合わないかも”と感じた人には、厳しい見方になってしまう──。そんな経験、心当たりのある方も多いのではないでしょうか。
このような先入観によるバイアスが、せっかくの候補者の“本来の力”を見えにくくしてしまっている可能性もあるのです。
2-3. 面接の“納得感”を生むのは“行動”という事実
では、こうした主観や印象に頼りすぎないためには、どうすればいいのでしょうか。
ひとつのヒントが、「行動ベースで見る」という評価視点のシフトです。つまり、「どんな考えを持っていたか」だけではなく、「実際にどんな行動をしたのか」を具体的に掘り下げていくこと。
たとえば「リーダーシップがあります」と言う学生がいたとしても、それをどう証明するかは人それぞれ。行動レベルで「どんな場面で、誰に対して、何をしたか」を聞いていくことで、その人ならではの“らしさ”が浮かび上がってきます。
このような面接の進め方は、主観を排除するだけでなく、面接官同士で評価のズレを防ぎ、「なぜこの人を採用したのか」という意思決定の納得感にもつながります。
次章では、こうした行動ベースの視点を面接にどう落とし込むか──具体的な方法として注目されている「コンピテンシー面接」についてご紹介します。

3. コンピテンシー面接の基本を知る
3-1. 「考えたこと」ではなく「やったこと」に注目する
「なぜそう考えたのか?」という問いももちろん大切ですが、面接において本当に知りたいのは、「その人が実際にどんな行動をしたか」ではないでしょうか。
たとえば、「課題に直面したとき、どんな工夫をしたのか」「うまくいかなかったとき、どう乗り越えたのか」といった具体的な行動は、その人の思考力や姿勢、柔軟性をリアルに映し出します。
コンピテンシー面接では、こうした「行動ベースの問いかけ」によって、その人が持っている力の“使い方”を丁寧に見ていきます。単なる知識やスキルの有無ではなく、「それをどう活かして成果につなげたか」に注目することが、見極めの質を高めるポイントになります。
3-2. エピソードを通じて“らしさ”や“強み”が見えてくる
「クラブ活動でリーダーを務めていた」「アルバイトで売上に貢献した」──このようなエピソードは、学生の多くが面接で語る内容かもしれません。
ただし、重要なのは“何をやったか”以上に、“どうやったか”です。
たとえば、「部員をまとめた」という話も、「どんな状況で」「どんな声かけをして」「どんな反応があったか」と深掘りしていくことで、その人ならではの工夫や関わり方、思考のクセなどが見えてきます。
エピソードを通じて“その人らしさ”がにじみ出てくる。そんなプロセスこそが、コンピテンシー面接の大きな魅力のひとつです。
3-3. 成果につながる行動を見抜く問いの工夫
「印象」や「自信のある話し方」だけでは、成果につながる力があるかどうかを見極めるのは難しいものです。
そこでコンピテンシー面接では、問いの設計にも工夫が必要になります。
たとえば──
・「そのとき、具体的にどんなことをしましたか?」
・「なぜその方法を選んだのですか?」
・「振り返ってみて、何が成功の要因だったと思いますか?」
こうした問いは、ただ出来事を語ってもらうだけでなく、本人の思考と行動のつながり、再現性のある力を引き出すヒントになります。
そして何より、「考えたこと」より「やったこと」を丁寧に深掘るこの面接スタイルは、面接官にとっても「納得して判断できる」プロセスにつながります。

4. 実践!行動を引き出す面接の進め方
4-1. まずは「テーマ」を決めてプロセスをたどる
行動ベースの面接を進めるうえで、まず重要なのは「何について聞くのか」というテーマ設定です。
ここでいうテーマとは、応募者が過去に力を入れて取り組んだ出来事やプロジェクトのこと。サークル活動、アルバイト、ゼミ、インターンなど、本人が「頑張った」と感じている取り組みを起点にすることで、記憶の振り返りがしやすくなります。
テーマが決まったら、その活動の中でどんなプロセスをたどっていったのか、時系列で深掘りしていきます。
たとえば:
「その取り組み、最初に何から始めましたか?」
「次にどんなことをしましたか?」
一つひとつ丁寧に聞いていくことで、実際の行動の全体像が見えてきます。
4-2. “場面”に落とし込んで記憶を引き出す
テーマとプロセスがある程度明らかになったら、次のステップは“具体的な場面”に落とし込むことです。
ここでのポイントは、「映像として思い出せるシーン」を本人に想起してもらうこと。人は出来事を思い出すとき、抽象的な話より、具体的なシーンの方が圧倒的に記憶が鮮明になります。
たとえば:
「そのとき、誰とどんなやりとりをしましたか?」
「どこで、どんな表情をしていたか覚えていますか?」
こうした問いを投げかけることで、よりリアルな行動事実が浮かび上がってきます。
4-3. 再現性のある力を見極める質問の仕方
最後に重要なのは、「その行動がなぜ成果につながったのか」を一緒にひもとくことです。
成果の大小よりも、その成果が“再現可能なものかどうか”を見極めることが、未来のパフォーマンスを判断するうえでのカギになります。
質問の例:
・「その成果を出せた要因は何だったと思いますか?」
・「もし同じ状況がもう一度あったら、また同じようにできますか?」
・「今振り返って、他に工夫できたことはありますか?」
こうした質問は、単なる事実確認にとどまらず、応募者の思考力や再現性、成長意欲といった“これからの活躍”につながる力を見極める手がかりになります。
?行動を引き出す面接のフロー ― コンピテンシーを可視化する6ステップ
STEP 1|テーマを定める
── 取り組みの中で「最も力を入れたこと」は何か?
STEP 2|プロセスをたどる
── ゴールに至るまでの流れを、時系列で整理する
STEP 3|場面を特定する
── 印象的なシーンを思い出し、具体的な行動を描き出す
STEP 4|行動を深掘る
── 誰が・いつ・どこで・なぜ・どのように、を掘り下げて聞く
STEP 5|工夫・困難の突破口を探る
── 自ら考え、行動した“再現性ある力”が最も表れやすい部分
STEP 6|次のシーンへ広げる
── 他にも発揮された行動は?別の場面も振り返ってもらう

5. 面接の精度を高めるための工夫
5-1. 面接中は“評価しない”が鉄則
面接の場では、つい「この人、いいかも」「ちょっと違うかな」と心の中で判断を下してしまいがちです。しかし、コンピテンシー面接においては、“評価”は後回しが鉄則です。
面接の目的はあくまで、“その人の過去の行動事実を収集すること”。評価をしながら話を聞こうとすると、無意識に自分の期待に沿うエピソードを引き出そうとしてしまうなど、質問の仕方にバイアスがかかる恐れがあります。
たとえば、面接中は「今はまだ点数をつけるタイミングではない」と自分に言い聞かせ、ひたすら行動を聞き出すことに集中する。その積み重ねが、選考の納得感を大きく左右します。
5-2. 聞き方・見方のすり合わせがチームの鍵
複数の面接官が関わる選考では、「誰が聞いても、同じように評価できる」ことが理想です。そのために欠かせないのが、“聞き方”と“見方”の共通言語化です。
たとえば、
- 「どこまで具体的に聞くか」
- 「どのような行動が“自走力”といえるのか」
- 「プロセスのどこに注目すべきか」
といった基準をチーム内で共有しておくことで、主観の混入を減らし、評価の精度を高めることができます。
まずはシンプルな「質問リスト」や「評価シート」をつくってみるのも一案です。面接官の経験やスタイルが異なっても、一定の型に沿って評価する仕組みがあれば、チームとして一貫性ある選考が可能になります。
5-3. 小さく始めて、じわじわ育てる面接の仕組み化
とはいえ、いきなり面接プロセスをフルリニューアルするのはハードルが高く感じられるかもしれません。そんなときは、小さく始めて、徐々に仕組みを育てていくのが現実的なアプローチです。
たとえば、まずは
- 1職種、1部門から試験導入してみる
- 特定の面接ステップだけコンピテンシー型にしてみる
- トライアル後にフィードバックをもらい改善する
といった形で、“スモールスタート”からのPDCAを回していく方法が有効です。
面接の制度化は、一度で完成するものではありません。現場との対話やトライアンドエラーを通じて、“自社らしい面接の型”を少しずつつくっていくことが、継続的な質向上につながります。
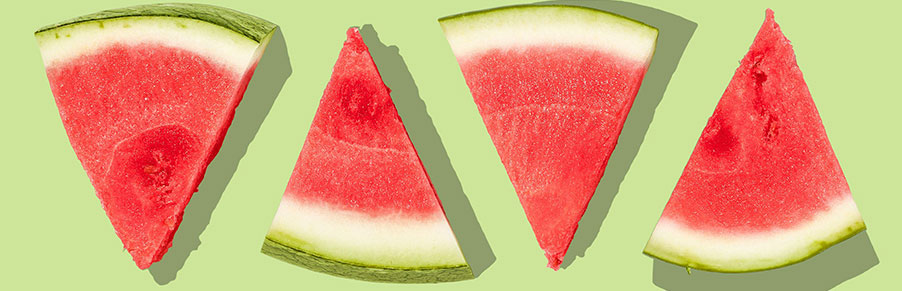
6. 未来につながる“行動ベース”の選考へ
6-1. 面接の“問い”が採用の質を変える
面接でどんな問いを投げかけるか――
それだけで、見えてくる人の姿は大きく変わります。
これまでのように「どんな人に見えるか」という印象で判断するのではなく、
「どんな行動をしてきたか」という事実に目を向ける。
そんな問いを重ねていくことで、候補者の“らしさ”や“強み”が自然と立ち上がってきます。
質問を少し変えるだけで、面接の質は大きく変わる。
その一歩が、組織の未来を変えるかもしれません。
6-2. 「なんとなく」から脱却する評価視点
人の印象は、驚くほどあいまいで主観的です。
だからこそ、評価の軸を“行動”という客観的な事実に置くことが大切です。
「何を考え、どんなふうに動いたか」
「その結果、何を得て、どんな工夫をしたのか」
こうした具体的なプロセスをたどることで、候補者の資質や思考のクセ、仕事への向き合い方まで見えてきます。
「なんとなく良さそう」で終わらせず、根拠ある“納得感のある選考”へ。
それが、これからの採用に欠かせない視点です。
6-3. これからの採用に求められる、確かな“見る目”
変化が激しく、正解のない時代だからこそ、
「これまで何をしてきたか」よりも「これからどう動けるか」を見極める力が求められています。
そのために必要なのは、過去の“行動”という足跡から、未来の再現性を読み取る目――
つまり、**コンピテンシーの視点を取り入れた“見る目”**です。
はじめから完璧を目指さなくても大丈夫です。
少しずつ問い方や聞き方を工夫していく中で、貴社ならではの面接スタイルが形になっていきます。
未来につながる採用のために、今できる一歩から。
“行動に着目する面接”は、きっとこれからの採用に、確かな前進をもたらしてくれるはずです。


サービスの
ご紹介
データドリブンな人材戦略を進めるうえで、適性検査の選定は重要な意思決定の一つです。特に、入社後の「成果」に直結する行動特性を見極めたい場合には、選考プロセスの中に戦略的に組み込める高機能な検査が求められます。
TG-WEBは、こうしたニーズに対応した多面的な適性検査であり、導入企業2,300社以上・年間60万人が受検する実績を誇ります。知的能力や性格特性のみならず、過去の行動に基づく“成果につながる再現性の高い特性”を可視化する点が特長です。さらに、面接官向けの分析シートや本人向けのフィードバックシート、配属先の上司向けの育成報告書なども提供され、採用選考だけでなく配属・育成・内定者フォローに至るまで幅広く活用できます。

コンピテンシー適性検査 Another8

© Humanage,Inc.

