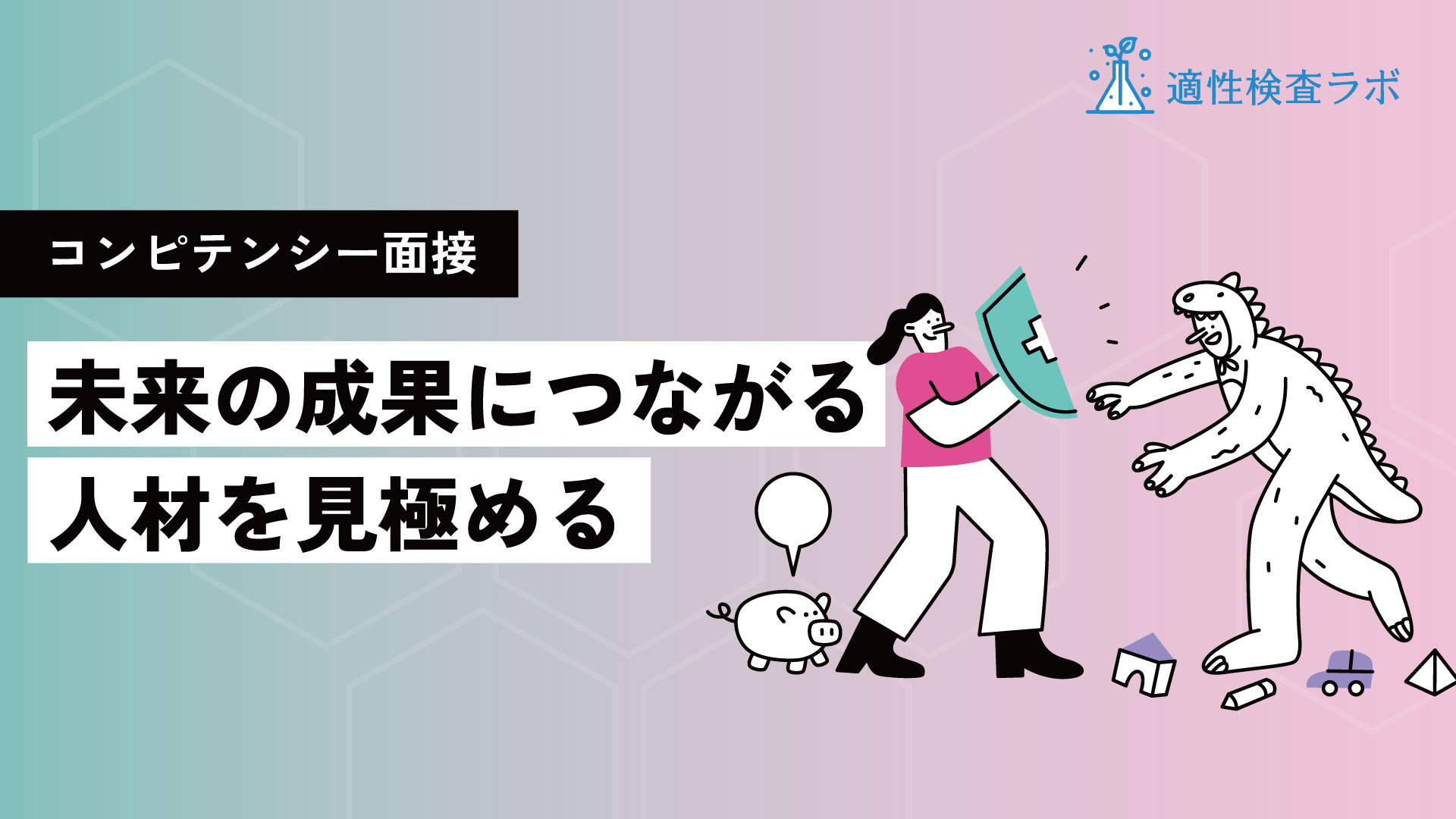
2025.05.09
コンピテンシー面接で、未来の成果につながる人材を見極める
「この候補者、感じはいいけれど、本当に活躍できるだろうか?」
採用の現場で、こんなモヤモヤを抱えた経験はありませんか?
応募者の印象は悪くない。でも、何かが引っかかる――そんな感覚は、面接官なら誰しも一度は感じたことがあるはずです。
面接において“勘”や“経験”は確かに重要です。しかし、それに頼りすぎると「なんとなく良さそう」「雰囲気が合いそう」といった直感が判断基準となり、結果として採用の精度が揺らぐことも。本記事では、採用における「見極め」の精度を高めるために、印象評価から脱却し、“行動事実”に基づく評価手法について解説します。明確な基準で採用を行うことで、採用担当者の納得感が高まり、企業にとっても応募者にとってもよりフェアな採用プロセスを実現できるはずです。
本記事では、採用活動における評価の精度を高めるための視点や手法についてご紹介します。特に、面接の際に感じる「なんとなく良さそう」「印象に頼った評価」から脱却し、より実践的で再現性のある判断ができるようになるためのヒントをお伝えします。採用活動の質を向上させるために、どのような行動ベースの評価方法が有効かを一緒に考えていきます。
INDEX
1.採用の”見極め”にモヤモヤしていませんか?
2.なぜ今「印象評価」では限界があるのか
3.コンピテンシー面接とは何か
4.面接の精度を上げるためのポイント
5.主観を排除した面接がなぜ有効なのか
6.採用の質を変える“行動ベース”の面接とは
サービス紹介
1.採用の“見極め”にモヤモヤしていませんか?
1-1. 「面接で本当に見極められているのか?」という問い
「この候補者、感じはいいけれど、入社後にちゃんと活躍してくれるだろうか?」 ――採用面接の場で、そんなモヤモヤを抱えたことはないでしょうか。
候補者の話す内容はそれなりに整っているし、受け答えも悪くない。でも、いまいちピンとこない……。一方で、少し不器用ながらも熱意や“らしさ”が垣間見える人に、「この人は化けるかも」と直感的に惹かれることもあります。そんなふうに「よくわからないけど、なんとなく良さそう/良くなさそう」で評価してしまうのは、実は面接における“あるある”です。もちろん、面接官の“勘”や“経験値”が完全に否定されるべきではありません。ただ、それだけに頼った判断が、企業にとって大きな機会損失を生んでしまうこともあるのです。
1-2. 採用の“感覚頼み”から脱却するには
「なんとなく良さそう」「雰囲気が合いそう」——面接の現場では、つい感覚で判断してしまうこともあるかもしれません。採用は“人”を見る仕事だからこそ、直感も大切な要素ではありますが、一方でそれだけに頼ってしまうと、判断がぶれたり、後から「あれ?」と思うことも出てきてしまいます。
たとえば、「話がうまい人が採用されやすい」「受け答えに慣れていない人が不利になる」といった現象が起きてしまうのは、評価の基準が感覚ベースになっていることも一因かもしれません。いま、採用活動のなかで大切になっているのは、「何をもって評価するか」をあらかじめ定め、それに沿って一貫性のある判断をしていくこと。そのための一つの視点として、「印象」ではなく「行動の事実」に注目する方法が注目されています。
1-3. いま見直される“行動ベース”の評価視点
採用における評価軸は、ここ数年で少しずつ変化しています。たとえば、「優秀そうに見える」ではなく「実際にどんな行動をとってきたか」に着目する“行動ベース”の評価視点が、多くの企業で導入されはじめています。これは「コンピテンシー面接」と呼ばれる手法に代表されるもので、応募者が過去にどんな経験をし、どのように考え、どのような行動をとったかを丁寧にたどることで、その人の強みや“らしさ”をより立体的に捉えていくというものです。「印象に左右されない」「誰が評価してもブレにくい」——
そんな面接を目指したいとき、行動ベースの視点は心強い指針になります。決して難しい方法ではありません。少しずつ取り入れていくことで、より納得感のある採用に近づいていけるはずです。

2. なぜ「印象評価」では限界があるのか
2-1. 従来型面接の評価がブレやすい理由
「面接官によって評価がバラバラになってしまう…」そんな課題を感じたことはありませんか?
従来の面接では、学生の話し方や雰囲気、態度など、“印象”から判断する場面が少なくありません。ですが、印象は面接官の経験や性格、気分などに左右されやすく、どうしても評価にブレが出てしまいがちです。
「この学生は好印象だったけれど、なぜ良かったのかを言語化できない」
「別の面接官は違う印象を持っていて、意見が割れてしまった」
——このようなシーンは、どの現場でも一度は経験されているかもしれません。
もちろん、人を見るという仕事において“直感”も大切ですが、それに頼りすぎると、「なんとなく」での判断が続き、採用の精度や納得感を高めるのが難しくなってしまいます。
2-2. 「印象」に引きずられるリスク
たとえば、第一印象が良い応募者については、その後のすべての評価も好意的に見えてしまう…。
一方で、最初にネガティブな印象を持ってしまうと、それを払拭するのはなかなか難しい…。
こうした「印象に引きずられる現象」は、心理学で「ハロー効果」や「スキーマ」とも呼ばれます。つまり、最初に持った印象が、その人に対する評価全体に影響を与えてしまうのです。もちろん、こうした影響を完全に排除するのは簡単ではありませんが、「評価軸を明確に持つこと」で、少しずつ印象の偏りを和らげることはできます。
“印象”より“行動の事実”にフォーカスする。
それだけでも、見えてくるものが変わってくるはずです。
2-3. 評価の軸を“主観”から“行動事実”へ
では、どうすれば評価のブレや主観を抑えることができるのでしょうか?
その鍵となるのが、「行動事実」に着目する評価視点です。応募者の“考え”や“意見”だけでなく、「実際にどんな行動をしたか」を丁寧に聞き取ることで、その人が発揮してきた力や、取り組みに対する姿勢が見えてきます。
「どんな場面で」「誰に対して」「どんな理由で」「何をしたか」
こうした情報は、評価のブレを小さくし、面接官同士の意見の食い違いも防ぐ助けになります。
行動ベースの面接は、採用担当者にとっても応募者にとっても、より納得感のある対話につながります。
少しずつでも、主観ではなく“行動の事実”に軸を移すことで、採用の質は着実に高めていけるはずです。

3. コンピテンシー面接とは何か
3-1. 「考えたこと」ではなく「やったこと」を深堀る
面接の場面で、つい「どう考えていましたか?」「どんな気持ちでしたか?」と聞いてしまうことはありませんか?
もちろん、応募者の価値観や考え方を知ることも大切です。ですが、思いや考えだけでは「実際に何をしたか」が見えづらく、評価が抽象的になりやすい側面もあります。そこで注目したいのが、“行動そのもの”に焦点を当てた聞き方です。
たとえば、「そのとき実際にどんな行動をとりましたか?」「どんなふうに周囲に働きかけたんですか?」といった問いを投げかけると、応募者の具体的な行動が浮かび上がってきます。このように、「考えたこと」ではなく「やったこと」に注目して深掘るのが、コンピテンシー面接の大きな特徴です。
3-2. エピソードから“らしさ”や強みが立ち上がる
印象だけでは掴めなかった、その人の“らしさ”や“強み”——それらが見えてくるのは、実は過去のエピソードを聞いたときだったりします。
たとえば、「困難な状況でどんな工夫をしたか」「チームの中でどんな役割を担っていたか」など、実際の行動に焦点を当てることで、本人の意識していなかった力や特徴が浮き彫りになることがあります。特別な体験でなくても構いません。日常の取り組みの中に、その人らしい行動パターンや、考え方のクセ、周囲への影響の仕方などが表れるものです。こうした“その人らしさ”に光を当てる面接こそが、これからの採用において求められているのではないでしょうか。
3-3. 面接に“再現性のある成果”という視点を
過去の成果が偶然によるものだったのか、それとも本人の工夫や粘り強さによって生まれたものなのか——そこを見極める視点が、「再現性のある成果」という考え方です。
たとえば、部活動で好成績を収めた学生がいたとしても、単に「運よく強いチームに所属していただけ」の場合もあれば、「戦略的に練習計画を立てて、チームを引っ張った」結果かもしれません。もし後者であれば、そのプロセスは将来、別の環境でも応用が利く可能性が高い。それこそが、“再現性のある成果”です。
コンピテンシー面接では、こうした成果のプロセスを丁寧にひもといていきます。未来にも成果を生み出せる人材かどうかを見極めるうえで、この視点は大きなヒントになるはずです。

4. 面接の精度を上げるためのポイント
コンピテンシー面接の大きな特徴は、「その人が過去にどんな行動をしたのか」を丁寧に掘り下げていくことにあります。ただ、いざ実践しようとすると「どこまで聞いていいの?」「うまく深ぼれない…」と感じることもあるかもしれません。ここでは、面接の質を高めるための具体的な工夫を3つの視点からご紹介します。
4-1. 5W1Hでエピソードを具体化する
行動を深掘るとき、頼りになるのが 「5W1H」 の視点です。
これはすでにおなじみのフレームかもしれませんが、コンピテンシー面接においてもとても有効です。
• When(いつ):それはいつ頃の出来事でしたか?
• Where(どこで):どんな場面で起こったことでしたか?
• Who(誰と):誰と関わりながら取り組みましたか?
• What(何を):どんな課題に取り組みましたか?
• Why(なぜ):そのとき、なぜそうしようと思ったのですか?
• How(どのように):具体的にどんな行動を取りましたか?
こうした問いかけを重ねることで、抽象的なアピールではなく、具体的な行動の流れや背景が浮かび上がってきます。「リーダーシップを発揮した」といった一言に対しても、5W1Hで深掘りしていくと、その人ならではの“スタイル”や“価値観”が自然と見えてくるはずです。
4-2. “すぐに答えられない学生”の真意を探る
面接中、こちらの質問にすぐ答えられない学生に出会うこともあるかもしれません。ですが、それは必ずしも「準備不足」や「自信がない」からとは限りません。多くの場合、「自分の行動を振り返って整理する機会がなかった」「質問の意図をじっくり考えている」といったケースもあります。そんなときは、少し間をとって待つこと、あるいは「どんなことが印象に残ってる?」「そのときどう感じた?」など、思い出しやすい質問から始めてみるのも有効です。焦らず、応募者のペースに寄り添いながら話を深めていく姿勢が、結果的に“本当の姿”を引き出すきっかけになります。
4-3. 再現性のある成果を引き出す聞き方
前章でも触れた「再現性のある成果」は、将来的な成長や活躍を見通すうえでとても重要な視点です。
では、その“再現性”を見極めるには、どんな聞き方が効果的なのでしょうか。以下のような質問を用意しておくと、自然にプロセスに光を当てることができます:
• そのとき、最初にどんな課題がありましたか?
• 解決のためにどんな工夫をしましたか?
• そのアイデアは、なぜ思いついたのですか?
• 結果に対して、自分ではどう評価していますか?
• 同じような場面が来たら、次はどう取り組みますか?
こうした質問を通じて、応募者が自ら考え、工夫し、実行した行動プロセスに迫ることができます。そしてそのプロセスが、自身の判断や工夫によるものであれば、別の場面でも応用できる=再現性があると考えられるのです。

5. 主観を排除した面接がなぜ有効なのか
面接をしていると、「この人、なんとなく良さそうだな」「うーん、ちょっと合わないかも…」といった直感が働くこと、ありませんか?もちろん、人間同士のコミュニケーションなので、ある程度の印象は避けられないもの。でも、その“印象”が評価の軸になってしまうと、せっかくの選考もブレやすくなってしまいます。ここでは、面接における“主観”との付き合い方と、その解決策について考えてみましょう。
5-1. 面接官の“好き嫌い”が選考に与える影響
面接官も人間ですから、どうしても「話しやすい」「自分と似ている」と感じる応募者にポジティブな印象を抱きやすいものです。逆に、緊張して言葉が詰まってしまう学生や、自分とはタイプが違うと感じる応募者に対しては、無意識のうちに評価が厳しくなることも。こうした“好き嫌い”が判断に入り込むと、本来の能力や適性ではなく、その場の印象で選考結果が左右されてしまいます。大切なのは、「人として好きかどうか」ではなく、「組織で成果を生み出せる可能性があるかどうか」を冷静に見極める視点です。
5-2. スキーマ(先入観)によるバイアスを減らすには
心理学では、「スキーマ」と呼ばれる“先入観”が、私たちの判断に大きく影響すると言われています。たとえば、「体育会系の学生はタフだ」「文学部の学生は論理的だ」など、無意識に抱いているイメージが、面接中の質問の仕方や、回答の受け取り方に影響してしまうことがあります。こうしたバイアスを完全に排除するのは難しいですが、「意識して向き合う」ことが第一歩です。コンピテンシー面接では、あくまで“行動事実”に基づいて評価することで、先入観に左右されない公平な判断がしやすくなります。
5-3. チームで共有できる評価軸が採用の質を上げる
「面接官ごとに判断がバラバラ」「最終面接で急に方向性が変わる」
こうした声を、社内で聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれません。
属人的な評価になりやすい面接では、どうしても判断基準が統一されず、最終的な意思決定も不透明になりがちです。そこで有効なのが、“共通の評価軸”をチームで持つこと。コンピテンシー面接では、「行動事実に基づいて、どの要素が、どのレベルで現れているか」を共有できるため、複数の面接官の間で納得感のあるすり合わせが可能になります。選考の透明性と一貫性が高まることで、候補者にもフェアなプロセスを提供でき、採用活動そのものの信頼性も向上していきます。

6. 採用の質を変える“行動ベース”の面接とは
「採用の質を上げたい」と感じたとき、何から見直すかは企業ごとに異なります。
ただ、どの企業にも共通する“第一歩”として、面接における“見方”を変えることは、とても有効な手段です。
6-1. 面接は「印象」より「行動事実」にフォーカスを
第一印象や話し方のスムーズさではなく、過去にどんな行動をとってきたかに注目してみる。
それだけでも、見えてくる資質や適性は大きく変わってきます。
たとえば「リーダーシップがある」と聞いても、どのように人を巻き込んだのか、どうやって物事を動かしたのかは人によってさまざま。抽象的な言葉の裏にある“具体的な行動”を掘り下げることで、その人ならではの強みやスタイルが見えてきます。こうした視点で対話を深めることで、表面的な“準備された答え”ではなく、本人の本質に近づくことができるのです。
6-2. 主観を排し、納得感のある選考を実現する
コンピテンシー面接は、面接官個人の感覚ではなく、共通の基準に基づいて評価することができる仕組みです。だからこそ、採用の透明性と納得感が高まり、チームでの意思決定もスムーズに進むようになります。選考に関わる複数の担当者が、それぞれの“感覚”ではなく、“行動事実に基づいた視点”で話し合えることは、ミスマッチを防ぐうえでも非常に重要です。「なぜこの人が採用に至ったのか」という説明がつけられるプロセスは、企業の採用ブランドや信頼性の向上にもつながっていくでしょう。
6-3. コンピテンシー面接が未来の成果を支える
「この人が入社したら、どんな活躍をしてくれるだろう?」
そうした未来への期待を、ただの“印象”ではなく、これまでの行動事実から丁寧にひもといていく。それが、コンピテンシー面接の大きな役割です。
面接で明らかになるエピソードの中には、思考のクセや動機、成果へのこだわりといった、その人ならではの“再現性のある力”が現れてきます。それは決して派手な実績ではなくても、組織のなかで確実に価値を生み出していく力の種かもしれません。だからこそ、過去の行動から未来の可能性を見極める――そんな視点を持つことが、変化の激しい時代において、強い組織をつくる第一歩になるのではないでしょうか。


サービスの
ご紹介
ヒューマネージの適性検査は、応募者の「行動事実」「性格特性」「ストレス耐性」を科学的に可視化し、再現性のある成果を生み出せる人材を見極めます。採用のブレを減らし、ミスマッチを防ぐために、ぜひご活用ください。

コンピテンシー適性検査 Another8

ベーシックパーソナリティ
適性検査 B5

© Humanage,Inc.

