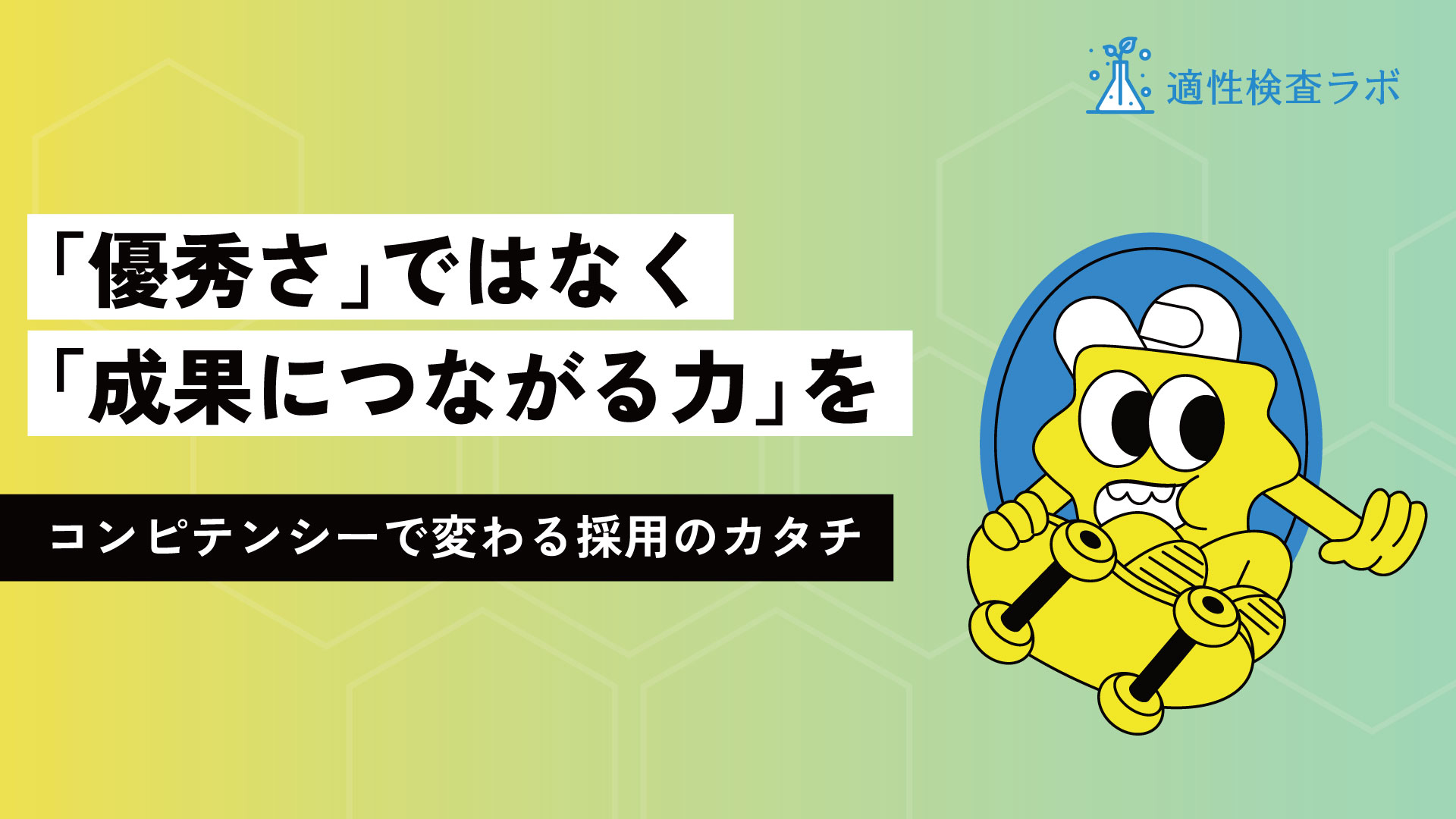
2025.05.02
「優秀さ」ではなく「成果につながる力」を──コンピテンシーで変わる採用のカタチ
新卒採用においては、限られた情報と短い接点の中で“将来の可能性”を見極める難しさがあります。特に、入社後すぐに結果を出す人には共通点があり、その差は何か、選考段階でどう見抜くかが大きな課題です。
現在、多くの企業が注目しているのが、「コンピテンシー(=成果につながる行動特性)」という視点です。これまでは“頭の良さ”や“地頭”に頼る部分がありましたが、再現性のある行動に焦点を当てることで、「優秀そう」ではなく「活躍できる」人材を見つけることができるのです。
本記事では、採用の現場でのミスマッチの原因から、コンピテンシーの基本、そして行動特性をどう可視化して評価に活かすかを解説します。
INDEX
1.はじめに:採用担当が直面する「見抜けない不安」
2.コンピテンシーとは何か?──能力を“行動”でとらえる考え方
3.行動を可視化する4つの要素とその関係
4.なぜ今、アジャイル型人材が求められるのか
5.ハイポテンシャル採用で“伸びしろ”を見極める
6.コンピテンシーと適性検査を組み合わせた採用戦略
7.まとめ:今、見極めるべきは「未来に成果を出せる人」
サービス紹介
1. はじめに:採用担当が直面する「見抜けない不安」
1-1. 採用の現場で起きている“感覚頼り”の限界
「面接では好印象だったのに、いざ配属してみると全然動けない」
「論理的でしっかり者に見えたけど、現場ではまったく応用が利かない」
そんな経験をお持ちの採用担当の方は少なくないのではないでしょうか。
特に新卒採用では、限られた情報のなかで“将来の可能性”を見極めるという難しさがあります。学生の話し方や態度、学歴やエントリーシートに書かれたエピソードをもとに、「この人は伸びそうだ」と期待をかけたものの、配属後に「思っていたのと違った」というギャップに悩むケースもよく耳にします。
これは採用担当者の見る目がない、という話ではありません。むしろ、“見極めるための材料”が不足していることが、ミスマッチの温床になっているのかもしれません。
1-2. 結果を出す人材の「共通点」は何か?
一方で、すぐに成果を出し、周囲からも信頼を集めている若手社員に共通する特徴とは何でしょうか。
「要領が良い」「地頭がいい」など、つい感覚的に説明しがちですが、実は多くの企業で共通して見られる“行動の傾向”があることが、近年の人材データの蓄積からわかってきています。
たとえば、「自ら学ぶ意欲がある」「先回りして動ける」「周囲の意見を柔軟に取り入れられる」など、結果を出している人は“特定の行動特性”を日常的に発揮していることが多いのです。
こうした行動の傾向は、「コンピテンシー(=成果に結びつく行動特性)」という概念で整理され、採用や育成の現場でも注目されるようになってきました。
1-3. 「コンピテンシー」という視点が、採用に新たな軸をもたらす
最近の採用トレンドでは、「優秀な人材を採る」から「自社で活躍できる人材を見極める」へと、採用の軸がシフトしています。特に新卒採用においては、学歴や表面的な印象だけでは測りきれない、“これからの成長可能性”をどう見極めるかがますます重要になっています。このときの新たなモノサシとして、コンピテンシーという考え方を取り入れる企業が増えています。
「面接でどんなエピソードを話してもらうか」
「どこに着目して評価をするのか」
「どんな特性を持った人が、自社で育ちやすいのか」
こうした問いに、感覚ではなく“根拠のある評価”で向き合うために、コンピテンシーをベースにした採用の仕組みを検討してみる価値があるのではないでしょうか。

2. コンピテンシーとは何か?──能力を“行動”でとらえる考え方
2-1. 「優秀そう」ではなく「成果を出せる」人を見極める
新卒採用の場では、「優秀そうな人」をどうしても選びたくなるものです。学歴や話し方、テストの点数、受け答えの印象──それらは確かに一つの判断材料になります。でも、いざ入社してみると「期待していたようには動いてくれない…」というケース、心当たりはないでしょうか?
このズレをなくすために必要なのが、「成果を出せるかどうか」という視点です。その人の“行動の特徴”を通して、「再現性のある成果」を生み出せる人かどうかを見極めていく──これが、コンピテンシーという考え方の出発点です。
2-2. なぜ“頭がいいだけの人”では成果に結びつかないのか
たとえば、社内で「頭の良い人」とされている人が、実際には企画を動かさない、他人のアイデアにケチをつけるばかり…という姿を見たことはないでしょうか?
知識や分析力はあっても、自分で動かない。提案しても実行に移さない。このような「評論家型」の人材は、結果として会社に貢献していないことも少なくありません。
一方で、「特別な学歴やスキルはないけれど、試行錯誤しながら行動して成果を出している」人もいます。こうした人こそ、実は組織にとって欠かせない存在です。つまり、真に成果につながるのは、“どれだけ考えたか”や“どれだけ知っているか”ではなく、どんな行動をとったかなのです。
2-3. 評価の軸を“主観”から“事実ベース”へ
面接や選考の場で、「なんとなく良さそう」「印象がいい」という直感で評価が決まってしまうケースもあります。けれど、その評価軸に一貫性がないと、採用後にミスマッチが起きてしまう可能性も。そこで注目したいのが、「実際にどう動いてきたか」という行動の事実です。たとえば、学生時代の経験についても、「何をしたか」ではなく「その中でどんな工夫や判断をしたか」を掘り下げることで、その人の行動特性(=コンピテンシー)を具体的に捉えることができます。
評価を“印象”や“感覚”ではなく、“行動に基づいた事実”で行うことができれば、選考の精度はぐっと高まります。

3. 行動を可視化する4つの要素とその関係
3-1. 成果を生む“行動”を中心に能力をとらえる
採用面接や選考の中で、「この人、頭は良さそうだけど、本当にうちの職場で活躍できるかな…?」そんなモヤモヤを感じたことはないでしょうか。人の能力やポテンシャルは見えにくく、だからこそ評価は難しい――。でも実際に現場で成果を出すのは、スキルや資格そのものではなく、「どう行動するか」だったりします。コンピテンシーの考え方では、この“行動”こそが最も注目すべきポイントです。持っている知識や能力をどう活かし、どう動いたか。それが、その人の再現性ある力として評価されます。たとえば、「どんな工夫をして、どんなアクションにつなげたか?」といった具体的な行動のエピソードは、履歴書だけでは見えてこない、貴重なヒントになり得ます。
3-2. 知識、動機、思考力、成果イメージ…その活かし方に注目
行動の背景には、いくつかの重要な“土台”があります。コンピテンシーの視点では、以下の4つの要素が、行動につながる源として捉えられています。
- 知識・経験:専門性や現場感覚
- 思考力:分析力や論理的な判断力
- 動機:内発的なやる気や価値観
- 成果イメージ:目的を明確に描けているか
これらのうち、どれか一つに秀でている人もいます。ただ、選考の場では「持っていること」以上に、「どう使っているか?」に目を向けると、その人の“行動パターン”が浮かび上がってきます。たとえば、成果イメージは明確でも、動機が弱いと行動が続かないことも。あるいは、知識はあるのに、それをうまく言語化・活用できていないケースもあるかもしれません。面接や適性検査の結果を通して、そうした要素の活かし方やバランスに気づくことができれば、「この人には、こういう場面で力を発揮してもらえそうだ」といった仮説が立てやすくなります。
3-3. バランスのとれた資質を引き出す評価視点とは?
一見すると、何か一つ飛び抜けた強みを持つ人が目立ちやすいものですが、実は長期的に活躍する人材には、バランスよく力を使えるタイプが多いように感じられます。もちろん、全ての要素を完璧に持ち合わせている必要はありません。大切なのは、その人なりの“動かし方”や“使い方”を見極めること。その視点を持つことで、候補者の魅力がぐっと立体的に見えてくることがあります。
たとえば、「知識は豊富だけど、自信が持てず行動が止まってしまっている」という方がいたとしたら、
「どうしたらその一歩が踏み出せるか?」という問いかけで、隠れていたポテンシャルを引き出せるかもしれません。採用は、「見抜く」だけでなく「見出す」ことでもあるはずです。候補者の一面だけで判断するのではなく、行動の背景にある“理由”に目を向けてみる。それが、より納得感ある採用につながっていくのではないでしょうか。

4. なぜ今、アジャイル型人材が求められるのか
4-1. 「指示待ち」から「自走」へ。時代が求める人材像の変化
「若手にはもっと主体的に動いてほしい」
「言われたことはできても、自ら提案する姿勢が見えにくい」
そんな声を、日々の採用や育成の現場で感じることはないでしょうか。
一方で、最近では「自分で考えて行動できる学生が増えている」と感じる場面もあるかもしれません。デジタルネイティブ世代の彼らは、情報を自ら取りに行き、柔軟に思考を切り替えながら行動する力を持っていることも多いのです。
では、これからの時代、私たちはどんな人材を採用すべきなのでしょうか。急速に変化する社会や市場環境のなかで、これまでのように「決まった仕事を、決まった手順でこなす」だけでは通用しないシーンが増えています。そんな状況だからこそ、“状況に応じて自分で考え、自ら動ける”人材の価値が高まっているのではないでしょうか。私たちは、こうした特性を持つ人材を「アジャイル型人材」と呼び、これからの組織に欠かせない存在として注目しています。
4-2. セルフマネジメント型人材がチームを強くする理由
では、アジャイル型人材とは、どんな力を備えた人なのでしょうか。私たちが特に注目しているのが、「セルフマネジメント力」です。
自分自身で目標を立て、進捗を確認し、必要に応じて修正していく。この一連のプロセスを自ら回せる人は、たとえ困難な環境でも、自分なりの突破口を見つけて行動を起こすことができます。
また、セルフマネジメント型人材は、周囲に与える影響も大きいです。チームの中で率先して動き、メンバーの背中を押す存在になることもあれば、誰かの課題に気づき、声をかけることで自然と支援の輪をつくることもあります。特別なリーダーシップがなくても、「動ける人」がいるだけで、チームの空気が変わる。そんな経験をしたことがある方も、きっといらっしゃるのではないでしょうか。
4-3. アジャイル型人材を見抜くために必要な観点
では、こうしたアジャイル型人材を、どのように採用の中で見極めていけばよいのでしょうか。「主体性があるか?」「自分で考えて動けるか?」という観点は、選考の中でもよく意識されているかもしれません。
ただ、それを「どう評価するか」が難しいところです。
たとえば、学生時代のエピソードで「リーダーを務めた」と話していても、その行動が“自ら考えたもの”だったのか、あるいは周囲に促されて動いたのかでは、評価の意味がまったく変わってきます。
ここで活用したいのが、「行動の背景を見る」という視点です。
- どういう目的をもって動いたのか?
- 何に悩み、どう工夫したのか?
- その経験から何を学び、次にどう活かしたか?
こうした問いかけを通じて、その人が“状況に応じて考え、動く”力を持っているかどうかが、少しずつ浮かび上がってきます。アジャイル型人材を見抜くには、答えの内容以上に、「どんな思考のプロセスをたどったのか?」を丁寧に捉えることがカギになるのです。

5. ハイポテンシャル採用で“伸びしろ”を見極める
5-1. 学生時代の実績より「再現性のある成果」に注目してみる
「学生時代に頑張ったことは何ですか?」
面接でよくあるこの問い。皆さんの中にも、これを通して学生の人物像や価値観を知ろうとしている方は多いのではないでしょうか。
たしかに、インパクトのある経験や大きな成果は目を引きます。しかしその一方で、「すごい経験だけど、本人の力だけで達成したのだろうか?」と迷ったこともあるのではないでしょうか。
たとえば、たまたま恵まれた環境やチームにいたことで達成できた成果もあるかもしれません。一方で、地道な努力や工夫を重ねて得た、目立たないけれど確かな成果もあるはずです。もしも私たちが注目すべきなのは、こうした「成果を生み出すまでのプロセス」だとしたら──。そこには、“どのように考え、行動し、工夫したか”という、その人の“伸びしろ”を感じさせるヒントが詰まっているかもしれません。
このような視点で人材を見ていこうという動きが、近年「ハイポテンシャル採用」として広がりつつあります。
5-2. 成果の“運”ではなく、“プロセス”を見るという視点
面接で目にする学生の「成果」。その背景には、実はさまざまな要素が絡んでいます。運よく結果が出たケースや、周囲の助けによって達成されたケースもあるかもしれません。
そこで、最近注目されているのが「どのように成果に至ったか」という“プロセス”を重視する考え方です。試行錯誤を重ねた工夫、目標達成のためにどんな行動をとったか、どんな判断をしたか。そうした行動の積み重ねにこそ、その人が今後も成果を生み出せる力、いわば“再現性”が表れるのではないでしょうか。
実績だけでは見えにくいポテンシャルも、このような視点から見れば、少しずつその輪郭が見えてくるはずです。
5-3. コンピテンシーでポテンシャルを可視化する方法
「この人は、入社後もきっと伸びてくれる」
そう感じる学生に出会うこと、ありますよね。でもその“伸びしろ”は、なかなか明確な評価基準を持ちづらいのも事実です。
そんなときに役立つのが、「コンピテンシー評価」の考え方です。成果につながる行動特性=コンピテンシーを軸に、過去の行動や思考の傾向をたどることで、その人が“今後も成果を再現できるかどうか”のヒントが得られます。
たとえば、
・どんな場面で主体的に動いたのか
・どんな課題にどう向き合ったのか
・周囲をどう巻き込みながら進めたのか
といったエピソードから、成果の再現性を探っていきます。
さらに、コンピテンシーの要素を測定できる適性検査を組み合わせれば、面接では捉えにくい資質や行動の傾向も“見える化”できます。学生の「今の実力」ではなく、「これからの成長可能性」を見極めたい。そんな採用担当者にとって、コンピテンシー評価は有力な味方になってくれるはずです。
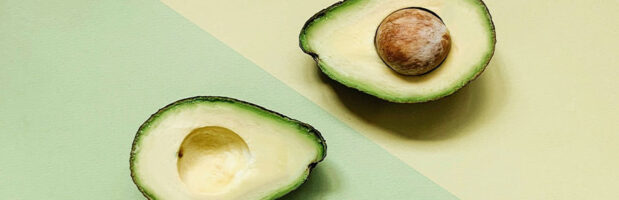
6. コンピテンシーと適性検査を組み合わせた採用戦略
6-1. 感覚に頼らない選考の仕組みづくりとは?
「面接の印象はよかったけれど、入社後にあまり活躍できていない…」
そんな経験をされた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
採用活動はどうしても、“人を見る”という不確実性を含んでいます。経験や直感に頼った選考も一定の価値はありますが、それだけでは属人的になりやすく、評価がブレやすくなるリスクも避けられません。
そこで今、注目されているのが「コンピテンシー評価 × 適性検査」による、感覚に依存しすぎない選考の仕組みづくりです。“成果につながる行動特性”を明らかにし、それを定量的なデータで補完することで、評価の一貫性と再現性を高めることができるのです。
感覚だけに頼らず、仕組みとして「見える選考」を整えることで、社内での納得感も高まり、振り返りや改善にもつなげやすくなります。
6-2. コンピテンシー評価と適性検査の組み合わせがもたらすもの
コンピテンシー評価と適性検査を併用することで、選考の精度が高まり、納得感ある採用が実現しやすくなります。主なメリットは以下の通りです。
- 見えにくい資質を“数値”で補える
「柔軟性」「変化への前向きさ」「主体性」など、面接では評価が難しい要素も可視化できるように。 - 選考情報を一元化しやすくなる
適性検査の結果を“共通言語”として使うことで、人事・現場・経営陣が足並みをそろえやすくなる。 - 選考に“根拠”を持たせられる
感覚的な印象に頼らず、データと行動の両面から候補者を捉えることで、属人的な判断を減らせる。
こうした仕組みづくりにより、判断の透明性が高まり、組織全体で納得できる採用がしやすくなります。
6-3. 採用から育成・評価へ。未来の人材マネジメントの基盤に
適性検査は「選考のためだけのツール」と思われがちですが、実は採用後の育成や配置、評価にも活用が広がってきています。
たとえば、入社時のコンピテンシー傾向を把握しておけば、
「どのような環境で力を発揮しやすいのか」
「どんな場面でつまずきやすいのか」
といった点を予測し、配属や育成プランの設計にも役立てることができます。
最近では、採用時のデータを起点に、その後のオンボーディングや1on1、キャリア支援まで一貫したマネジメントに活用する企業も増えています。“採用はゴールではなくスタート”という意識のもと、採用から育成・活躍までをつなげる仕組みづくりが、これからの人事のテーマになりつつあります。
7. まとめ:今、見極めるべきは「未来に成果を出せる人」
7-1. 採用を“未来への投資”ととらえる時代に
企業にとって、新卒採用は「今の人手を満たすための活動」ではなく、「これからの成長に向けた投資」である——。そのような考え方が、少しずつ浸透してきています。
変化のスピードが増す今、「今できる人材」だけでなく、「これから活躍できる可能性を持った人材」をいかに見極め、育てていくか。まさに、未来を見据えた視点が求められているのではないでしょうか。
7-2. 見えにくい“可能性”をコンピテンシーで捉える
未来に成果を出せるかどうかを測るのは簡単ではありません。ですが、再現性のある成果に着目し、行動の傾向から資質を捉える「コンピテンシー」の考え方を採用に取り入れることで、その見えにくい“伸びしろ”を可視化することができます。
さらに、適性検査と組み合わせることで、感覚だけでは見抜けないポテンシャルやリスクを補完しながら、より根拠のある選考が可能になります。
7-3. 変化に強い組織をつくる採用のあり方とは
柔軟に考え、主体的に動き、周囲と協働しながら成果を生み出していく「アジャイル型人材」。このような人材を見極め、迎え入れ、育てていくことこそ、これからの組織づくりに欠かせない鍵ではないでしょうか。
その第一歩が、採用です。
これからの変化に強く、持続的に成長できる組織を築くために。
採用活動を、単なる“選考”から“未来づくりの戦略”へと進化させていく。
その一助として、コンピテンシー評価や適性検査の活用を、ぜひご検討いただけたらと思います。


サービスの
ご紹介
面接だけでは見抜けない「成果につながる行動特性」や「職場で活躍する力」。そんな“未来の可能性”を科学的に見極めるには、適性検査の活用が効果的です。コンピテンシー、パーソナリティ、コーピング……目的に応じたツールを選ぶことで、採用の質は大きく変わります。未来につながる「人材の可能性」を、感覚ではなくデータで捉える。その一歩として、適性検査の活用を検討してみませんか?

コンピテンシー適性検査 Another8

ベーシックパーソナリティ
適性検査 B5

© Humanage,Inc.

