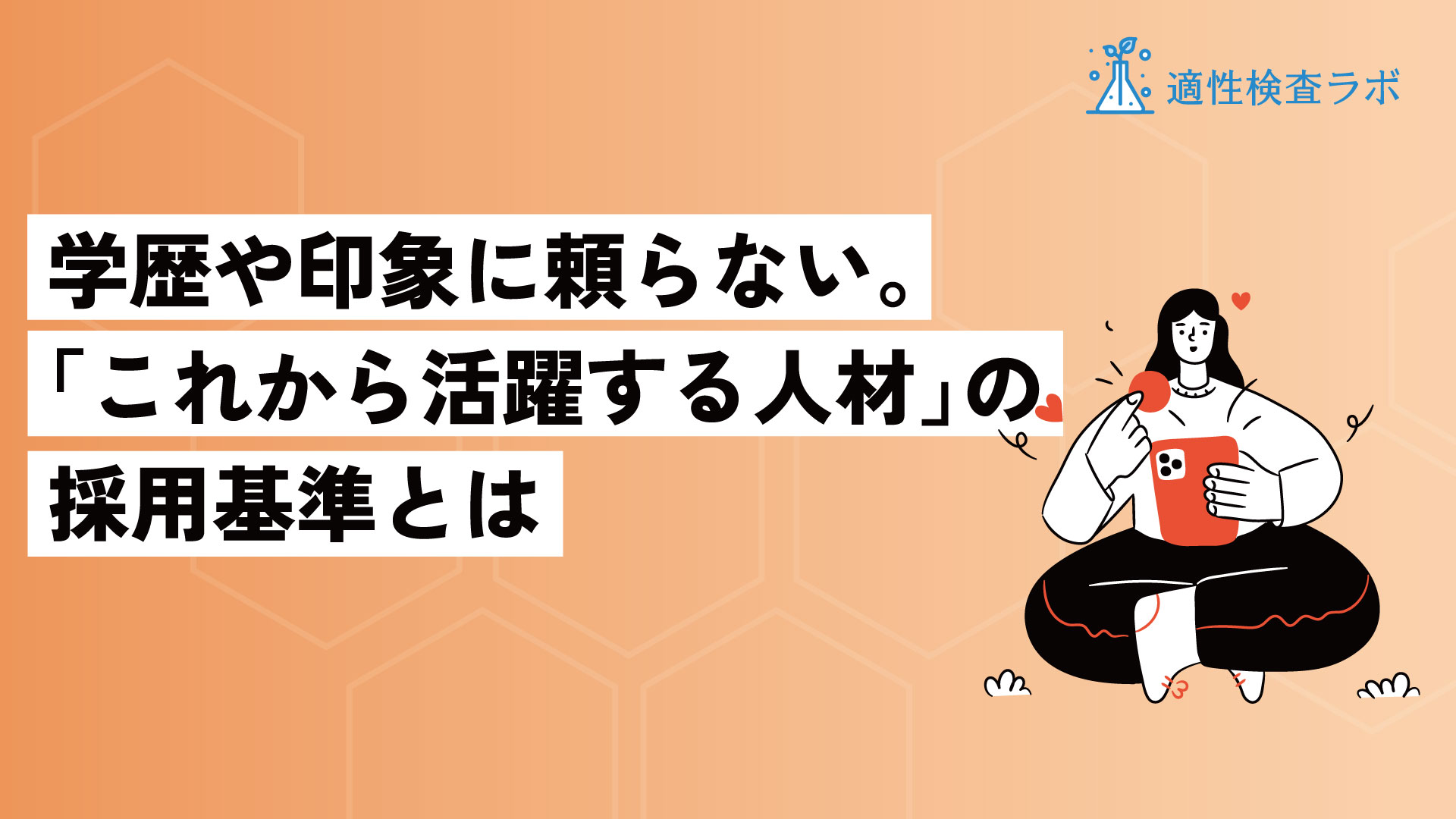
2025.04.25
学歴や印象に頼らない。「これから活躍する人材」の採用基準とは
学生の受け答えや学歴、第一印象をもとに「この人はできそうだ」と判断して採用を進める。
従来の新卒採用では、そうした見立てがスタート地点になっていることも少なくありません。
しかし、入社後に「思ったよりも早く辞めてしまった」「現場で思うように力を発揮できていない」といった声があがるケースも増えています。
こうしたミスマッチはなぜ起きてしまうのでしょうか。
社会が急速に変化し、仕事のあり方や職場の在り方も日々アップデートされるいま。
新卒採用においても、「すでにできる人」を選ぶのではなく、「変化に向き合いながら、これから成長していける人」を見極める視点が求められています。
どんな環境でも前向きに学び、自分の役割を見つけ、まわりと協働しながら力を発揮できる。そんな人材に出会うためには、何を手がかりに、どのように見極めていくべきなのでしょうか。
この記事では、これからの採用で大切にしたい視点や、見抜くための方法について考えていきます。
INDEX
1. はじめに
2. 従来型新卒採用の問題点
3. 採用選考が「雑談」になる理由
4. 情報化社会で広がる採用格差
5. 「学歴採用」の限界
6. 新卒採用の改革が必要な理由
7. 適性検査を活用した採用戦略の最適化
8. これからの新卒採用に必要な視点とは
サービス紹介
1. はじめに
1-1. 新卒採用に戦略が求められる背景
近年、「採用」というテーマは、企業にとってますます重要な戦略領域となっています。特に新卒採用においては、単なる人員補充という観点だけでなく、将来の組織を支える人材をどのように見つけるかが重要な課題です。
「毎年決まった人数を採る」「例年通りの選考フローを実施する」といった従来のアプローチに物足りなさを感じることもあるのではないでしょうか。人材の定着率、活躍のスピード、組織とのフィット感など、採用の先を見据えた戦略的なアプローチが求められています。
特に、変化の激しい時代においては、「今の課題に対応できる人材」だけでなく、「これからの組織に変化をもたらし、成長をけん引できる人材」を見つけることが重要となってきています。
1-2. 企業の未来を支える「アジャイル型」人材とは
これからの採用においては、変化に柔軟に対応し、自ら学び、動き、周囲と協力して成果を生み出せる人材が求められています。このような資質を持つ人材を、「アジャイル型人材」と呼んでいます。
たとえば、明確なルールや定型のプロセスがない中でも、状況を読み取り、自分なりに工夫して行動できる力。チームと協働しながら、目標達成に向けた対話を生み出せる力。こうした資質は、今の多くの現場でますます重視されるようになっています。
もちろん、すべての職種や業種において一律に「アジャイル型人材」が最適であるわけではありません。ただし、予測困難な時代において、こうした力を持つ人材がチームにいることは、組織の大きな強みになるはずです。そのため、新卒採用段階でこのような資質を重視することは、企業の未来を見据えた重要な選択となるでしょう。

2. 従来型新卒採用の問題点
2-1. 採用方針に「戦略」がない現実
「優秀な人材を採りたい」と考え、従来の新卒採用を続けてきた企業も多いのではないでしょうか。大きなトラブルがなければ、選考フローや基準を大きく変更する機会は少ないものです。しかし、最近では「採用した人材が育たない」「組織に馴染まずに早期離職してしまう」という声が増えています。これまでの方法が、現在の環境や組織に適しているかどうかを見直す時期が来ているかもしれません。
特に、企業がこれからどのような事業に注力し、どのような組織を目指すのか──その方向性と採用がしっかりと連携しているかどうかは非常に重要です。立ち止まって「どんな人を採るべきか?」を戦略的に考えることが、より有意義な採用活動を実現する手助けとなるでしょう。
2-2. 曖昧な「優秀さ」の基準
面接で「この学生は優秀だ」と感じることは多いと思います。しかし、その「優秀さ」がどの基準で判断されたのか、振り返ってみると少し曖昧に感じることはありませんか?
例えば、受け答えがしっかりしている、学歴が高い、話し方が洗練されている、などの理由で「できそうな人」と評価することがあるかもしれません。一方で、少し不器用に見えても、現場で着実に成果を上げるタイプの人材を見落としてしまう可能性もあります。
優秀さとは、単に「頭の回転が速い」といった一面的な評価ではなく、「その人が持つ力を、どのように行動や成果に繋げるか」という視点で捉えることが、より実践的な採用につながるのではないでしょうか。
2-3. 主観と学歴に頼った評価のリスク
面接の場ではどうしても、「なんとなく印象が良かった」「話が合いそう」といった主観が入りがちです。また、無意識のうちに学歴などに影響されて評価をしてしまうケースも多いかもしれません。
学歴や話し方が参考になる場面もありますが、それらに偏りすぎると、組織に適合する可能性がある人材を見落としてしまうリスクもあります。面接官自身が「なぜこの人が印象が良かったのか」「本当に必要な力を見抜けているか」を問い直し、評価基準を客観的に整えることが重要です。これにより、より納得感のある採用につながります。

3. 採用選考が「雑談」になる理由
3-1. 志望動機や学生時代の体験を尋ねるだけの面接
「志望動機は?」「学生時代に力を入れたことは?」といった質問をベースに面接を進めるのは一般的ですが、このような質問だけでは「実際にこの人が現場で活躍するか」はわかりにくい場合があります。
多くの学生が事前に用意した回答を準備しているため、面接官も「事前の準備を超えた情報」を引き出すのが難しくなることもあります。ここで大切なのは、「何を聞くか」だけでなく、「なぜその質問をするのか」「その答えから何を見たいのか」という目的を明確に持つことです。その目的を意識するだけで、同じ質問でも深掘りの角度が変わり、より実践的な情報を得ることができるでしょう。
3-2. 学生との「信頼関係の構築」
学生が本音を話さない、企業側が表面的な評価しかしていない──このような不信感が面接の場で生まれることもあります。現代の就職活動は高度化し、学生も「どう見られるか」を意識しすぎてしまうため、面接が形式的なやりとりになってしまうこともあります。
しかし、採用活動は企業と学生の「最初の出会いの場」であり、信頼を築くための重要な機会でもあります。面接を試す場と捉えず、お互いを理解し合うための対話として進めることで、より良い関係が築けるかもしれません。

4. 情報化社会で広がる採用格差
4-1. 採用活動が企業ブランドに直結する時代
現代では、採用活動の進行過程が企業ブランドに直結する時代になっています。学生が面接を受けた際の印象や経験が、SNSやクチコミサイトで広まり、企業のイメージに影響を与えることが少なくありません。企業側も、選考の質を意識して対応しなければ、企業ブランドに影響を与える可能性があることを認識する必要があります。
4-2. 高評価を得る企業と採用難に苦しむ企業の差
採用活動における透明性や誠実な対応が学生からの信頼を得る要因になり、その結果、応募数や質が向上する良い循環を生むことがわかっています。逆に、選考フローが不明確だったり、面接官が圧迫的だったりすると、候補者のエントリーは減少し、採用活動に苦戦する可能性が高まります。
5. 「学歴採用」の限界
5-1. 学歴フィルターの問題点
採用選考において、履歴書に記載された「出身大学」に目がいくことはよくあります。しかし、学歴だけでその人の能力や将来性を完全に判断するのは難しいことです。学歴フィルターをかけることで、実際には素晴らしいポテンシャルを持った人材を取り逃がす可能性もあります。
今の時代、「過去の学歴」だけでなく「これからどれだけ自分を成長させられるか」に目を向けることが、採用活動をより効果的にする一つの方法かもしれません。
5-2. 学歴と成果は必ずしも一致しない
「有名大学出身=優秀」といった印象が残っている一方で、実際には学歴と成果が必ずしも比例するわけではありません。高学歴でも、論理的な思考力や行動力に欠ける場合もあれば、学歴が目立たない人でも現場で結果を出し続ける人材もいます。
大切なのは、「どこで学んだか」ではなく、「どのように行動して成果を出す力を持っているか」に注目することです。
5-3. 学歴重視の採用方法に伴うリスク
学歴を重視した採用には、分かりやすく判断しやすいというメリットがある反面、いくつかのリスクも存在します。例えば、似た学歴の人が集まることで組織内の多様性が失われ、柔軟な発想が生まれにくくなることがあります。また、学歴を基準にすると、学歴が低い学生が応募しづらくなり、せっかくの優秀な人材を逃してしまう可能性もあります。
学歴に依存せず、どんな行動をして成果を出せるかを重視する方が、今後の採用活動にとっては有益かもしれません。

6. 新卒採用の改革が必要な理由
6-1. 人材採用の目的を明確化する
採用活動において、「なぜ新卒採用を行うのか」を考えたことはありますか? 最近では、「カルチャーフィット」や「ポテンシャル重視」といった視点が注目されています。学歴やスキルだけでなく、将来自社で活躍できる可能性を見極めることが大切だと感じる企業が増えています。
一方で、「毎年何となく採用している」「感覚的に選んでいる」という場合もあります。採用基準が曖昧なままだと、入社後にミスマッチが起こりやすくなるため、採用の目的を明確にし、チーム全体で共有することが重要です。
6-2. コンピテンシー採用がこれからを切り開く
「学生時代の経験を聞いても、将来の活躍が想像できない」と感じる採用担当者も少なくないのではないでしょうか。そんな中で注目されているのが「コンピテンシー採用」です。コンピテンシーとは、「成果を生み出す行動特性」のことです。例えば、学生が語るエピソードを深掘りして、「どんな考え方をし、どう行動したか」を確認することで、その人の行動パターンや思考の仕方を見抜くことができます。
このプロセスを通じて、「この人は自社でも同じように成果を上げられるかもしれない」という具体的なイメージが湧いてきます。
6-3. 新卒採用に「投資」の視点を持つ
新卒採用にかかるコストは、初任給や研修費だけでなく、面接や選考に関わる人件費、育成にかかるリソースなどを含めると、かなりの額になります。そのため、近年では「採用は投資である」という視点が注目されています。
採用における投資として、どれだけ効率よくかつ効果的にリソースを活用できるかを考え、どんな人材を採り、どのように育て、活かすのかを一貫して考えることが重要です。コンピテンシーや適性検査を活用することで、採用の精度を高め、投資のリターンを最大化できるでしょう。
7. 適性検査を活用した採用戦略の最適化
7-1. 採用基準を数値化して評価のブレを解消
面接で「この学生は良さそうだ」と思っても、採用基準があいまいだと、評価にブレが生じてしまうことがあります。感覚に頼るだけでは、「なぜこの人を採ったのか」「なぜあの人を落としたのか」が不明確になる可能性があります。
そのため、適性検査を導入することで、候補者の行動特性や思考の傾向を客観的に数値化することができます。これにより、面接官ごとの主観を減らし、より納得感のある採用ができるようになります。
7-2. 「アジャイル型」人材を見極める適性検査
今後の時代には、自分で課題を見つけ、主体的に行動し、周囲と協力しながら変化に適応していく人材が求められています。これを「アジャイル型人材」と呼びます。適性検査を使って、このような資質を持つ人材を見極めることができます。
たとえば、未経験の課題に前向きに挑戦できるか、自分で考えて動けるか、仲間と協力して成果を出せるかといった要素を数値化することで、表面的な印象にとらわれず、実際に活躍が期待できる人材を見つけやすくなります。
7-3. 採用活動をデータドリブンにシフトする
従来の採用活動は、直感や経験に頼ることが多かったかもしれませんが、最近ではデータを活用した採用活動が増えています。採用した人の定着率や、早期に活躍する人の共通点をデータで分析することで、次回の採用活動に生かすことができます。
例えば、活躍している人に共通する適性検査の結果を抽出すれば、次回の選考でその項目を重点的に見ていくことができます。逆に、退職が早かった人の特徴から、リスク要因を特定し、今後の選考で避けるべきポイントを見つけることも可能です。

8. これからの新卒採用に必要な視点とは
8-1. 新卒採用は企業の未来を左右する経営戦略
採用は「人事の仕事」として捉えられることが多いですが、実際には企業の成長に直結する重要な経営判断です。特に新卒採用は、ポテンシャルのある人材を確保し、企業文化や価値観を共有しながら育成できる貴重なチャンスです。
短期的な成果だけでなく、「この人が数年後にチームを支え、事業を牽引するかもしれない」という視点で採用に臨むことが、企業の競争力を大きく向上させるでしょう。
8-2. 適性検査でこれからの企業を支える人材を見極める
新卒採用で重視されるのは、将来性を見抜く力です。面接だけでは見えてこない部分、学歴や資格では測れない部分が、企業にとって非常に重要なポイントとなっています。
適性検査を導入することで、より正確に求める資質を持った人材を見極めることができます。特に、今後求められるのは「自分で考え、動き、変化に対応できる人材」です。適性検査は、そのような人材を見つけるための重要な手段となるでしょう。
8-3. 採用活動にコンピテンシー採用を導入するべき理由
従来の学歴や印象を重視した採用方法から、「行動に結びつく力」や「成果の再現性」を重視するコンピテンシー採用へのシフトが進んでいます。いきなりすべてを変える必要はありませんが、少しずつ採用プロセスに適性検査を取り入れてみると、採用の精度が向上し、企業に合った人材を見つけやすくなります。


サービスの
ご紹介
未来の組織を担う人材を見極めるには、行動の再現性や内面の特性を科学的に把握する視点が不可欠です。ヒューマネージの『TG-WEB』は、「成果につながる力」「ストレス対処力」「チームでの協働力」など、現代のビジネスに必要な力を多面的に可視化します。下記の検査から、貴社の採用課題に合ったツールをぜひご活用ください。

コンピテンシー適性検査 Another8

ベーシックパーソナリティ
適性検査 B5

コーピング適性検査 G9

チーム・コミュニケーション適性検査 W8

© Humanage,Inc.

