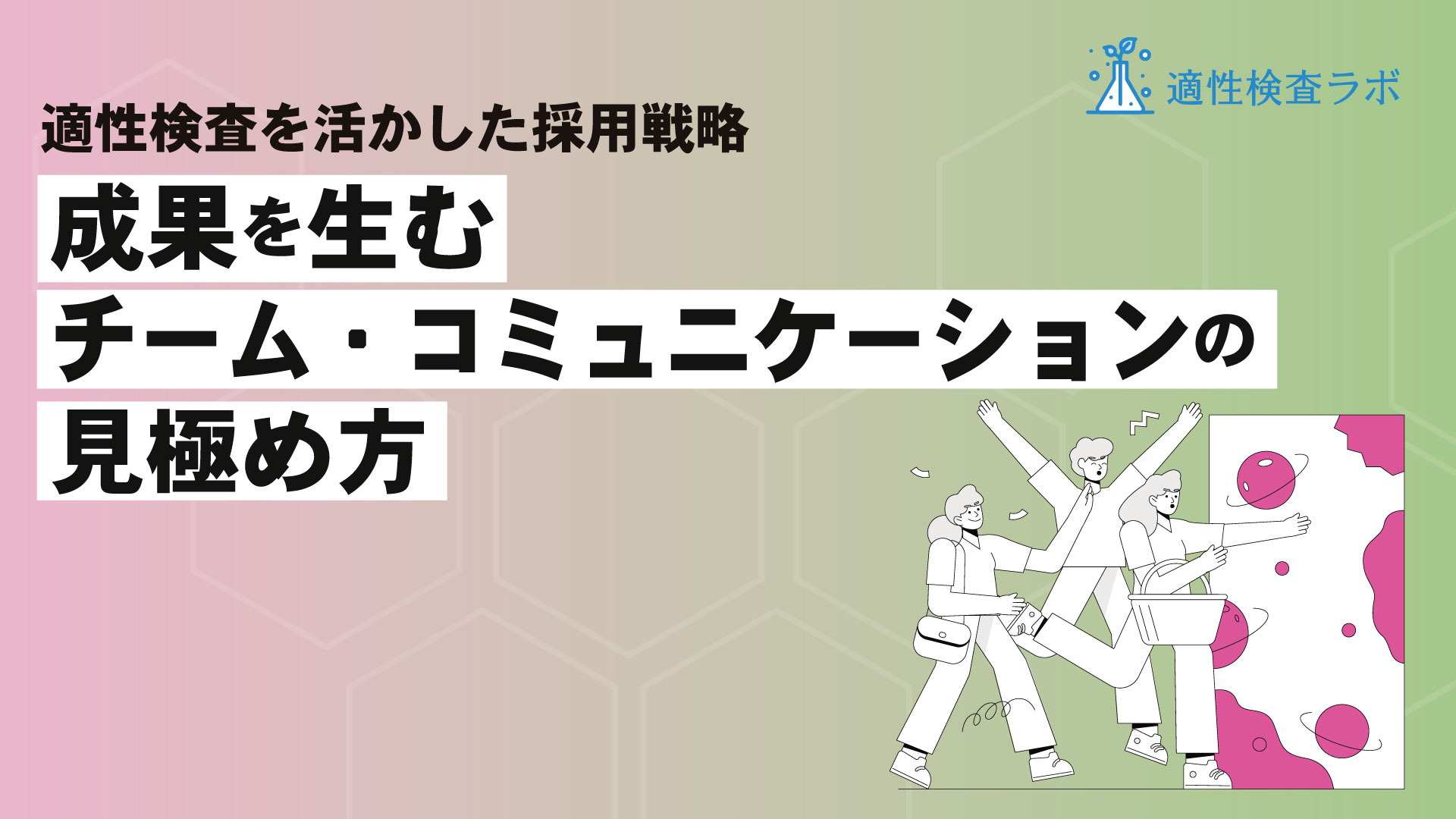
2025.03.21
適性検査を活かした採用戦略:成果を生むチーム・コミュニケーションの見極め方
働き方の多様化、世代間の価値観の違い、そしてグローバル化による異文化との協働。こうした変化が加速する現代において、「コミュニケーション能力」はこれまで以上に重要な能力として注目されています。
特に、単なる「協調性」ではなく、「チームで成果を生み出すためのコミュニケーション能力」、すなわちチーム・コミュニケーション力が、個人と組織のパフォーマンスに直結する力として注目されつつあります。
本記事では、適性検査を活用してこの「チーム・コミュニケーション力」をどのように見極め、採用や人材育成に結びつけていくかを解説します。
INDEX
1.コミュニケーション能力の変遷と現代的要請
2.チーム・コミュニケーションとは何か
3.適性検査で見極めるチーム・コミュニケーション力
4.行動事実を引き出すための面接と検査の併用
5.注意すべき“似て非なる行動特性”
6.採用から定着・活躍へ:チーム・コミュニケーションの戦略的活用
サービス紹介
1. コミュニケーション能力の変遷と現代の要請
1-1. 従来の「協調性」から「シナジー創出力」へ
採用における最重視項目として、長年にわたり上位に位置づけられてきた「コミュニケーション能力」。しかし、その定義は時代とともに変容しています。
かつての「コミュニケーション能力」は、「空気を読む」「和を乱さない」「同調する」能力、つまり協調性の高さを意味するものでした。これは、同質性の高い組織や国内市場が中心だった時代においては、業務の円滑な遂行を促す有効な特性でした。
1-2. チームで成果を出す時代背景と現代の職場の特徴
現代の職場では、業務の複雑化と並行して、多様なバックグラウンドをもつ人々がチームを組みます。異なる専門性、文化、価値観を持つメンバーが同じゴールに向かう中で求められるのは、単なる「合わせる力」ではなく、異質性を活かし、シナジーを生む力です。
このような背景から、「チーム・コミュニケーション力」は、未来志向の能力として再定義されつつあるのです。

2. チーム・コミュニケーションとは何か
2-1. 「I’m OK」「You’re OK」の考え方と心理的背景
心理学に基づいた研究から、「チーム・コミュニケーションが高い人材」は、自己肯定感(=自尊)と他者肯定感(=他尊)の両方が高いことが分かっています。
• 自尊(I’m OK):自分の価値を認め、「自分にはできる」という信念を持って行動する傾向
• 他尊(You’re OK):他者の価値や強みを認め、貢献しようとする姿勢
この両輪がバランス良く機能することで、チーム内にポジティブな連携と信頼関係が生まれます。
2-2. 自尊・他尊のバランスが生む“真の協働力”
チーム・コミュニケーションは、「自尊」と「他尊」のバランスが取れていることが大切です。この2つのバランスが取れていない場合、チームでシナジーを生む阻害要因となる恐れもあります。
| I‘m OK. You‘re not OK. 信念はあるが、 《高攻撃性》 |
I‘m OK. You‘re OK. 信念があり、 《チーム・コミュニケーションが高い》 |
| I‘m not OK. You‘re not OK. 信念はなく、 《高孤立性》 |
I‘m not OK. You‘re OK. 信念はないが、 《高服従性》 |
3. 適性検査で見極めるチーム・コミュニケーション力
3-1. 発揮される能力を可視化する
チーム・コミュニケーション力は、履歴書や学歴、自己PRだけでは正確に把握することが難しい能力です。そのため、行動の傾向や思考の特性を定量的に把握する適性検査の活用が有効です。
特に、普段どのような場面でどんな行動をとってきたかといった「行動特性」を測定できる検査では、成果につながる行動の再現性を確認することが可能です。これは、「知っている」「考えられる」といった能力ではなく、「実際にやっている(やってきた)」かを評価できるという意味で、採用において非常に重要な視点です。
3-2. 性格や価値観との相互補完
また、行動だけでなく、その背景にある性格特性や価値観の傾向を測る検査を組み合わせることで、より立体的に人物像を把握することができます。
たとえば、「他者を尊重する姿勢」が高いとされる人が、実際の行動では他者を遮ったりする傾向が強ければ、性格と行動の不一致があるということになります。こうしたギャップを面接や育成に活かすことも、適性検査の大きな役割です。

4. 行動事実を引き出すための面接と検査の併用
4-1. 記憶に基づいたエピソードを問う
適性検査の結果はあくまで“傾向”を示すものであり、その裏付けとして過去の行動事実を面接で確認するプロセスが非常に重要です。
このとき有効なのが、「どんな状況で・どのような行動をとり・どんな結果が得られたか」といった具体的なエピソードを本人の記憶から引き出す質問です。これは、評価のブレをなくし、表面的な印象に左右されない採用判断を可能にします。
4-2. 多面的な情報を統合して判断する
適性検査の結果と面接で得られたエピソードや態度を突き合わせることで、より信頼性の高い人物評価が可能になります。
- 検査:定量的な傾向を把握
- 面接:定性的な事実を確認
- 統合評価:再現性や成長可能性を総合的に判断
このプロセスによって、「チームで成果を出せる人材」を見逃すことなく採用することができます。

5. 注意すべき“似て非なる行動特性”
5-1. 「自尊」と「傲慢」の違いをどう見抜くか
「自尊心が高い」と聞くと一見ポジティブな印象を受けますが、そこには注意が必要です。本当の自尊心とは、他者を貶めることなく、自分を信じられる安定感のことを指します。
一方で、「傲慢さ」は、他者との比較に基づく優越感であり、チーム内では摩擦を生みやすい要因となります。この違いを見抜くには、本人が他者の成功にどう反応するか、どのような場面で謙虚さを保てるか、といった視点が重要になります。
5-2. 「他尊」と「取り入り」の違いとリスク判断
他者の良さを認め、協力する姿勢は組織にとって不可欠な資質ですが、それが「取り入り(ご機嫌取り)」である場合、持続性や信頼性に欠ける行動となる可能性があります。
適性検査や面接では、その行動が自己利益のためか、他者への純粋な貢献の意識かを見極めることが求められます。
6. 採用から定着・活躍へ:チーム・コミュニケーションの戦略的活用
6-1. 採用後の配置や育成にも活かす
適性検査を採用の場面だけで終わらせてしまうのは非常にもったいないことです。検査によって得られた「強み」や「課題」は、配属や育成、オンボーディングの設計にも役立てることができます。
たとえば、自尊が高く他尊が低めな人材には、最初からリーダー的役割を与えるのではなく、他者と共同で成果を出すプロジェクトを通じて「他尊」の感覚を育むような経験を意図的に設計するなど、戦略的な育成が可能になります。
6-2. 組織を強くする“科学的アプローチ”
従来のように、「面接官の経験と勘」に頼った採用・配置では、組織の成長に限界が生じる場面もあります。今後の人材マネジメントでは、可視化されたデータに基づく意思決定=科学的人事が重要な視点となります。
適性検査の活用は、その出発点として最適です。特にチーム単位で成果を出す現代の組織では、「協調性の高い人材」ではなく、「シナジーを生み出せる人材」をいかに見つけ、育て、活かしていくかが勝負の分かれ目となるのです。


サービスの
ご紹介
これまで見てきたように、これからの組織では「協調性」だけではなく、チームでシナジーを生み出せる人材を見極めることが不可欠です。しかし、この「チーム・コミュニケーション力」は、従来の面接や履歴書だけでは適切に評価することが難しいのが現実です。
そこで、「W8」適性検査を活用することで、候補者や社員の「I’m OK.(自尊)」と「You’re OK.(他尊)」のバランスを数値化し、成果を生むチーム・コミュニケーション力を可視化することが可能になります。

チーム・コミュニケーション適性検査 W8

© Humanage,Inc.

