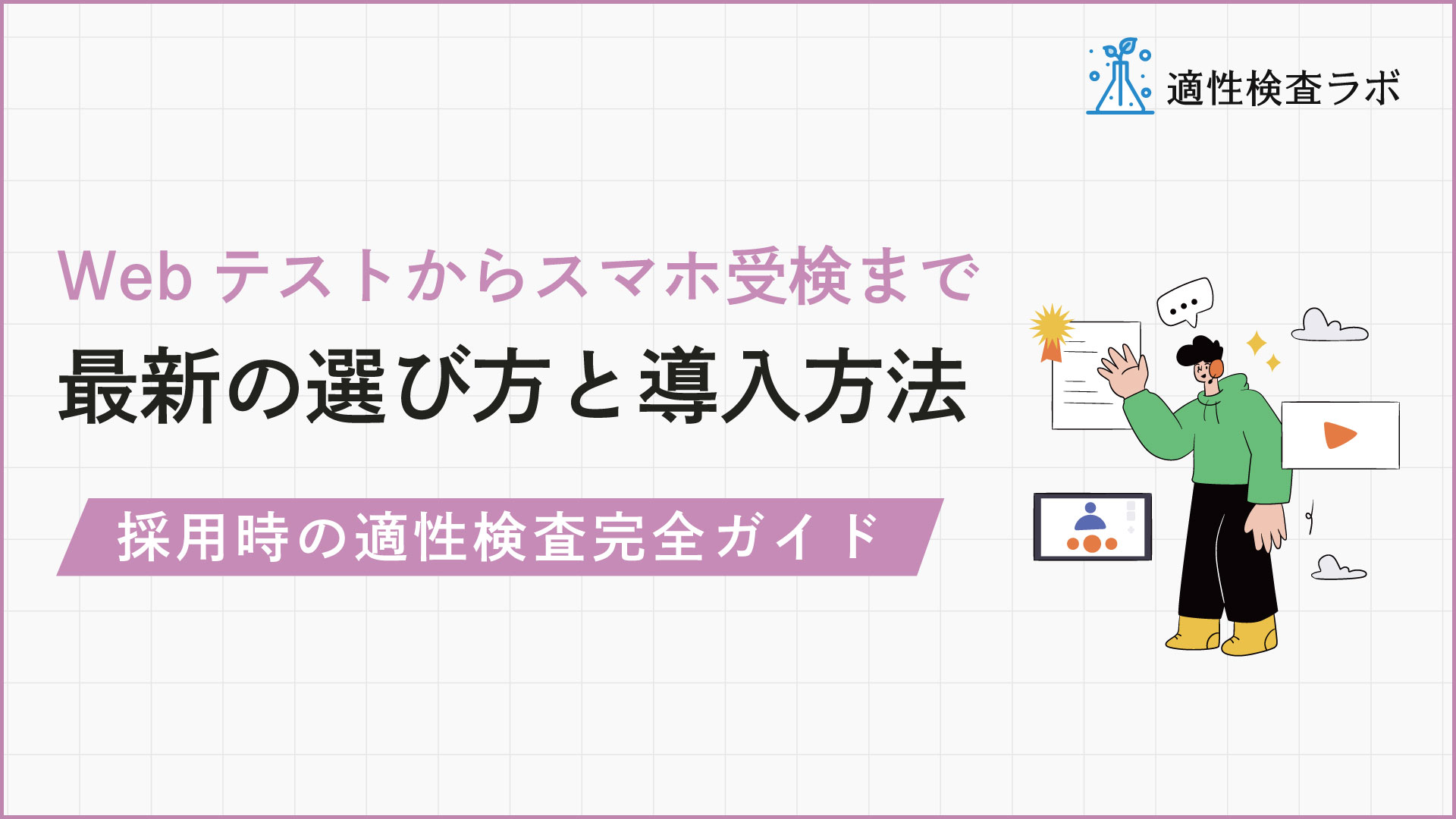
2024.02.05
採用時の適性検査完全ガイド:Webテストからスマホ受検まで最新の選び方と導入方法
スマートフォンが生活の中心となっている現在、多くの新卒就活生はエントリーや企業研究、面接の予約まで、すべてスマホで完結させるのが当たり前になっています。しかし、適性検査の能力検査はいまだにPC受検が主流です。「どうしてスマホでは受検できないのか?」「適性検査の受検方式にはどんな違いがあるのか?」本記事では、適性検査の歴史やWebテストの普及、そしてスマホ受検が進まない理由を紐解きながら、実際にスマホで受検できる適性検査の種類や特徴を紹介します。
INDEX
1. 適性検査とは? その役割と進化
2. なぜWebテストが主流になったのか?
3. 適性検査の受検方式とその違い
4.スマホ受検が進まない理由とは?
5. スマホ受検が可能な適性検査とは?
6. 企業が適性検査を選ぶ際のポイント
サービスのご紹介
1. 適性検査とは? その役割と進化
1-1. 採用における適性検査の目的と重要性
企業が採用時に実施する適性検査は、応募者の能力や性格、行動特性を評価し、業務適性や組織適合性を判断する重要なプロセスです。適性検査は主に「能力検査」と「適性検査(性格・行動特性含む)」に分かれます。能力検査は論理的思考力や数的処理能力を評価し、適性検査は価値観や行動特性を評価します。これにより、企業は求める人材像に合致した応募者を選別することが可能となります。
1-2. 適性検査の変遷:紙からWebへ
適性検査は、かつては紙と鉛筆を使った筆記試験形式が一般的でした。しかし、インターネットの普及に伴い、現在ではWebテストが主流となっています。企業はコスト削減や効率化を目的に、オンライン上での適性検査を導入し、受検者も好きな場所・時間でテストを受けることが可能になりました。これにより、試験会場の手配や試験用紙の印刷・採点といった手間が大幅に削減されました。採用市場の変化とも関連し、Webテストの導入が加速しました。 もともとペーパー方式だった適性検査ですが、時代の流れとともにパソコンを活用する形式が主流になりました。検査項目も、これまで一般的だった総合的な人格特性を測定するものから、ストレス耐性に特化したものや将来の活躍予測を重視したものまで、さまざまな特徴を持つ検査が生み出されるようになりました。 適性検査そのものも、単に問題を文字で説明し、回答してもらうだけのものから、音声・動画形式の問題や他者評価の導入、AIの活用といった最新のテクノロジーを駆使したものが現れ始めています。ここ数年は、他者比較やコンピテンシーの抽出などがより簡単に実施できるクラウド型の適性検査も増加しています。

2. なぜWebテストが主流になったのか?
2-1. Webテストの普及とその理由
Webテストが普及した背景には、受検者にとっての利便性の向上、企業側のコスト削減、そして迅速な結果確認の実現といった要因があります。受検者は自宅やカフェなど好きな場所で都合の良い時間に受検できるようになり、企業側も試験会場の手配や試験用紙の印刷・採点などの手間を削減できるようになりました。また、Webテストの導入により、採用プロセス全体のスピードアップが図られました。
2-2. Webテストがもたらしたメリットと課題
Webテストは多くのメリットをもたらしましたが、一方で課題も浮上しています。不正受検のリスクが増加し、本人確認の厳格化が求められるようになりました。また、通信環境が不安定な場合、受検がスムーズに進まないこともあります。
そのため、公平性と公正性を確保するために、受検者が統一された環境で試験を受けられるテストセンターが設けられました。しかし、密閉空間での受検は新型コロナウイルスの感染リスクの観点から安全面で問題視され、従来のテストセンターでの受検が推奨されなくなる状況も生じています。
このような背景から、オンライン受験の需要が急増し、企業の適性検査も急速にWeb化が進みました。これに対応するため、「AI監視型Webテスト」も登場し、受検者の不正行為を検知できる仕組みが導入されています。これにより、替え玉受検やカンニングを防ぐ仕組みが強化されています。
3. 適性検査の受検方式とその違い
適性検査にはさまざまな受検方式が存在し、それぞれに特徴やメリット・デメリットがあります。以下では、主要な受検方式について詳細に説明します。
マークシート方式
マークシート方式は、紙と鉛筆を使用して受検する従来の方式です。
- 費用: 〇
印刷費や採点処理対応分の費用が必要です。 - 抑止(監視精度): ◎
来社時の受検のため不正が抑止されます。 - 採用担当者の負担: ×
試験官の対応が必要であり、負担が大きいです。 - 実施上限人数: ×
受検可能上限人数があり、会場のキャパシティに依存します。 - 受検(予約)可能時間: ×
来社時のみ受検が可能で、柔軟な時間設定が難しいです。 - その他の受検者負担(実費負担/受検時の負担等): ×
会場までの交通費の負担が必要です。
Web方式
Web方式は、インターネットを通じてオンラインで受検する方法です。
- 費用: ◎
資材・会場を必要としないことから、大量実施時に割引されることが多く、コスト効率が良いです。 - 抑止(監視精度): ×
不正受検のリスクがあります。。 - 採用担当者の負担: ◎
受検案内(メール)のみで済み、問い合わせ対応もテスト運営会社が実施することが多いため負担が少ないです。 - 実施上限人数: ◎
上限がなく、多数の受検者に対応可能です。 - 受検(予約)可能時間: ◎
事前予約なく、24時間365日受検が可能です。 - その他の受検者負担(実費負担/受検時の負担等): ◎
PCがあれば受検可能で、交通費の負担が不要です。
AI監視型Web方式
AI監視型Web方式は、人工知能を活用して受検者の行動を監視し、不正を検出するWebテストの一種です。
- 費用: 〇
Webテストと比較して若干の追加費用がかかります。 - 抑止(監視精度): ○
AIによる不正検知があり、抑止効果があります。 - 採用担当者の負担: ◎
受検案内(メール)のみで、問い合わせ対応もテスト運営会社が実施することが多いです。 - 実施上限人数: ◎
上限がなく、多数の受検者に対応可能です。 - 受検(予約)可能時間: ◎
事前予約なく、24時間365日受検が可能です。 - その他の受検者負担(実費負担/受検時の負担等): ◎
カメラ付きPCのみで受検可能で、ネットワークの負荷も少ないです。
テストセンター方式
テストセンター方式は、指定のテストセンターで受検する方法です。
- 費用: ×
会場費や試験官費用が発生するため、WEB方式と比較し、費用が高額になります。 - 抑止(監視精度): ◎
本人確認と会場への持ち込み制限があり、不正行為を防止します。 - 採用担当者の負担: △
大量実施の場合、会場調整や欠席者対応などが別途必要です。 - 実施上限人数: ×
会場のキャパシティに依存し、受検機会の損失につながる可能性があります。 - 受検(予約)可能時間: ×
事前予約が必要で、会場の営業時間(9~20時の間)に限定されます。 - その他の受検者負担(実費負担/受検時の負担等): ×
会場までの交通費の負担が必要です。
有人監視型Web会場方式(外部委託)
有人監視型Web会場方式(外部委託)は、外部の監視会社を利用してWeb会場で受検を行う方法です。
- 費用: ×
会場費や試験官費用が発生するため、WEB方式と比較し、費用が高額になります。 - 抑止(監視精度): ◎
本人確認と会場での監視があり、不正行為を防止します。 - 採用担当者の負担: △
大量実施の場合、試験官の調整や欠席者対応などが必要です。 - 実施上限人数: ×
会場のキャパシティに依存し、受検機会の損失につながる可能性があります。 - 受検(予約)可能時間: ×
事前予約が必要で、試験官や他受検者と同時に受検開始が必要となります。 - その他の受検者負担(実費負担/受検時の負担等): ×
会場までの交通費の負担が必要です。
有人監視型Web方式(自社対応)
有人監視型Web方式(自社対応)は、自社で監視体制を整えてWeb受検を行う方法です。
- 費用: ◎
自社設備のみで対応可能で、コスト効率が良いです。 - 抑止(監視精度): ◎
本人確認と受検途中の監視があり、撮影範囲のみを対象にして不正行為を防ぎます。 - 採用担当者の負担: ×
予約から試験官対応まで全て自社で対応する必要があり、負担が大きいです。 - 実施上限人数: ×
試験官一人あたりの監視上限があり、予約可能上限人数にも制限があります。 - 受検(予約)可能時間: ×
事前予約が必要で、勤務時間内のみ受検が可能です。 - その他の受検者負担(実費負担/受検時の負担等): ◎
カメラ付きPCがあれば受検可能で、交通費の負担が不要です。

4. スマホ受検が進まない理由とは?
4-1. 画面サイズ・操作性の課題
冒頭お話しましたが、現在、日本のほとんどの方がスマートフォンを持っています。しかし、WEB適性検査でスマホ受検できないことも目にされます。その理由を説明します。
まず、スマホはPCに比べて画面が小さいため、適性検査のような長文読解や、図形解読、数的処理を必要とする問題では、視認性や操作性が大きな課題となります。もともと、試験という位置づけの能力検査では、特定の受検環境が必要であり、スマホやタブレット端末での受検は想定しておらず、PCでのWeb方式受検を想定した問題作成となっているため、図形問題や文章の並び替え問題など、スマホの画面上での文字認識や回答操作が困難です。これにより、問題文の量に起因するスクロール等の操作が必要となり、スマホ受検は向いていません。 小さな画面では問題文が見づらく、解答に時間がかかることが考えられます。また、スマホではスクロールやタップ操作が必要となるため、PCでの受検に比べて操作が煩雑になる場合があります。 これらの理由から、能力検査はPCでの受検が推奨されており、スマホ受検には制限があるのが現状です。
4-2. 検査の公平性・不正対策の問題
スマホでの受検では、スクリーンショットや外部アプリを活用した不正が容易になる可能性があります。また、通信環境が不安定な場合、途中で受検が中断されるリスクも高まります。これらの課題を解決しない限り、スマホ受検の本格的な普及は難しいでしょう。
4-3. 通知やアプリの干渉による集中力の低下
スマホでの受検中に電話やメッセージアプリからの通知が入ると、受検者の集中力が途切れ、受検の質に影響を与える可能性があります。PC受検では受検中に他のアプリケーションが動作しにくく、集中しやすい環境が整っていますが、スマホではこれが難しいため、公平な受検環境を維持することが困難です。

5. スマホ受検が可能な適性検査とは?
5-1. スマホ対応の適性検査の種類と特徴
知的能力検査と適性検査では、スマホ対応に関して対応が分かれているケースが多いです。特に、知的能力検査は前述の通り、図形問題や文章の並び替え問題など、スマホの画面サイズや操作性の制約から難しいため、スマホ受検が難しい傾向にあります。 一方で、性格診断や価値観に基づく検査などはスマホでの受検が可能なケースが多く、今後の普及が期待されています。
5-2. スマホ受検が向いているケースと注意点
スマホ受検が適しているのは、比較的短時間で完了するシンプルな検査や、操作が容易な性格診断などです。しかし、知的能力検査のように複雑な問題や長文読解を必要とする検査には向いていません。また、スマホ受検を導入する際には、受検者の通信環境や使用するデバイスの性能を考慮し、安定した受検環境を提供する必要があります。
6. 企業が適性検査を選ぶ際のポイント
6-1. 企業の採用方針に合った適性検査の選び方
適性検査を選定する際には、自社の採用目的に合った検査形式を選ぶことが重要です。求める人材像に合わせて、能力検査と適性検査(性格・行動特性含む)のバランスを考慮し、採用プロセス全体でどのように活用するかを計画する必要があります。
6-2. 受験方式の選択方法
適性検査の受検方式を選択する際には、以下のポイントを考慮することが重要です。
採用目的と人材像の明確化
企業が求める人材のスキルや特性に基づいて、必要な検査項目を決定します。能力検査が重視される場合は、論理的思考力や数的処理能力を評価できる方式を選びます。適性検査が重要な場合は、性格や行動特性を詳細に評価できる方式が適しています。
コストと効率性のバランス
予算に応じて、費用対効果の高い受検方式を選びます。大量実施時の割引が適用されるWeb方式やAI監視型Web方式は、コスト効率が良い場合があります。一方、テストセンター方式は費用が高額になるため、予算に余裕がある場合に適しています。
不正対策の重要性
公平性を重視する企業は、不正対策が強固な受検方式を選ぶ必要があります。AI監視型Web方式やテストセンター方式は、高い抑止効果を持つため、不正を防ぎたい場合に適しています。
受検者の利便性と負担
受検者の利便性を考慮し、オンラインで24時間受検可能なWeb方式やスマホ受検を選ぶことで、受検者の負担を軽減できます。ただし、操作性や画面サイズの課題があるため、受検方式の選択には慎重さが求められます。
受検環境の安定性
PC受検やテストセンター方式は、安定した通信環境や監視体制を確保できるため、受検環境の安定性が求められる場合に適しています。
これらのポイントを総合的に評価し、企業の採用方針や目的に最も適した受検方式を選択することが重要です。

7. まとめ
適性検査の導入を検討する際には、企業の採用方針や受検者の環境を考慮し、適切な受検方式を選択することが求められます。採用活動の効率化と公平性の確保を両立させるために、適性検査の活用方法を慎重に検討する必要があります。

サービスの
ご紹介
理系採用の課題を解決し、採用後のパフォーマンスを向上させるには、適性検査の活用が不可欠です。以下の適性検査は、候補者の特性を客観的に評価し、採用ミスマッチの防止や採用プロセスの効率化に役立ちます。

判断推理力検査 i9

ベーシックパーソナリティ
適性検査 B5

オンラインAI監視型Webテスト

© Humanage,Inc.

