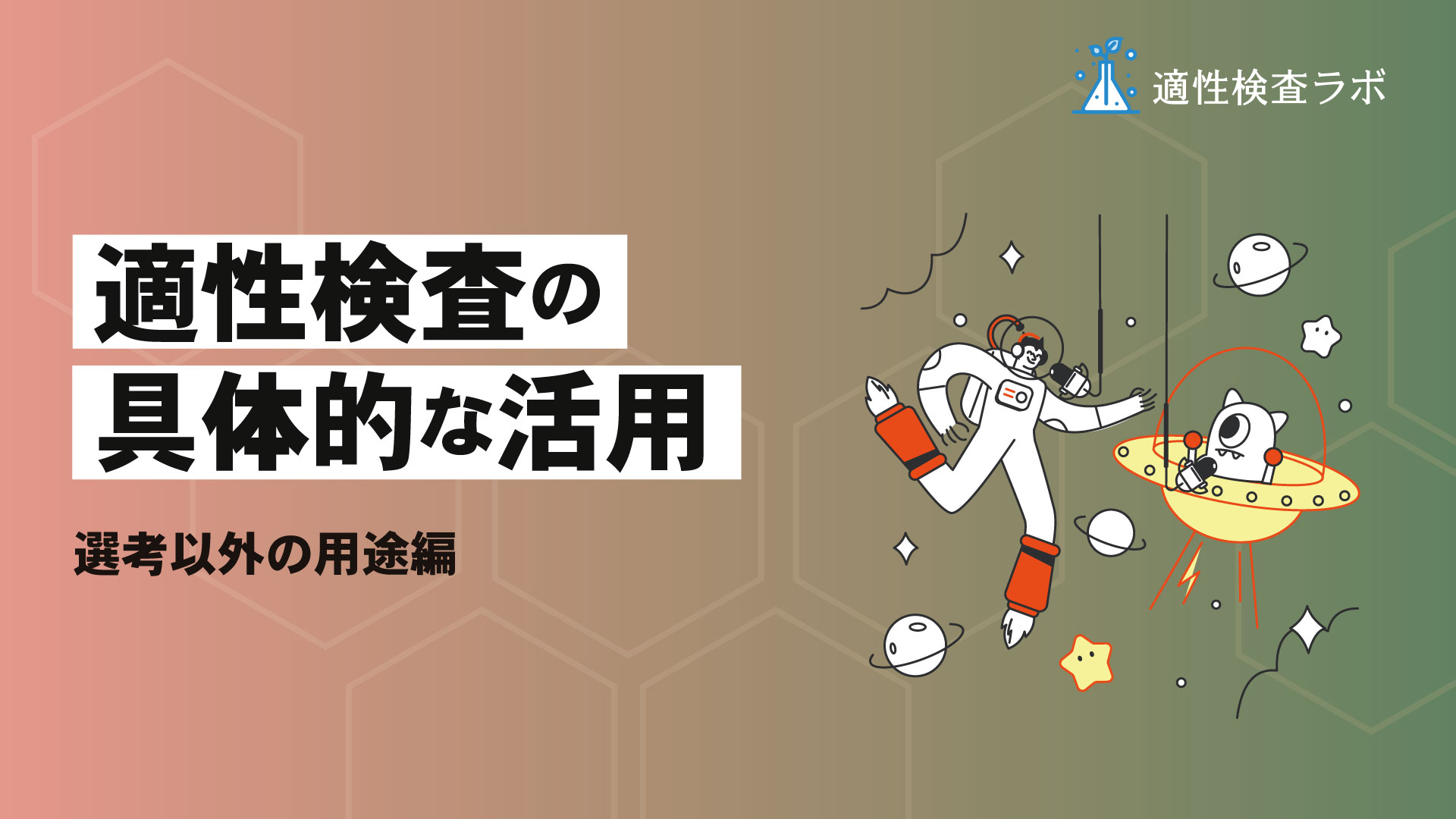
2024.12.05
適性検査の具体的な活用(選考~内定者フォロー編)
近年、採用選考の場面でよく利用される「適性検査」は、その用途がますます拡大しています。特に社員のパフォーマンスや組織の生産性向上を支える「ピープルアナリティクス」への注目が高まり、採用のみならず、入社後の配置や育成、昇進・昇格までを見据えた総合的な人事戦略ツールとして活用されるケースが増えています。適性検査は、本人の価値観や思考特性、行動特性などを可視化し、データにもとづいた客観的な判断材料を提供してくれるため、人事や現場管理職が抱えるさまざまな課題を効率的かつ的確に解決する可能性を秘めています。
本記事では、選考以外の用途として適性検査をどのように使うか、その具体的な活用方法や活用にあたってのポイントを解説します。採用後のフォロー体制から昇進・昇格の評価基準まで、多角的な視点で適性検査を活用することで、組織の人材育成をさらに進化させるヒントをご紹介します。
INDEX
1.適性検査を選考以外で活用する意義
2.自社で活躍する人材を可視化する
3.入社後の配属・教育への応用
4.昇進・昇格でより多角的な視点を取り入れる
5.適性検査結果を長期的に活用する仕組みづくり
6.ピープルアナリティクス時代における適性検査の展望
サービスのご紹介
1. 適性検査を選考以外で活用する意義
1-1. 人材マネジメントと適性検査の連動
人材マネジメントは、採用時の選考だけではなく、入社後の定着や活躍度合い、さらには社員のキャリアアップや組織全体の生産性向上までも視野に入れて実践されるべきものです。適性検査は、本来こうした一連のプロセス全体をバックアップできるポテンシャルを持っています。
たとえば、コンピテンシーモデルと呼ばれる手法を用いれば、自社の中で成果を出している社員の行動パターンを分析し、求める人材像を定義できます。これを適性検査の結果と照合することで、科学的根拠に基づくマッチング度合いや潜在的な強み・弱みを把握することが可能になります。採用時の適性検査結果だけでなく、その後のキャリアパスや配置転換においても継続的に活用すれば、人材マネジメント全体を円滑にする土台を作ることができます。
1-2. 科学的データにもとづく客観評価の利点
人事評価や昇進・昇格の判断が、属人的な主観や経験則だけに頼っていると、評価の一貫性や公平性が失われがちです。この問題を解決するうえでも、適性検査を用いた「客観的な評価基準の確立」は非常に有効です。
適性検査では、一般的に思考パターンや行動特性、モチベーションの方向性などが数値やチャートで示されます。これらの数値化されたデータがあれば、上司や人事担当者の主観に偏ることなく、複数の視点から対象者を評価しやすくなります。面接官間の評価のブレを抑え、候補者にとっても納得感のある選考・配置を行うための重要なツールとなるのです。

2. 自社で活躍する人材を可視化する
2-1. ハイパフォーマー分析の具体的な手法
「自社で活躍する人材」を可視化する際に有効なのが、すでに社内にいるハイパフォーマーの特性を洗い出す方法です。具体的には、特定部署や特定階層の社員に適性検査を実施し、その結果を業績データや評価データと突き合わせることで、「高い成果を上げる人材の共通点」を抽出します。
たとえば、営業部門でトップクラスの成績を残す人たちの検査結果を分析すると、「リスクを恐れずチャレンジする傾向が強い」「対人コミュニケーションを好み、高いストレス耐性がある」といった要素が浮かび上がるかもしれません。こうした情報を採用選考の基準に活用すれば、企業全体として目指す成果を出しやすい人材を精度高く採用しやすくなります。
2-2. 企業風土とのマッチングと面接官教育
ハイパフォーマー分析で得られた知見は、企業の風土に合うかどうかを判断する材料にもなります。個人の能力が高くても、組織文化と合わなければ、パフォーマンスを十分に発揮できない場合があります。
また、こうした「科学的データにもとづく基準」を面接官が共有することで、面接の際にどのようなポイントに注目すべきかが明確になります。面接官同士で判断にばらつきが生まれにくくなり、「主観的な好き嫌い」や「なんとなくのフィーリング」による評価ミスを減らせるのも大きなメリットです。さらに、面接官が適性検査結果の読み解き方を学ぶこと自体が、人材を見る視点を養うトレーニングとなり、より戦略的な採用活動につながるでしょう。
3. 入社後の配属・教育への応用
3-1. 適性検査で見極める最適な部署配置
選考場面での使い道が注目されがちな適性検査ですが、入社後における活躍支援の場面でこそ、その真価が発揮されます。まず代表的な活用方法として挙げられるのが、配属部署の決定です。
新卒社員の大量採用を行う場合は、適性検査の結果をもとに、「この人材は営業に向いているか、それとも企画部門に適性が高いか」などを初期段階で見極めることができます。本人の希望だけでなく、客観的データを合わせて配属を検討することで、早期戦力化やミスマッチによる離職防止につながりやすくなります。
3-2. 現場指導に活かすフィードバックシートの活用
最近は、適性検査結果を上司や指導担当者へフィードバックする仕組みを整えている企業が増えています。受検者本人にはもちろんのこと、指導担当にもわかりやすい形でレポートを提供することで、新メンバーの強み・弱みを事前に把握し、一人ひとりに合った育成プランや指導方法を選択しやすくなります。
たとえば、コミュニケーションが得意だが計画性にやや弱みがあるタイプであれば、目標管理やスケジュール管理の方法を丁寧に教えるなど、ピンポイントで指導を強化できます。一方で、自分のペースで物事を進めたいタイプには、早めに課題を共有し、余裕を持って準備を進めさせるような配慮が必要になるかもしれません。このように、適性検査結果を育成・指導計画の一助とすることで、現場での教育効果を一層高めることが可能です。

4. 昇進・昇格でより多角的な視点を取り入れる
4-1. 「マネジメント適性」と「専門性」の両軸評価
優れたプレイヤーが必ずしも優れたマネージャーになるとは限らない――これはビジネスシーンでよく聞かれる言葉です。昇進や昇格を検討する際、これまでの業績や勤怠状況、人柄の評価など「過去の実績」を重視するのは当然ですが、マネジメントポジションやリーダーシップポジションには、異なる資質が求められる場合が多いです。
適性検査には、リーダーシップやチームビルディング、対人サポート力など、マネジメントに欠かせない要素を測定できるものがあります。こうしたデータと実績評価をあわせて検討することで、新たな役職に就く人材がそのポジションにマッチするかどうかを、より多角的に判断できるようになります。
4-2. 昇格試験と適性検査による登用の最適化
ある企業では、昇格試験の一環として小論文や面接に加え、適性検査を活用しています。そこでは新しい役職で要求される能力を事前に定義し、その要件を満たすだけの潜在能力があるかどうかを検証する指標の一つとして適性検査結果を利用しているそうです。
これにより、「現時点の実績は十分だが、マネジメント適性の面でリスクがありそうな候補者」を早期に把握できるため、昇格後に混乱をきたすリスクを軽減できます。また、本人も検査結果から自らの得意・不得意を自覚し、必要なスキル開発に取り組みやすくなります。こうした仕組みを取り入れることで、企業側も適材適所の配置を行いやすくなり、長期的に見ても組織全体のパフォーマンスが底上げされるでしょう。
5. 適性検査結果を長期的に活用する仕組みづくり
5-1. 複数回の受検で成長度合いを数値化
適性検査は一度きりの受検で終わりというイメージがありますが、より高い精度で人材育成に活かすためには、入社後3年目、5年目など複数回実施するケースが理想的です。
特に行動特性やコンピテンシーを測定できるタイプの適性検査では、受検者の行動傾向がどのように変化したかを比較できるため、実際の成長や活躍の度合いとの相関関係を分析しやすくなります。たとえば、最初はストレス耐性が低めだった社員が、3年後には管理職候補として挙げられるほどストレスコントロール能力を身に着けている場合、どのような経験や研修が効果的だったのかを振り返るきっかけになるでしょう。
5-2. データ管理と検索性向上による人材活用の最適化
長期的な視点で適性検査の結果を活用するためには、データを組織的に保管・管理する仕組みが欠かせません。人事情報や社員の評価データ、研修履歴などとあわせて適性検査の結果を一元管理できるシステムを整えることで、必要なタイミングで過去のデータを検索・加工し、意思決定に役立てることが可能になります。
たとえば、全社的な異動や新規プロジェクトのチーム編成を検討する際、適性検査のデータを参照しながら「新しい環境で活躍できそうな人材は誰か」「このチームに不足している特性を補完できる社員はいるか」などをスピーディに検討できます。これにより、異動や配属にかかる時間や手間を削減できるだけでなく、社員それぞれが強みを活かせる配属を実現しやすくなるのです。

6. ピープルアナリティクス時代における適性検査の展望
6-1. 根拠のあるデータの蓄積が生む組織変革
ピープルアナリティクスが注目される背景には、人に関するあらゆるデータを活用して組織の生産性向上や人材の定着率アップ、イノベーション創出などにつなげたいという企業の強いニーズがあります。その中で、適性検査は「個人の特性」という重要なデータソースを提供します。
適性検査の結果を長期的に蓄積し、組織のパフォーマンスや研修実績など、他のデータと掛け合わせることで、どのようなタイプの人材がどの部署で高い成果を上げているのか、あるいはどんな組み合わせのチームが創造的な成果を出しやすいのか、具体的な傾向をつかむことができます。こうした分析結果は、経営や人事部門の意志決定を科学的な根拠のもとに行うための大きな武器となるでしょう。
6-2. 適性検査の活用範囲と今後の可能性
適性検査の用途は、今後ますます拡大すると考えられます。たとえば、テレワークやリモートワークが普及したことで、離れた場所で働く社員のマネジメントやエンゲージメント維持が大きな課題になりました。こうした場合でも、適性検査の結果を活用することで、オンライン上でのコミュニケーションスタイルや指示出しの方法を工夫できる可能性があります。
また、ダイバーシティ推進の観点から、さまざまな背景を持つ社員がそれぞれの強みを発揮できるようにするための指標としても、適性検査は有効です。これからの時代、企業は多様性を受け入れて成長することが求められるため、適性検査による「個の特性の見える化」はさらに重要性を増すでしょう。
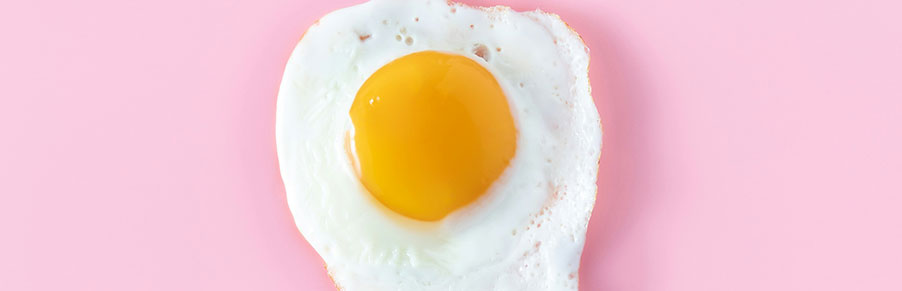
7.まとめ
適性検査は、採用選考時の見極めだけでなく、入社後活躍のための科学的なデータとしてその活用範囲を広げています。現有社員一人ひとりの強み・弱みを把握し、強みを発揮するアサインメントをすること、弱みを補完するチーム編成をおこなうことが叶えば、さらなる成果創出につながります。
ピープルアナリティクスで成果を生みだすためには、そのデータが正しく、根拠のあるものであることが欠かせませんが、適性検査はその点でも活用の価値があり、今後も活用範囲を拡大していくと考えられます。ぜひこの機会に、自社での適性検査の活用方法を改めて検討してみてはいかがでしょうか。


サービスの
ご紹介
適性検査を導入する際、実際にどの検査が自社に最適かを見極めることが重要です。まずは、実際の検査を体験してみることをおすすめします。自社のニーズに最適な適性検査を見つけるために、トライアル受検を実施して、サービスの使い勝手や結果を実感してみてください。
興味のある方は、下記のリンクから無料でトライアル受検をお試しいただけます。ぜひ、この機会に検査の効果を確認し、自社の採用に役立ててください。

© Humanage,Inc.

